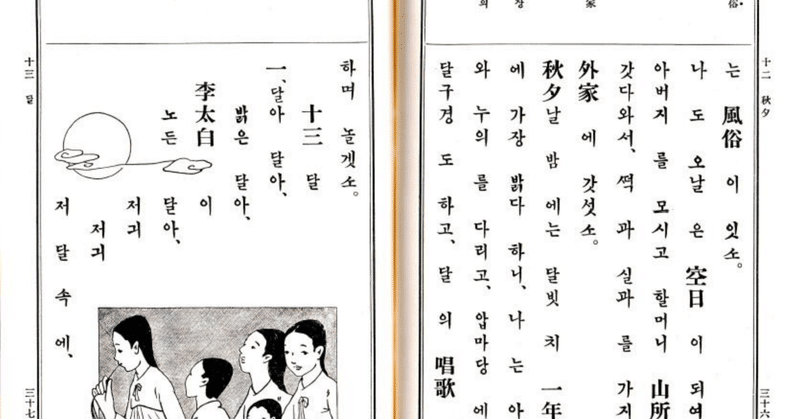
植民地支配における日本語教育と日本近代文学の成立(11)(2004)
11 日本近代文学の成立
この儀式化は文学でも同様であり、日露戦争が終わった1905年(明治38年)、島崎藤村は『破戒』を刊行、次のような口語文体を確立する。
丑松は大急ぎで下宿へ帰つた。月給を受け取つて来て妙に気強いやうな心地になつた。昨日は湯にも入らず、煙草も買はず、早く蓮花寺へ、と思ひあせるばかりで、暗い一日を過したのである。実際、櫂中(ふところ)に一文の小使もなくて、笑ふといふ気には誰がならう。悉皆(すつかり)下宿の払ひを済まし、車さへ来れば直に出掛けられるばかりに用意して、さて巻煙草に火を点けた時は、言ふに言はれぬ愉快を感ずるのであつた。
ここでは、活用語尾は過去形である「だ」に統一され、現在形は「体的見方」の場合に使われている。言文一致体は資本主義的価値観が浸透しているため、読者=語り手=登場人物の三者の関係が平等に見えなければならない。語り手は、この場合、「国民」、すなわち成人男性である。語り手は中性ではない。国民国家において、「国民」は公教育と常備軍を通じて生産されるが、戦前、女性に選挙権や高等教育への機会が制限されていたように、それはあくまでも健常の成人男性を意味している。
登場人物と語り手が混在化することを通じ、読者も登場人物と一体化する。しかし、語り手によって因果関係が整理されている。
漱石は、『破戒』と同じ年に発表した『吾輩は猫である』において、過去形ではなく、現在形を中心に次のような文体で書いている。
吾輩は猫である。名前はまだ無い。
どこで生まれたか頓と見當がつかぬ。何ても暗薄いじめじめした所でニャー/\泣いて居た事丈は記憶して居る。吾輩はこゝで始めて人間といふものを見た。然もあとで聞くとそれは書生といふ人間で一番獰惡な種族であつたさうだ。此書生といふのは時々我々を捕へて煮て食ふといふ話である。然し其當時は何といふ考もなかつたから別段恐しいとも思はなかつた。但彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフハフハした感じが有つた許りである。掌の上で少し落ち付いて書生の顏を見たが所謂人間といふものゝ見始であらう。此の時妙なものだと思つた感じが今でも殘つて居る。第一毛を以て裝飾されべき筈の顏がつる/\して丸で藥罐だ。其後猫にも大分逢つたがこんな片輪には一度も出會はした事がない。加之顏の眞中が餘りに突起して居る。そうして其穴の中から時々ぷう/\と烟を吹く。どうも咽せぽくて實に弱つた。是が人間の飮む烟草といふものである事は漸く此頃知つた。
子の文体は現在形が中心である。語り手は登場人物のスポークスマンではないし、因果関係を整理するつもりもない。『吾輩は猫である』は滑稽本のように見えるが、語り手が登場人物をからかうのではなく、むしろ、自分自身に対する諧謔がある。漱石は落語の語りを大胆に導入、これは円朝の落語のパロディである。また、身分制から解放された「私」ではなく、「吾輩」を使っている点は、鴎外流の一人称小説や自然主義文学に対するユーモアである。他にも、手紙の候文、物理学的論文、山の手言葉、江戸弁などさまざまな文体を操っているように、国語だけを話さない語り手は「国民」ではない。つまり、『吾輩は猫である』は言文一致運動から自然主義文学に至るまでの日本文学全般のパロディである。
藤村の『破戒』によって、日本近代文学=国民文学が始まる。近代的な自我の確立を背景にする近代文学は告白である。だが、その告白は日本文学では儀式化する。それを通じて、近代的自我の確立が日本近代文学であるという神話が生まれる。
藤村の『破戒』の主人公瀬川丑松は小学校教師である。丑松は、信州の書店で、猪子連太郎の『懺悔録』を購入する。猪子連太郎は、丑松と同じ被差別部落出身者であり、『懺悔録』はその出自を告白した書物である。丑松は告白という行為に惹かれてしまう。藤村は被差別部落問題という社会的な課題が題材であったにもかかわらず、告白という個人的な行為に重点を置いて描いている。告白という制度が先にあり、それを儀式として繰り返す。
こうした傾向は国木田独歩の作品にすでに見られる。国木田独歩の『牛肉と馬鈴薯』の主人公岡本誠夫は「驚きたい」という「不思議なる願」を持っている。それは「宇宙の不思議を知りたいという願ではない、不思議なる宇宙を驚きたいという願」である。先に「驚き」という制度があり、儀式として体験する。告白が後に私小説になるのは、告白を儀式として捉えたからである。告白すること自体、すなわち告白という行為が重要なのであって、何を、いかに告白するかは問題にならない。告白を通じて、因習や権威を打破し、新しい道徳を創出するのではない。告白するために、作家は古い道徳に依拠するようになってしまう。主観的で知的な告白は気分だけを書き綴る私小説になる。そこには近代的自我はなく、ただ儀式だけがある。
日露戦争の勝利が告白を前面に押し出した自然主義の流行を生んでいる。歴史との断絶をもはや考慮する必要はない。日本の自然主義は人間と社会を自然科学的に観察すると言うより、身辺雑事を気分に基づいて描写する傾向が強く、そこから私小説が派生している。
フランスの自然主義はオーギュスト・コントの実証主義に則り、写実主義に実験医学を筆頭にした自然科学的説明を加えて誕生している。確かに、徳田秋声の『黴』(1911)は、進化論や優生学といった自然科学に依拠しており、エミール・ゾラに代表されるフランス自然主義の流れと合致する。もっとも、福井勝義の『東アフリカ・色と模様の世界』によると、東アフリカの部族社会の人々は、メンデルの遺伝の法則とは比較にならないほど牛の遺伝に関する複雑かつ詳細な知識を所有し、それを用いて牛の交配を進めているだけでなく、遺伝の認識を人の名づけにも援用している。
ただ、日本の自然主義文学は自然科学への依拠が次第に後退していく。人間と社会のメカニズムを自然科学を基盤にして小説化するはずの自然主義文学は、日本語フェンティシズムへと変容してしまう。日露戦争以降、それ以前の文学が整理され、日本近代文学史のパースペクティヴが形成される。
明治20年代までは欧米の諸制度を導入しつつも、日本の現状に合わせて変えていく試行錯誤の時代である。そこには近代に対する無理解も含まれる。近代は政教分離が大原則である。ところが、明治政府はそれを理解していない。おまけに、共同体を超越した一神教と共同体内属の多神教の神観念を混同している。日本の宗教は伝統的に習合思想に要約できる。純粋な神道・仏教・儒教はない。ただ、近世に純粋化が指向され始め、学問として洗練されたものの、民衆からかい離する。日本の神観念は共同体内の作用である多神教のそれであって、人格伸・超越神の一神教と異なる。明治政府は天皇制を神道と結びつけ、擬似一神教的な擬似国教としたグロテスクな試みを行う。言文一致運動も文学における試行錯誤である。明治30年代に入ると、日本は帝国主義化し始め、中華文明を克服したという優越感が生まれた反面、台湾の植民地支配を通じて、世界史における近代日本の矛盾が顕在化する。支配のイデオロギーは文化に基づかなければならない。しかし、日本の伝統的な固有文化を探索したものの、それを日本語に求めざるを得ないほど苦しい。
国語という概念はたんに国民国家日本の言語としての日本語を意味しない。国語は「東亜共通語」としての日本語を前提にしている。日本の固有文化は日本語そのものであり、欧米が帝国主義を通じて近代化を輸出しているように、日本は東亜にそれを文化として伝播する必要がある。そのためには標準化された言語を規定しなければならない。
戦後になっても、変化の時代が到来し、日本人のアイデンティティが問われると、日本語を賛美し始めるのはこうした理由による。文学では、日清戦争以後のロマン主義が脱亜主義だったとすれば、自然主義は入欧主義である。日本「国民」は、世界に向けて、脱亜入王を告白したくてうずうずしている。西洋近代文明と中華文明の間に生きているという意識が日本「国民」の間で解消された時、日本近代文学が成立する。自然主義文学の主導権獲得によって正統派として国民文学の地位を占め、日本近代文学が形成される。自然主義文学は私小説へと変容し、文壇が形成され、数々の文学賞が生まれていくにつれ、日本文学の儀式化が加速する。
自然主義の文学における覇権の獲得はたんなる文学上の論争の勝利の結果ではない。極めて、政治的な動きによって帰結している。政治における権力闘争は正統性の争いである。正統性のない政治権力は他の政治権力から承認されない。異端の政治権力は、政治の場では、ありえない。国語としての日本語が近代日本の正統性の基盤である以上、日本近代文学もそれと整合性がとれるように、政治的に決着させなくてはならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
