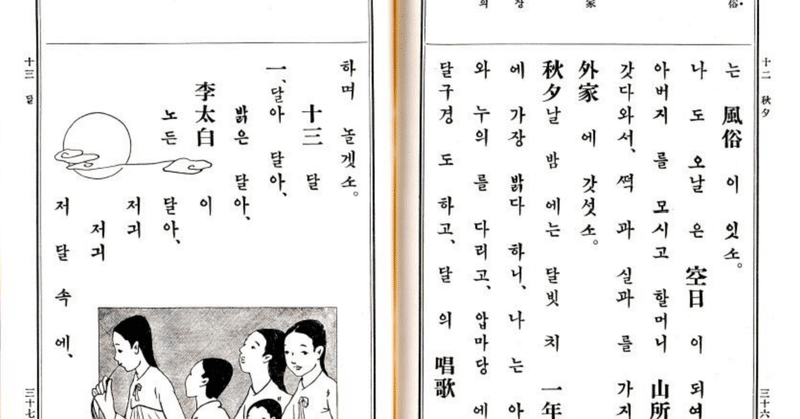
植民地支配における日本語教育と日本近代文学の成立(10)(2004)
10 日本語教育という<儀式>
1930年代以降、植民地では、宮城遥拝や神社参拝、日の丸掲揚といった学校儀式が質的にも量的にも重視されるようになり、さらに、中国や東南アジアの占有地でもこれが踏襲される。ジャワの学校では、毎朝の朝礼の際、宮城遥拝、日の丸掲揚、さらには「私どもは、大東亜の学徒です。大日本に従い、新しいアジアのために尽くします」という「新ジャワ学徒の誓い」を子供たちに斉唱させている。
駒込武は、「教育における『内』と『外』(2)」(佐藤秀夫編『教育の歴史』所収)において、日本語教育が<儀式>だったと次のように述べている。
植民地・占領地において、日本語教育は一種の<儀式>であったということもできる。それはまず何よりも身体的なレベルでの強制であり、身体的な感覚を通じて「同情同感」のきずな、一体感を醸成するための装置だった。さらに、日本語教育重視の方針のよって何を教えるのかという内容の問題が棚上げされたことに象徴されるように、<儀式>的な行為が何を意味するのかという問題は限りなくあいまいにされる傾向があった。<儀式>の意味への疑問が封じられる中で、共感のための共感、同調のための同調への圧力は自己増殖的に高まり、<儀式>の拒否は排除のための十分な口実となっていく。学校儀式と日本語教育に違いがあったとすれば、日本語教育が、日常的で惰性的な時間の中で延々と続く<儀式>であったということだろう。
考えてみれば、植民地教育のこうした特徴は植民地支配に特有な現象というよりも、近代日本の学校の本質的な側面を濃縮して表現したものとみることもできるかもしれない。欧米の植民地支配の場合は、宣教師達が学校教育の外で自ら「文明の宗教」と信ずるキリスト教をアグレッシヴに布教していたが、天皇制が擬似的な<国教>の地位を占めていた日本の場合は、学校が半ば<教会>の役割も兼ねていた。社会的な亀裂が顕著だった植民地支配の場合、そうした学校の<儀式>的な機能がさらに形式化しながら拡大していったと考えられるのである。
近代日本の歴史は正統性の欠落を極端な儀式化によって覆い隠そうとすることで貫かれている。制度は儀式にすり替わる。儀式を通じて日本の精神が身体化されるという倒錯した教育に基づいて、日本「国民」は邁進していく。すべてを儀式化してしまうために、制度を変更しても、何も変わらない。日本の学校教育には、甲子園の野球大会を含めて、行進が溢れている。近代の兵士はマーチに合わせて行進するが、それはオスマン帝国の軍隊が軍楽隊に合わせて行進してきた姿に影響されてヨーロッパに拡大している。近代以前の日本人は行進をしたことがない。歩き方は、ヨハン・ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトのオペラ同様、身分を表わしている。大名行列が通れば、農民がそろって歩くことなど許されず、土下座していなくてはならない。近代的な軍隊が成立した後、軍隊の行進が普及している。それは、日本では、学校によって強化される。近代日本は、国民国家・資本主義体制の根幹にかかわる神の死さえも、たんなる儀式にしてしまう。
この儀式化への傾向をアレクサンドル・コジューヴは、『ヘーゲル読解入門』の中で、伝統的に日本に見られると指摘している。彼は、「歴史の終わり」の後、人々に残されている二つの生き方として、アメリカ的生活様式の追求、すなわち「動物への回帰」と並んで、日本的な「スノビズム」をあげている。コジューヴは戦後アメリカで台頭してきた消費者の姿を「動物」と呼んでいる。人間が人間的であるためには、与えられた環境を否定する行動、すなわち環境との闘争を経なければならない。一方、動物はつねに自然と協調して生きている。消費者の「ニーズ」に応える商品に囲まれ、メディアが提供する流行にのっているアメリカの消費社会はもはや「人間的」ではなく、「動物的」でしかない。
「スノビズム」は、環境を否定する理由がないにもかかわらず、「形式化された価値に基づいて」それを否定する行動様式である。コジューヴは日本的「スノビズム」の典型として「切腹」をあげている。人間が人間的であるためには、与えられた環境を否定する行動、すなわち自然との闘争を経なければならない。ところが、「スノビズム」は、そうした環境を否定する実質的な理由がないにもかかわらず、「形式化された価値に基づいて」、すなわち儀礼的に、それを否定する行動様式である。スノッブは、「動物」と違って、環境と調和することを拒否する。否定の契機がなかったとしても、意図的に、環境を否定し、形式的な対立をつくりだし、その対立に耽溺する。「切腹」は、実質的には死ぬ理由がないにもかかわらず、名誉や秩序といった形式的な価値に基づいて、実行される。しかし、これはあくまで儀礼でしかなく、歴史を動かす力にはならない。
「切腹」がスノビズムであるかどうかは別にしても、19世紀の半ば、イギリスの小説家ウィリアム・メイクピース・サッカレーの作品を通じてその言葉が普及したように、スノビズムは神の死と共に出現している。スノッブは、鈴木道彦の『プルーストを読む』によると、「一つの階層、サロン、グループに受け入れられ、そこに溶けこむことを求めながら、その環境から閉め出されている者たちに対するけちな優越感にひたる人々」である。封建制がまだ残っている19世紀では新興のブルジョアジーがスノッブの中心だったが、大衆社会に突入した20世紀になると、誰もが、程度の差こそあれ、スノビズムに染まっていく。近代日本のスローガンである脱亜入欧は典型的なスノビズムであり、まさに国家を挙げてスノビズムに邁進している。
スノビズムに対抗する姿勢としてダンディズムがある。シャルル・ボードレールの『現代生活の中の画家』によると、ダンディーは精神主義や禁欲主義と境界を接した「自己崇拝の一種」であり、「独創性を身につけたいという熱烈な熱狂」であって、「民主制がまだ全能ではなく、貴族制がまだ部分的にしか動揺し堕落してはいないような、過渡期にあらわれ」、「頽廃期(デカダンス)における英雄主義の最後の輝き」である。近代日本は戦前には脱亜入欧、戦後になると対米追従というスノビズムに支配されてきたため、一般に、毅然とした態度のダンディズムヘの憧れが非常に強い。けれども、貴族制が完全に後退した20世紀において、スノビズムがあまりに凡庸であったとしても、ダンディズムは陳腐なアナクロニズムにすぎない。そういったダンディズムを目指すこと自体凡庸なスノビズムであろう。「スノビズムか、ダンディズムか」という二項対立ではなく、両者の弁証法的な止揚が志向されないまま、ダンディズムを目指しながら、スノビズムが日本の外交姿勢として現在に至るまで続いている限り、過剰なまでの儀式化の傾向は根強く残る。
近代日本語の基礎を築いた二葉亭四迷自身が日本語を相対化するために、エスペラント語の普及を推奨している。彼はスノビズムに陥っていない。エスペラントは、1906年に著わされた二葉亭の『エスペラントの話』によると、非常に文法・発音が簡単で、国際的なコミュニケーション手段であるだけでなく、ネイティヴ・スピーカーがいないから、エスペラントで表現すると、そこには話者のネイティヴな言語の「臭味」があり、狭量なナショナリズムを克服できる。けれども、二葉亭のように、言語を政治的な支配の同一性を強化するための儀式に狭めるべきではないと警告し、言語に関する新しい認識の提案をしたのは少数派にとどまってしまう。テオドール・W・アドルノは、『プリズメン』の中で、「アウシュヴィッツ以降、詩を書くことは野蛮である」と言ったが、「日本の植民地支配以降、日本語を使うことは野蛮である」というテーゼが発せられなければならない。
漱石は、1911年(明治44年)6月日長野県会議事院で行った講演『教育と文芸』において、明治維新以前とそれ以降の教育について次のように述べている。
よく誤解される事がありますので、そんな事があっては済みませんから、ちょっと注意を申述(もうしのべ)べて置きます。教育といえばおもに学校教育であるように思われますが、今私の教育というのは社会教育及家庭教育までも含んだものであります。
また私のここにいわゆる文芸は文学である、日本における文学といえば先(まず)小説戯曲であると思います。順序は矛盾しましたが、広義の教育、殊に、徳育とそれから文学の方面殊に、小説戯曲との関係連絡の状態についてお話致します。日本における教育を昔と今とに区別して相比較するに、昔の教育は、一種の理想を立て、その理想を是非実現しようとする教育である。しこうして、その理想なるものが、忠とか孝とかいう、一種抽象した概念を直ちに実際として、即ち、この世にあり得るものとして、それを理想とさせた、即ち孔子を本家として、全然その通りにならなくともとにかくそれを目あてとして行くのであります。
さて当時は理想を目前に置き、自分の理想を実現しようと一種の感激を前に置いてやるから、一種の感激教育となりまして、知の方は主でなく、インスピレーションともいうような情緒(じょうしょ)の教育でありました。なんでも出来ると思う、精神一(せいしんいっ)到(とう)何事(なにごとか)不成(ならざらん)というような事を、事実と思っている。意気天を衝(つ)く。怒髪天をつく。炳(へい)として日月(じつげつ)云々という如き、こういう詞(ことば)を古人は盛(さかん)に用いた。感激的というのはこんな有様で情緒的教育でありましたから一般の人の生活状態も、エモーショナルで努力主義でありました。そういう教育を受ける者は、前のような有様でありますが社会は如何(どう)かというと、非常に厳格で少しのあやまちも許さぬというようになり、少しく申訳がなければ坊主となり切腹するという感激主義であった、即ち社会の本能からそういうことになったもので、大体よりこれが日本の主眼とする所でありました、それが明治になって非常に異ってきました。
四十余年間の歴史を見ると、昔は理想から出立(しゅったつ)した教育が、今は事実から出発する教育に変化しつつあるのであります、事実から出発する方は、理想はあるけれども実行は出来ぬ、概念的の精神に依って人は成立する者でない、人間は表裏(ひょうり)のあるものであるとして、社会も己も教育するのであります。昔は公(こう)でも私(し)でも何でも皆孝で押し通したものであるが今は一面に孝があれば他面に不孝があるものとしてやって行く。即ち昔は一元的、今は二元的である、すべて孝で貫き忠で貫く事はできぬ。これは想像の結果である。昔の感激主義に対して今の教育はそれを失わする教育である、西洋では迷(まよい)より覚めるという、日本では意味が違うが、まあディスイリュージョン、さめる、というのであります。なぜ昔はそんな風であったか。話は余談に入るが、独逸(ドイツ)の哲学者が概念を作って定義を作ったのであります。しかし巡査の概念として白い服を着てサーベルをさしているときめると一面には巡査が和服で兵児帯(へこおび)のこともあるから概念できめてしまうと窮屈になる。定義できめてしまっては世の中の事がわからなくなると仏国の学者はいうている。
明治期の教育は実学を目指していたのに、斥けてきたはずの江戸時代の学問以上に儀式化してしまう。「少時好んで漢籍を学びたり。之を学ぶ事短きにも関らず、文学は斯くの如き者なりとの定義を漠然と冥々裏に左国史漢より得たり。ひそかに思ふに英文学も亦かくの如きものなるべし」と『文学論』(1907)で書く漱石は日本文学ではなく、漢文学に向かっている。古代から明治維新に至るまで、漢学が中心的な学問であり、国学は近世後期に生まれたばかりの歴史の浅い学問にすぎなかったが、王政復古に伴って、国学者は政府に起用されている。ひらがなやカタカナを指す「仮名」は、平安期、漢字ならびに漢文を意味する「真名」に対する概念として使われている。他にも、「榊」のような日本独自の漢字も生まれている。和文はあくまで仮であって、漢文こそが真の文章というわけだ。
平安期、実際には日本文学の主流は漢詩のような漢文学である。公式文書は漢文で記されているのだから、その読み書きが自在でなければならない。日本は中華文明の辺境にすぎず、日本文学は漢文学の強い影響下で形成されてきたのであり、現在使われている「日本文学」という概念は近代化を通じて構成されている。国学者は漢学と新興勢力の洋学を国学の支配下に置く「皇学」を画策したものの、たんなる政治的主導権への欲しか持っていなかったため、理論的脆弱さばかりが目立ち、将来的な見通しを欠き、たちまち漢学派に蹴散らされている。漢学派と国学派の対立抗争は教育制度改革の停滞を招き、産業革命を成し遂げた欧米の先進的技術を支える政治・経済・文化の早急な導入を目的として、洋学を教育・文化政策において主流にすると政府は決定している。学問の面でも、神の死を迎えつつあったにもかかわらず、この原則が堅持されることなく、放棄されてしまい、空疎な儀式が強調されていく。
森毅は、『むしろ洋魂和才』において、近代日本は、諸制度を西洋から輸入しながらも、その背景にある文化を顧みなかったと次のように述べている。
明治以来、西洋の制度をいろいろとりいれたけれど、最大の失敗は「和魂洋才」にあったと思う。制度を変えながらも、文化をとりいれなかった、ちぐはぐさにある。戦後教育だって、制度は変わっても、文化はむしろ過去への一元化を志向している。
制度を変えるからには、それに伴う文化の変化をイメージしなければなるまい。さまざまな価値を持った人たちが、それぞれに生きていくにはどうしたらよいか、それは洋魂に学ぶほうがよい。制度よりむしろ、そのことを考えてほしい。
多様化と自由化を肯定したうえで、どのような制度がありうるかと考えさえするなら、制度はどうあってもたいしたことじゃない。
文化の裏打ちがなければ、制度は儀式化する。和魂洋才といった傲慢かつ怠惰な姿勢がその事態を招いている。台湾に渡る前から伊沢修二は、近代化推進を掲げながら、忠君愛国の国民教育運動を推進しているが、これが明治維新のイデオロギーに相反するという認識が彼にはない。これは伊沢に限らず、多くの明治政府を構成したり、周辺に位置したりする人たちにも見られる。国民国家・資本主義体制を導入する際、すべての面で封建的発想を廃棄しなければならないのに、道徳イデオロギーになると、それに依存してしまう。文化的な観点から制度を考えるという発想が根本的に欠落している。こうした状況は現在にまで至っている。「政治は、まず制度を考える。制度が変わっても文化が変わらねば、教育の流れは変わらない」(森毅『制度より文化を』)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
