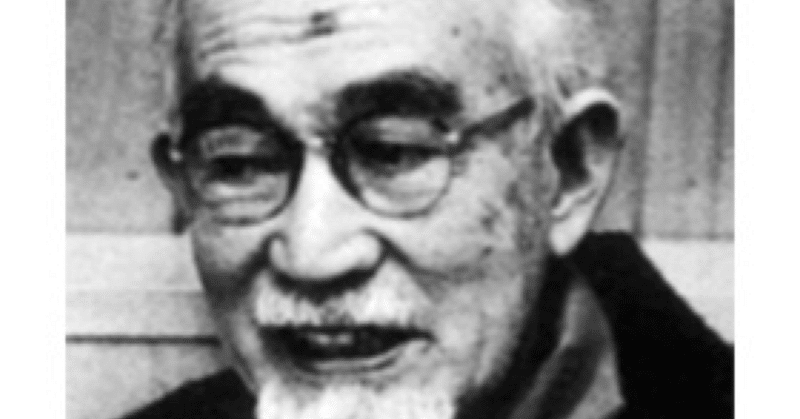
志賀直哉が「小説の神様」?(2)(2021)
第2章 小説の達人
この志賀直哉は、日本近代文学史において、「小説の神様」と呼ばれている。しかし、近代が「神の死」を背景にしているとすれば、これは明らかに背理である。近代を理解しないで、文学を書いてきた証だ。「私の考えでは、人生は愚女神の戯れにすぎないということ以外の意味は、そこにないと思いますね。……『愚かな者は月のように変わり、賢い者は太陽のように変わることがない』……要するに、人間は愚であって、『賢者』の名は神のみのものだという意味でしょう。月は人間の本性を表わしており、あらゆる光の根源である太陽は、神を表わしているからです」(エラスムス『愚神礼讃』)。
西洋ではヘンリー・ジェイムズが文学における「小説の達人(The Master)」と呼ばれている。彼の作品は心理主義小説であり、モダニズム文学の先駆でもある。彼がそう呼ばれる理由を理解するには、近代小説がいかに近代の理念に基づいているかを知る必要がある。
前近代の政治の目的は徳の実践である。ところが、欧州で宗教戦争が勃発、各勢力は自身の道徳の正しさに基づいて殺し合いを繰り返す。そこで、17世紀英国の思想家トマス・ホッブズは政治の目的を平和の実現へ変更する。平和でなければ、よい生き方もできない。これが近代の理論的始まりである。
ホッブズは、そのため、政治を公、信仰を私の領域にあり、相互に干渉してはならないと政教分離を主張する。共同体が認める規範に従うのではなく、個人が価値観を自由に選択できる。政治は道徳と別なのだから、それに依拠して戦争など起こらない。この政教分離は公私の区別へと拡張する。
ホッブズは自説を展開する際、自然状態と社会契約を想定する。これは近代が前近代と断絶した人為的社会だという意味である。文学者を含め少なからずの日本の知識人は社会契約の有無を論拠に西洋と日本の違いを主張するが、それは西洋にも現実にはない。近代社会の人為性を理解していないだけである。そういう知識人は、耳度島のごとく、近代に関する基礎的理論を体系的に承知しないまま、近代を批判したり、西洋と違う日本の独自性を主張したりする。近代は理論によって基礎づけられている。それを理解した上で、近代の事象を論じるべきだ。
ホッブズを踏まえて、ジョン・ロックはこの個人が集まって社会を形成すると説く。この社会の近代人は自由で平等、自立した個人である。こうした社会がうまく機能するために、政府が必要となる。前近代は共同体が個人より先にある。義務の対価として権利が個人に共同体から賦与されている。しかし、近代は個人主義である。政府が社会のために働くとして個人はその権利の一部を信託する。政府は権利の対価として個人や社会に義務を負う。
近代の徴税はこのジョン・ロックの思想に基づく課税協賛説を論拠にしている。前近代と違い、近代は権力が税を人々から取り立てているのではない。政府の活動に社会が協賛して納税するとしている。もちろん、実際には政府は人々に納税をビむとしている。しかし、課税協賛説が根拠であるから、納税者は税の使い道が適切であるかどうかを政府に問いただすことができる。近代の仕組みはこのように理論によって基礎づけられている。近代を批判するためには、それを十分に理解していなければならない。
前近代では、共同体の規範に即した生き方をすることが幸福である。けれども、近代は故人に価値観お選択が委ねられている。一見バラバラのようであるが、いずれの価値観も幸福を目指すことに違いはない。それは満足として同じなのだから、計算することができる。社会全体として幸福の総量が増え、不幸の総量が減ることが望ましい。政府はこれが実現するように働くことで社会のためになる。これがジェレミー・ベンサムの言う「最大多数の最大幸福」である。
近代小説はこうした近代社会を舞台にして、近代人を登場人物にする。この近代人は等身大の人物である。こういった凡人が文学作品の主人公たり得るのは、その内面にドラマがあるからだ。価値観の選択が個人に委ねられている以上、内面は人それぞれである。そこにドラマがあり、同じく近代人である読者も感情移入する。
ヘンリー・ジェイムズの小説は事件や出来事が特に目立って怒らない。けれども、主人公をめぐる心理描写に溢れ、内面のドラマが展開されている。それは近代小説の理論に忠実な作品である。しかも、彼は肝心の場面を描かない。出来事がピークを迎えそうになると、小津安二郎のように、その前で書き進めることをやめる。以後のことは読者の想像力に任せている。こうした創作術により、彼は「ザ・マスター」と評されている。
第3章 気分の呪縛
一方、志賀直哉の小説には心理描写が乏しい。志賀の小説を形成する重要な側面は父との対立だと考えられている。確かに、『大津順吉』・『或る男・その姉の死』・『和解』の中編三部作は父と子の対立・和解をめぐって書かれている。また、他のいくつかの短編作品にも父の影が色濃く映し出されており、唯一の長編小説『暗夜行路』にしても父の姿が見え隠れしている。こういう父子の対立が物語の中心にあるのだから、それをめぐる葛藤や摩擦など内面のドラマが展開されるのかと思いきや、心理描写と呼べるものはない。
それどころか、三部作に原因さえはっきりと書かれていない。『大津順吉』や『或る男・その姉の死』において、主人公は、父に対して、何の説明もなく「不快」をつのらせていく。ところが、『和解』では主人公はいつのまにか「調和的な気分」になって父と和解する。主人公の父との対立が「不快」から始まり、「調和的な気分」によって和解してしまう。なぜ主人公はこうなっていくのかがまったく読者にはわからない。感情移入の入り口がない。その舌たらずのため、物わかりのよい人はともかく、読者を「調和的な気分」にさせることなく、「不快」にさせてしまう。
すでに述べた通り、近代において個人は自身の価値観に基づき、快を求め、不快を避ける幸福追求が認められている。誰もが「不快」の状態は嫌なもので、そこから抜け出したいと思うものだ。それを文学作品に描くことに問題はない。しかし、立脚する価値観が異なる以上、快・不快の根拠を示す必要がある。規範を共有していないのだから、言わなくてもわかるだろうとはならない。示さなければ、なぜ「不快」なのか、その「不快」はどのようなものなのか、この「不快」は他の「不快」とどう違うのかを作家であるなら書いてしかるべきだ。こういう粗雑を見逃してきたとしたら、文学者たちはあまりにぬるいと言わざるを得ない。
『或る男・その姉の死』(1920)の主人公は足尾鉱毒事件に対して父へ反発する。しかし、それ以前から父と子はすでに対立し、足尾鉱毒事件はきっかけにすぎず、両者の対立は世代的もしくは思想的なものに根ざしていない。志賀は1887年の生まれなので、この作品を書いた時、35歳を超えている。足尾鉱毒事件が特に世間の耳目を集めるのは1890年代である。10代の頃の自分自身をこの年齢になって振り返って書いているとは思えない内省の乏しさだ。ヘンリー・ジェイムズであれば、肝心の場面は飛ばされるものの、そこに至る過程が綿密に描写されている。しかし、志賀直哉の記述はキセルである。その時の感情をただ記しているだけで、読者は想像力を働かせようがない。
それで結局、いやこんな議論をするまでもなく現実には、父はやや居心地悪く存在し、母は子どもを外から眺めてはらはらする、そんなものだろう。むしろ、そんなもんだと思っていれば、家庭幻想が肥大することもなかろう。父はなにかの規範になろうと無理することもなかろうし、母はすべてを包みこもうなどと苦労しなくてすむ。そして、その間に、子どもが彼の領分として、管理の抑圧に耐える堡塁を、彼の心の中に築いてくれることを、期待するよりあるまい。それは、子の領分に属するのであって、父も母も干渉することはできぬ。父にとっても母にとっても、そしてなにより子にとって、『父とはなにか』とか『母とはなにか』と、問い直さねばならないのは、不幸なことである。父が自然に父であってしまい、母が自然に母であってしまい、そして子は、父とか母とかを意識しないですむ、それは古きよき時代の幸福にすぎないのだろうか。
(森毅『父と母と、そして子と』)
ほぼ同時期に発表された夏目漱石の『道草』(1915)と比較すれば、そのことははっきりとする。“Where we born, we must die-whence we come, whither we tend? Answer! ”という青年期特有の根こぎ感を『断片』に記していた漱石の『道草』において、家族間の対立が思想的・世代的なものとして明確に描かれている。海外留学帰りで大学教師の主人公健三の「不快」はたんに「不快」としてのみ表出されない。自己に対しては存在として、家族に対しては自己の相対性の認識として、つねに二重に対象化されている。
『道草』に対して、『和解』(1917)では、「不快」はただ「不快」としてのみ放出される。次のような記述を目にする時、父と子の和解の原因が読者には不明瞭であると言わざるを得ない。
自分は自分が段々に調和的な気分になりつつある事を感じた。これでいいかしらと云う気も少しはした。然し今まで不調和よりは進んだ調和だと考えた。そして自分も好人物の好運ばかりを何時迄も書いてはいられないと云うような事も考えた。
自分の調和的な気分は父との関係にも少しずつ働きかけて行った。然し或時、例えば妻と一緒に上京して電話で祖母を見舞うと、丁度父が留守だから直ぐ来て呉れと母が云う。自分達は電車で直ぐ麻布へ向う。そして門を入ろうとすると其所に立って待っていた隆子が駆けよって来て、小声で「お父さんがお帰りになったのよ」と云う。自分達は門を入っただけで誰にも逢わず、直ぐ引っ返して来る。こう云う場合、流石に自分の調和的な気持も一時調子が変る。然し又或る時、人の口から、父が自分の妹達などの事でジリジリと苛立って気むずかしい事を云う噂などを聴くと、父のそういう気分の根が猶且つ自分との不快にある事を考えずにはいられない点で、そして今の自分が自分だけで調和的な気分になりかけているのにという気のする点で、段々年寄って行く父の不幸なその気分に心から同情を持つ事もあった。
父も子もいい大人であるから、「悩み」や「苦しみ」、「苦悩」ならわかる。ところが、主人公は「不快」という気分を言っている。父と子の対立が「気分」を原因にしているというわけだ。幼稚な説明である。人間関係に相性があることは確かである。また、不和が蓄積されてきて理由を一口で言い表せないこともある。けれども、父と長年対立してきた30歳過ぎの男がその原因を「不快」と答えるとしたら、どうかしている人と思われるのが関の山である。
しかも、「自分」の父への「同情」も幼い。いろいろあったが、自分も親になって見て父の気持ちがわかるようになったと共感するなら理解できる。しかし、「自分」が「同情」しているのは父自身ではない。同じ「気分」の呪縛に父があるので、「同情」している。「気分」を離れて、「自分」は父に「同情」することはない。こうした説明からは父と子の対立の原因は「気分」であると了解するほかない。自分も世界も「不快」や「調和的気分」という意味を表現する記号である。「気分」があたかもエーテルのごとくに実体化されている。
この主人公の精神性はジャン・ピアジェの嗜好発達段階説の第2段階である「前操作段階」に相当する。年齢で言うと、これは2~7歳で、他者の立場に立って考えることができず、自己中心的という特徴がある。主人公には教育歴も知識もある。けれども、精神的な発達は幼児レベルである。
なお、これは発達障害の指摘ではない。発達障害に当たるかどうかは専門家による検査・診断を必要とする。精神疾患火も同様であるが、非専門家が安易にそうだと決めつけるべきではない。実際、志賀は認知行動に偏りがあるけれども、特にそれを思わせるような学習上・社会上の困難さは認められない。功成り名を遂げても、インタビューを含めたメディア上での言動から精神性や道徳性の面において幼い人物も少なくない。ここでは志賀をそうしたタイプの一人として扱っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
