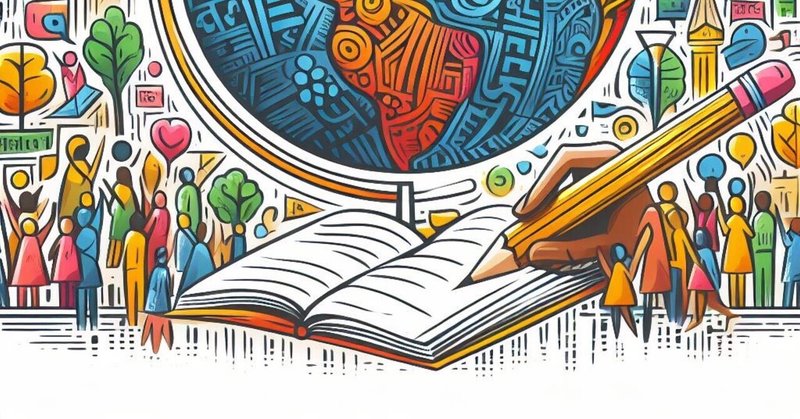
ナラティブとクリティシズム(3)(2023)
4 批評なき物語
第二次世界大戦後、実存主義が世界的に流行する。この思想におけるもっとも重要なキーワードの一つが「主体」である。近代人は自由で平等、自立した主体的存在である。個々人は相互に同じ主体として扱わなければならない。しかし、現代社会において客体、すなわち物や道具と見なされているのではないかと実存主義は真の主体のありようを語る。そこで、思想家は「アンガージュマン」に取り組んでいる。それを批判して登場した構造主義は「主体」が同一性の暴力を秘めているとして「差異」を提唱する。フェルディナン・ド・ソシュールの「恣意性」に触発された彼らは「社会参加」ではなく、「差異」の実践として「異議申し立て」を試みる。
その後の展開は大きく二つの流れがある。一つはポスト構造主義で、これは構造主義のラディカリズムである。構造主義の異議申し立てを徹底化した彼らが見出した世界がポストモダンである。もう一つは主体の復権である。彼らは構造主義の批判を踏まえ、公共性の再検討に臨む。
この二つの流れに共通するキーワードが「他者」である。「他者は」自己と非対称的な関係にある。それは自己との同一化を拒む。そこで求められるのが倫理である。長らく無視されてきた宗教的な理論や概念を思想家たちは盛んに引用し始める。
しかし、90年代に入ると、状況が変わる。「他者」をキーワードにして思想が展開されていくにつれ、思想家はそれが単数ではないことに気がつく。他者にも他者がいる。それは複数であり、空間は言うに及ばず、過去にも未来にもいる。他者の連鎖は無限に続く。そうなると、他者を一般化して論じることが困難である。各々の他者に個別対応する必要がある。これにより思想が錯綜する。当然、大思想家は登場しにくい。専門性の高い研究者が協同して個々の諸問題を通じて思想を語らざるを得ない。
このような状況の下、無数の物語が噴出する。社会の流動性から国家や民族にアイデンティティを直結させる個人が客観的な論拠に乏しい短絡的な物語を共有していく。傍から見ればまがまがしい妄想や狂信的な陰謀論でしかないが、同質集団の中でそれは極論化する。ナラティブは価値観に基づいているため、行動を促す。行動は理論ではなく、感情を共有させる。グロテスクなナラティブはその過激な行動により社会を分断化し、反近代的な価値観を支配的にしようとする。
奥泉光は第二次世界大戦をめぐる単純化された「物語」を批判する。その上で、彼は、『朝日新聞DIGITAL』2023年8月15日6時30分配信「『新しい戦前』の今こそ、加害の歴史忘れず『経験化』を」において、そうした物語の危険性を回避するために「批評」が必要だと次のように述べている。
戦争「体験」はたくさんあるが…
――芥川賞を受賞した「石の来歴」をはじめ、「グランド・ミステリー」「神器」など、アジア太平洋戦争についての小説を発表してきました。
「日本だけで310万人、アジアなど交戦国を含めて2千万人超とも言われる犠牲者を出した巨大な体験です。繰り返し参照し、こだわり続けるべき歴史ですが、日本人にとってなお未解決の課題をはらんだ対象だからでもあります」
「僕が書いてきた作品は、いわゆる歴史小説ではなく、あくまでも日本が現在直面している問題に迫ってきたつもりです。別の言い方をすれば、私たちは1945年8月15日の前後で質の違う時間を生きているわけではない、ということを常に出発点にしています」
「作品を書くにあたって、参考のために将兵の証言や様々な記録、作家の戦中日記や戦争文学を読み込みました。そこで痛感したのは、戦争『体験』は有り余るほどあるのに、日本社会はそれを十分に『経験化』できていない、ということです」
――「経験化」ですか。
「体験は繰り返し問われ論じられることで、はじめて国民の経験、すなわち歴史になります」
「先の大戦の『失敗の本質』については戦後、様々な識者が論じてきました。戦闘死よりも餓死や病死が多かったとされる無謀な作戦や、補給軽視に表れる非合理性の問題。あるいは、政治学者の丸山真男が指摘した、誰も自分が戦争を始めたという自覚がない『無責任の体系』の病理もそうです。戦犯として訴追された人の多くが『自分は戦争などしたくなかった』などと言い始める。戦争がまるで天災だったかのようです」
「でも、その『失敗』を国民集団として反省的に言語化し、教訓として共有したことは、一度もなかったと言えます」
「犠牲者」という「物語」に安住してきた
――なにが経験化を妨げてきたのでしょうか?
「大きな理由は、戦後長らく、悪いのは軍部であり民衆と天皇はイノセントだったという『物語』が流布してきたことです。これはGHQ(連合国軍総司令部)と政府の『合作』ですが、定着させたのは、小説をはじめとする文化芸術作品でした」
「戦後広く読まれ映画にもなった『二十四の瞳』や『ビルマの竪琴』などの文学作品は、この欺瞞(ぎまん)的とも言えるビジョンを強く映しています」
「ここでは、植民地支配の側面が見事なまでに消去されている。アジアは登場するものの、あくまで幻想の表象としてであり、兵士も国民も犠牲者であるという描き方です。感動して泣けるのは確かなんですが、徹頭徹尾、戦後的な語りの位相に無自覚に埋没してしまっている」
「善玉と悪玉の二元論も、物語というものが抱える基本的構造の一つです」
――国民の側も、そうした物語を積極的に受け入れてきた面がありますね。
「負の歴史から目を背けたい願望は、いわゆる右派だけのものではありません。国民的作家と言われた司馬遼太郎も、日本近代史で昭和前期だけが「異胎」だったと書いています。
「輝かしい明治と明るい戦後に挟まれた狂った戦前という『司馬史観』が本人の意思を超えて独り歩きしたのは、国民にとって、加害性を忘却し犠牲者としての自画像に安住できる好都合なものだったからでしょう」
「昭和天皇のいわゆる『人間宣言』が、明治元年の『五箇条の御誓文』への言及から始まっているのは示唆的です。軍部が踏みにじった、万機公論に決すべしという明治の精神が、戦後民主主義と接合されるわけです。占領体制下で作られたこの『物語』は、戦後80年近く経ったいまもなお、続いています」
――ただ、人間にとって「物語」は、認識の枠組みの一つでもありますね。
「因果関係でものごとを把握している私たちは、物語なしでは現実を認識できない。ものを書く、語るという行為そのものが、避けがたく物語を呼び込んでしまいます」
「歴史の叙述も、史料や事実に基づいているものの、それ自体が一種の物語です。ただ、優れた歴史書ほど、面白い小説と同じく、複数の視点や声を含有し、多層性がある。一つのテキスト内に『対話』があるんです。占領期の歴史を描いたジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』も、そうした作品の一つだと思います」
「つまり、大事なことは、単一の物語に世界を閉じ込めないこと、固着化し硬化した物語を批評していくことです」
「実は小説も本来は、物語に限りなく近接しながら、物語そのものではなく、それを批評し相対化していくジャンルなんです」
単純で単一の「物語」は危うい 対話と批評を
――ただ、単一の物語の方がわかりやすく、受け入れられやすい。
「そうなんです。わかりやすい物語東京新聞
で世界を捉えたいというのは、人間の基本的欲求です。それに応える物語がたくさん供給されてきたし、それは日本だけの問題でもない」
「ただ、先の大戦について言えば、直接の体験者がいなくなる今後は、いっそう物語化される時代を迎えます。特攻隊を美化するような単純な物語も増えていくでしょう」
「文学は、言葉以外に何ら裏打ちされるものがないにもかかわらず、人の心を揺さぶり動かしてしまう。非常に危険なものです。実際に多くの文学者が戦時下、体制賛美に利用されたり、加担したりしてきました。危険物を扱っているということにあまりに無自覚な作家が少なくない」
「小説家として、この流れに断固抵抗したいと思います。奥泉の小説はわかりにくい、といくら言われようとも(笑)」
――小説における物語だけでなく、歴史も相対化して見ていく必要があるということですね。
「そうです。ただ、歴史を相対化するというのは、超越的な視点から歴史を見るということではない。歴史修正主義も含めた様々な立場や歴史認識がタコつぼ化して乱立すればよい、ということでもありません。歴史の叙述が物語性から逃れられない以上、それぞれの歴史観について批評性、対話性を持つということです。歴史は、現在からの過去に対する問いかけでもある。そもそも原理的に対話性をはらんでいるものです」
示唆に富むインタビューである。奥泉光は戦争を題材にした『石の来歴』や『グランド・ミステリー』、『神器』、『浪漫的な行軍の記録』などを発表している。また、歴史学者の加藤陽子と共著『この国の戦争』も刊行している。個々の体験を一つの単純な物語に回収させないような文学活動を続ける。
その奥泉は「実は小説も本来は、物語に限りなく近接しながら、物語そのものではなく、それを批評し相対化していくジャンル」と述べている。彼にとっての「物語」は「ロマンス」を指している。しかし、すでに述べた通り、現代小説は近代小説の経験を踏まえた復権したロマンスである。この件に限らず、「物語」の危険防止に「批評」が必要だという主張には同意するものの、内容には再構成が要る。
奥泉によれば、「物語」の危険性を回避するために「批評」が必須である。ただ、彼の「批評性」は「対話性」を意味している。時として相対立する複数の声の対話が一つの物語の絶対性を斥ける。これは近代におけるコミュニケーションを通じた公共性の形成の言いかえである。個々の「体験」の社会にとっての「経験化」が一つの物語の絶対化を防ぐという主張を彼は「批評」に要約している。しかし、それは「公共性」である。奥泉の意見は近代の基礎の再認識の提唱と理解できる。
批評は、むしろ、『二十四の瞳』や『ビルマの竪琴』の暗黙の前提の明示化の方に認められる。それは戦後長らく流布してきた「悪いのは軍部であり民衆と天皇はイノセントだったという『物語』」に依拠し、そこでは「植民地支配の側面が見事なまでに消去されている。アジアは登場するものの、あくまで幻想の表象としてであり、兵士も国民も犠牲者であるという描き方です。感動して泣けるのは確かなんですが、徹頭徹尾、戦後的な語りの位相に無自覚に埋没してしまっている」。批評は筋や登場人物を必ずしも必要としない。そのため、具体的・個別的なものを抽象化・一般化してその暗黙の前提を明示化することができる。『批評性』は「対話性」ではなく、メタ認知である。「物語」の相対化は「別の物語」を提示することではない。
『ビルマの竪琴』は、内容以前にそのタイトルが「植民地支配の側面が見事なまでに消去されている。アジアは登場するものの、あくまで幻想の表象」であることを告げている。ビルマ(ミャンマー)の仏教は上座部で、僧侶が音楽を楽しむことを禁止している。出家僧が竪琴を弾くことなどありえない。
小説家と批評家ではものの見方が違う。前者はある出来事を作品化しようとする時、場面や登場人物、筋を考えるなど具体化・個別化の作業を試みる。一方、後者は出来事を抽象化・一般化して体系に位置付けたうえで論じる。奥泉光は小説家なので、相対化を「対話性」に求めている。それは物語に対して具体的・個別的な別の物語を提示することである。しかし、批評家にとって相対化はメタ認知に基づく対象化である。物語の暗黙の前提を明示化し、抽象化したものを体系の中で位置づけて一般化することだ。
「批評(Criticism)」は対象を「評し(Appreciate)」、「体系付け(Systematize)」、他者に「納得(Empathy)」させる行為である。作品の出来を「判断(Administrate)」したり、他の作品との優劣を「評価(Evaluate)」したりするだけではない。「感想(Book Report)」や「印象(Impression)」にとどまらず、他者と認識を共有するために、論証を示して体系に意味づける必要がある。その際、「理解力(Comprehension)」・「洞察力(Insight)」・「方法論(Methodology)」・「全体認識(Whole Understanding)」・「コミュニケーション能力(Communication Capability)」が求められる。こうした属性により批評は創作や鑑賞のメタ認知たり得る。
物語と批評の関係は現代医療におけるNBMとEBMのアナロジーとして理解できる。現代の医療は「EBM(Evidence Based Medicine)」と「NBM(Narrative Based Medicine)」の二つのアプローチを方法論としている。それは患者と医療関係者が共通の目的に向かうチームだという発想に立脚している。治療を進めるに際して「エビデンス」もしくは「ナラティブ」を関係者は共有する必要がある。
「EBM」はエビデンスに基づく医療である。「エビデンス」は科学的根拠、より正確にはインパクトファクターの大きな学術誌に発表された研究成果を指す。このアプローチでは、それを重視しつつ、専門家の経験・知識と患者の価値観を総合的に判断して治療方針を決める。
一方、「NBM」はナラティブに基づく医療である。「ナラティブ」は闘病記を含め患者の体験談を指す。特定の患者における疾病の具体的背景を理解し、個別的な最適医療方針を決める。エビデンスは全般的に定量的知識である。抽象的・一般的であるため、汎用性は高いものの、個々の患者にとってそれは因果性ではなく、相関性として適用される。しかし、患者の主観的認識の村長が個別的・具体的な医療行為には必要だ。今日、EBMが中心であるが、NBMはそれを補完するためのものであり,互いに対立する概念ではない。
ナラティブが人間にとって必要だとしても、危険性を自覚していなければならない。そのために、批評は不可欠だ。しかし、文学の状況は医療と逆である。「NBL(Narrative Based Literature)」が圧倒的で、「CBL(Criticism Based Literature)」の活動はわずかだ。5台文芸誌は2023年10月現在、新人を対象にした小説の公募を行っているけれども、批評にそれはない。『文藝』に至っては、掲載作品は小説のみである。「文学は、言葉以外に何ら裏打ちされるものがないにもかかわらず、人の心を揺さぶり動かしてしまう。非常に危険なものです。実際に多くの文学者が戦時下、体制賛美に利用されたり、加担したりしてきました。危険物を扱っているということにあまりに無自覚な作家が少なくない」。それは、批評を軽視しているのだから、当然の帰結だろう。グロテスクな物語が社会を脅かしている現状に文学は加担している。
A narrative is like a room on whose walls a number of false doors have been painted; while within the narrative, we have many apparent choices of exit, but when the author leads us to one particular door, we know it is the right one because it opens.
(John Updike)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
