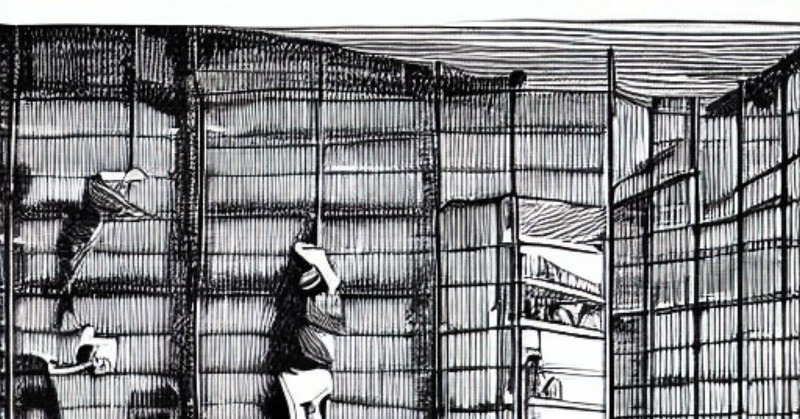
惰性の閉じ込め、あるいは社会的収容(2014)
惰性の閉じ込め、あるいは社会的収容
Saven Satow
Jul. 27, 2014
「人にとって最も恐ろしいのは、惰性で日を送ることである」。
西堀栄三郎
ミシェル・フーコーは、1650年以降、ヨーロッパ社会において犯罪や狂気に対する「大いなる閉じ込め(Great Confinement)」が始まったと指摘している。それが妥当かはさておき、近年、日本で刑務所や病院における「惰性の閉じ込め(Routine Confinement)」が問題になっていることは確かだ。それは収容しておく根拠が乏しいにもかかわらず、制度変更・整備が十分でないなど社会的理由から入所や入院が継続している状態である。「社会的収容(Social Confinement)」とも呼べよう。
退院後の受け皿がないなど治療目的以外の理由で病院に長期に亘って留め置くことを「社会的入院(Social Hospitalization)」と総称される。特に深刻なのが精神病院での事例である。
今日、収容中心の精神医療から地域精神医療の重視へと移行している。入院は急性症状の治療や自殺の防止、投薬治療の効果の向上などの目的に限り、抑制的に行われなければならない。しかし、収容中心時代には措置入院や同意入院など社会防衛の意図を持った強制入院が精神衛生法で認められている。この時期に収容された患者を中心に社会的入院がしばしば見られる。
欧米で第二次世界大戦以前に採用されていた考えが日本では戦後になって浸透する。戦前の日本は精神障碍者が家長の権限と責任において私宅監置、すなわち私宅の敷地内に監禁されていなければならないとされている。戦後、それが禁止されて、各都道府県に精神病院の設置が義務づけられ、行政が精神保健に権限と責任を持つようになる。こうして収容中心の精神医療が始まる。他方、戦後の欧米では地域精神医療へと転換する。その状況の中でフーコーは病院を通じた閉じ込めの歴史を明らかにしている。しかし、彼が取り組んでいる同時代に日本ではその閉じ込めが強化されていく。
1984年、宇都宮病院事件が発覚、国際的に日本の精神医療の後進性や人権意識の低さが問題視され、政府もようやく世界標準へと方針を変更する。87年に精神衛生法を抜本的に改正した精神保健法を実施、95年には精神保健福祉法へとさらに改められる。
しかし、日本の精神病院には社会的入院が今も少なくない。5年以上の長期入院患者の3割がそれと推定されている。これには収容中心時代に入院し、社会復帰の機会を逃した高齢者が多いこともある。入院患者で最も多い疾病は統合失調症である。これは15~35歳の間に発症するのがほとんどであるから、入院した年齢も比較的若い。退院後の適切なケアが確保できなかったり、身寄りがなかったり、差別・偏見のために身内が身元引受を拒否したりするなどして入院せざるを得ない。
ただ、それだけでは説明できないことも多々ある。2014年7月24日NHKテレビ放映『クローズアップ現代』の「精神科病床が住居に? 長期入院は減らせるか」は精神科における社会的入院の実態について迫っている。番組では40年入院していた元患者を中心に展開されているが、人生の半分以上を病院内ですごす人は決して珍しくはない。
この7月、厚労省は社会的入院の解消に向け、病床の大幅削減の方針を打ち出している。ところが、退院者の受け皿として削減した病床を居住施設に転換することを認める。敷地内での退院は地域医療という現在の世親衛生の理念と矛盾する。そこで患者や家族ら3200人が国に対し方針撤回の抗議声明を示している。「惰性の閉じ込め」がこれでは継続してしまう。
病床数が多いから社会的入院が減らないと厚労省は言わんばかりだ。日本の精神病院の大半が民間病院である。長期入院によって病床が使われていると、経営には助かる。地域精神医療を病院が進めたくても、現行制度では長期入院の方が利益につながる。収容中心時代は終わったはずなのに、長期入院患者が新たに生産されていく。科学的根拠が失われたにもかかわらず、旧来の制度・体制が惰性のまま維持されているため、社会的入院が解決されない。今回の厚労省の方針はそこに手をつけていない。
次に「社会的入所」(Social Imprison)に話を進めよう。この概念は一般的ではない。これは主に高齢受刑者の問題である。社会構造の変化が予測されるにもかかわらず、それに対応した社会復帰の整備が不作為・不十分であるため、累積的に長期入所している状態のことである。
近年の受刑者の特徴の一つに高齢者の増加が挙げられる。少々古いが平成16年度版『犯罪白書』は高齢受刑者問題についてよくまとめてあるので、これを参考にする。全受刑者に占める60歳以上の高齢者比は年々上昇している。60歳以上の新受刑者は1973年には341人(1.3%)であったのに対し,2004年には2,929人(9.3%)と大幅に増加している。また、欧米諸国と比較してもこの比率は高い。英仏独は60歳以上が2.6~3.6%,米国は55歳以上の者が3.1%である。日本の人口の高齢化率が他国より高いとしても、突出している。
高齢受刑者の罪状の6割以上が窃盗と詐欺である。また、高齢受刑者には入所歴が多い比率が大きい。年齢が高くなればある程度再犯が増えてくるのも当然だが、「6度~9度」と「10度以上」の多重累犯者の比率が非常に大きい。
個々の事情はあるけれども、こうしたデータからこのようなシナリオが思い浮かぶ。高齢者には雇用の機会が少ない。また、貧しかったり、入所したりすると、人間関係が狭かったり、社会保障などの知識が乏しかったりする。失業すると、ホームレスになり、犯罪に手を染め、刑務所に入って、更生保護施設を経た後、再びホームレスへ舞い戻るとい悪循環に陥る。この簡に基礎体力の低下や健康状態の悪化、社会的な孤立化などが進む。
このような高齢者は、所内でも、移動には車椅子が欠かせなかったり、刑務作業も座ったままだったりするケースも少なくない。入所回数が多ければ、仮釈放が認められることは少ない。こうなると、社会復帰しようという気力も失せてしまう。刑務所は高齢者の介護施設と化す。高齢受刑者は「社会的入所」をしていると言える。このような現状では刑務所を高齢者に対応できるユニバーサル・デザインで設計せざるを得なくなったり、刑務官に介護士の資格が必要になったりするだろう。
高齢化の進展は今に始まった事態ではない。かなり以前から予想されている。ところが、それに対応する制度の整備が十分ではない。しかも、蓄えの差などによって高齢者の間で経済格差が拡大する。高齢化に応じた社会保障制度を構築しておかなければ、犯罪に向かう高齢者も増えると予想される。犯罪が成功しなくてもかまわない。自由は制限されるが、無一文でもムショなら飯が食える。
社会的入院にしろ、社会的入所にしろ、社会的収容は惰性の産物であることは共通している。科学的根拠が失われたり、社会的構造の変化が明らかに予想されたりして、それに対応するために必要とされる制度・体制の変更が不作為であることによって、個人や集団が閉じ込められる。惰性であるから積極的な意味がなく、逆に、社会にとってその閉じ込め自体が認知されにくい。想像力も刺激せず、報道によって初めて社会的収容を知るというのが世間の一般的な認識である。
この社会的収容は「社会的排除(social exclusion)」の一種とも考えられるだろう。人々は社会に参加・帰属している。しかし、貧困や不安定な立場など何らかの原因で個人または集団が社会から排除されることがある。この状態が社会的排除である。社会的収容は閉じ込めであるから、排除されている。
ある施設に長期間収容されれば、その人の社会性が弱体する。社会復帰の機会も逃されてしまう。彼らの収容生活にも費用が要り、それは公金によって支出される。施設外で暮らしていた方がかかるコストはおそらく低い。社会的収容はその死によって最終的に解決される。その埋葬や供養も、場合によっては、税金が使われる。ただ、社会的収容の最大の問題点は費用よりも当事者・関係者以外にとって他人事にしてしまい、人間の尊厳が尊重されていない点だ。閉じ込めが続けられている間に、誰からも見捨てられた気になり、社会復帰しようという気力がしなわれる。自立した思考がなくなってしまう。近代は自由で平等、自立した個人によって形成された社会が理念である。その近代は人権を尊重する。人権は人間の尊厳の法的保障である。社会的収容は人間の尊厳への冒涜である。
惰性の閉じ込めの最たる例は日本におけるハンセン病患者の隔離政策だろう。1941年に治療薬が開発されて以降、国際的に隔離政策が廃止されていくのに、日本はそれに逆行する。この方針を政府が正式に謝罪するのは2001年、すなわち21世紀のことである。ある時代において科学的知見に基づき、収容が適切とする制度が運用される。しかし、その後、隔離の科学的根拠に決定的反証が加えられ、制度変更の必要性が明らかになる。ところが、国際的流れから見てみっともないので改革提言が政府やその周辺から発せられたとしても、絵に描いた餅に終わる。既得権益の保持や官僚主義的前例主義、直観主義的発想、無関心によって制度が維持される。かくして惰性の閉じ込めが続く。ハンセン病はまさに典型である。
惰性の閉じ込めはハンセン病だけではない。すでに言及した通り、社会的収容として多くの事象でも見られる。惰性は当事者意識の希薄から生じる。それは世間にとっていつでもなかったこととされかねない。しかし、人間の尊厳の尊重は他人事にできる問題ではない。
〈了〉
参照文献
石丸昌彦他、『精神医学特論』、放送大学教育振興会、2010年
大越義久、『現代の犯罪と刑罰』、放送大学教育振興会、2009年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
