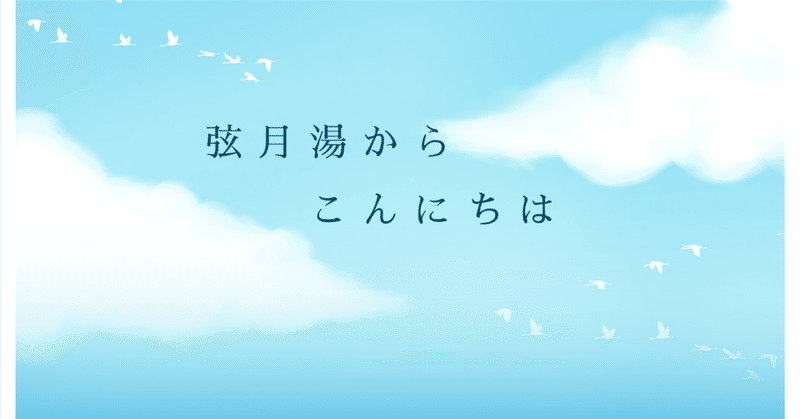
小説「弦月湯からこんにちは」第1話(全15話)
【あらすじ】
仕事も、住処も、すべてを失った。拾われた先は、銭湯だった。
世界的なツァイトウイルスの流行によって、仕事も住処も失った山口壱子。ある朝、意を決して外に出た壱子が辿り着いたのは、ガウディへのオマージュに満ちた銭湯「弦月湯」。住み込み募集の張り紙を見つけた壱子は番台にいた小柄な女性、若月いずみに思わず声をかける。
いずみの従弟であり、かつて壱子のもとで働いていたノンバイナリージェンダーのデザイナー・若月暦との再会、そして弦月湯の再建を通じて壱子の心は蘇り始める。
喪失から再生の過程をゆるやかに描く、中編小説。
*
第1話
*
──「お目覚めかね、イチコ」
いつもの低いしゃがれ声が聞こえる。肩に置かれた手は、ずっしりと重い。見上げないでも分かっている、そこには獅子頭の男がいる。舌なめずりしながら、私を待ち構えている、獅子頭の男が。
あたりを見回す。いつもの白い部屋にいた。床も、壁も、天井も、どこもかしこも白くて、つるつるしている。換気扇が回るぶーんという音が、薄く聞こえる。夢の中だとはわかっていても、あまり気分のいいものではない。私は、ため息をついて、高い天井を見上げた。蛍光灯がチカチカと揺れている。
「私にとっては、こっちが夢の中なんだけどね」
「イチコにとって夢であろうと、現実であろうと、儂にとってはどちらでも構わない。ずっと待っていた、イチコが儂のところまで降りてくる時を」
獅子頭の男は、私を抱きすくめようとする。私はその手を払い、立ち上がる。獅子頭の男をじっと睨む。ライオンの頭を持った長身の男は、喉から唸り声を発する。
「そう怖い顔をするな。儂はお前、お前は儂なのだから」
「私は決して、お前のものになるつもりはない。子供の頃から、そう言っているだろう」
獅子頭の男は、低く嗤った。そして、埃をうっすらとかぶった蓄音機の前に進む。
「そう怖い顔をするな」
獅子頭の男はレコードに針を落とす。ややあって、蓄音機特有のざざっ…というノイズと共に、『茶色の小瓶』の陽気なメロディが流れ出す。子供の頃から大好きだったグレン・ミラーだ。
「踊ろう、イチコ。儂と一緒に」
獅子頭の男は、私の手を取り、恭しくお辞儀をした。そしてリズムに合わせて体を揺らし始める。獅子頭の男は目を閉じて、うっとりと音楽に感じ入っているようだ。
私は男を突き飛ばし、部屋の隅に走る。けれど、走っても、走っても、部屋の隅にはたどり着かない。息が苦しい。私は立ち止まり、肩で息をする。
「逃げることはできない、イチコ。儂はお前、お前は儂なのだから」
獅子頭の男の声が追いかけてくる。やめろ、やめろ、私を支配するな。お前は私の夢なのだから。そう叫びたいのに、喉の奥に真綿がつめられたようで、声が出ない。舌が、もつれる。足も、もつれる。全てが、もつれ、ぐんにゃりと絡まっていく。
やがて、視界が歪む。床と、壁と、天井の境界線がなくなって、まるでカフェラテをかきまぜていくような、マーブルの渦に呑み込まれていく。私は叫び声を上げようとする。けれど、やはり舌は動かない。うぐ、うぐあ、という意味のない喘ぎ声と涎しか出てこない。
「忘れるな、イチコ。儂はいつでも、ここでお前を待っているぞ」
獅子頭の男の、低くしゃがれた唸り声が響く。いや、いや、と私は頭を振って、付き纏うその影を振り払おうとした。
……目をぱちっと開く。全身が汗だくだ。気がつくと、寝苦しかったのか、布団を蹴飛ばしていたらしい。手を天井に伸ばし、グーパーを繰り返して、指の感覚を確かめる。そうだ、こっちが現実。私は深く、深く、息を吐く。全身が心臓になったように、動悸が激しい。
獅子頭の男の夢を見るようになって、どれくらい経つだろう。最初に、あの白い部屋に行ったのは、小学校3年生の時のことだった。クラスの中で、ささいな事で孤立してしまった私は、気がつけばあの白い部屋の夢ばかり見るようになっていた。そして獅子頭の男は、私の成長と共に獰猛に育ち続けている。ドラマのように継続していく夢、現実を侵蝕するようなもう一つの現実に恐れを抱いて、病院に真剣に救いを求めたこともあった。今も継続して薬を飲んではいるものの、改善する兆しはまったく見られない。ひとつだけ分かっていることは、私が精神的に不安定になっている時ほど、あの白い部屋に行きやすいということ。私は、深いため息をついた。
布団から、のそのそと這い出る。立ち上がって、カーテンを開く。外は薄曇り。今は何時なのか、さっぱり分からない。私はスウェットを脱ぎ、タオルで体を拭う。水をひと口飲み、テレビをリモコンで点ける。天気予報で、関東地方の地図が大きく映る。今日は、午後から晴れ。テレビの時計によると、もうすぐ朝の7時になるらしい。本当なら、もう家を出る時間だったのにね、と思いながら、私は大きなあくびをした。もう、どこにも私の職場はない。そして、今月末には、この家も出て行かなくてはならない。私はこれらの事実を淡々と反芻しながら、水をもうひと口飲んだ。
今年に入って、しばらくしてから、例のツァイトウイルスの影響が出てきた。最初は中国の一都市だけの限定的な流行かと思っていたウイルスは、気がつくと世界中に伝播していった。遠巻きに眺めていた日本が慌て始めたのは、2月の頭から。神戸港に停泊していた豪華客船の中でクラスターが発生してしまい、思わぬところで自国の対応が問われることになってからのことだった。
3月になると、日本国内の感染者数も増えていった。あらゆるイベントが中止・延期となり、オンラインでの活動が活発化していった。そして、多くの仕事はオンラインに切り替わっていった。けれど、オンラインでは対応出来ない仕事もある。私が携わっていた飲食業界は、まさにその代表的な業種といえるだろう。関東地方を中心に、パエリアや小皿料理などのスペイン料理を提供していたファミリーレストランのチェーンで、東京の北西にある北三日月町店の店長を務めていた私は、感染対策の徹底と同時に、売上げの維持という難題を本社から突き付けられた。頭を抱えながら、毎晩2時3時までパソコンと向き合い続けた。けれど、政府から非常事態宣言が発令され、飲食業界にも対応が求められると、大部分の店舗を閉鎖するという決断を、本社は早々と下した。その中には、ツァイトウイルスの流行前から売上げが思うように伸びなくなったうちの店も入っていた。それと同時に、私が入っていた社員寮も閉鎖になるという報せが入り、2ヶ月後の月末までには退去するようにとの命令が出たのだ。
この乱暴な取り決めに対して、当然ながら一部の社員は猛然と反発した。訴訟問題にも発展していると聞く。だが、本社からの最後の通知を受け取ってから、私の心はぽっきりと音を立てて折れてしまった。訴訟に加わる気力など、当然起きなかった。
7年前に北三日月町の駅前への第1号店の出店が決まってから、ずっと走り続けてきた。当時は鳴り物入りの旗艦店として、業界の中でも大いに注目された。本社の中で企画段階から携わり、実店舗でのマーケティング対策も兼ねて店長も任されるようになった私は、いくつかの取材も受け、メディアへの露出も続いた。メニュー開発のために、何度かチームでスペインにも赴いた。男性社員の多い企画本部の中で、店舗での実務を兼ねながら、結果を出し続けなければならないというプレッシャーの中で、食べ物の味がわからなくなったこともあった。それでもなんとか、北三日月町の第1号店は、全国での売上げトップを守り続けてきた。
雲行きがあやしくなってきたのは、去年の年度始めのメニュー刷新の頃からだった。スペイン料理への愛情が人一倍強かった初代の社長が亡くなり、実務的な能力に長けていた副社長が次期社長に就任して以来、売上げが下がってきた本社は、経費削減のために食材の仕入れ先を変更したり、ファミリー層開拓のためにメニューにカレーやパスタを入れたりするという悪手を打ってきたのだ。本社の会議の席で初めてそれを知った私は、猛然と反発した。しかし、他の社員は漆喰を塗りつけた壁のような顔でそれを聞き流した。つまりは、私を除いて、根回しは済んでいたというわけだった。その後、なんやかんやと理由をつけられて、私は本社の企画部から外されて、北三日月町店の運営だけを任されるようになった。私もまた、壁に漆喰をべったりと塗りつけたような顔で、その辞令を聞いた。
北三日月町の駅の反対側に、創意工夫をこらした個人経営のスペイン家庭料理店がオープンしたのは、それからしばらくしてのことだった。バルセロナ出身の女性がシェフを務め、その夫である日本の男性が経営するそのお店は、女性が生まれ育った明るいバルセロナの街を思い起こさせる内装だった。食器もスペインから取り寄せたものばかりで、どの料理も丁寧で愛情がこもっていて、思わず涙が出た。ああ、うちの店もこういう店にしたかった……そんな苦い思いを抱きながら、ワインをぐいっと飲んだ。ハウスワインとして供されたリオハの赤は深く濃く、私の乾いた心に染み込んだ。
うちの店でスペイン料理の味を知ったものの、日に日にスペイン色が失われていくうちの店から常連さんが、そちらの店に移っていったのは、当然の流れだった。うちの店には空席が目立つようになり、若い母親たちがドリンクとフライドポテトを前に盛り上がる中、子供達が走り回るようになった。5日置きに取り替えていた生花も、本社の方針で造花となった。造花の上にうっすらと埃が積もっていくように、私の心にも虚無感が積もっていった。もう、私一人の力ではどうにもならないのだ……。半透明のゼリーのような諦めが、私の心を支配していった。
そんなところに訪れた、ツァイトウイルス禍の渦が、全てを呑み込んでいった。本社からの無茶ぶりと、日々荒れていく店内と、それでも残ってくれているスタッフのケアに対応しながらも、見えない砂時計の砂がさらさらと流れ落ちていくのをずっと感じていた。何も考えずに泥のように深く眠り続けたいと思いながら、疲労で重たくなっていく体に鞭打って、エネルギードリンクを一日に何本も飲み続けながら、先の見えない陣頭指揮を続けた。
だから、本社から北三日月町店を閉鎖する通知が記されたメールを受け取った時には、安堵のため息が洩れた。もう、いいんだ。もうこんな、先の見えない、どこにも辿り着くことのない、不毛な努力を重ねなくてもいいんだ。そのまま私の心は、ぽきりと音を立てて折れて、砂のようにさらさらと散っていった。社員寮を出て行かなくてはならないというメールを受け取っても、不思議と心は動かなかった。そうか、この日々が終わるのだな。ただ、その事実だけを受け止めた。
北三日月町店を閉めてから、もう2週間は経つだろうか。最後にドアを閉めて、鍵を掛ける時は感慨深くなるのだろうかと思っていたけれど、そんなことは全くなかった。いつも通りの手順で鍵を閉めて、ドアに背中を向けても、心はぴくりとも動かなかった。私は振り向くことなく、7年の歳月を過ごした北三日月町店を後にした。そして、化粧も落とさず、シャワーも浴びず、朝から敷きっぱなしにしていた布団に潜り込み、何も考えずに泥のように深く眠ることが、ようやく出来た。
それ以来、私の時間はどこかで止まったままになっている。毎日は流れるままに過ぎていき、惰性でつけているテレビを眺めるうちに、陽が傾き、お腹が空いてくる。買い置きをしていたカップラーメンにお湯を注いで、味の違いも分からないままに啜り込む。そのまま夜までテレビを眺めて、店を閉めて帰ってきて以来、敷きっぱなしにしたままの布団にごそごそと潜り込んで眠る。それが、このところの私の新しい日常だ。テレビは新しい生活様式だなんだって声高に騒いでいるけれど、もうなんだっていい。このまま、布団ごと溶けてなくなってしまいたいと思いながら、どうしようもない眠気に身を任せる。
そうするうちに、このところ毎日のように、夢の中であの白い部屋に行くようになってしまった。獅子頭の男との距離は、息の匂いを感じる程に、どんどん近くなっていく。このままでは、あの白い部屋の夢に、あの獅子頭の男に、私は骨の随まで喰われてしまうかもしれない。
そう思い至ると、私は首筋が冷たくなった。そんな未来を振り払おうと、頭を左右に激しく振る。だめだ、このままでは。なんとかしなくては、いけない。
私は久しぶりにブラジャーを付けた。長袖のTシャツとジーンズを身につける。髪を梳かし、後ろで一つに結び、日焼け止めを塗って、眉毛を描き、マスクをつける。トートバッグにスマートフォンと財布と鍵を放り込む。とにもかくにも、まずはこの部屋から外に出なくては。
私は、ドアを開けた。薄曇りの空が広がっている。久しぶりに頬を撫でる4月の風が、新鮮だった。
「いってきます」
私は小さく呟いて、ドアの外に一歩踏み出した。足が生まれたての子鹿のように震えた。
(つづく)
*
つづきのお話
・第2話はこちら
・第3話はこちら
・第4話はこちら
・第5話はこちら
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
・第10話はこちら
・第11話はこちら
・第12話はこちら
・第13話はこちら
・第14話はこちら
・第15話(最終話)はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

