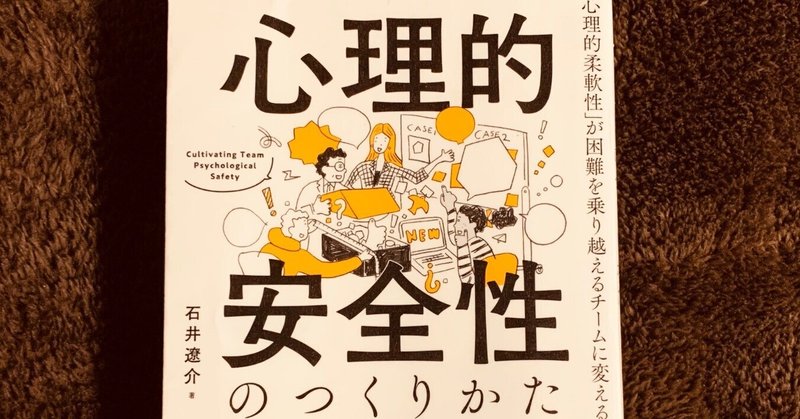
【読書録】『心理的安全性のつくりかた』石井遼介
今日ご紹介する本は、石井遼介氏のビジネス書『心理的安全性のつくりかた』(2020年、日本能率協会マネジメントセンター)。副題は『「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える』。
著者の石井氏は、株式会社ZENTech取締役、一般社団法人日本認知科学研究所理事、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科の研究員をされている。研究者であり、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャーである。組織・チーム・個人のパフォーマンスを研究し、アカデミアの知見とビジネス現場の橋渡しを行っているということだ。
「心理的安全性」という言葉について、お聞きになったことがあるビジネスパーソンは多いだろう。もともとは、ハーバード大学のエイミー・C・エドモントン教授が1999年に発表した概念だ。それが2016年頃から急に有名になった。それは、Google社が2012年から4年をかけて実施した社内調査の結果に基づいて、生産的なチーム作りにあたって心理的安全性が重要であることを提唱したからだ。
私もチームを率いる者として、この「心理的安全性」という概念に興味を持ち、きちんと理解したいと思った。そのような動機から、本書を手に取った。
本書を読んだ結果、「自信をもって、心理的安全性の強い組織を作ることに成功した!」・・・という段階までには、残念ながら、まだ至っていない。そんな簡単なものではなく、一朝一夕にはゆかない。
しかし、心理的安全性についての基礎的な考え方、日本の組織での心理的安全性の因子、そして、実際にチームの心理的安全性を高めるための具体的アイデアなどが分かりやすく綴られていて、スムーズに理解することができた。あとは、これを少しずつ、自分なりに実践、応用していきたいと思っている。
以下、備忘のために、大切だと思った箇所を要約しておく。
*****
チームの心理的安全性とは、チームの中で対人関係におけるリスクをとっても大丈夫だ、というチームメンバーに共有される信念
心理的安全なチームとは、メンバー同士が健全に意見を戦わせ、生産的でよい仕事をすることに力を注げるチーム・職場のこと
対人関係の4つのリスク
「無知」だと思われたくない → 質問せず相談しない
「無能」だと思われたくない → ミスを隠す、考えを言わない
「邪魔」だと思われたくない → 助けを求めず、不十分でも妥協
「否定的」だと思われたくない → 率直に意見を言わない
心理的安全性のメリットは、チームの学習が促進されること
心理的安全性の誤解の最たるものが「ヌルい職場」。心理的安全性は、チームのために必要なことを発言したり、試したり、挑戦したりしても安全である(罰を与えられない)ということ。
学習する職場は、心理的安全性に加えて仕事の基準も高い。
良い業績を上げるためには心理的安全性のある状況での「健全な対立(ヘルシー・コンフリクト)」が重要。
日本の組織での心理的安全性の4因子は、①話しやすさ、②助け合い、③挑戦、④新奇歓迎。
心理的柔軟なリーダーシップ:様々なリーダーシップスタイルをチームと状況に合わせて使い分ける。
トランザクショナル・リーダーシップ(取引型):アメとムチ、成果主義
トランスフォーメーショナル(変革型):ビジョンと啓発
サーヴァント・リーダーシップ:メンバーを支えて支援
オーセンティック・リーダーシップ:自分らしく弱さも見せられる
心理的安全性とは、組織・チームの「関係性・カルチャー」(または風土・文化など)。実際には1つ1つの行動の集積。行動へフォーカスし、望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすことがリーダーの役割。
具体的アイデア集
感謝を「I message」で伝え、理由つきで述べる。
「のび太力」を上げる。相手より一枚薄く鎧を着る。オープンに助けを求め、ダメな自分を晒す。
1:1でメンバーと目線を合わせる、メンバーと一緒に困る
「心理的安全宣言」をする。(例「この場の安全性は私が担保します」。)
日常業務から切り離した研修(料理教室の例)
「話しやすさ」について対話するワークショップ:チームならではの知見をあつめ、意見を言いやすい、言いにくいと感じた瞬間を可視化する
*****
私は、今まで25年以上の社会人経験において、ずっと何らかの組織のチームに属して、またはチームを率いて働いてきた。本書を読んだ後に、今まで属し、率いたチームについてひとつひとつ思い出してみると、この、心理的安全性というものが、チームの成否を大きく分けていたなあ、と、感覚的に分かる。
心理的安全性のあった職場では、お互いに話しやすく、率先して助け合う雰囲気があり、とても機動的で生産性が高かったと思う。何よりシンプルに、チームで活動するのが楽しかったし、ポジティブな気持ちで頑張れて、色々なアイデアが浮かび、いいことづくしだった。
逆に、そうでないチームでは、発言しづらい緊張感が漂ったり、やらされ感や白々しさなどのネガティブな空気感に包まれたりして、メンバーとミーティングをしたり、協同作業をすることが苦痛だった。何より楽しくなかった。会社に行くのが億劫で、日曜の夜にはサザエさん症候群にかかった。そんな状況で生産性も業績も上がるわけはなかった。
でも、もう大丈夫。この本が助けてくれる。チームに心理的安全性をもたらし、一層高めるために、自分に何ができるか、それぞれの立場で考えられるヒントをくれる。チームをリードする立場の方にはもちろん、チームの構成員として何ができるかを考えたい人にもお薦めだ。
ご参考になれば幸いです!
私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
