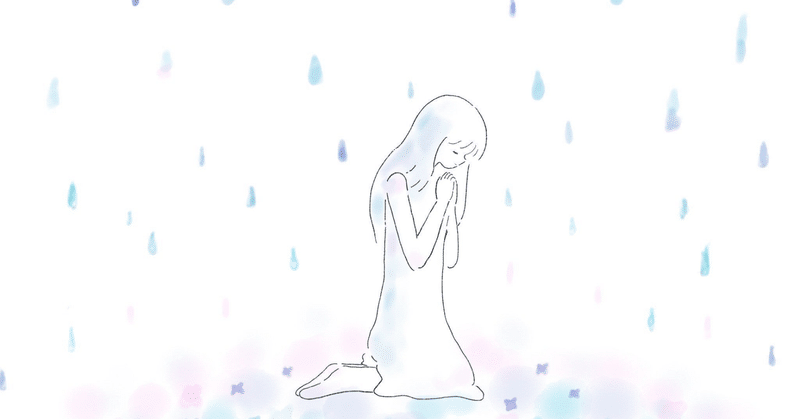
頭痛の季節/六淫と気象病の話 【漢方医放浪記】
気温と気圧の変動に加えて、梅雨特有の多湿な環境。体調を崩す人が多いように感じます。数日の間に幾人も頭痛の訴えがあり、それぞれの治療が奏功しましたので、理論と併せて記録しておこうと筆を執りました。
ある妙齢の女性は、ひどく疲労がたまっていて、脾胃も腎も虚していました。疲労が精神にまで影響を及ぼす状態でしたから、こういうときには帰脾湯の出番です。肝気鬱結と胃熱も伴う複雑な病態でしたから、柴胡と山梔子を加えます。これで快方に向かっていましたが、昨今の異常気象の中でひどい頭痛をきたしました。吐くほど激しい頭痛であって、脈をみますと沈・遅・やや大・上焦浮。冷えて水が溜まり、気逆と水逆です。これは工夫が必要と判断し、呉茱萸湯合五苓散を処方しました。30分以内に効果が現れ、翌朝にはすっかり頭痛は消えたそうです。
またある貴婦人は、更年期障害に悩み抜いた末、私の外来を訪れました。加味逍遙散が奏功しましたが、慢性的な頭痛が治りません。根本に太陰病位の裏寒証がみられましたから、呉茱萸湯を加えたところ、数日以内に頭痛が軽快しました。ところが台風の影響か、悪天候に重なるように頭痛発作が再燃して、これは経絡治療が良かろうと鍼を併用しました。手三里、肩井、足三里の左右6箇所のみ鍼を打ち、気鬱を解除すべく指先から気を送り込み、気の流れを治しました。すると10分ほどで頭痛が和らぎ、彼女は晴れやかな表情で診察室を後にしました。
長年の片頭痛に悩む青年を診察すると、腹部に特徴的な所見がみられました。臍の右側に圧痛点があり、これが頭尾側に貫くように張っています。季肋部では苦満し、鼠径部に索状の圧痛部位がありました。聞くと、寒冷刺激や多湿の環境で頭痛が起きやすいといいます。これは典型的な「疝」です。当帰四逆加呉茱萸生姜湯を処方したところ、それから一度も頭痛を起こさなくなりました。
古来より気候は体調に影響を及ぼすことが知られており、それは六の邪として説明されます。
風・寒・暑・湿・燥・火を総じて「六淫」といいます。淫の字が卑猥な印象を与えかねませんので、最近では「六邪」とか「外邪」という表現も見かけますが、すべて同義語です。
寒は寒冷刺激、暑は暑熱刺激、湿は多湿刺激、燥は乾燥刺激とイメージがつきやすいものの、「風」と「火」が難解です。
私見ですが、火邪は限局的な高温刺激と考えます。例えば猛暑の屋外や高温サウナは「暑邪」で、熱い風呂や不適切な温熱カイロ、灸などは「火邪」と捉えます。
一方の「風」は極めて厄介なもので、一般に解釈されるようなピューと吹く!ジャガー風(wind)ではありません。吹き流れる風を生み出すのは地球の自転と気圧差ですから、言い換えると「空気の変化」が「風」であろうと私は解釈します。さらに風邪は体内を縦横無尽に駆け巡ると云われておりますから、変化という現象に加えて、物質的には「(細菌やウイルスなど)微生物あるいは(自己抗体など)免疫反応を惹起する何か」と捉えると、病態把握と治療戦略の理解に丁度良いように感じます。
いわゆる「気象病」は、漢方医学的には「風」と「湿」の病です。
「気」は通常、頭から足の方向へ流れるものですが、低気圧変化は気を逆流する方向に働きます。気の量が充分ならば取るに足らない変化であっても、元々が微弱な流れだと大いに影響を受けて滞ったり(気鬱)逆流したり(気逆)します。湿度は浮腫に結びつきますから、身体の色々なところに水が溜まってむくみます。気や血の流れが悪いところには水が溜まり易く、頭に水滞が起きれば頭痛を生じ、胃腸に水滞が起きれば消化不良や下痢をきたします。
水滞がそれだけで存在することは稀ですから、その背後には気の異常か血の異常があるはずです。言い換えると、むくみは結果ということです。
気虚のある方は気を補うことを、瘀血のある方は血流を改善することを意識するのが良いでしょう。具体的にはどうすればいいか。そのヒントは拙作「漢方医放浪記」シリーズを含む医療記事にあるかもしれません。
拙文に最後までお付き合い頂き誠にありがとうございました。願わくは、貴方がこの梅雨と猛暑の季節を、健康に過ごせますように。
#漢方医放浪記 #私の仕事 #漢方医 #呼吸器内科医
#気象病 #とは #風湿の病 #六淫
#エッセイ #医師 #漢方医学
ご支援いただいたものは全て人の幸せに還元いたします。
