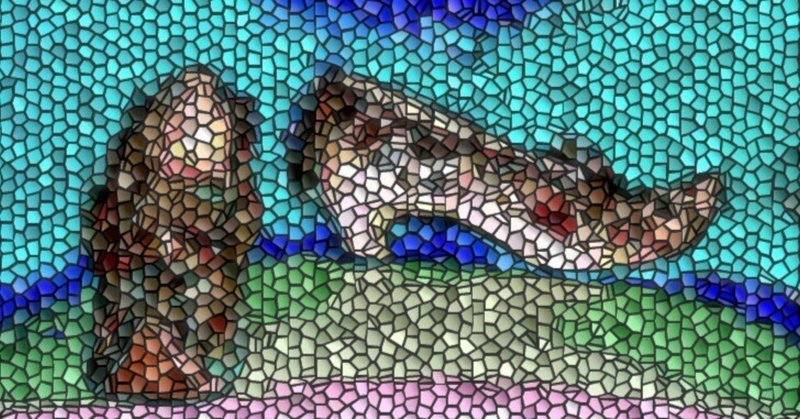
魔法の靴④ 靴フェチに語られました!
「だからさぁ、おまえ、見かけが怖すぎなんだよ」
「うっせーよ」
「せめて、ピアスやめろよ。見た目がそんなじゃ、香奈恵ちゃんみたいな真面目な女の子は、怖がるだろ?」
「関係ねーよ」
テーブルの真ん中で、ミニトマトと茹でた人参とブロッコリーに囲まれて、チキンの丸焼きがじゅわじゅわと音を立てている。隣には、銀の蓋がかぶさって中身が見えない大皿。反対側のチキンの隣には、リネンのナプキンで包まれたバゲットが、ほかほか暖まっている。
そのむこうで、希美の彼氏の拓也が、そっぽをむく例の男を、こんこんと諭している。
こちら側では、香奈恵の隣で、希美が香奈恵をまじまじと見つめている。香奈恵はもぞもぞ体を動かした。希美が長いため息をついた。
「あんたさあ、よく知らない人だからって、いきなり通報とか不法侵入とか……もうちょっと落ち着いて物事を判断しないとさあ」
「……うん」
「人を見かけで即断するのはさぁ。そりゃ、誠くん、チャラそうで怖そうな雰囲気っちゃ、そうだけど」
「でしょ? 怖そうだよね? 希美のマンションに絶対いなさそうな雰囲気でしょ?」
「調子に乗るんじゃありません」
「……ごめんなさい」
チキンの向こうとこちら側で反省会が開かれ、仲直りした四人は一斉にチキンにナイフを刺した。
チャラそうで怖そうな男は、希美の彼氏の幼なじみで、覚正誠一という堅苦しい名前を持っていた。香奈恵より1つ上の25歳。シューズショップのスタッフだそうだ。どうりで靴に詳しいわけだ。
「拓也君と、ずいぶん雰囲気違うよね。えーと……その、どういうお付き合いで……」
希美が香奈恵の脇を肘でこづき、香奈恵はまた小さくなった。誠一が軽く吹き出した。脇から拓也が大きな体を乗り出して、優しく口を挟んだ。
「こいつとは、中学の吹奏楽部で一緒だったんだよ。高校から別れちゃったけど、なんとなく腐れ縁でね~。吹奏楽部に入った当時は、俺がホルンで、こいつはトロンボーン」
「トロンボーンって……あの、なが~く伸びる楽器?」と、香奈恵は演奏会の舞台で見た記憶を探る。
「そうそう。金管で、腕でスライドさせて音を調節する、細長いヤツね。こいつ、中1の時から、もう上背があったから、吹奏楽部の顧問の先生が一目見るなり『あら、腕長そうね。ちょっと右手を伸ばしてみて。はい、君トロンボーン』って即決」
「俺はトロンボーンなんて知らなかった。かっこよく、トランペットをぱっぱ~ってやりたかったのにさ」
「っていう愚痴を、最初の演奏会が終わった後に聞かされたよ」
「お前だって、中1のときに縦にも横にもでかくなりやがって、中2になったとたん『君、重い楽器いけそうだから、チューバね』って宣告されてショック受けてたよな」
「そうそう、体格だけで楽器決められるんだよな、中学の吹奏楽って。俺と拓也は、そういう相哀れむ仲だったわけ」
誠一はこうしてみると、茶髪とピアスと顎ひげを除けば、拓也に似た穏やかな雰囲気を持っていた。
「チキンと一緒に、こちらもどうぞ」
拓也が大皿の銀の蓋をとると、女子2人から歓声が上がった。赤味がかったオレンジと緑の幾何学模様が、鮮やかに四角く固められている。
「野菜のテリーヌだよ」と、拓也が得意げに鼻を鳴らした。誠一が一人一人の皿を集めて拓也にわたし、拓也がテリーヌを一切れずつ乗せて香奈恵と希美に手渡す。
香奈恵が手を伸ばすと、誠一は低く呟いた。
「落とすなよ」
見かけによらず、声は優しい響きを帯びていた。皿を受け渡すとき、一瞬、2人の指先が触れた。細く長い誠一の指先は、意外に硬い感触だ。
一切れ口に運んで、香奈恵は叫んだ。
「おいしい! なにこれ、何の魔法?」
テリーヌは口の中ではらりとほぐれ、ゼリーが解けて、野菜の甘みと一緒に爽やかな香りが鼻に抜ける。
「拓也くん、どんだけ料理の腕磨いてんの」
拓也は頭をかいた。「いや、これはね、俺じゃないの。誠一なんだ」
「えーっ、誠くんも料理うまいんだ!」と、希美。
「俺はチキンとケーキで手いっぱいだったからさ、誠一に、もう一品なんか作ってよって頼んだんだよね。そしたら、使い残したブロッコリーの茎と人参が、ぱぱっとテリーヌになっちゃって。あれ、この味、ブイヨンじゃないね?」
拓也の疑問に、誠一はかすかな微笑みを浮かべてうなずいた。
「そう言えば、なんだか懐かしいような香り」。香奈恵は素朴に口を挟んだ。「お馴染みなような、でも食べたことがないような」
誠一はにやにや笑う。拓也は真顔でもう一切れを口に運んだ。
「ほんとだ。ん~、なんだこれ。悔しい、わからん。誠一、レシピくれよ」
「……いや、適当だから」
「適当で、これだけおいしくできるなんて。誠くん、もしかして料理の天才?」と、目を丸くしてのけぞった希美が、抜け目なさそうな表情になって身を乗り出した。「ねえねえ。拓也がオーケストラ辞めて店開くとき、パートナーでどう?」
「こら、俺のチューバ人生を勝手に終わらせるな」
「もちろん、あたしと拓也が一緒にウイーンフィルで吹くって夢をかなえたあとよ」
「ウイーンフィル……って、女性いたっけ? うん。いきなりチューバ人生が長くなった気がする」
「もちろん、あたしのオーボエでオーボエ協奏曲だから」
「ああっ、また、主役になれる楽器であることを自慢する! どーせチューバは万年、脇役ですよ~。第九のシーズンは出番がなくて暇ですよ~」
誠一が吹き出した。香奈恵は意味が分からなくてきょとんとする。誠一は低音で注釈をくれた。
「ベートーベンの交響曲第九番に、もともとチューバは登場しないんだ。チューバは新しい楽器で、ベートーベンのころはなかったからな」
「あ、なるほど。年末はどこも第九ばっかりだもんね」
香奈恵はくすくす笑った。
「そうだ!」
拓也が大声を上げて、テリーヌのフォークを握りしめたまま誠一に向きなおった。
「この味、思い出したよ。お前のオヤジのカフェで食べた」
誠一の顔からほんの一瞬、表情が消えたのは、香奈恵の気のせいかもしれない。誠一はすぐ、いたずらがばれたような苦笑いを拓也に返した。
「ばれたか。オヤジのメニューだ。ブイヨンじゃなくて、昆布と鰹。あとでレシピ書くよ」
「サンキュー」
拓也は太い腕で誠一に巻き付いた。
「へぇぇ、誠君のご実家って、カフェやってらっしゃるの? どこで?」
希美の目がまた大きくなる。再び、一瞬だけ、誠一の顔に何の色もない時間があったように、香奈恵には見えた。
「神奈川県の湘ガ浜の浜辺の近くだよ」。拓也が先に答えた。「自家製野菜と地産食材のビストロカフェで、地元じゃ、有名店だったんだぜ。ま、俺は誠一の友人枠で、ときどきタダで食わしてもらったけど」
「ああ。そうだったっけ。もう、店、ないけどな」
ぽつりと、誠一の低い声が聞こえた。拓也は分厚い手のひらで、誠一の肩をゆっくり叩いた。
「ええ~、もうないなんて残念。行ってみたかったな。お父様は引退されたんですか? 覚正さん、料理上手なのに継がなかったんですか?」
香奈恵の質問は、純粋に好奇心からで、軽く答えが返ってくるのを期待していた。誠一でなく、拓也からでもよかった。
なのに、半分以上つつかれたチキンの向こう側、男子二人の席は、瞬間にして固まった。
しばらく、不自然な沈黙が落ちた。
香奈恵の隣で、希美がガタンと音を立てて椅子を後ろに引き、立ち上がった。
「さて、と。甘いものが欲しくなっちゃった。拓也のケーキ出さない?」
「お前ってやつは……チキンを見ろ。まだ半分くらい残ってるじゃないか。平らげてやらないと、トリさんがかわいそうじゃないか」
「え~、でも、甘いものが食べたぁい。食べ盛りの男子が二人もいるんだから、チキンくらい、何とでもなるでしょ」
「わがままもたいがいにしなさい」
「だって~拓也のケーキ食べたい」
希美と拓也は、いつもより大きな声でじゃれあいつつキッチンに消えた。キッチンから、こちらに十分聞こえるボリュームのやりとりが漏れてくる。
「ちが~う。そのお皿じゃイヤ」「どれならいいんだよ」「せっかく拓也のケーキだから、とっておきのノリタケ。あっ、コーヒーじゃなくて紅茶~」「君は相変わらず紅茶党だね。僕の中では、クリスマスケーキにはコーヒーと決まっているんだよ」「それは拓也ルールでしょ。あたしルールでは紅茶なの~。レディ・グレイじゃないと嫌~」「仕方がないなあ、じゃ、両方と言うことで。お湯を沸かすか」
香奈恵は、テーブルでもじもじうつむいた。何か、いけないことを聞いたかも。そんなにおかしな発言はしていないと思うのだが。
「……あのお、もしかして、ごめんなさい? って言うところ、だよね?」
おそるおそる誠一を見上げる。
誠一は無表情に下を向いていたが、ふっと顔をあげたときは穏やかな笑顔になっていた。
「いや、別に。どうってことないよ。こっちこそ変に黙って悪かった」
すうっと息を吸い込んだ。
「オヤジは、五年前に死んだんだ。俺はもう、そのときは家を出てた。カフェを継がなかったのは、ほかにやりたいことがあったからだ」
「そうなんだ」
ずいぶん早く父親を亡くしたのだな。香奈恵は不躾な質問を反省し、誠一に小さく頭を下げた。
……てことは、一人息子かな。うちの実家の荒物屋も、子供が三人いるのに、継ぎそうなのは弟だけで、兄もあたしも家を出ちゃったし。今どき、子供だからって家業を継がなきゃいけないわけでもない。
「やりたいことって、何? 聞いてよければ、だけど」
「なに、急に遠慮がち?」 誠一は短く笑った。「地下鉄の駅で人の向こうずねにパンプス蹴り飛ばしてきたり、コンサート会場で通行人の邪魔してまで履いてる靴を見せようとしたりした人物とは思えないな」
「……そこ蒸し返す?」 香奈恵は耳まで赤くなった。
「いや、ちょっと意外なだけ」
香奈恵をちくりと刺した誠一の瞳は、茶目っ気たっぷりな色合いだった。茶髪にピアスに刈った顎髭とは少しちぐはぐな、穏やかな温かみを感じる。
「靴、作りたいんだ」
誠一がさらりと言ったので、香奈恵はとっさに聞き取れなかった。
「え?」
「靴だよ、靴。あんたみたいに靴が足に合わなくて悩む人が、世の中にたくさんいるだろ。そんな悩みがなくなるような、履き心地がよくて頼りになる靴を、オレは作りたいんだ」
「っていうと、スニーカーとか、ウオーキングシューズとか?」
「いろんな靴だよ。ビジネスシューズも、パンプスも、ブーツも、サンダルも」
誠一の目がきらきら輝き出したのは、照明の反射ではないと、香奈恵は思った。
「靴ってのは、生きてる限りつきあうものだ。靴がなけりゃ、買い物にも学校にも仕事にもいけない。人間の体重を支えて、足を前に進めてくれる。いわば人生を一緒に歩いていくパートナーだ。足に合わない靴はストレスの元で、体の調子だって崩しちまう。でも、ちゃんと合った靴を履けば、心まで軽くなって、前向きになれるんだ」
香奈恵は口をぽかんとあけて、誠一を見つめた。誠一は身を乗り出して、口調が熱く、早口になっている。
「知ってるか? 人間の体を構成する骨の数はざっと200個。その4分の1は、足に集中してる。足は『第二の心臓』とも言われ、骨はきれいなアーチ型で、体重を支えるクッションの役割を果たす。でも、靴の選び方を間違えると、この美しい足の骨が変形して、とんでもないトラブルを引き起こす。たとえば、ほら、あんたの足」
と、誠一は突然、椅子を放り出して身を屈め、香奈恵の足下にうずくまった。香奈恵は反射的に足を引こうとしたが、誠一の腕が一瞬早く、足首をつかんだ。力が強い。
ちょっと待て。今日のタイツは爪先に穴が……
しかし誠一は待たなかった。タイツの穴など見向きもせず、香奈恵の足の親指の付け根を指さす。
「ほら、親指の付け根が少し外側に張り出しかけてる。放っておくと外反母趾になるぞ。あんたの足は、幅が細くて甲が薄くて踵が出っ張ってない、日本人の典型なんだ。こういう足には普通のパンプスは……」
「なにやってんだよ誠一」
香奈恵の後頭部に、ホルンみたいな太くて柔らかい声が降ってきた。香奈恵と誠一が一緒にそちらを見上げる。4人分のケーキ皿をトレイに乗せて運んできた拓也だった。
誠一は、ぱっと香奈恵の足首を離した。そそくさと自分の席に戻ってそっぽを向く。
拓也はケーキ皿を香奈恵の目の前に置いて苦笑いした。
「びっくりしたろ。コイツ、靴を語り出すと止まらないんだよね。オタクだから。オレはチューバオタクで、コイツは靴オタク。あ、言っておくけど、フェチじゃないから。二人ともオタクだから、そこ間違えないでね。でも、腕は悪くないよ」
香奈恵に続いて、誠一の前にケーキ皿をおく。
「靴職人としては、まだ見習いだけど、練習つってオレにも一足作ってくれた。玄関にあるワラビー。オレ、足がチューバ並みにでかくて分厚いんで、靴探すのに苦労してたんだけどさ。コイツが作った靴は、なんだか足取りが軽くなるのだよ」
誠一が、幼稚園児みたいな交じりっ気なしの笑顔になった。
「俺が世界的チューバ奏者になったら、靴は全部、誠一にオーダーするからな。それまでに一流職人になれよ」
「先に一流職人になるから、待たせるなよ」
未来の世界的チューバ奏者と一流職人のやりとりに、香奈恵の胸の奥が、ずきっと疼いた。
どうして、夢に向かって進む人々は、まぶしく力強いのか。あたしには、目指したい夢なんて、かけらも見えてこないのに。
そこへ、希美が、キルティングの帽子をかぶったティーポットと四人分のカップを持って登場した。
拓也のクリスマスケーキはふわふわのシフォンケーキで、ラズベリー風味の濃いピンクと抹茶風味の薄緑の2色のクリームで彩られていた。
爽やかで軽い口当たりなのに、香奈恵の心は一口ごとに重く沈んだ。
希美も、拓也も、誠一も、夢を見据えて歩んでいる。真っ直ぐな視線がまぶしい。ぐっとあげた顎が尊い。
わからない。どうやって、目指す夢を見いだしたのか。そこに向かって進もうと思える何かを、どこから探し出したのか。
香奈恵には、なにも見えない。親に「失業中」と言いたくないから、再就職を目指しているだけで。会社がつぶれて失業するのはもうまっぴらだから、安定した企業に雇われたいだけで。これがやりたいから、この仕事に就きたいから、だから何かを頑張ることが、全く想像もつかない。
夢なんて……いったいどこに埋まっているの。
「そうだ」
希美の声で、香奈恵ははっとした。みんなのケーキ皿はとっくに空なのに、香奈恵だけいつの間にか、フォークが止まっている。
「誠くん、女性ものの靴も作れるの?」
誠一が少し目を見開いた。「まだ、ユニセックスなデザインしかできないけど……なんで?」
「あたし、一足オーダーしたい。あたしの靴じゃないけどね」
「へ?」
希美は香奈恵の黒髪をぐしゃっと撫でた。勢いで香奈恵の頭が左右に揺れる。
「香奈恵の靴を、作ってくれない?」
「えっ、なに言ってんの、希美」と、香奈恵は希美の手を振り払って向き直った。「オーダーの靴なんて、値段が高そうじゃん。もらえないよ」
「気にしないで。クリスマスプレゼント、何年かあげてなかったから、まとめて受け取って」
希美はウィンクした。ウィンクって、かわいい女の子がやると、様になるんだな。香奈恵は妙に感心し、我に返った。
「いやそんな、嬉しいけどさ」
「あたしがあげたくなったんだから、受け取って」
そう言って、希美が急に柔らかく巻き付いてきた。
「その靴ができたら、きっと、あんたの時が進み出す。前に向かって、ね」
香奈恵にだけ聞こえる囁きだった。香奈恵は唇をかみしめて、不意にこみ上げた涙をおさえ、希美の背中に手を回した。
そういうわけで、香奈恵と誠一は、連絡先を交換し、採寸やデザインの打ち合わせのために再び会うことになった。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
