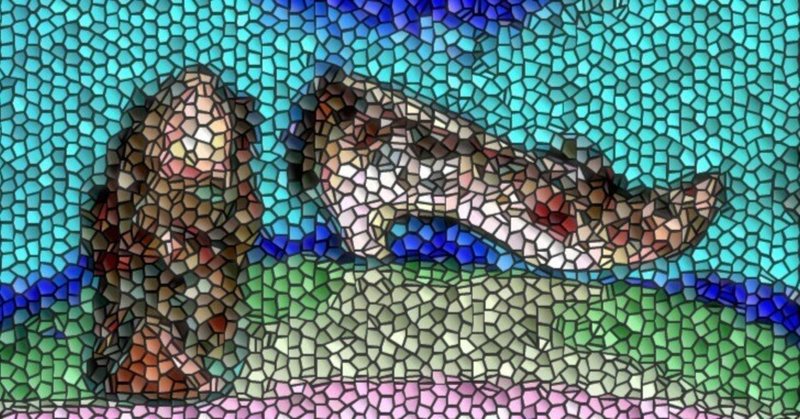
魔法の靴 最終回 ありがとう、そしてさよなら!
翌日、香奈恵は希美の実家の門の前をうろうろしていた。希美の家は広い。敷地には門から緩やかな上りの傾斜が付いており、まず開けた庭園がある。その奥に母屋と離れと蔵が建っている。離れが希美の音楽室で、グランドピアノが置いてあるはずだ。幼いころから、遊びに来ると必ずピアノの音が響いていたが、高校に上がると、いつの間にか聞こえるのはオーボエばかりになっていた。希美の笑顔は変わらなかったけれど、振り返れば、そのころに大好きなピアノを諦めて、オーボエに転向したのだろう。
今も、離れからはオーボエの音色が聞こえる。
幼稚園のころは簡単だった。力いっぱい大声で「あーそーぼっ」と呼びかければ、離れのガラス戸が開いて、希美がとことこ出てきた。進学して、二人の進路が別れてからは、会うのに電話やLINEが必要になった。アポなしの突撃訪問は、何年ぶりだろう。
不自然に門の前を行ったり来たりしている香奈恵は、家の中の人の注意を引いたらしい。母屋の玄関が開いて、男性が出てきた。希美の父親だとすぐ分かった。向こうも、門に近付くにつれ、うろうろしているのが香奈恵だとわかったらしい。玄関を出たときは顰め面だったのが、途中から笑顔になった。
「なんだ、香奈恵ちゃんじゃないの。久しぶりだね。きれいになったじゃないか。希美かい? 今、呼んでくるよ」
昔から変わらない早口と飲み込みの良さで、希美の父親は香奈恵の返事を待たず、一人で頷いてさっさと身をひるがえした。覚悟ができていない香奈恵は一人、取り残されて、あわあわと口を動かして固まった。
離れのガラス戸が開けられ、希美の父親が中に向かって話しかける。オーボエの音色が止む。しばし間があって、ガラス戸は閉められた。
やっぱり会ってくれないのかな。香奈恵はがっくり肩を落とした。
希美の父親は、香奈恵に笑顔で一礼して、そのまま母屋に帰ってしまった。
と、離れのガラス戸が開いた。見慣れた栗色の巻き毛が出てきた。希美だ。足元はつっかけサンダルだけど、白いノースリーブのワンピースのすそが揺らめいて、お姫様みたいだ。
希美はゆっくり歩いてくる。香奈恵の胸が高鳴った。
門扉が開いた。
「久しぶり」。希美が無表情に言った。
「あの、あたし……」。言いかけた香奈恵の手を、希美は突然、乱暴に握って、そのまま道を歩き出した。真っ直ぐ行けば、川に出る。子供のころ、二人でどじょうやアメリカザリガニを探した。
川辺は昔のままだった。石の間から雑草が生い茂り、緑と泥の匂いがむせるようだ。
二人は立ち止まって、水面を眺めた。
沈黙に耐えかねて口を開いたのは、もちろん香奈恵だった。
「あの。演奏会のとき、ごめんね。あたし、余計なこと言った」
希美は答えない。香奈恵は続けた。
「それだけじゃなく、いろいろ、ごめん。あたし、自分が努力しないのを棚に上げて、希美の華やかなところだけ見てた。陰でどんなに頑張ってるか想像もしなかった」
「別に、謝ることじゃないよ」
希美がぶっきらぼうに遮った。香奈恵は希美の白い横顔を見詰めた。表情は、無い。
希美のピンクの唇が、再び動いた。
「あたしがそうしてほしかったから。みっともないところ見せたくなくて、かっこいいところだけ見てほしくて、そうしてきたんだから、いいの。それより」
言葉を切った希美は、やや高いところにある香奈恵の顔を真正面から見つめた。大きな目が鋭い光を放ち、口元は引き締まっている。細い眉がぎゅっと寄った。希美の腕が上がった。
殴られる? 香奈恵は目をつぶった。
が、次の感触は、顔でなく肩や背中に来た。ふわっと温かいものが巻きついてくる。目を開けると、希美が香奈恵に抱きついていた。
「こっちこそ、ごめん」
香奈恵の胸で、希美のくぐもった声がした。
「許してもらえないかと思ってた。あたし、最低のこと言った。怖くてLINEも見られなかったし、連絡もできなかった。香奈恵は頑張ってるの、わかってるのに」
香奈恵は希美の背中をぽんぽん叩いた。
「何、言ってんだか」
二人のくすくす笑いが、ハモってだんだんフォルテになる。川も、風景も、二人の仲も、昔と同じだった。

暑さの中に秋の気配を感じるころに、佳乃の靴が出来上がったという連絡が来た。
ギャラリーカフェ・オカノには、香奈恵が先に到着した。ドアを開けると澄んだ鈴の音が響いた。ブラインドが下りた客席には、佳乃がすでにお茶の用意をしていた。
「チャイは、誠一が来てから入れるから、まずはコーヒーをどうぞ」と、佳乃は白磁のコーヒーカップに銀のポットからコーヒーを注いだ。
佳乃は、そのまま黙りこんだ。誠一は、まだ来ない。
「あの」。香奈恵は思い切って口を開いた。
「なあに?」と、佳乃が長い首をかしげる。
「佳乃さんは、どうしてここでカフェをやっているんですか? 慎太くんが亡くなってから、大変だったろうに、ご実家に帰ろうとは思われなかったんですか?」
「あなたって、本当に、何でも聞いちゃう子なのねえ」。佳乃はくすくす笑った。
「ごめんなさい、不躾で」と、香奈恵は縮こまる。
「今さら」。佳乃は軽くいなして、ブラインド越しに遠い空を見つめる。
「実家なんて……帰る理由がなかったのよね。逆に、ここにいる理由なら、あったわ」
「ここにいる理由、ですか?」
「そうよ」と、佳乃は目を細めた。「だって、私の家族はみんな、この近くにいる。慎太も、岡野も、近くのお寺に眠っているわ。前の夫が眠っているお寺も、そんなに遠くないの。誠一だって、この場所ならわかるから、いつか帰ってくるかもしれない。実際、帰って来たでしょう。ほら」
と、佳乃の声と、ドアの鈴の音が重なった。
誠一だ……とわかるのに、しばらくかかった。
短い黒髪の下に、生真面目な表情の、髭がない顔がある。耳にも鼻にもピアスはない。白いシャツに紺のスーツ。臙脂の細い畝が光るネクタイをきちんと締め、足元は黒いウイングチップのビジネスシューズ。片手に、シューズボックスが入った大きな紙袋を提げている。
佳乃の顔が柔らかく輝いた。「お帰りなさい、誠一」
誠一は軽く頭を下げた。

佳乃はキッチンでチャイを作っている。
「髪、黒くしたんだね。ずいぶん見違えたね」。香奈恵はおどけて、誠一に言ってみた。
「とりあえず、中学時代まで戻ってみた」。誠一の声も笑っている。
「佳乃さんの靴、早く見たいな」
誠一はちらっと足元の紙袋に目をやり、ついでに香奈恵の足元に目を止めた。
「おお、ローファー、きれいに履いてくれてるな」。純粋に嬉しそうな声だった。
「うん。もう、足から離れない。毎日のように履いちゃってるよ」
「そうか。じゃ、しばらく会えなくても大丈夫かな」
静かな響きが、香奈恵の胸に刺さった。
「……会えなくなるの?」
「うん。たぶんね」。誠一は穏やかな笑顔を崩さない。
「どうするか、決めたんだね」
「オレ、慎太の墓参りして、しっかり謝ってケリつけて、それからフィレンツェに行くわ。靴づくりの修行をして、一流の職人になる。そんで、世界中の誰もが、履いたら心が軽くなって前に進める靴を作る」
香奈恵は下を向いた。
誠一が、名残惜しそうに言った。
「夏物も作ってやればよかったな」
「え?」と、香奈恵は顔を上げる。
誠一は香奈恵のローファーを指差した。
「それ、夏は暑かっただろ。サンダルかミュールがあればよかったと思ってさ」
「じゃ、作ってよ」
香奈恵は身を乗り出した。誠一の細い目が丸くなる。
「いや、でも、オレはこれから……。いつになるかわからないぞ」
「いつでもいいよ」
香奈恵はにっこり笑った。
「一流職人になったら、夏物のサンダル作って。あと、替えのローファーも欲しいな。お給料貯めて待ってるから」
誠一があっけにとられた顔になり、続いて顔が笑み崩れた。
「クッカの仕事、頑張れよ。山際チーフが褒めてたぞ」
「え、いつ? ていうか、お店に行ったの?」
「来る途中に挨拶してきた。無断欠勤で迷惑かけたし。おまえは絶対、無断欠勤するなよ」。誠一はしれっと言った。
「しないよ」と、香奈恵は頬を膨らませる。
「で、夢は見つかったか」と、誠一。
香奈恵は、ブラインドの羽を手でちょっと下げて、空を見上げた。まぶしい光が飛び込んでくる。
「まだ、そんなにはっきりしないけど……この間、お客様に『村瀬さんに歩く楽しみを教えてもらった』って言われたの。あたしも教えてもらった気がした。靴選びのお手伝いは、履く人が前に進むお手伝いをするってことなんだなって。いい靴は、体も心も前に進めてくれる。誠一さんが言ったとおり。あたし、みんながそれぞれのハッピーエンドに向かって、歩いていく手伝いをしたい」
誠一が、ぐっと親指を立てた右手を香奈恵に突き出す。
「オレの靴で歩いて行けよ。お前のハッピーエンドに向かって」
佳乃が、三人分のチャイとバナナケーキを乗せたトレイを重そうに運んできた。
(了)
################################
つ い に ! 最終回ですよ……
いや~長かったですね! 最後まで読んでくださった方、もしいらっしゃいましたら、本当に本当に本当に本当にありがとうございました!
1回目から読みたい方はこちらからどうぞ↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
