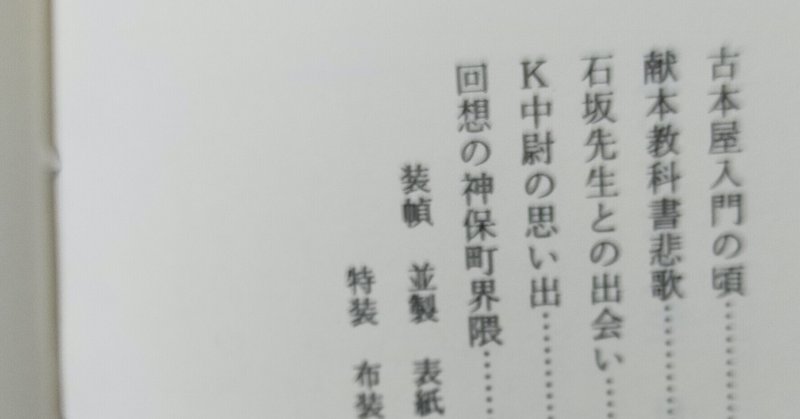
神保町に救われた命 - 「K中尉の思い出」
文章を追っているペン先が止まった。原稿に向けていた目を上へと反らす。滲んだ涙は隠さない、私のほかに店内にいるのは喫茶店の主人だけだった。涙しようとして滲ませているのではなく、紙片の語るひとりの人生に涙していた。
働いている古本屋の店主に頼まれて、古書組合の出す本に載せる文章の校正をしていた。組合が長年発行してきた機関誌には数多の古本屋の文章が詰まっている。古本屋の文章の存在は、古本に関わっていない人びとには知られる由がない。書いている私自身でさえ、校正の機会を得るまでは、古書組合なんてものがあって、更にはそこが機関誌を出しているなんて知らなかった。古本屋の書いた文章、というある種の色眼鏡を外して見るならば、人の生きる上での転変や機微に触れた心地にするものだった。古本屋へ一度でも足を運んで、というのではなく、本にまつわっての運命の不可思議を伝えたいと思い、私の眼の滲んだ話をひとつ伝えたい。吉祥寺にある藤井書店さんの初代店主・藤井正さんの体験である。
「番兵、貴様どこからきた」
「東京であります」
「東京と云ったっていささか広い。東京のどこだ」
「神田は神保町であります」
「神保町かあ、懐かしいことをいうんだなあ」
この会話のなかの番兵が藤井である。昭和19年の暮れ、岩国にあった海軍航空隊の基地に藤井はいた。当直をしていると、年のころ24歳ほどのK中尉に声をかけられた。神保町のことを話しかけられて藤井は嬉しかったが、上官にはうっかりでも気を許すことはできない。中尉は続ける。
「そうか、神保町か。神保町は本屋の町だ。古本屋がズラリと並んでいたな。貴様神保町のどこにいた」
「巌松堂書店におりました」
「巌松堂ね、あの店か、角っこの。右側が新刊本で、左が古本、大きな店だったなあ。奥の路地の左側に欧文古書部なんかあったよな。おれはよく知っているよ。ずいぶんと買ったよ」
藤井は驚いた。いくら神保町を歩いているからといって巌松堂の欧文古書部までもつぶさに言い当てるのは相当歩き慣れていると言わねばならない。K中尉とはそれきりかと藤井は思っていた。しかし期せずして再びK中尉と藤井は言葉を交わす。1週間後のことである。
K中尉は前回とは別人のように親しげに藤井に話しかけてきた。そこで藤井のほうからもつい言葉をかけた。
「神保町はどこを歩かれましたか」
「どこったって、端から端まで知っているよ。片っ端から店に入り、持てるだけ金の続くかぎり買って帰った。おふくろが、どうせ戦争に行くのにどうしてそんなに本を買いあさるの、と笑いながら許してくれた。だからおれの部屋は本でいっぱいだよ」
外では音もなく雪が降っている。突然、中尉が
「どうじゃ、おれが三省堂からはじめて九段下までの古本屋の店名を順に云ってみようか。始めるぞ」
「まずだな。たしか大屋書房を振り出しに、東書店だよな。そして東陽堂、玉英堂・・・・・・」
「いえ、その間に三軒ほどあります」と藤井
「そうか、続いて文川、村山、悠久堂、そして一誠堂支店、角に島崎、小宮山」
神保町や本に親しんだ生活から遠く隔たれた、戦時下の音のない夜、二人の目の前に往時の感覚が、街並みという姿を借りて現れてくる。K中尉と藤井は、書店名を呼び合いながら、将校と兵隊の階級を忘れ、久々に大声で笑い合ったのだった。笑いがやむと、突然K中尉は黙り込んで、考え込むように遠くを見つめた。藤井ははっとして身を固くした。運命は迫っていた。
K中尉と三度目に会ったのも夜中の勤務でだった。その夜の中尉は、年長の藤井になんだか甘えた調子で彼の身の上を話した。父のいない家庭で育ち、大学中途で学徒出陣をし、海軍飛行予備学生として厳しい訓練をうけ中尉になった。中尉は吐き捨てるように叫んだ。
「お前なら分かってくれるだろうが、おれは神保町を一軒一軒歩いて集めた本をもう一度見てみたい。母や妹のことはもう諦めているが、本だけは何としても読みたい。おれはそれが心残りだ。」
そして1週間が経った。藤井がK中尉を目にしたのはその時が最後であった。中尉は飛行帽をかぶり、純白の襟巻をしてまったく凛々しく輝いていた。
「藤井上整、別れの時がきた。いままで3回、お互いの勤務はほんとに楽しかった。神保町で集めた本のことは忘れていたが、藤井上整と会ってまた思い出し、2、3日やりきれない気持ちですごした。おれの青春時代そのものの神保町だった。藤井上整、おれは昨日たった一つの願いを上司に伝えた。もしも藤井上整がいつの日か故郷へ帰ることになったら、必ずまた神保町へ復帰してほしい。そしてこれから続く若い学徒にいい本を安く与えてもらいたい。お互いあすの日が分からないが、おれの方はダメだ。」
K中尉は自らが上官であるのに自ら挙手の敬礼をして、部屋を出ていった。中尉との永遠の別れであった。
翌日、時ならぬ全体集合があった。同年の兵180人が整列すると、藤井1人のみ大阪へ移動、残りの179人は某所へ移動の旨が告げられた。陰鬱な雰囲気の岩国から抜け出せると喜んでいた彼らは、輸送船の撃沈でほとんどが全滅したと、藤井は後に伝え聞いた。
藤井は本のなかで述懐している。
「考えてみると別れ際、中尉が上司に伝えたという『たった一つの願い』とは私の大阪移動のことだったに違いない。死地に赴くに当って、上司に願う唯一の特権を、中尉は私に与えてくれたものと思う。思うだに不思議な私の後半生というほかない。軍隊は運隊ともいうが、中尉のことを思うたびに胸が痛んだ。神保町という古書の街に救われた私の命でもある。」
戦争が終わったのち、藤井は中央線吉祥寺でふたたび古本を扱い始めた。K中尉の望んだ神保町へ戻ることはとうとうできなかったが、年の瀬になるたびに藤井は中尉のことを思い出すという。
※下記の書籍からの抜粋です。興味持たれた方は「日本の古本屋」というサイトで検索すればヒットするかと思います。Amazonでは取り扱いないようです。
こつう豆本103「私の古本人生」藤井正 日本古書通信社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
