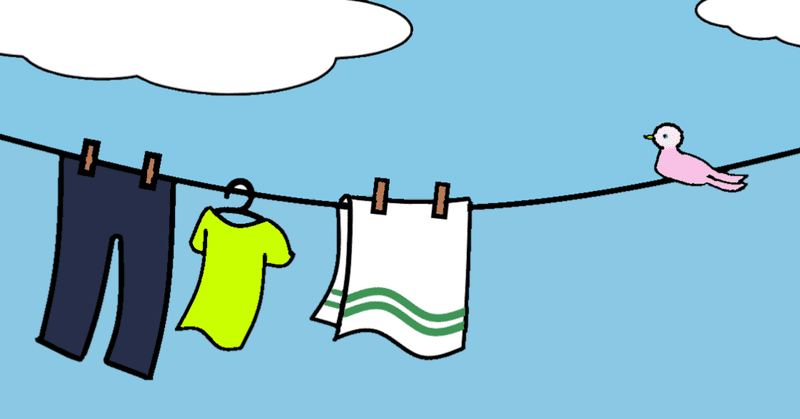
何が怒りを買う?【『炎上CMでよみとくジェンダー論』を読んで】
はじめに
東京大学大学院総合文化研究科教授である瀬地山角氏の『炎上CMでよみとくジェンダー論』(光文社、2020年)を読んだ感想を述べる。本書は、CMが「炎上」した例を見ながら、ジェンダー論の基本的な考え方が学べるものである。巻末に付録として「広告の”炎上”史」がある。
著者は大学でジェンダー論に関する講義を行っており、そこでの様子も本書のなかで語られる。講義は爆笑で包まれるそうであるが、その雰囲気がなんとなく本書からも伝わってくる。
男女の「平等」と「自由」は同時に考えるべき
筆者の男女平等に関する考え方は、非常に説得的である。それは、男女平等を目指す際は、同時に性別にまつわる「自由」も考慮するべきであるというものである。
「男女の平等」は、「性別からの自由」を一緒に含めて考えなくては意味がないというのが、私の一貫した立場です。性別に関しては「平等」という概念だけでなく、「自由」という概念が不可欠なのです。この場合の自由というのは、性別にかかわりなくある人が自分の能力を発揮できる、性別にかかわりなく、個人として扱われる、ということを意味します。(p.49)
男女をまず平等にして、そこから性別からの解放を志向するべき、という段階的な意見も目にする。ところが、それで男女平等は実現できるのであろうか。言い換えれば、「男性/女性らしさ」の観念を強く残した状態での男女平等は、本当に「平等」であるといえるのか。男女の「平等」と性別からの「自由」は、表裏一体なのである。
そして、この理念の下、炎上したCMを分析していくのであるが、その類型化も興味深い。CMの訴求対象が男性か女性かという視点の軸と、「性役割」か「容姿・性的メッセージ」かという領域の軸のマトリックスで4つに分類される。このように、批判された過去のCMのポイントが、グラフで明文化されているということで分かりやすい。また、それらとは対照的に炎上しなかった「成功した」CMも紹介される。
「炎上」とは何か?
ところで、本書において「炎上」とは何を指すのかが、いまいち明確に読み取れなかった。「批判された」「反感を買った」のような表現がされるが、どのような方法で、どのくらい人が何と言ったら炎上とカウントするのか、というのが少し気になるところである。
炎上することがどういうことかについては、漠然であってよいとしても、筆者の立場がよくわからなくなることもあった。タイトルが『炎上CMで‴よみとく”ジェンダー論』であるから、炎上するメカニズムが説明的(因果関係を記すように客観的)に議論されると考えていた。ところが本書の構成は、筆者の理念とするべきジェンダー論がまずあって、それに反しているCMを批判するというものであるようにみえる。「私が問題と感じた」というような切り口で始まるのである。正しいとされるジェンダー観が存在し、それに反しているCMを批判するということが議論の目的であるならば、議論の対象を「炎上」したCMにする意義は薄くなるのではないであろうか。反対に、炎上したということにスポットライトを当てるのであれば、炎上という現象の背景にあるジェンダー論が重要であるということになり、分析者となる筆者の理想とするジェンダー規範がどういうものなのかはさほど問題ではなくなる。このように、「○○のようなCMがジェンダー論的に正しい」という規範的な議論なのか、「ジェンダー論的な立場に立つ人がいて、その人たちがこのように感じたから、△△は炎上した」という説明的な議論なのかというのが、私はよくわからなくなってしまった。
加えて、筆者の「問題である」という表現について、どのような意味で用いられているかがはっきりとは理解できなかった。
インターネットはかつて、ある特定の人たちが見る者でした。しかしいまはまったく違います。これまで取り上げた事例のほとんどがウェブサイトでの広告・PR動画ですし、炎上というのはつねにネット上で起きています。ネットはほぼ公的空間になり、想定外の人が見る可能性が十二分にある。マニア向けのサイトなら何も問題にならないはずのコンテンツを、広告に持ってきて失敗したというのがこれらの事例なのです。(p.133)
ここでの「問題」とは、ジェンダー論的に認められないことをいうのか。いやそうではなく、あるいは、「○○では問題なかったのに、広告であったから失敗した」という内容から、問題は炎上することを指すと読める。
しかしそうであるなら、炎上することはなぜ問題なのかを考える必要があり、それは読者が行う必要があるということなのかもしれない。「炎上」が主観的な「嫌い」の集まりであるとしたら、その「問題」とはなにか。人に不快な思いをさせてはならないという道徳的な問題なのか。人気が落ちて商品が売れなくなるといった経営戦略的な問題なのか(もっとも、売り上げがどれだけ落ちた、のような議論はあまりないようである)。ということで結局は、「炎上とは何か」という話にもつながってくる。
理想と現実のはざま
筆者は、炎上するCMの特性として、現実を映し出していることであると指摘する。
高度成長期に生まれた性役割分業規範にそのまま乗っかった広告が批判の的となるは当たり前、といいかえることもできます。こうして見てくるとストライクゾーンが狭くなるなか、CMや宣伝動画が目指す方向性は、極端にエッジを効かせるのではなく、また現状を追認するのでもなく、時代の「半歩先」を描くことなのではないかと思います。(p.188-189)
企業の思惑としては、現状をリアルに描き出すことで、視聴者、消費者の共感を誘い、認知、購入などさせるということであろう。しかし、その現状に不満を持つ者にとっては、批判の対象になり「炎上」するという仕組みである。
ところが、CMを批判をした人以外に、企業の狙い通り共感した者もいたことは否定できない。企業にとっては、より多く商品が売れることが重要であると考えることが多い。万が一、批判した者は少数で、どうも思わなかった、あるいは肯定的に捉える者の方が多かった場合は、炎上したのに「成功」ということになってしまう(もっとも、この本で取り上げられた炎上CMの多くが炎上後CMを取り下げている)。やはり、どのくらいの人が批判したのかということが分からない限りは、なんともいえない。
ちなみに、その「現状」について、本書の第1章には、総務省のデータが掲載されている。夫と妻の家事時間に関するグラフで、「共働き世帯」は両者9~10時間を「仕事等」または「家事関連」に費やしていることがわかる。夫は仕事等に8.31時間、家事関連に0.46時間、妻は仕事等に4.44時間、家事関連4.54時間である。共働き世帯は一般に、夫の方が労働時間が多く妻の方が家事の時間が多いようである。
筆者はこのことについて、以下のように述べている。
共働き世帯の家事関連時間、夫婦の時間を足し合わせると5時間40分なので約6時間。つまり夫が1日3時間家事をすれば、妻も正社員で働けるという計算になります。(p.72)
そもそも年間に残業代で300万だの500万だの稼げますか?年間300万だとすると月の残業代が約25万になり、かなり無理がある額ですが、仮にできたとしても、そんな働き方を1年も続けたら、翌年は「あの世」でしょう。つまり妻が正社員での就労は、家計に異次元の追加収入をもたらすのです。(中略)どう考えても合理的なのに、なぜ普及しないかというと、男性が自分自身のアウトプットだけを最大化しようと考えてしまうからです。自分の成果や収入だけを最大化するという戦略をとらず、夫婦ふたりのアウトプットを最大化するというスタンスをとれば、残業など断ってさっさと保育所に直行し、夕食を作って妻の帰りを待つ方が、はるかに合理的な行動なのです。(p.74-75)
たしかに、夫婦両者が正社員ならば多くの収入が稼げると思われる。理想としては機能する。しかし現実問題として、男性はそのために簡単に残業を減らすことができるのであろうか。残業して仕事を終わらせることは、企業など組織全体の要請であり、ある一人が「家事をするので!」と早く帰っていくことを(黙示的なものも含めて)許すかというと難しい。理想的な状況は何かと考えるのと同時に、現実的に実現させるにはどうするべきかということも考えたい。
つまり、これは男性(夫)の意識といった個人的な問題ではなく、会社での雇用の仕方、働かせ方、休業の取り方といった社会的な構造の問題である。働きたい女性が多くいるとしたら、彼女らがより社会で就労できるような仕組みができるように、社会の労働システムを抜本的に変えれば、筆者の提案が実現すると思われる。
「僕」は男性的か
東京オリンピックのボランティアのキャンペーンの広告で、「僕らのアイデア」というように一人称で「僕」が使われていることを筆者は批判した。
「僕」は男性が自分を表すときに使う代名詞。ボランティアをするのは男性だけではありません。また、このアイデアコンテストは応募者を男性に限定したものではないはずです。それなのに、どうして「僕」という表現を使うのか?しかも、よりによってオリンピック・パラリンピック大会に関連してのキャンペーンで、です。下の応募資格にはご丁寧に「国籍不問」となっているのに、最初の表現が性別を問うワーディングになっています。(p.195-197)
筆者が運営事務局に抗議のメールを送ったところ、以下のような返信が来たという(一部抜粋)。
若者向けのヒット曲の歌詞にもいくつか見られますが、若い世代が「僕」という言葉を男性・女性の区別の意識なく受け止めているという側面に着目し、この言葉を採用した、という経緯になります。(p.199)
筆者はこれに対し以下のようにさらに批判する。
確かに、一人称として、「僕」を使う女性はいるかもしれません。おっしゃる通り、若者向けの音楽の歌詞にも出てくるでしょう。欅坂46の『不協和音』で「僕は嫌だ!」と叫ぶ箇所がありますが、あれの主語は男性のように思えます。いずれにせよ発話の際に、自分のことを「僕」という女性は圧倒的に少数であり、あえて「僕」を使う理由にはなりません。(p.200)
私は率直な感想として、「そうかな?」と思った。たしかに、「僕」と言う人が男性か女性かどちらが多いかといえば、しいていうなら男性という感じではある。しかし、男性の方が使う人が多いから「男性的」であり、それを公的に使うのは男女平等ではないとなってくると、ではどのくらいの偏りが生まれたら「男性的/女性的」なのかという問いが浮かび上がる。私は「僕」という言葉が男性的であるという印象を感じないので(メールを返信したオリンピックの関連会社もそのよう)、個人差の問題になってしまうのであろうか?
むしろ、「僕というのは男性的である」と主張することは、ジェンダー的規範を再生産してしまい、「性別からの自由」とは逆向きになってしまうのではないかという危惧がある。「僕」を使うのが男性的である(と社会一般で考えられている)とすると、上記のような広告を「男性的で偏っている」と批判する必要があるかもしれないが、一方でそれ自体が「男性の規範」を再構成するというジレンマに陥る。やはり、性別からの自由という理想があるが、「○○は男性的」とか「△△をするのは女性」のような規範的意識が実際として存在しているとき、どのように平等を実現するかというのは難しい。ここでも、理想と現実のはざまで揺れ動くジェンダーが見え隠れする。
ただし、とりわけ公的な機関は、自分たちは僕が男性的であるとは考えないが、そう思う人もいるかもしれないので避ける、というような危機管理は必須であると思われる。
「上から目線」の主張は受け入れられるか
最後に、本書の議論の本筋とは少しずれるが、感じたことを述べておく。
著者は、本書のいくつかのところで、ジェンダー論的視点を持たない、受け入れない者に対して少々否定的な評価をしていた。
自信満々で「なんの問題もないですよ」といわんばかりの返答です。全然わかっていません。メールを読んだ瞬間に「あ~ぁ、やっちゃった」と思ってしまいました。(p.199)
こうした一連のことに対して、「言葉狩りだ」としか思えないとすれば、越した言葉をめぐる政治に関して、知識が不足している、もしくは古いと考えた方がよいと思います。(中略)もう少し人権感覚をアップデートしてほしいと思います。(p.212)
私は、著者の言っている理論は正しいと思う(私の能力不足からか、前述のように議論の方法や構成に関してはわからないところがあったが、根本の理念に関してはほぼすべてについて適切であると考える)。「男女『平等』には性別からの『自由』も必要」「家事をシェアしうる社会がよい」「半歩先を描くと炎上しずらい」など、本書の内容は共感・納得するものが多かった。
しかし、それを受け入れない人がいるのも事実である。理由はさまざまであろうが、「炎上」が起きていることからも、現状としてはジェンダー論的考え方はまだ完全には受け入れられていない。
そこで、ジェンダー論的考え方をより広める、理解を求める、受け入れさせる必要があるとしたときに、どのようにすればそれが実現するかという戦略的な問題が別に浮上してくる。特に、制度的に変革しようとしたら、他の人間の選挙などの投票行動を変えてもらわなけらば困難である。
その際、「わかってない」「知識不足」「アップデートしろ」というな内容を主張すると、「わかってない」人たちはどのように感じるのか。少なくとも快くは感じないであろう。もしかしたら、怒ったり心を閉ざしたり話を聞かなくなったりするかもしれない。そうすると、「正しい」理念を持っていても、受け入れられるという目的は達成されない。
アメリカの元連邦最高裁判事のルース・ベイダー・ギンズバーグは、”Fight for the things that you care about. But do it in a way that will lead others to join you.”という言葉を残したとされる。「あなたが大切に思うことのために戦いなさい。ただしそれは他の人をあなたに同調する気にさせるであろう方法で。」といった意味である。何が正しいかという「正当性」の議論と、どのようにすれば受け入れられるかという「正統性」の議論は、分けた上で同時に考えなければならないのではないか、というのが私の感想である。
おわりに
本書は、ジェンダー論の基本的な考え方を学ぶのによい本である。また、そういった思考法が、CMという生活の一部にあるものを分析するうえで役立つということがわかったのが面白かった。本書の著者はとても愉快な感じがするという印象を受けたので、彼の講義を聞いてみたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
