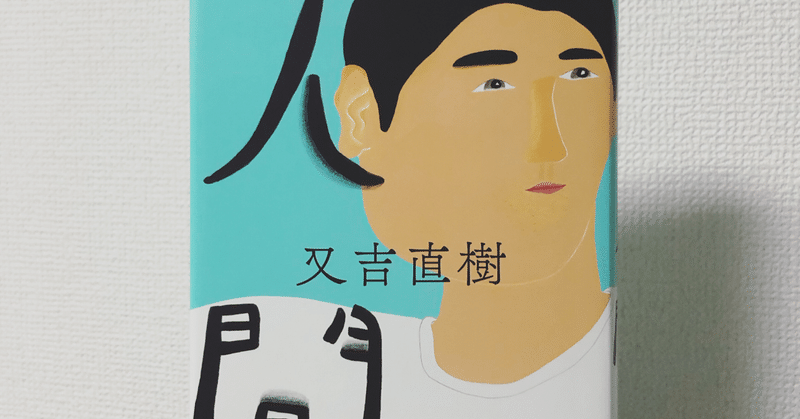
人間(又吉直樹)
顔も名前も覚えているのに、自分が彼をなんと呼んでいたかが思い出せず不安になる。
_冒頭に出てくるこの文が、主人公の不器用さと繊細さを教えてくれる気がして。
あぁ、この主人公は考えなくてもいいことを考えて悩んでしまうんだろうなと、同じことを思ったことがある私はそれだけでこの本が好きになった。
「いまが尊いと最近おもうようになった。ほとんどの時間を忘れてしまうから。その過ぎていく時間に自分がなにを感じていたのかさえ忘れてしまうかもしれへん。それが、たまらなく怖くて、たまらなく嬉しい。
いまという時間のなかで自分が自在であることに、ようやく気づいた。」
_人間にとって、記憶は切り離せないもの。
だけれどそれはひどく曖昧で、誰しも確実とは言い切れないものばかり。
そしてその曖昧な記憶は、時間の経過とともに削られたり、その時の雰囲気などを纏ったりする。
そうすることで生まれた記憶は、時に事実と異なってしまうこともある。
でもそれもひとつの記憶のあり方かもしれない。
起きた出来事に、自分が感じた感情や温度が混ざり合って記憶として残るのであれば、それはその人にとってのまぎれもない"記憶"ともいえる気がする。
曖昧であることを意識している人間は、意識してない人間よりずっと不器用かもしれない。
ただ、みんながみんな上手に人間をやれないからこそ、生まれるものがあるのだと思う
____
自分が把握している自身の記憶なんてものは、やはりほんの一部分でしかなく、おなじ人生であったとしても、どの点と点をむすぶかによって、それぞれ喜びに満ちた物語にも暗澹たる物語にもなり得るのかもしれないとおもった。
この感覚は自分が本来持っていたものではなく、彼から聞いた話に影響を受け、新たな言葉で構築された記憶かもしれない。
僕が話したのは、見たものそのものだけではないのかもしれなかった。風景と感じたことが融合されたものこそが見えたものだった。僕にとって物語るとはそういうことであり、状況をそのまま説明することではなかった。
---------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
