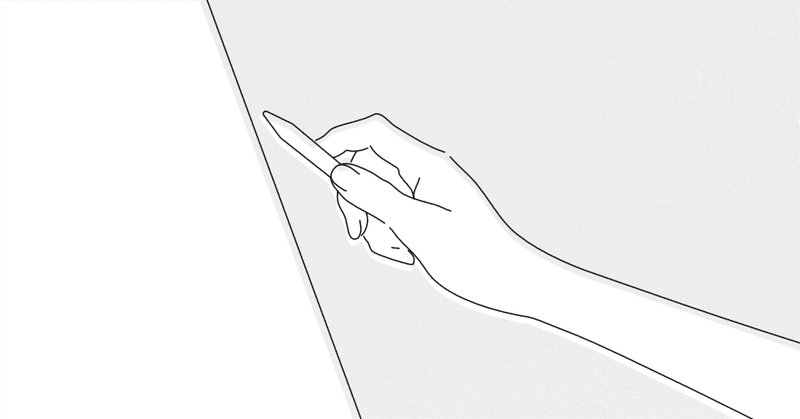
【短編小説】 余白とキャンディー
「君には余白がないよ、窮屈だ」
そんな捨て台詞で5年間付き合ってきた恋人はアパートを出ていった。二人暮らしのために借りていた部屋は一人には広すぎる。皮肉だ。そうやって彼を失ってから私の生活には有り余るほどの余白が生まれてしまった。別れ際は気丈に振る舞っていたというのに、そんなことに気づいてしまってからは涙が洪水のように溢れてダブルベッドに顔をうずめてわんわんと泣いた、それでもベッドシーツの皺は一人分しかできない。寂しさの果てに私の体はマットレスに沈んで真っ暗な部屋で立ち上がることができなくなってしまった。比喩表現の類ではない、本当に、なんだか力が入らなくなってしまったのだ。心にも体にも。そのまま眠って、カーテンから差し込む光で目覚めて起きあがろうとしてもやっぱりうまく体が反応しない。
そんな事件というか変化があってから、私の人生は流れを変えた。不動産の営業として男社会の企業風土の中で泥臭く働いた結果、同期の誰よりも早く営業課長に昇進したそんな人生から、平日の午前中に心療内科に通って、その帰り道に河川敷を見渡せる大橋の欄干に体を預けて川の流れをぼんやりと眺める日々へと。
溜め込んだ有給を注ぎ込んでとりあえずは1ヶ月の休みを申請した。それでも崩れたバランスは戻らずに、半年間仕事を休職することになった。昇進は白紙になってあれだけ燃えていた仕事に対するモチベーションは嘘みたいに鎮火してしまった。実家には帰らずに貯金を切り崩しながらの生活。焦りだけが目の前に広がって、いてもたってもいられなくなるのだけれど、そんなときにはポケットから包み紙を取り出して、それを解いては中から出てくるカラフルな塊を「今日は紫だ」なんて色占いのように確認してから口に含む。溶け出す果糖は甘く口の中に広がって、心が和らいでいく。そうしてただただ河川敷を散歩する人や昼下がりの日差しを反射する水面に目を向ける。
「君には余白がないよ、窮屈だ」
その言葉に心の中で返す。
「今の私には余白があるよ。だけど肝心の中身も全部消えちゃったよ」
小さく、圧の強い字でぎっしりと書き込んだ自己PR、職務経歴が自慢だった。いつかの面接で答えた「私を動物に例えるならマグロです。理由は、立ち止まることなくずっと動き続けるからです」なんて言葉が蘇る。残業終わりの居酒屋でジョッキを開けて先輩後輩分け隔てなく語りかける自分が好きだった。人口減少の時代に不動産業が見据えるビジョンだとか、この投資熱を不動産ビシネスとしてどう活かすべきかとか、思い返せばやっぱり窮屈だったのかなって思う。
口の中でキャンディーの甘さが潮が引くような緩やかさで消えていく。季節の移ろいを告げる涼風が髪を掠めて揺らす。この風もこの大河を渡って海へと還っていくのだろう。私は預けていた体を起こして、再び橋を渡る。いつもは車で通り過ぎるだけだったこの場所を歩くようになって、見てるようで見えていなかった風景や店が目に映るようになった。
「今の私には余白があるよ。だけど肝心の中身も全部消えちゃったよ」
自分の言葉を反芻して、私は堤防沿いに開かれたアトリエに足を踏み入れる。中からは恰幅の良いマダム風情の先生がいつもの朗らかさで迎えてくれた。挨拶をして教室に入り、定位置にイーゼルを立てキャンバスをかける。まだ習い始めたばかりで、おろしたてのキャンバスには贅沢な余白があって、そこに新しい色を書き足していく。
【あとがき】
人生には想定外のことがたくさんある。僕の経験をとっても、この人と結婚するんだろうな、とか、この仕事ずっと続けていくんだろうな、とか見据えていた人生の道が突然阻まれて、全く違う方向に進んでしまったことがある。それでも日常は続いて、人間というのは適応する生き物だからいまの環境に当たり前のように慣れてしまっている。20歳の自分に「今の自分こんなだよ」なんてタイムマシーンに乗って伝えたら多分腰を抜かして驚くと思う。だけどそれで、過去の自分が「じゃあ、どこかで選択肢を変えましょうか」なんて気を利かせてくれても、「まぁ、大丈夫」って答える気がする。ここまでの道のりに後悔がないわけではないけど、そもそもまだ道半ばだし、やっぱり「まぁ、大丈夫」って答えるんだろうなと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
