
ぼくと彼女は大哺乳類展へ行く
ぼくと彼女は『大哺乳類展』へ行く。4月のある日曜のこと。ぼくは彼女(ぼくがゲイであることを知らずにぼくと付き合っている気の毒な横浜市民)の由梨と一緒に、国立科学博物館の特別展『大哺乳類展3-わけてつなげて大行進』へ行った。
変な言い方になるが、ぼくは哺乳類が結構好きな人間である。どれぐらい好きかっていうと、去年の夏にも由梨と一緒に国立科学博物館の企画展『科博の標本・資料でたどる日本の哺乳類学の軌跡』へ行ったっていう程度には好きだ(「ぼくは哺乳類が好きだ」という記事を書きました)。ただ、よくよく考えてみなくても、ぼくは哺乳類より恐竜のほうが好きで、本気で哺乳類が好きなのは由梨のほうかもしれない。今回、『大哺乳類展』行きを提案したのも由梨の側だったし。ただ、ぼくも「『大哺乳類展』行こうよ!」と提案されて「おっ、いいね。行こう、行こう」と素直に応じてしまった程度には哺乳類が好きだ。
国立科学博物館では『大哺乳類展』というのを過去に2回やったことがあるらしい。1回目は2010年、2回目は2019年に開催されたそうだ(ぼくはどちらも行っていない)。そして今回は第3弾となる。サブタイトルは『わけてつなげて大行進』。なんのこっちゃという感じだが、このサブタイトルの意味は展示を見ているうちに判明する。っていうか、このサブタイトルはまさに今回の展覧会を一言で言い表すドンピシャなサブタイトルであった。
4月のよく晴れた日曜日。JR京浜東北線の蒲田駅のホーム(大宮方面)で由梨と待ち合わせ。今回のぼくは20分近く遅刻してしまった。4月に入ってからぼくは体調が優れないんだよな。体調が悪い……っていうか、気力があんまり湧かないっていう感じ。インカレの放送サークルの番組発表会が控えているのにそんなこと言っている場合ではないし、いつも長文のnoteを書いておいて何を言っているんだと思われるかもしれないが、それとこれとは話が別ということで。とりあえず、その日のぼくは遅刻したので由梨に平謝りで、お詫びのしるしに「あとで言うこと何でも聞く」と約束した。
上野駅に到着。公園口に出て、国立科学博物館の特別展チケット売場へ。学生証を見せて割引料金で入場させてもらう。ぼくの大学も由梨の大学も「大学パートナーシップ制度」というのに加盟しているので、常設展は無料、特別展も通常の料金より割安で入れるのだ。どうだ、羨ましいだろう?(生意気ですみません)
100円入れないといけないけどあとで100円返ってくるロッカーに荷物を預け、エスカレーターを降りて特別展の会場へ向かう。国立科学博物館の敷地内に入った時点でもはや察せられたことではあるが、場内は大勢の観覧客で大変に混雑していた(かくいうぼくらも混雑に貢献した一味である)。一応「ごあいさつ」のパネルを撮影したが、混雑の中でパッと撮ったのでめちゃくちゃ写真がブレてしまったよ!
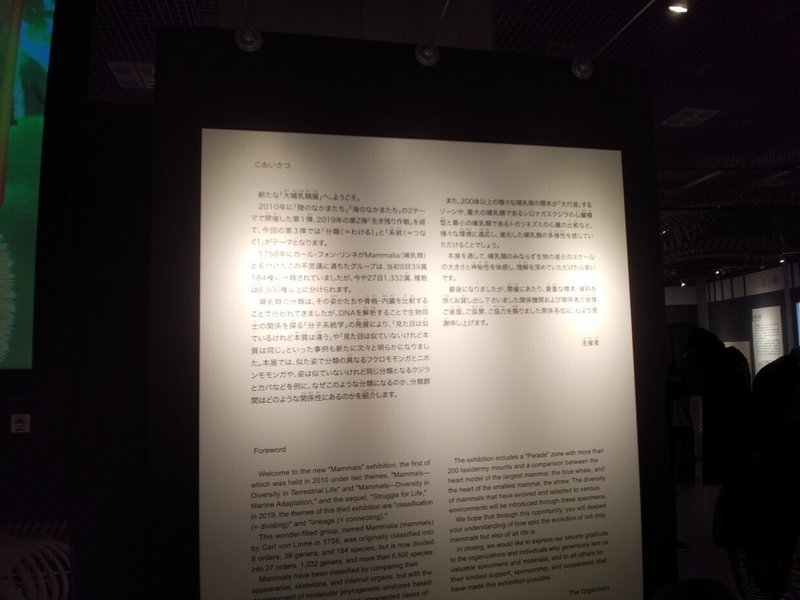
「哺乳類」というのは1758年にカール・フォン・リンネという生物学者が名付けたグループである。哺乳類は当初は184種だったが、現在は6,500種以上が存在する。当初、哺乳類は姿かたちや骨格や内臓によって分類されていたが、DNAを解析して生物同士の関係を見つける「分子系統学」の発展によって、「見た目は似ているけど本質は違う」とか「見た目は違うけど本質は同じ」とかいうことが分かってきた。今回の『大哺乳類展3』はその「分類(=わける)」と「系統(=つなぐ)」の歴史を標本とともに紹介する大展覧会である。……ということが、この「ごあいさつ」のパネルには書かれてあった。いつも思うけど、展覧会のこういう解説パネルの文章を書くひとって優秀だよな。無駄がなくて分かりやすい文章を書くじゃん。「『大哺乳類展3』に彼女と行ったけど待ち合わせ時間に20分近く遅刻しました」という話を1,000文字かけて書いているぼくとは大違い。ぼくも本当はもっと効率的な人間になりたいのですが……
『大哺乳類展3』の展示物で最初にぼくの目を引いたのは、シロナガスクジラの心臓(実物大レプリカ)だ。高さ約166cm。もちろん由梨の身長より高い。ぼくはこのレプリカを見て、動物の心臓の大きさは体の大きさに比例するということを初めて知った。動物の心臓の大きさなんて考えたことがなかったのである。ぼくが「由梨よりデカいじゃん、この心臓」と言うと、由梨は「うん、かくれんぼの時にこの中に入ったら見つからなさそう」と返してきた。相変わらず変なことを発想するひとである。

そしてお次は「分類と系統」のゾーンへ。「比べて、わけて、つなげる。分類学はあらゆる自然史研究の基礎である」ということで、哺乳類の分類の基準が紹介されていく。「見た目で分類しました」とか「内臓で分類しました」とか。ぼくは結構このゾーンが好きだ。倫理学徒(西洋倫理思想史専攻)っぽく言うなら、西洋の思想家を「経験論派」とか「ドイツ観念論派」とか「プラグマティズム派」とか分類するの大好き。


哺乳類の種類の中で、ぼくがいちばん心ときめいたのは「皮翼目(ひよくもく)」と「翼手目(よくしゅもく)」だ。なんていうか……ふつうにかわいくないですか? どちらも見た目は似ている。コウモリみたいなやつ。もしくはコウモリそのもの。ぼくが「皮翼目」のマレーヒヨケザルの標本を見ながら「かわいいなあ、これ」と言ったら、由梨は「ね! ちいかわに出てくるモモンガみたい」と返してきたけど、ぼくはちいかわに詳しくないのでよく分かりません。それどころか、この前の春休みにちいかわコラボキャンペーン目当てでくら寿司に2週連続で連れて行かれたことを思い出して、なんとなく複雑な気持ちになりました……


「見た目にだまされるな」というコーナーも気になったな。見た目は似ているんだけど分類的には違うカテゴリなんですっていう。世の中にはそういう哺乳類もいるのだ。「見た目にだまされるな」というのは人間社会にも当てはまる話かもしれない。例えば、ぼくと由梨は傍目には異性愛カップルに見えると思うが、実際には「ゲイであることを隠している男とそのことに気付いていない女の迷コンビ」である。見た目にだまされるな。

ちなみに、哺乳類には陰茎にも分類がある。ウシの陰茎はS字状に折り畳まれているそうだ。キリンの交尾は「一突き型」と呼ばれていて、外敵に襲われないように一瞬で終えるそうだ。ぼくはゲイなので、正直言って陰茎に興味がないわけではない(というかある)。ぼくは由梨に不自然に思われないように、「他の展示物の写真をパシャパシャ撮っている流れでこれも撮っちゃいました」的なノリで哺乳類の陰茎の写真を撮りましたとさ。

さて、いよいよ我々は『大哺乳類展3』のいちばんの目玉(?)、「哺乳類大行進」ゾーンへ向かいます。ここでは200体以上の哺乳類の標本がびっしり展示されている。だけど、大きさや見栄えを気にして並べているんじゃなくて、詳細な系統関係の順に並べているっていうのが国立科学博物館の国立科学博物館たる所以ですね。学術的ー!


由梨はジュゴンとかマナティーが好きなひとなので、そういう海系(?)の哺乳類の標本を見て興奮していた。ぼくが撮影したこれ(写真の左側のやつ)がジュゴンなのかどうかは記憶が定かじゃないんですけど。それから由梨はキリンの骨格標本にも感心してたな。「キリンって細いね!」とか言って。たしかにあの大きな体をこの細い脚の骨で支えているのかと思うと、ぼくもキリン先輩にリスペクトの念を抱かないわけではない。


ぼくはこう見えて(?)ハイエナが好きなので、ブチハイエナとシマハイエナの標本を見て興奮した。ぼくが「かわいいー! ハイエナがこっち見てる!」と言ったら、由梨は「そこに立ってればね。自然と目線は合うよね」と冷静にツッコんできた。ぼくが由梨の肩を掴み、ぼくの立っていた位置に由梨を立たせて「ほら、ハイエナと目が合うでしょ?」と聞いたら、由梨は苦笑いしながら「合った、合った。目が合った」と冷ややかに反応していたけど、実はあの時の由梨はハイエナと目が合って内心怖かったんじゃないかとぼくは睨んでいる(だとしたらごめんなさい)。


特別展の第1会場を出て、廊下を通って第2会場へ。哺乳類の分類に貢献した歴史的人物(動物学者とか博物学者とか)を紹介するコーナーだ。第2会場といってもこの部屋は狭い。そしてひとが少ない。さっきまでたくさんいた観覧客のほとんどはここを素通りしてしまうんだろうな。「昔の学者の紹介なんて知ったことかよ」って。でも、哲学科に在籍する身としては「アリストテレス」なんて単語を見ると無意識に立ち止まってしまうわけでして、ぼくと由梨はこのコーナーもしっかり観覧しました。まあ、ぼくより由梨のほうが解説パネルの文章を真面目に読んでましたけどね。

オールドフィールド・トーマス(1858-1929)という英国の動物学者を紹介するパネルの前に4歳か5歳ぐらいの男の子がいて、その子がお母さんらしき保護者に「トーマスだあ! ぼくトーマス知ってるよ!」と言っていた。たぶんその子が知っている「トーマス」は英国の動物学者のほうではなく、人間の言葉をしゃべる機関車のほうだと思うのだが、その「ぼくトーマス知ってるよ!」の言い方がものすごくかわいかったので、ぼくと由梨は顔を見合わせて黙って微笑んだ。ほとんどの客がここを素通りする中、第2会場の展示物をしっかり観覧していたあの親子に幸あれ。

第2会場の最後では、「哺乳類分類学のこれから」と題して、「分子系統学は完璧ではない」とか「それどころか種の定義が揺らいでいる」とか「未知の哺乳類はまだまだいる」とかいうコラムを載せたパネルが掲示されていた。『大哺乳類展3』は哺乳類の分類をテーマにした展覧会だが、結局、この分類というのは、人間が「これが妥当だろう」という基準で勝手に仕分けたものにすぎない。しかもその基準自体も時代の変化や技術革新によって揺れ動いていっているわけで、絶対視したり神聖視したりすべきものではない。だったらそもそも動物の分類なんてやらなきゃいいじゃねえかという話になりそうだが、そうではない。生物を分類して体系的にまとめることによって初めて見えてくる「生物の実態」があるのだ。我々は答えを定めるために分類するのではない。答えを探すために分類するのである。
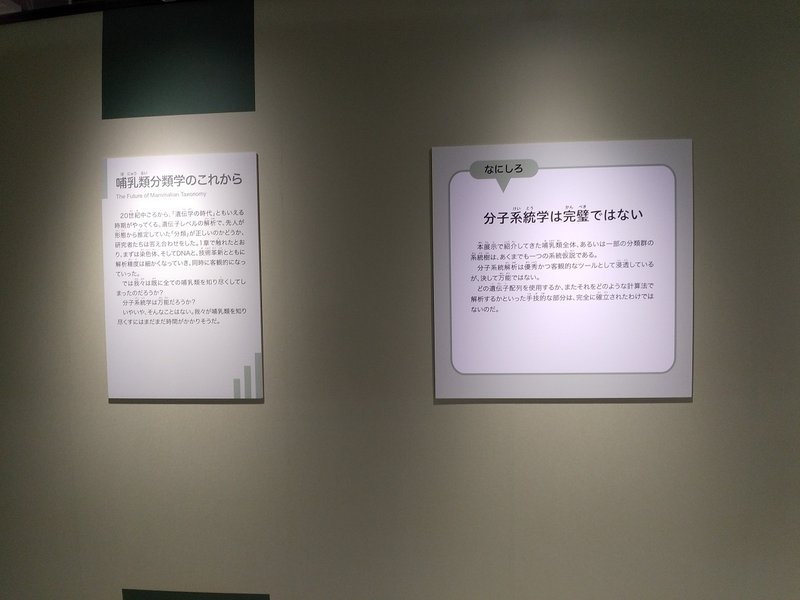

名言が飛び出たところで『大哺乳類展3』を退場し、特設グッズショップへなだれ込みます。由梨は北欧風イラストの巾着(だったかハンカチだったか)とお菓子を買って、ぼくは『鳥獣戯画』コラボのミニクリアファイルだけ買った。以前のぼくだったら放送研究会の部室に持って行くお土産用でお菓子も買ったと思うけど、いまはもう引退してしまったのでね。まあ、引退はしたが部員ではあるのだから部室にお菓子を持って行っていいはずだし、インカレの放送サークルで集まる時に持って行ってもいいはずなので、実際のところは「お土産代をケチった」というのが真相なのですが……
『大哺乳類展3』を出て、ロッカーに荷物を預けたまま、日本館1階の企画展示室へ行く。ここでは『大哺乳類展3』の関連企画として、企画展『知られざる海生無脊椎動物の世界』が開催されているのだ。カニやクラゲのような無脊椎動物(背骨を持たない動物)だけを紹介するという、ちょっと変わった展覧会です。ちなみに、ここは常設展料金だけでも入場できますよ。


珊瑚や真珠で作った宝石のコーナーを由梨が結構熱心に見ていたので、ぼくが「こういう宝石ほしいの?」と冗談っぽく聞いたら「ほしくないよ。こんな大きいの、使いみちがないし」と笑って返されたけど、もしかしたら本当は由梨も大きな宝石がほしいのかもな。そういえばぼくは由梨に一度もちゃんとしたアクセサリーを買ってあげたことないや(横浜のサンキューマートで買った390円のネックレスを除く)。
律儀にアンケート用紙に感想を記入したあと(ぼくらは放送研究会のモニターシートに育てられた人間なので)、ロッカーから荷物を回収し、出入口近くの売店で由梨の弟の孝彦くん用に宇宙食を買って(この前もらった東京ディズニーシーのお土産のお返し)、国立科学博物館を退館する。本日のぼくらはこのあとの予定もあるので常設展は廻りません。楽しかったよ、哺乳類たち! ついでに海生無脊椎動物たちも!
ぼくらはこのあと、上野駅公園口前の広い通りで阿久澤(放送研究会兼インカレサークルの後輩)とその彼女に偶然出会ったのだが、その話をここで書くと長くなりそうなのでやめます(たぶん次回書く)。その代わり、お昼ご飯で行ったレストランじゅらく上野駅前店にて、ぼくが由梨から呆れられた一件をご紹介しよう。ぼくがハヤシライスを食べながら「ジュゴンが哺乳類だなんて知らなかった。てっきり魚類だと思ってた」という話をしたら、由梨は「……ジュゴンは哺乳類だよ。哺乳類。人魚のモデルの動物なんだから」と真面目な顔でぼくを諭してきた。ぼくが少しビビりながら「……あはは、ぼくは理系の知識が欠けてるんだよねー!」と言い訳すると、由梨は「じゃあ、水が何度で沸騰するかは分かる?」とクイズを出してきた。ぼくが「……35……40℃ぐらい?」とおそるおそる答えると、由梨は「本気で言ってる?」と呆れ顔で聞き返してきた。
由梨の話によると、正解は「100℃」らしい。どうして100℃なのかというと、昔の人間が「水が沸騰する温度は100℃」と決めたかららしい。……なんだそれ! とんちじゃねえか! 人間の都合で「お前は水」「お前はお湯」「お前は哺乳類」「お前は魚類」などと分類される液体や動物たちが気の毒である。ジュゴンなんて哺乳類に分類されたはずなのに人魚のモデルにされちゃってるし。まったく、「分類」なんてふざけた行為だ!
……しかし、分類によって新たに見出される発想、新たに拓かれる世界があるのも事実である。例えば「カレーライス」と「ハヤシライス」は姿かたちは似ているが発祥の地も味付けのベースも違っていて(見た目にだまされるな)、両者が別の種類に分類されているおかげで「辛い料理が苦手なひとに振る舞うならカレーライスよりハヤシライスのほうがいいかも」と判断できるようになるとか。喩えとして合っているのか分からないけど。
でもまあ、『大哺乳類展3』に行ったことで、ぼくが「分類」の価値を意識できるようになったのは確かだ。「分類」には「わける」だけじゃなくて「つなげる」の要素もあって、異なるものを排除するのではなく結び付ける働きもあるしね。だからみなさんも、水が何度で沸騰するのか分からないひとが目の前にいても、「こいつは馬鹿なやつだ」と分類して切り捨てるのではなく、「こういうひとがいるおかげで理科の面白さを再発見できるね」という視点で温かく接してあげてください。くれぐれも、卵が乗ったミートソーススパゲッティを食べながら「小学生の時に習ったと思うんだけどなあ」などとイジるのはやめましょう。当事者からのお願いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

