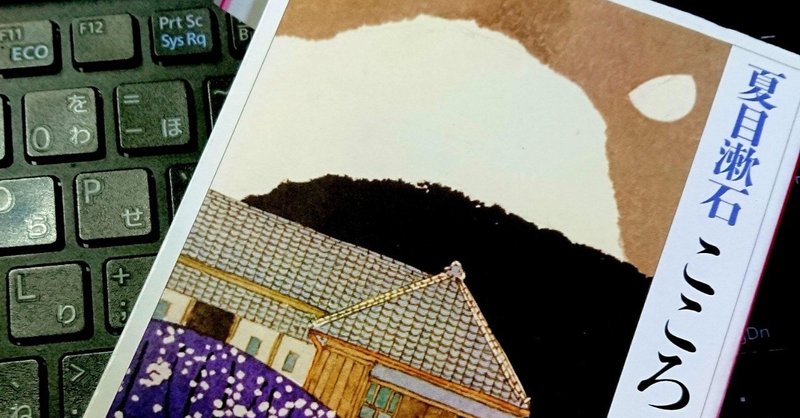
「文学部って何やってるの?」に対する答え方
「そりゃ君、『世界を面白くする』以外に何があるんだい」
とか言ってみたい。そしてジャケットを風にはためかせ、意味ありげに去っていきたい。しかしそれを許されるのは一部の才人だけだろう。よって天下に多く産み落とされた凡人の一人としてはできるだけ要領を得るようなことを書きたい。
というわけで、たまに見る問い「文学部って何やってるの?」に対する、現状での僕の答え方を書きます。「正解」はわからないので「答え方」としました。大枠は以前ブログで公開済みの内容ではあるけど、かなり加筆・修正してるから許してください。かの『To LOVEる』が天下を獲ったのもコミックス化のときの乳首加筆の力が大きい。それくらい乳首は偉大である……じゃなくて、加筆は偉大である。
また、文学部文学部言ってるくせに留年の関係上まだ「教養学部」所属なのも許してください。これのせいでじつはジモコロの文系不要論の記事もタイトルの時点で嘘が混じっていることになる。世の中にどうでもいいフェイクニュースをひとつ増やしました。
文学部=「文学+部」ではない
まず勘違いされがちなのが、文学部って別に「文学」をやるところではありません。「文学+部」じゃなくて「文+学部」、つまり「文」に関わるあらゆることを学ぶ学部なのです。って文学部長だかなんだかの偉い人が昔言ってました。
かつて、ある文学部社会心理学科の友人にこれを話すと「言われてみれば、文学部なのになんで俺文学やってないんやろ?ってずっと思ってたwww」などとのたまう始末。むべなるかな、やつは授業用に買わされた分厚い『万葉集』を枕にして安田講堂前で寝てたくらいの人である。言葉通り、枕頭(ちんとう)の書と言えなくもない。
まあ実際、東大で言えば「文学部」の中にも言語学、宗教学、考古学……と、わけのわからないカオス状態が広がっているわけです。したがって僕は自分の属する「国文学専修(国文)」以外の話はできません……と言いたいのだけど、残念ながら国文の話さえ満足にはできません。だって近代ならまだしも、上代や中世のことは何も分からない。今回は「大島の考える近代日本文学研究」くらいにまでジャンルを狭めます。本当はこれでもまだ広いかもしれない。
文学研究って何?
まずは知られざる名著の前書きから引用します。
批評やエッセイは商品である。研究論文も商品である。(中略)どちらも商品である以上、買ってよかった、読んでよかったと思ってもらわなければならない。一般の読者の「ふつう」の読み方に対して、それを念頭に置きながら、「ふつうでない」ことを言わなければならない。したがって、これらの商品は「ふつうは~だが、実は(しかし)~である」という文章構成になっていることが多い。(夏目漱石『坊っちゃん』をどう読むか :石原 千秋|河出書房新社)
この本自体も、『坊っちゃん』を100倍面白く読めるドーピング剤じみたシロモノなので別の機会にちゃんと紹介したい。ひとまず後書きへ続く。
(前略)もちろん、そういう「ふつう」がレベルが低いというわけでは決してない。「ふつう」が楽しい読者もいれば、「実は(しかし)」が楽しい読者がいるだけの話である。因果なことに、研究者や批評家は、どのようなレベルであれ、「実は(しかし)」と書けなければ食べていけないのである。
つまり「実は(しかし)」と書き、しかもそれが「面白い」ことが絶対条件だというのです。僕も同じような考えを持っていて、タイトルの「文学部って何やってるの?」に対してはさしあたり「文学をもっと面白く読む方法を探すこと」という風に答えております。あるいは、世界はボケと突っ込みで成り立っているとするボケ・突っ込み二元論(去年思いついた概念である)の立場から言えば「文学に斬新な突っ込みを入れること」でもいいです。
「人称と語りの構造はどうなっているのか?」(地の文は特定の誰かの視点に寄り添っているのか、あるいは作中人物の視点を行き来できる神の視点なのか、など)
「そうなるとここの地の文にこの表現が使われているのはおかしくないか?」
「つまり一人称の回想体の語りに伴うバイアスを考慮して物語を読み直すと、また別のストーリーが浮かび上がるのではないか?」
このアプローチは氷山の一角ですが、こうして既存の文学作品をこねくり回してはいろんな解釈を試みています。その「解釈」の余地が豊穣であればあるほど面白いのは当然で、僕がバカみたいに漱石漱石と言っている所以のひとつもそこにあるわけです。
イキり読者であれ
ともあれ言いたいのは、文学部とかじゃない人もぜひもっと「イキり読者」になってほしい、ということ。
冒頭の石原千秋先生の文章を見れば分かるように、文学研究者あるいは文学徒ってやつは新たな解釈(らしきもの)を生み出してはドヤ顔をキメている連中です。「イキる」という言葉は好きではないけど、学問として文学をやってる人は基本的にイキっている。
ちなみに石原先生は「ふつう」の読みが低レベルだと言ってるわけではありません。文学部だからって、「解釈」に熱を上げずニュートラルに楽しもうというときももちろんあります。
とはいえ昔の文学なんてのは時代背景からして違います。そうするとテクストに織り込む「面白さ」の質も違うわけで、当時の読者には面白かったことも現代の読者にとっては「何が面白いねんこれ?」って話になりかねません。僕も『三四郎』を初めて読んだときは正直あまりハマれませんでした。でも今ではあんなに面白い小説はそうそうないと思っています。(過去の自分にひとつ言わせてもらうなら、試験前にあわてて読む小説が面白いわけがないだろう。バカめ。)
もちろん文学の価値を決めるのは読者です。2019年現在の読者がつまらないと感じるのならそれは単純な「賞味期限切れ」なのではないか。
そう思う一方で、僕はまだ近代文学を諦めきれません。近代文学が、漱石文学が、終わっていくのを認めたくありません。なぜなら自分自身が感動してしまったから。イマイチ面白くないと思っていた『三四郎』が、文学者の施す「解釈」によって無限の遊び場へと転じていくプロセスを味わってしまったから。
だからもっと各々好き勝手にイキった解釈をして、語り合って楽しんだらいいんだろうなと思います。そもそも「文学」って字面が悪い。カタくて近寄りがたいでしょう。こちとらもっと低俗(とあえて言う)な楽しみ方がしたいのだ。たとえば、『こころ』にまつわる以下の5通りのストーリー。

・『こころ』は「私」と「先生」とのBL物語である。
・静(奥さん)はKと結婚したかった。しかしKがなかなかアクションを起こさないので、Kを焦らせるため、あえて好きでもない「先生」を誘惑するという策を講じた。
・静はKの自殺をきっかけに変貌し感情をなくしたサイコパス女である。
・「先生」は、このままだと静とKが結婚しそうな気配を感じた。そうなれば愛すべきKは静のものになってしまう(これもBL)。ならば自分が静と結婚してしまえば、Kは誰のものにもならない……。
・「先生」亡き後、「私」は静と事実上の夫婦となってしかも静は「私」の子どもを宿している。
どれも一見正気の沙汰じゃない感じですが、こういうのを大真面目に研究しているのが文学研究者。そして実際に「そういう物語なんだ」というつもりで『こころ』のテクストを読むと、確かにどの解釈のラインもありえたりする(厳密にはどれか1つのルートってわけではなく、レベルの強弱がありつつ複合的に絡み合うのでしょう)。
もし嘘だと思われた方は、ぜひお手元にある(なくてもいいけど)『こころ』を読み返してみてほしいなと思います。そして、上の5つのルートたちに賛同できるかどうかを聞かせてください。
きっとそういう対話から、文学復活の一歩が始まるのだ、と確信しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
