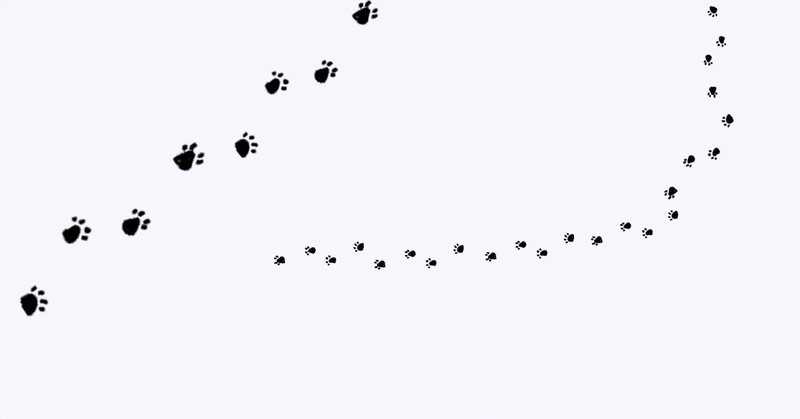
犬のひと
夕方の4時くらいになると、おくさんは雲隠れをするかのようにいなくなる。
「奥にいるからなにかあったら声かけてね」
そういう日もあるけれど、たいていはなにもいわずにいなくなる。そしておおむね夕方の5時半前くらいに、パチパチと小さな子どもをあやすような拍手が聞こえてきて、ああそういうことかと納得をする。
奥の部屋というのはわたしたちがお昼ご飯とかを食べる小さな部屋のことでそこにはテレビがあり、おくさんは相撲をみているのだ。
定時が5時半だということもあって、その部屋に入り、ロッカーがあるので着替えやバックを取りにいくと、おくさんは、お疲れさま〜といいながらも、目だけは相撲から離れない。
おくさん、だれが好きなんですか? そう質問をすると、そうねぇーと顎に手を添え、だれってこともないのよ、とまた顎をさわり、日本人力士ならだれでも好きだわとつづけた。
わたしのママも相撲が好きだから、歳を食うと相撲が好きになるのかなぁとかおもったけれど、同じ事務員で四十代の森さんに訊いてみたところ、え? まるで興味がないわよと一蹴されてしまい、大人が皆相撲が好きとは限らないことを知る。
おくさんは八十歳だ。わたしが働いてる工務店の社長のお母さんでまだ現役で会社の雑用などをおこなっている。
そして会社にくる銀行員のイナくん贔屓で、おくさん、イナくんがきましたよ。と教えると、あら、と頬を赤く染め、何も用事がないけれど顔だけでも拝みにいきましょうかねとまるで少女のようなことをいう。
イナさんは二十五歳でわたしよりも四歳年上でそして無駄にイケメン。会社ではとてもいい顔をしてくるけれど、あれはきっと遊んでるなとわたしはおもっている。
以前ママにイナくんのことを話したら、いいじゃないの! その付き合ってみないとわかんないからさ。と強くいわれたけれど、わたしはしかしどうでもよくて、というか顔がいいっていっただけだったのに、勝手にそういわれてなぜか腹が立ったので
「だってさ、もし結婚をしたとするでしょ? そうしたら『イナマイ』になっちゃうじゃん。苗字が素敵なひとがいいの。たとえば、北村とか、そういうの」
え? そんなことなの? とママはおどろきそしてゲラゲラと笑った。どうでもいいうそをついた。彼氏がいらないというわけではない。いまは特にいらないのだ。もっとも出会いがない。
相撲は15日間開催し、二ヶ月おきだということはママから聞いている。タマリセキとやらに妖精さんがいるのよ。毎場所いるの。ということも。とうぶんの間はおくさんのかわいらしい拍手が隣の部屋から聞こえてくるのだろう。そしてママの声援も。
昨日、裏玄関のチャイムが鳴り
「あ、イワタさんでてくれるぅ」
なにかをしていて手が離せないおくさんにかわってわたしが、はいとパソコンを打っている手を止め、裏玄関にいき、インターホンをみると、おくさんと仲良しの『犬のおばさん』が犬を連れて立っていた。
『犬のおばさん』と『猫のおばさん』と『菊のおばさん』。他にもお友達がいるけれど皆一様に同じような風貌なので『○○のおばさん』とわたしが勝手にそう呼んでいる。
「おくさん、犬のひとです」
事務所に戻りおくさんにそう告げる。午後3時。ちょうどおやつの時間におくさんのお友達はやってくる。
「はーい」
おくさんはとても嬉しそうに玄関に向かう。八十歳でお友達がいるとか素敵だなとおもう。わたしにも友達がいるけれど、八十歳になるまで友達でいられたらいいなともおもう。二十一歳。まだ、先は長いし想像もつかない。
ふと、窓の外に目を向ける。午後特有の日差しが目に優しい。初夏をおもわせるような雲が浮いている。
おくさんが戻ってきて、あのね、とわたしと森さんのそばにきて、話をしだす。あのね、聞いてくれる?
「あのひとのね、わんちゃんいたでしょ? 亡くなったんですって。この前。かなり、ショックを受けてたわ。あなた、そうそう、エドちゃんね。大事にしてあげてね」
「え」
わたしはそれらの話をし終えたおくさんに大声で、えそんなおかしいですって! わたし、さっきみたんですよ! モニター越しに! ときっと真っ青な顔して叫んでいたとおもう。
「なにを、みたっていうの?」
おくさんと森さんの声がうまい具合に重なる。わたしは背中が冷たくなるっていく過程の中、話をつづける。
「犬のおばさんです。モニターにいつもいる犬がちゃんと映っていたんです! みたんですよ。わたし。ほんとうに。みたんです……」
最後の語尾あたりの、みたんですぅはもはや泣き声になっていた。ほんとうに犬がいたのだ。映っていたのだ。だから『犬のおばさん』だと確信をしおくさんに告げたのだ。死んだって……。どういうことなのだろう。菊のおばさんであればまだ納得がいく。葬式には菊がつきものだから。というかそんなのはどうでもよくて、わたしはとても背中がつめたくなった。
「イワタさん、」
ぽんと肩をたたかれ、小さなおくさんの手のひらがわたしの肩に乗り
「そうね。ワンちゃんはいたかもね。きっとまだ離れなくないのよね。あのひとのもとからね。そうね。あなた、みたのね。うん、そっか。泣かないで」
目頭が熱くなり決壊寸前だった涙が崩壊をし、頬になん本もの涙のあとをつくった。わたしはひっそりと泣いていた。
死んだ犬をおもい、猫のエドのことをおもい、世界中の動物のことを考えた。
そして、死を考えた。
あのわんちゃん、いつ天国にいけるのかな。わたしは涙をハンカチで拭き、仕事を再会した。
まだ夕方の四時半。隣の部屋からおくさんの拍手が聞こえてくる。相撲が始まったようだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
