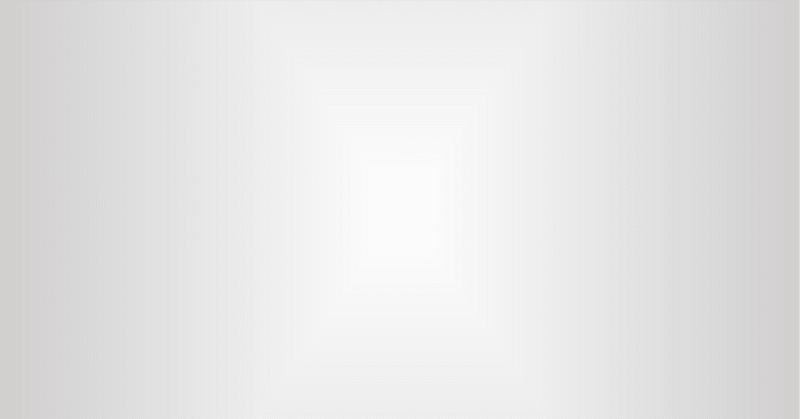
鮮烈な感性が示す伝統の大きさ──エカテリーナ・デルジャヴィナ『J.S.バッハ:フランス組曲』【名盤への招待状】第13回
芸術表現に触れるということは、他者の話に耳を傾けること──それも、実際の話し言葉では伝え得ない複雑にして痛切な話に耳を傾けることである。だから、話を聴いたあとでその内容や語り口にさまざまな感想を抱くことは自由だが、話を聴く前から話者に対して「自分はこういう話が聴きたい」と求めるのは、本来的に慎まなければならない態度である。
そのことを踏まえた上で、個々の内容というより芸術体験そのものに望まれることを述べるなら、それはその話を聴いたあと、自分のなかになにがしかの変化があることだろう。優れた表現に触れると、変化の程度や質、場合はさまざまだが、それに触れる前の自分ではもうなくなってしまう。ある芸術体験が、自分のなかの常識を確認するようなものに終わることもあって、そういうときには確かに安心はするが、何か、これでいいのだろうかとの思いも残る。ほんとうの感動は予定調和ではなく常に意外性を伴う。芸術は、私たちの通念を揺るがせるものなのだ。
ロシアのピアニスト、エカテリーナ・デルジャヴィナが『J.S.バッハ:フランス組曲』に聴かせる表現からも、そうした新鮮な驚きを得ることができる。
あらゆる点で一様でない演奏だが、なにより刺激的なのは多声に対するアプローチだろう。各声部それぞれの動きがしなやかで、それが目に見えるように明瞭に聴き取れるが、デルジャヴィナは、ある声部を前面に出したり背後に退かせたりといった凡庸な手を採っていない。動きのあるパートとそうでないパート、メインの旋律と対旋律などの区別を強調するのではなく、ひとつひとつの声部それぞれに輝度や色の異なる光を当てているのである。そしてその光の当て方が鮮烈で、通常は影に回りがちなパートを浮かび上がらせてみせ、さらに、繰り返しの際にすべての声部に一度目とは違う仕方で光を当てるのだ。
そこにはまったく設計や作為の匂いが感じられない。パターン化に陥らない装飾の数々や融通無碍なアーティキュレーション、微かなニュアンスや呼吸の違いというように、音楽に多様な彩りをほどこすデルジャヴィナの手つきはどこまでも才気の翔けめぐるような即興性に溢れていて、だからこそそれぞれの声部がまったく自由に呼吸し、躍動することができる。次々と繰り出される確信に満ちた表現がこちらの予想を超えていくのは、すべてのパートが等しく、まさに一瞬一瞬を生きているからなのだろう。
多声部の動きを洩らさず把握する聴覚と技術に支えられた、繊細で鋭い感性のほとばしりは、楽譜からいくつもの意外性に富んだ多彩さを引き出してゆく。音楽の基本的な運びは機敏で、各番のクーラントなどの急速な舞曲をその敏捷性で一気呵成に駆け抜けるさまは技巧的ですらあり、高揚感にも事欠かないが、彼女が音楽に当てる光にはどこか仄暗さと痛みが伴っているように感じられる。
それは、それらの表現をかたちづくる最小要素である音色が、深い陰りに満ちているからだろう。デルジャヴィナの非凡な感受性は、その音に凝縮されていると言っていいかもしれない。つぼを押さえた打鍵の放つ一音それ自体がすでに陰影を含んだ感じやすい歌を感じさせ、響きの最も澄んだ部分を繋いでいくような上質なレガートによって連なる。フランス組曲の第二番や第三番、フランス風序曲の演奏には、観客の帰ったあとの誰もいない薄暗いステージで独り舞う踊り手のような寂しさが浸みわたっている。
アルバム中でもとりわけ踏み込んだ解釈を聴かせているのはフランス組曲第六番のメヌエットで、二小節ごとに立ち止まるような運びが舞曲の性質を限りなく抽象化させて、最終的にはモノローグのような表現を聴かせるに至っている。メインの六曲のフランス組曲は二〇一四年、フランス風序曲など併録の三作は一九九六年と、録音された年代には隔たりがあるが、いずれの時代の演奏においても述べてきた特質と姿勢は貫かれている。しかし、意志的に様式を壊そうとしている気配はどの曲の演奏からも感じられない。彼女の閃くような演奏は確かに通念に染まらないものだが、その鮮烈な解釈によって同時に実感されるのは、これほど多様な「読み」が可能なバッハの世界の深さである。
偏見や差別意識に満ちた「常識」が解体し、これまで見過ごされてきたものに光を当てていこうとしている現代にあって、その「常識」に浸されていた時代の人であったバッハのような歴史的な芸術家には関心が持てないという人も、ある映画で描かれていたようにいるかもしれない。しかし、彼の作品には今の時代に通ずるものが確かに宿っていることを、デルジャヴィナの演奏は鮮やかに示してくれている。
反対に、バッハなどの名前を持ち出し、浅はかな伝統主義を振りかざして旧弊な価値観や通念を改めることを拒む固陋な者がいるが、芸術のような伝統的な文化は、あるひとつの価値観を「正解」としてそれに固執することによって保たれているのではない。それは、常に時代や人によって異なる新しい表現や「読み」を生み、深化と進化を繰り返してきたからこそ──そしてまた、それが可能な大きさや深さを備えているからこそ、今日まで受け継がれているのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
