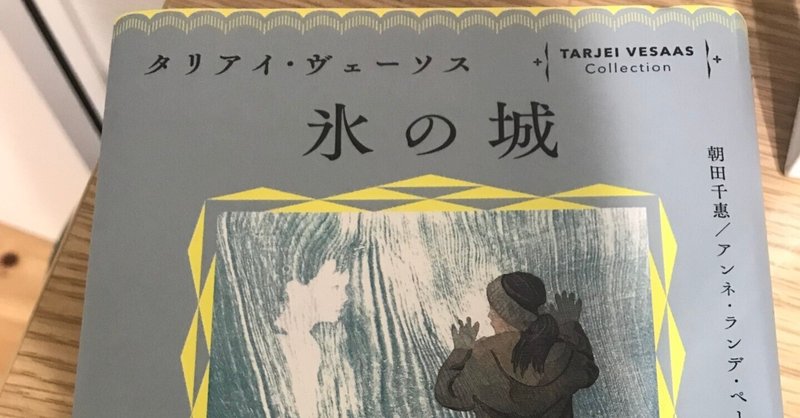
書評・タリアイ・ヴェーソス『氷の城』朝田千惠、アンネ・ランデ・ペータス訳、国書刊行会
一読後、決して忘れることのできない物語だ。平易な言葉で綴られるシンプルなストーリーであり、格別の寓意性が感じられるわけでもない。それなのに、心の奥底に響いてくる冷気が全編に通底しているのだ。
「20世紀を代表するノルウェーの大作家」と紹介されているタリアイ・ヴェーソスのことを、ぼくはちっとも知らなかった。恥ずかしながら、名前を聞いたこともなかったくらいだ。だからこそ余計に、作品の力強さに衝撃を受けた。これが例えば、トルストイのような名だたる文豪の作品だったら、「さすがに世界の名作は凄いな」と思っただろう。しかし、知らない作家の作品の質の高さに驚かされたのだから、「どうしてこの作家のことを今まで知らなかったのだろう」と思わずにはいられない。
作品の根幹をなす1つのポイントは、「氷の城」を筆頭とする北欧の危険なほどの寒さである。そして、その危険に引き寄せられてしまう人間の不思議さが描かれる。同時に、「氷の城」に行ってしまった少女を失って、そのことによって自分も失ってしまったもう1人の少女に焦点が当てられる。
そして読者はどうにもできないやるせなさとともに、少女の一挙手一投足から目が離せなくなってしまう。
思春期の危うさと強さがない混ぜになった状態を丁寧に表現して、生きることの固い核を浮かび上がらせた傑作だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
