
自分自身と向き合う勇気
何したいの?
これからどうしたいの?
そう聞かれて答えられますか?
私は、答えられません。
やりたいことが見つからない人は
自分の強みがわかっていない人。
自分の強みがわかる=やれることがわかる。
やりたいことも見えてくる。
と言われたことがある。
言いたいことはわかるし、何の反論もない。
でも自分の強みがわかっている人って
世の中にどのくらいいるのだろう。
強みを「スキル」ととらえる人が多いけど
私はその単語がどうにもこうにも苦手。
なぜなら、私は“スキル”というものとは
かけ離れたところで過ごしてきたから。
これといった自分のスキルを、“固有名詞”を、
何一つ挙げることができないからです。
「自己肯定感」という言葉は
職業柄、毎日のように聞くワードですが
正直、ナニソレ美味しいの?状態です。
教育学部卒業生として、
東京都教育委員会の言葉をお借りするなら
「自己に対する評価を行う際に、自分のよさを肯定的に認める感情」
要するに自分の好きなところ言えるかって話ですね。
※私の心の声「言えません(即答)」
相談に来る就活生の多くが
「自分は自己肯定感が低い」と言う。
本音を言ってしまえばそんなの知ったこっちゃない。
私だって自己肯定感低いんだ!
自己肯定感のかけらもないんだ!
と叫びたい気持ちを抑えながら
毎日相談に乗っているわけですが、
何が言いたいかというと…
自分のことを考えるというのはそれだけ難しい。
※仕事が嫌だというわけではありません笑
私も同じ悩みを抱えているからこそ
それっぽい言葉で誤魔化したりしないし、
適当なことは絶対に言いたくない。
たまに信じられないほどポジティブな人、
自己肯定感の塊みたいな人いますよね。
刺激や新しい気付きをくれるありがたい存在。
だけど、どうも理解し難い人種です。笑
そういう人たちからしたら
逆に自己肯定感って何?って感じらしいです。
今日は自己肯定感で悩んでいる一人として
noteを書いていきたいと思います。
チーム自己肯定感低いーズの皆さん!
得体の知れない「自己肯定感」という魔物を
敵⇒知り合い⇒友人にしていくために
共に戦い、向き合いましょう!!!笑

私の思う自己肯定感の低い人の特徴
1:人の目を気にする
2:心配性
3:優柔不断
4:失敗を恐れる
5:嫌われたくない
6:誰かに認められたい
7:自分のことを人に話すのが苦手
とにもかくにも
常に他人からの見られ方を気にする人種です。
そこから派生して2~7が出てくる。
※私は全て該当しております…
最近なんで自分はこんなにも自信がないのか
考えてみたものの、特に面白い気付きはなく。
シンプルに育ってきた環境だと感じました。
【私の小学生時代~今に至るまで】
本当はそれも書こうと思ったんですが、
長くなるので次回に繰り越します!笑
日本人の特徴
実際に内閣府の出している資料を見てみても、
他の国と比べて日本人の自己肯定感は
低いというデータが出ていました。
❶諸外国と比べて,自己を肯定的に捉えている者の割合が低い。
(図表1,図表2)(図表1,図表2)


えーと…見ました?低すぎません?笑
もはや自己肯定感が低いというのは国民性?
これなら仕方ないって思ってしまう…
負けちゃだめだ…
逃げちゃダメ、逃げちゃダメ、逃げちゃダメ…
それに加えてさらに恐ろしいデータがこれ。
❷諸外国と比べて,うまくいくかわからないことに対し意欲的に取り組むという意識が低く,つまらない,やる気が出ないと感じる若者が多い。(図表3,図表4)


何が言いたいかというと…
❶のデータにあるように
・今の自分に満足してない
・自分の長所が見つからない
その認識はあるものの長所を生み出そうと思う人、
何かアクションしようとする人が少ないということ。
うまくいかないと憂鬱になる。嫌になる。
うまくいかないことが恥ずかしい。
うまくいかなくて申し訳ない。
そういう思考になるんだと思うんです。
意識が周りに行き過ぎてなかなか主体的になれない。
自己肯定感と積極性の関係
自己肯定感が低くても変化は好む。
新しいことも好きだし、挑戦もする。
自己肯定感がない=自分に自信がない。
だからと言って大人しくじっとしているわけではない。
私自身も好奇心は旺盛だし、
新しいこと始めるのは好き。
しかしながら、私自身振り返ってみると
その挑戦の中でも無意識に安全な道を選んでいたり、
大事な決断を誰かに委ねたりすることが多かった。
道から大きく外れるようなことは少なかった。
(自己肯定感の低い人って優等生なのかな?w)
自分で決めたものの中に、
嫌いなことや苦手なことって必ずある。
壁にぶつかって乗り越えたり挫折したりして
好きなことや得意なことが明確になっていく。
人は「挑戦」だけでは成長しない。変われない。
失敗したときこそ、成長する。
気付きと反省によって人は変わる。
極端な言い方をするなら
自分で決断したことで失敗することが
人を強くして自己肯定感を高めるのかも。
私自身、失敗することや嫌われることを避けてきた。
常に、人からどう思われているかが気になる。
他人の評価がどうしようもなく怖い。
ある日を境にある出来ことをきっかけにそうなった。
他人に何かを褒められたとしても
本当にそう思っているのか疑ったり
そんなことないと否定したりして
自分を受け入れることができない。
何者かになりたいと思いながらも
結局はマジョリティーを選んでしまう。
☆どころか〇になっている自分がいる。
「人気者になりたい」のではなく
「嫌われ者になりたくない」のだった。
まだまだ自分と向き合えていないと思った。
向き合うどころか逃げていた。
だからいつまで経っても変われないのだと気付いた。
➌諸外国の若者と同程度かそれ以上に,規範意識を持っている。(図表6)

あれ、もしかしていいこと気付いたかも…?
と思ったら図表6を見るとこれも国民性らしい。
私は典型的な日本人なのかもしれない。笑
そして私が一番課題に感じているのは次の部分。
自己肯定感が低い若者が多い日本だからこその課題。
自分の将来をイメージできない
➍諸外国と比べて,自分の将来に明るい希望を持っていない。
(図表8,図表9)

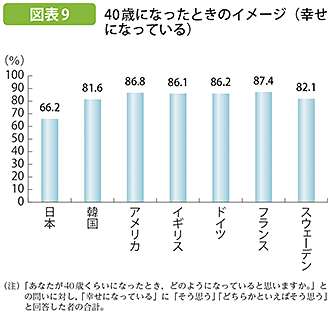
引用:内閣府「特集 今を生きる若者の意識~国際比較からみえてくるもの~」
将来に明るい希望を持っていないのに
やりたいことを聞かれて答えられるはずがない。
正直5年後、10年後、20年後なんてわからない。
今回のコロナで誰もが痛感していることだと思う。
だからこそ今は、
近い将来にやりたいことを考えるべきだと思う。
そのために自分の「好きなもの」を考えてほしい。
〇年後を考えるのはそれからでいい。
それからでいいのだ!
(自分にも言い聞かせています)
やりたいこととは何か
好きなこと、得意なこと、仕事にするなら?
どちらを仕事にしたらいいのか迷う人は多い。
そんな人は 八木仁平さんの記事を読んでもらいたい。
やりたいこと=好きなこと×得意なこと

私が前回の note で書いた
「誰もが自分の人生を愛せる世界」の実現には
自己肯定感をなんとかせねばならんわけです。
それがどうにかなれば
好きなことや得意なことを声に出せるようになる
そしてやりたいことに向かって
自分の気持ちに素直に進める人が増える。
と、私は考えているわけです。
そんな簡単な事じゃないのは100も承知です。
だって私自身がそうだから!!!笑
仕事となれば話は別ですが基本的に
人に自分のこと話すのは大の苦手。
なんか恥ずかしいし…
話されても困るって人いるじゃん?
そもそも私の話なんて興味ないかもしれない。
考えれば考えるほど話せなくなる~!
分かりますか、この気持ち…
だからこそ他人事じゃなく、向き合える。
自惚れかもしれないけどそう思ってます。
やりたいことを見つけるために
やりたいことをみつけるために
まずは好きなものを言語化しよう。
好きなものをとことん深ぼって突き詰めて
誰に何を言われようとこれが好きだと
胸を張って言えるようになってほしい。
そうやって小さなところから一つずつ
自信をつけていったらいいと思う。
私自身も最近好きなものについて考えている。
・人の笑顔をみること
・人が変わる瞬間に関わること
・知らないことを知ること
人と直接関わりたいって思っていた。
沢山の人と関わるにはどうしたらいいか。
人前に出ることは苦手じゃない。
どちらかと言えばむしろ好きだし得意。
先日、よき理解者 「シャンディさん」に
しおりは根っからのサポーター気質だから
企業とかフリーランスは向いていないよね。
ってズバッと言われて、確かにと思った。
自分がやりたいことって人前に立ってもできるけど
立たなくてもできることなんだって気付かされた。
新しいことは好きだけど0⇒1より
1⇒10の方が性には合っているのかもしれない。
実際に、自らの0⇒1ではなく
誰かの0⇒1のサポートの方が
ワクワクしている気がする。
それは実際に今の会社で0⇒1ならではの
いろんな経験をさせてもらったからこそ
気付けたことでもあると思う。
「したことがないこと」を減らす大切さを
実感することができた。
正直、今の私に出来ることなんてわからないし、
想像もつかないというのが本音ではあるけど
好きなことに自信をもってもらうため、
苦手なこと、新しいことに挑戦するときの
「不安」や「恐怖」を和らげてあげられるような
そんな手助けができるようになれたらいいな。
好きなことを明確にする
好きなことに自信を持つ
自分を好きになるために
一歩ずつ一緒に進んでいく。
自分を好きになるために自分を知ろう。
私に似た悩みを持つ人の背中を
少しでも押してあげられますように。

(1)自分の好きなことを考えよう
好きなものを名詞でなく、動詞で挙げる。
これは就活生にもおすすめしてる。
重要なのは名詞ではなく動詞で考えること。
名詞で考えるとミスマッチが起きやすい。
前回も書いたように
夢を聞かれた日本人は「職業」を答える。
・野球選手になりたい
・客室乗務員になりたい
・医者になりたい
いざ就職してみると、
「あれ、自分がしたいことってこれだっけ?」
そんな風に感じる人は少なくない。
それが名詞で職業を選ぶリスク。
元旅行会社の私がいうのはあれですが
旅行が好きという理由で旅行会社に入った多くの人が
数年でやめてしまう原因の一つはそれです。
・野球で有名になって、大きな家に住みたい
・客室乗務員になって、多くの人を笑顔にしたい
・医者なって、たくさんの人を救いたい
これらは大体、過去の体験からきている。
試合で勝てて嬉しかった体験。
人に優しくしてもらって幸せな気持ちになった体験。
命を救ってもらって心から感謝した体験。
野球選手になれなくても大きな家には住めるし、
客室乗務員じゃなくても人を笑顔にすることはできる。
職業は目的を実現する手段にすぎない。
だから「どの職に就くか」はそれほど重要ではなく
その職を通じて行う「動作」に着目するべきだ。
職業が変わっても人の根本的な部分は変わらない。
だからこそ動詞で考えた方がいい。

私の前職、添乗員&留学エージェントで考えてみる。
※写真は6年前の今日、5月7日です(笑)
好きなものが「英語」「海外」「教育」だとすると
その職業を目指す理由は色々考えらえる。
A「英語を使いたい」
B「海外に行きたい」
C「教育に関わりたい」
D「自由に飛び回りたい」
Aなら外資系の企業の方が使えるだろうし
Bなら海外進出している企業全般が当てはまる。
Cなら一番近いのは教員でしょうし、
Dならフリーランスやブロガーの方があっている。
前職でのやりがいを振り返ってみた。
・流暢に英語を話す人達の中で刺激を受けていた。
・国内外問わず企画や添乗をやらせてもらえた。
・学校、現役の教員たちと直接やり取りができた。
「英語」「海外」「教育」という名詞を使わずに
私が好きなことを動詞で考えると…
「言語の壁を越えてチームで目的を達成すること」
「エリアを縛られずに広い領域で挑戦すること」
「学生の目が輝く瞬間を創造すること」
今は全く違う人材という業界にいるけど
確かに、見事に当てはまっている。
好きなものを名詞ではなく動詞で考えること。
ぜひとも一度試してもらいたい。
そうやって自分のことを考えることで
少しづつ自分のことを理解し受け入れる。
それが自己肯定感を高める一歩かもしれない。
そう思って私は頑張ってみることにします!
まずは比較的、取っ掛かりやすい
「好きなこと」を考えてみましょう。
自分のやりたいことを見つける2つの要素
(1)好きなこと、(2)得意なこと
そのうちの一つの要素(1)好きなことについて
書いてみました。
次回はもう一つの要素(2)得意なことについて
書きたいと思います。
今回も長くなってしまった…
最後まで読んでくださったあなた…
ありがとうございます…らぶ!!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
