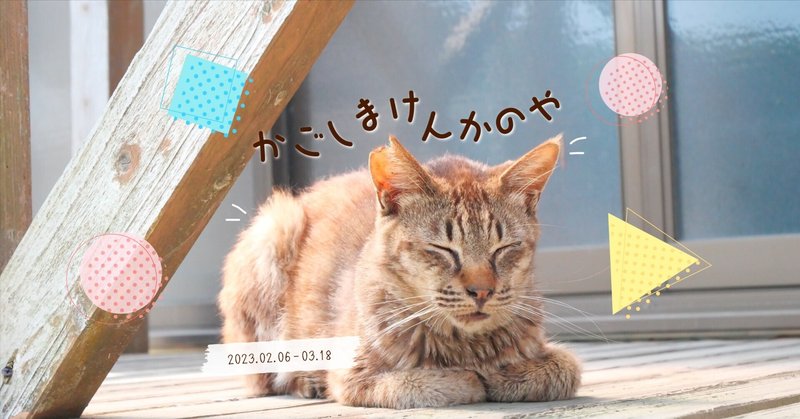
鹿屋は、泊まるより暮らす場所
人生が変わった地、鹿児島県鹿屋に2023年2月6日〜3月18日まで滞在してきました。
鹿屋がどんなところか、レポートしていきます!
鹿屋ってどこ?

鹿児島県鹿屋市は、東側の大隅半島にあります。錦江湾の桜島を挟んで反対側には、県庁所在地の鹿児島市があります。
鹿児島市は路面電車も通っており、車なしでもなんとかなるのに対し、鹿屋は電車が通ってないので、車必須です。
鹿児島市の人口が591,772人(鹿児島市HP「推計人口」より 令和4年4月1日現在)なのに対し、鹿屋市は99,373人(鹿屋市HP「推計人口」より 令和5年3月1日現在)と10万人を切っています。
私の出身地、神奈川県横浜市は300万人超なので、とても少なく感じます。
農業のまち、鹿屋。

実は、鹿児島県は農業産出額が北海道に次いで全国2位となっている、農業のまちなのです。
鹿児島といえば、さつまいも。地元では「からいも」と呼ばれますが、焼酎や菓子の原料に使われています。他にも、ごぼう、ブロッコリー、大根、にんじん、水稲も盛んです。
そして意外にも、お茶の生産量が静岡県についで全国2位の生産量を誇っています。お土産屋さんには緑茶はもちろん、ごぼう茶など野菜を焙煎したお茶も多く並びます。関東・関西という大きな経済圏から離れているため、痛みやすい野菜の保存方法として、焙煎が多く採用されているのかもしれません。
農業というと、野菜や米を想像してしまいがちですが、北海道に次ぐ農業出荷額を支えているのが畜産です。広く知られている黒豚や黒牛は全国上位の飼養頭数となっており、農業産出額の約65%を占めています。
スーパーで買える黒豚でもかなりレベルが高く、ピーマンの肉詰めを作った時は美味しすぎて、思わず声がでました。
ひたすらピーマン

約1ヶ月の滞在期間、私はひたすらピーマンを収穫しておりました。
今回は人伝てに受け入れ農家さんを紹介いただきました。主に水稲をやっている農家さんですが、1年を通して小麦・そばなども育てており、昨年末から初めてビニールハウスでピーマン栽培を始めたところでした。
1週間のルーティンは決まっていて、週の初めは収穫、終われば整枝などの手入れを行いました。
収穫は割と早くなれたのですが、整枝はどの枝を切っていいか不安との戦いでした。「切りすぎたかも・・・」と不安になっても、翌週になると青々と膨らんだピーマンがたくさんなっていて、嬉しくなりました。
受け入れられている、という感覚。

私の旅の目的は、「さまざまな田舎の景色の中で暮らして、自分の生き方を考える」でした。こちら側の不安として収入やキャリアの不安要素がありましたが、そもそも「田舎(受け入れ)側が歓迎してくれるか」も大きな不安要素でした。ご近所トラブルで移住を中断したケースも、よくニュースに取り上げられていたからです。
結論、鹿屋は非常に住みやすいまちでした。
鹿屋に到着した日、薄着で道を歩いていると、すれ違ったおばあちゃんに「今日は寒いよ、コート着ないとね」と優しく声をかけられました。
受け入れ先の農家さんは、農業を勉強したいという私の意を汲んで、休憩中は私の畑のアドバイスをしてくれました。ピーマンの手入れも、都度優しくアドバイスしてくれるし、暑い日は体調を気にかけてくれました。
郵便屋さんでさえも、荷物を受け取る際に世間話したりしました。
東京にいたころは、街を歩く時はイヤホンをつけていたし、近所の人と世間話をすることもありませんでした。防犯上、知らない人とはあまり話さないように教育を受けてきたことも影響していると思います。
物理的な距離は近いのに、人との間に見えない壁があるようでした。
鹿屋の人との距離感が、自分にはすごく合っていました。「受け入れられている」感覚は非常に心地よいものでした。この感覚は、観光で来るよりも暮らしてみることでより実感するものだと思います。
鹿屋は、何もないまち?

「鹿屋がきっかけで、会社を辞めました」というと、鹿屋の人たちは大体こう言います。
「こんな、何にもないまちで!?」
鹿屋は、そんなに魅力がないまちなのでしょうか?
鹿屋を出て行く人の中には、「鹿屋にはわくわくするところがない」と言う方もいるみたいです。確かに、鹿屋はキラキラした観光地は多くありません。鹿屋の中で一番栄えている市街地も、大都市圏に比べればかなり小さいです。
でも、私が探している「安住の地」はキラキラした観光地ではありません。起きて、仕事して、ご飯を作って、食べて、寝る、日常の地です。そういう意味で、「ふわっ」と受け入れてくれる鹿屋のふところの広さは、控えめにいって最高なのです。
そして、新鮮な野菜が直売所にあり、スーパーで美味しい豚肉や鳥刺しが買えて、ちょっと足を伸ばせば山も海も滝もあって、海鮮が美味しくて、330円で銭湯に入れる、そんな日常はとても幸せだと思うんです。
私が好きな鹿屋で、何かしたい。
私にとって最高な場所の鹿屋ですが、人口減少や若手の人材流出という社会問題を抱えています。鹿屋に限らず、多くの地方自治体が抱えている問題だと思います。
私だって、できることなら鹿屋の移住者を増やしてあげたいのですが…友達は少ないし…自分もまだまだ人生の夏休み中なので1箇所にとどまりたくありません。
そこで、移住者は増やせないけど、短期的に鹿屋に人を呼ぶことはできるかも、と思いました。元々、人生の夏休みを経て、悩める若者に人生の夏休みを提供する農業インターンを企画しようと思っており、その実施場所を探していたのですが、鹿屋はぴったりだと思いました。
ギラギラした観光地ではなく、人の懐が深いふんわりとした雰囲気、何より農業のまちで自然がたくさんあり、海も山も近い。そんな鹿屋は人生の夏休みの場所に最適です。
移住者を直接的に増やすことはできませんが、鹿屋を知っている人が増えます。知っているだけ?と思われるかもしれませんが、今の時代、知らないと検索すらされません。この移住潜在層を増やして行くことが、人口減少解決への一助になると思っています。
ということで、第一弾は今年度中に開催したいと思っています。
今後農業インターンについても詳しく投稿していきますので、ぜひご覧ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
