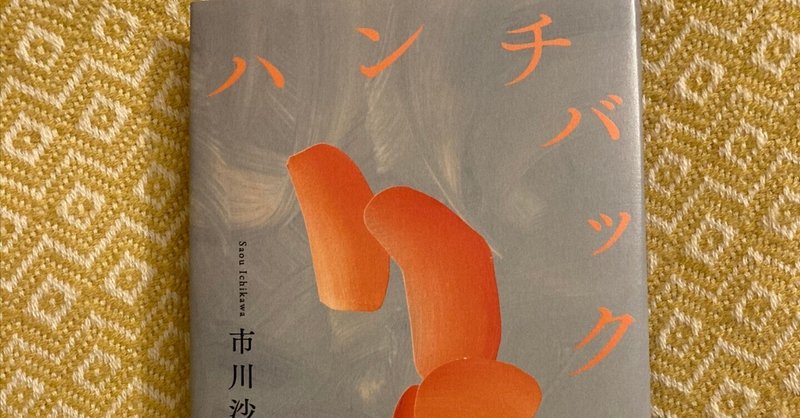
市川沙央さんの『ハンチバック」を読む
連休からの一週間は暑さと戦いながら出張をこなし(楽しんで)、家ではストレッチに励み、市川沙央さんの『ハンチバック』を読み、男子日本バレーの応援をし、インドやスリランカのカレーを食べ、小さな山を歩いた。暑くてもうろうとしている時間もまあまああったし、あまり仕事に身が入らない時間ももちろんあったのだけど、こうして書き出してみると、わりと充実していたんだな。
市川沙央さんの『ハンチバック』。先日の朝比奈秋さんの『植物少女』もそうだけれど、とりわけ去年から今年にかけて、「体がままならなくなった人」の話ばかり読んでいる。村井理子さんの『更年期だと思ったら重病だった話』、山本文緒さんの『無人島のふたり』『再婚生活 私のうつ闘病日記』――。『ハンチバック』の感想を書き留める前に、なぜ自分はそういう本ばかりをいま、手にしているのかについて考えてみた。
思い出したのは、小学校3年生か4年生の頃、学校の図書室で何度も借りて読んだ『さと子の日記』のことだった。本を読んで泣いたのは、多分これが初めてだったと思う。先天性胆道閉鎖症という病気と闘う少女の実話。黄疸が出て、熱にうなされ、手が震えるなど、さと子の身に起こることへの恐怖と不安、入学式に出られず、病室で迎えた悲しさ、それでも最後の最後まで世話をしてくれる母を気遣い、健気に生きる姿に、当時胸を打たれた。
聞き慣れない病気の不思議を知り、自分にとっては非日常の病室で生きる少女の日常をのぞき見るような、秘密をわけてもらっているようにも感じていたかもしれない。
当時のような感覚を、ここ最近読んだ本にももれなく感じている。また、自分も彼らと同様に「ある種のままならなさを抱えた一人」として、どう振る舞うべきかを学びたいという潜在欲求があるのかもしれない。
それだけじゃない。こんなことを言うと、少し不謹慎かもしれないけれど、実は体や病に抱く純粋な好奇心を刺激されるというところも、正直ある。
だから、『ハンチバック』のなかで市川さんが「健常者優位主義」を「マチズモ(本来は男性優位主義と訳されることが多い)」と表現したところは、とりわけずっしりと響いた。自分のそういう好奇心こそが健常者優位主義を一番体現してしまっていることなんじゃないか。
そうした罪悪感と背徳感にこそ、こういう本を手にする甘美があると、実は思っているんじゃないか――そんなことを考える自分がこわい。とくに『ハンチバック』を読んで、そういう自分の無意識に気づいてしまった。
釈華(市川さんと近い境遇の主人公)がTwitterに裏垢で投稿する欲求に共感できる自分にも驚いた。冷静に見ると言葉にするのがはばかられるような怖い文字列のつぶやきもあるのだけど、どれも釈華がまるで叫んでいるように感じた。その言葉だけでなく、作品全体から市川さんの挑戦的な姿勢を感じたし、健常者優位主義の世界で戦う市川さんの姿を見たような気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
