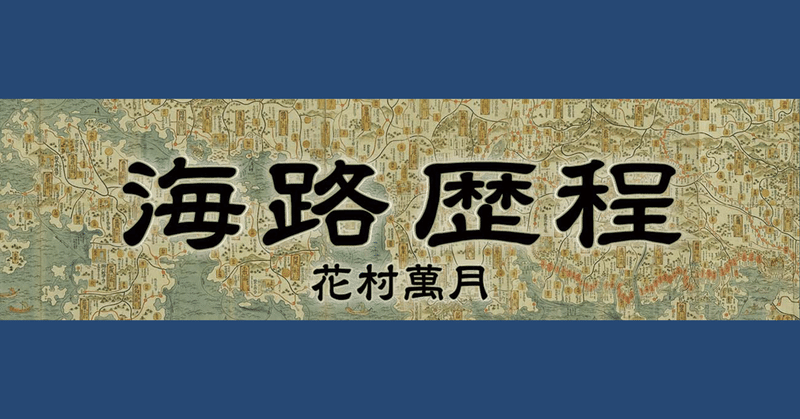
海路歴程 第六回<下>/花村萬月
. *
侍の名を知りません──と月静は笑う。実際は名乗ることさえ許さないのである。侍は月静に隷属していた。命じれば足の裏でも恭しく舐めるだろう。
一応はお勤めであるからと、月静は琉球が清との密貿易を疑われていることを聞得大君に報せた。聞得大君は王に薩摩からかけられている嫌疑を伝えた。
興味がないので諸々深く知ろうとしない月静であったが、どうやら薩摩の昆布を少しずつ着服して清にわたしていたらしい。小首をかしげて婆に問う。
「それで琉球が富むならば、よろこばしいことですよね」
小麦粉を捏ねながら手の甲で額の汗を拭ったので、月静のおでこには白く太く雑な線が引かれている。婆が問う。
「昆布を見たことがあるか」
「ありません」
婆が侍を意識して言う。
「そもそも琉球が抜荷でほんのわずかの昆布を清に送って、なにほどのものが得られるというのか」
「そうです、そうです」
昆布を見たこともないくせに大仰に頷く。けれど月静は、昆布というものが途轍もない宝であることを悟っていた。
小耳にはさんだあれこれを綜合すると、遠く寒冷な蝦夷ヶ島では二束三文でも、遥か彼方の琉球まで、そして清国にまで運べば、途方もない値が付くのだ。
「商いとは面白いものですね」
月静がなにを言おうとしているのか婆にはわからず、不明瞭にとぼけた。さらに心の中で月静と侍の交わりが程々であるようにと念じた。
「だいじょうぶですよ、婆様。さすがに粉まみれで交わる気にはなれません。それよりも初めてのそば打ち、とても愉しい」
侍は炊事場の隅に端座し、ただただひたすら月静の姿を追っている。下命を受けるのを待っている。刀を持った下男である。
粉まみれ云々と月静は言うが、粉にまみれた部分で交わるわけではない。月静が腰を折って前屈み、侍が背後から──という姿を目の当たりにしたことがある婆は、二人だけにすることに対する不安を抑えこんで、炊事場から出ていった。
月静は竈の上で煮えたぎりはじめた大鍋の湯を一瞥し、湿り気を頬で受ける。
「榕樹の木で灰をつくっていたのは知っているでしょう」
声がけされた侍は立ちあがり、一礼して手拭いで月静の額や首筋の汗を拭う。侍の顔が近い。息が月静の首筋をくすぐる。月静が許しさえすれば、即座に月静の着衣を捲りあげるところだ。
「木灰、とんでもない代物でした」
「と、申されますと?」
「上澄み。苦くて渋くて舌が痛かった」
月静が目で示した大甕を覗きこむ。底には灰白色の木灰が沈殿している。ほぼ透明な上澄みを凝視していると、舐めてみなさいと月静から命じられた。
言われるがままに侍は灰が沈んだ打ち水を舐めた。苦渋く、顔が歪んだ。月静が小麦粉で覆われた指を立てた。
「指先がぼろぼろに荒れてしまいました」
「この上澄みのせいで?」
月静は侍の問いかけを無視して、そばを打つ。息みながら掌で押す。くるりと引っ繰り返して折り曲げ、ふたたび掌で押す。はじめは白かった小麦粉が、ほんの少しだけ黄色くなってきた。
侍は気まぐれな月静を崇めている。気まぐれだからこそ、崇めている。
「崇めているのですか。物好きです。崇めるという字は、祟るという字に似ていますね。祟るという字は、出て示すと書きます」
侍は倒錯していて、心を読まれることに快美を覚えるようになっていた。
「祟りは、出て示されるのです。恐ろしげです。ところで」
「はい」
「貴男は、もどらなくてよいのですか」
「もどりません。もどれません」
「なにやら貴男を探して薩摩の方々がやってきたみたいですよ」
月静と交わってから完全に内面を引き裂かれている侍であったが、月静を通して神と交わったおかげで分裂は起きず、薩摩は棄て去られ、忘却された。
いきなり薩摩云々を突きつけられた侍であるが、惚けたようにまともな反応をかえさない。遠い世界の話を聞いたかのような眼差しである。月静のことしか頭にない。
「もどったら、お仕置きを受けなければならないのですか」
「──腹を切らされるでしょう」
月静が手を叩いた。
「そうなんですか。私、一度見てみたかったんですよね」
婆が乾ききった黒い帯のようなものを小脇に抱えてもどった。
「なにをはしゃいでおるか」
「婆様。この人、切腹するんです」
「ま、当然であろうな」
「私、見にいきます。切腹。お腹を切るんでしょう。痛いでしょうね。凄い!」
侍は顔色を赤くしたり白くしたり忙しい。婆も月静もそんな侍に頓着せず、濡れ布巾を用意して、捏ねあげられた麺を寝かし、熟成させる算段に入る。
「月静は、そばを食ったことがないというのだからな」
「婆様、呆れてますか」
「いや、おまえは血以外に少しばかりの菜しか与えられずに育った。不憫に思う」
「──飢えて死ぬ子もいるのですから」
「そうだな。うまく打てたな」
婆が平たい楕円のかたちにまとまった小麦粉を一瞥して褒めると、月静の顔が輝く。
「ほんとうですか! 心を込めて、力も込めて打ちあげました」
「ほれ、こいつをほどけ」
「なんですか、これ」
「これが昆布だ」
月静は器用に素早く細い藁縄をほどいて、昆布を一枚眼前に掲げた。
途轍もない価値がある代物であることは把握しているが、実際に目の当たりにすると、合点がいかぬ。こんなものが? と怪訝そうだ。
婆が火の粉に舌打ちしながら薪を引っこぬいて火加減を見る。昆布を折り切って、沸騰がおさまってきた鍋に抛り込む。本来ならば燠で静かに水から煮るのがよいのだが──と独白し、腕組みして焔を見守る。
「婆様、心配があるのです」
「切腹か?」
「まさか。そばです。木灰の上澄みで捏ねたでしょう」
婆が鷹揚に頷く。
「すごく苦くて渋くて、顔が歪みました。そんな汁で捏ねたんですよ。ほんとうに、これを食べるんですか」
婆がもう一つの大鍋を示した。
「案ずるな。茹でれば木灰の汁や塩は湯の中に流れ出ていく。そばには残らない。いや、そばに艶と腰だけを残していく」
「ああ、安心しました。あんな苦渋い物を食べさせられるのかと思うと、気が気でなかった。婆様の意地悪じゃないかって、ちょっとだけ悩みましたからね」
「つまらんことを吐かしてないで、ちょいと蓬を採ってきなさい」
月静は炊事場から跳ねるように弾んで出ていった。
侍は月静の背を目で追い、婆に咎める眼差しを投げられて、所在なげに立ち尽くして木灰の上澄みに挿しいれた指先を一瞥する。
「腹を切って、なにかが変わるか?」
唐突な婆の問いかけに、侍は悲しげに俯いた。
「率直に申して、拙者が腹を切ってもなにも変わらないのではないかと」
「死にたくないか?」
「月静様のお姿を目の当たりにするまでは、死を希っておりました」
「薩摩を裏切ったこと、どう思う?」
「なにも感じません。おそらく」
「おそらく?」
「月静様が拙者の心を──」
「みなまで言わずともよい。ただ」
「ただ?」
「月静は本気でおまえが腹を切るのを見たいようだ」
「では、切りましょう」
「打って変わって、嬉しそうだな」
「はい。喜悦と申すのですか。この胸を焦がす幸。たまりませぬ」
「そうか。果報者だの」
「はい。拙者は巡り合わせがよい。早く月静様の前にて腹を切りたい」
「おまえは薩摩の侍。城の外で切れ」
「されど城の外では──」
「なにか不満か?」
「はい。拙者は月静様に我が血を飲んでいただきたいのです」
「その前に薩摩に引きもどされるのではないか。そうなれば、血を飲ませるどころではないわ」
侍は婆から目をそらして顎など弄んでいたが、妙に明るい声で言った。
「婆様の言葉がわかるのは、月静様と拙者だけです」
「それがどうした」
「誇らしい」
「下賤だが、かわいらしいところもある。剣術はどうじゃ?」
「腕に覚えはございます」
「幾人斬った?」
「さあ。たくさん、とお答えしましょう。月静様には、この刀で幾人斬ったかと訊かれたので、三人とお答え致しました」
「人殺しめ」
言葉はきついが、婆は決して侍を咎めていない。亀のように首を伸ばして問う。
「もし薩摩にもどされたら、昆布のこと、どう告げる」
「告げませぬ」
「拷問されるぞ」
「月静様のことを思い描けば耐えられます」
「月静は、琉球が滅べばよいと念じておる」
「まさか」
「同じように、おまえも滅べばよいと思っておる」
侍の顔が歓喜に輝く。婆が苦笑する。
「処置なしだが、幸せなのはよいことだ」
「拙者、このような境地を知らず、命じられるがままに人をあやめ、地を這う虫のように生きてまいりました」
「砕いて言えば、月静は月の神。夜の神。休息を与えてくれる。休息の究極は、死」
「休息の究極は、死」
繰り返して、侍は大きく頷いた。
. *
薩摩の追及が厳しくなり、侍を匿うのも難しくなってきた。
迷惑をかけては──と、侍が呟く。
茹で加減に集中する月静が無視すると、侍は静かに一礼して出ていった。
婆が指図せずとも、月静は麺の茹で具合を見極められるようになってきた。煮えたぎる湯のなかで踊るそばを凝視し、自分の分だけ先にあげる。歯のない婆のために、さらに茹でる。
「伸びるぞ。早く食え」
「月静は婆様といっしょがいい」
「それは取り違えというものだ。おまえが食わねば、儂は見かねて早々に麺を引きあげるしかない」
歯茎で嚙みきれるまで煮ることができぬ、というのである。月静は上目遣いに頭を下げると、婆が拵えたそばの汁を麺にかける。食えと婆が顎をしゃくる。
ふーふーして、一口、汁を啜る。一呼吸おいて目を瞠る。
「婆様! 凄い。月静は近ごろ、だしの美味さというものを知りましたが、今日のは格別すばらしい。昆布の旨味がたまりません」
月静を喜ばせるために、婆はくすねてきた昆布を一晩水につけてだしを取ったのだ。
「淡いのに強いって言うんですか。こんな美味しい物を食べることができて、月静は果報者です」
「おまえが打った麺も、なかなかだぞ」
かたちが失せるまで煮込まれた麺のどこがなかなかなのか。
月静は笑いかけて、泣き顔になった。婆とそばを食うのも、これが最後だ。
「どうした? 涙で塩気を足すつもりか」
「月静は泣いておりませぬ」
「そうだな」
「そうです」
「とっとと食え」
月静は頷き、箸を使う。今日は麺を平打ちにしたが、つるつるがより増して、嚙まずに呑みこめるほどだ。もちろん婆が食べやすいよう心を砕いた平打ちだ。
「月静よ。侍がおらぬぞ」
「あれ、ほんとだ」
「他人事だな」
月静は笑んだ。婆は唇をすぼめた。湯気をあげる丼に視線を落とす。
「最後に振る舞ってやればよかったのに」
「振る舞えば、決心が鈍るでしょう」
「見事、腹を切るかのう」
「どうでしょう」
「いざ死ぬとなると、じたばたするか」
月静の笑みが深くなる。
婆は月静が何事か悟っていることを感じとった。
婆と月静は黙ってそばを食べた。
翌日、薩摩の者がやってきた。月静を捕縛するという。高飛車で、嫌疑さえも口にしない。
婆が声にならない声をあげ、曲がった腰のまま両手を拡げて月静を護ろうとした。
「婆様、よいのです」
「月静よ、やはりおまえは」
死にたかったのか──という言葉を呑む。
「婆様、お世話になりました。正直に言います。月静は、婆様以外は大嫌いです。聞得大君も琉球も大嫌いです。虫唾が走ります」
「──わかっておったさ」
「ああ、婆様に隠し事はできませんね」
「おまえ、あの侍が好きであろう」
「ますます隠し事ができません」
「されど、なぜ、おまえが」
捕縛されるのか、と途方に暮れた眼差しを月静に投げる。
月静は小首をかしげる。
「罪状なんて、どうにでもなるでしょう」
月静は膝をついて婆を抱き締めた。
「婆様。孤児の私がここまで生きてこられたのは、婆様がいてくれたからです」
抱き締めたまま、婆の心に囁きかける。
「婆様がいなかったら、とうにこの首、豚がされたように自ら掻き切って、果てておりましたでしょう」
「どうしても死ぬ気か」
笑みだけが返ってきた。
せめて、祝女の死に装束を用意してやりたい。けれど月静は薩摩の役人共に引きたてられて、婆の前から消えた。
婆は土間に突っ伏し、嗚咽した。
. *
あえて首里城正殿の前に俄づくりされた土壇場に、侍と月静が引きだされた。共謀して琉球の抜荷を隠蔽したという罪状で、有り体にいってしまえば見せしめだ。
抜荷自体の証拠がないにもかかわらず、抜荷の事実を隠したというのだから、道理も筋もあったものではないが、月静は平静にして寂静であり、口許は柔らかであった。
侍は月静と並んで土壇場の前にある。顔は圧しころした歓喜で輝いている。侍が上ずった声をあげる。
「信じ難く、有り得ぬことです。すべては有り得ぬことです」
「なにが有り得ぬのです?」
「こうして月静様と御一緒できることです」
後ろ手に縛られたまま、お喋りである。
「拙者、心残りは月静様に切腹するところをお目にかけられなかったことです」
「それです。月静は、貴男の切腹が見たかった」
「──卑しい身分ゆえ、切腹相成らぬと」
「卑しいのは、どちらでしょうね」
平然と薩摩を、そして居並ぶ琉球の王族を見渡す月静であった。その眼差しに聞得大君が狼狽え、眼差しを泳がせる。尚貞王も下を向いて微動だにしない。
婆が地面に額を擦りつけて慟哭した。
月静はその泣き声に返すように、一筋の涙を頬に記した。
婆様は追っつけ月静のところにいらしてくださる。願わくば、そのとき、痛み苦しみがないとよいのですが──。
息を整え、侍に向きなおる。視線が絡みあう。
切腹をさせてもらえぬ侍は、すなわち切腹を月静に見せることができない侍は、思いあまって月静を売ったのだ。けれど罪の意識は欠片もない。
侍は悟っていた。総ては月静様の思し召しであると。侍の心を受けた月静が訊く。
「私を土壇場に呼び寄せること、悩みましたか」
「それは、もう身悶えするほどでした。月静様を、売る。その思いがじわりと心に忍びこんできたときの煩悶ときたら──。己の身勝手わがままにすぎぬのではと突っ伏して頭を抱えました」
「いまは悩んでおりませんね」
「率直に申して、歓喜しかございませぬ」
言葉を交わす二人を咎める者はいない。月静の力である。
「ひとつ、お尋ねしたい」
「なんなりと」
「月静様は、拙者が腹を切ったら、どうするおつもりでした?」
「もちろんあとを追って、首を掻き切るつもりでした。けれど、すぐにそうはならないことを知りました。月の神様は粋な計らいをしてくださるものです。結果、こうして二人並んで死ぬことができるのですから」
侍は深く長い息をつく。
月静が囁く。
「静四郎様」
「拙者の名を!」
「もちろん知っていました。月静の静の字と静四郎様の静の字がつながって、それは嬉しかったのです。でも、好きな人にはなぜか意地悪をしてしまう」
「拙者、月静様にお仕えして、名を呼んでもらえぬこと、たいそう胸苦しかった」
「御免なさい。ほんとうに私は意地悪です。ほんとうのところは、月静は意気地がないので静四郎様の名をお呼びするのが恥ずかしくてならず、口にできぬままに過ぎてしまいました。もちろん意地悪な心もありました。無視して、知らんふりをして気を惹きたかったのです」
静四郎の口許に苦笑いが泛ぶ。
「あの世では、静四郎と名を呼んでいただけますね」
「もちろん。ただ」
「ただ?」
「はい。お願いがあるのです」
切実のにじむ真顔になった月静を、眼差しで抱きこむように見つめる。言い渋る月静に向けて、頷きながら促す。
「なんなりと申してください。拙者、鈍いところがあるので、仰有ってくださらぬと、なにもできませぬ」
「私、豚が怖くて」
「豚?」
意外さに大きく首をかしげる。
「私、豚の血で育ったのです」
静四郎は月静に千切られて欠損した乳首のあたりに視線を投げた。
「豚の血で育ったということは、私が手にかけたのではないにせよ、たくさんの豚をあやめたということです。否応なしとはいえ、たくさんの豚の命を戴いたのです。夜毎、豚の夢を見るのです。豚が怒っているのです」
怯えもあらわな、しかも舌足らずな口調だった。静四郎は力まずに答えた。
「護りましょう。豚から月静様をお護りいたします。が、静四郎が思うところを述べますと、豚は月静様を恨んではおりません」
静四郎の言葉に、月静の頬から強張りが消え、目尻には安堵の涙さえにじんだ。
「非道いでしょう、私」
「なにが?」
「死にたくて仕方がなかったのですが、あっちの世界で、私に血を飲まれた豚たちに虐められるのが怖くて、独りで死ぬ決心がつかなかったのです」
「そこで、この静四郎に白羽の矢を立てられた」
「そうです。その通りです」
「訊きづらいのですが」
「なんでしょう」
「静四郎は用心棒代わり、それだけですか」
「まさか。貴男をはじめて見たとき、貴男の額から放たれる光に刺し貫かれました」
「光」
月静は笑み、続けた。
「貴男の硬い胸板が好きで、貴男と肌を合わせるのが大好きで、人斬りに一途だった貴男の心根がなによりも好ましく、あっちの世界で添い遂げられたら──と心窃かに念じておりました」
静四郎は迫りあがる喜悦を抑えこみ、目で促す。
「私のまわりにいたのは、殺せるのはせいぜい豚の、口先だけの弱い男でした。静四郎様のような一途で頼りがいのある危うい方は、いませんでした」
「危うい?」
「まさか静四郎様、御自分が危うくないとでも?」
「──自分では、わかりません」
「静四郎様は、とても危うい。力は危ういものに宿るのです。静四郎様はじつに危うい悪です。いつだって真の力があるのは善ではなく悪なのです。だからあっちの世界でも、いっしょにいられたらと」
「あの世ではなく、あっちの世界ですか」
「豚はいますが、二人だけの世界です」
「地獄極楽は?」
「なんですか、それ。私たちに必要ですか」
「あっちの世界に必要なのは豚と、月静様と危うい悪の静四郎です」
月静は深く静かに息をつき、父に甘えるかの眼差しを静四郎に投げた。
「頼みがあるのです」
「なんなりと」
「あっちの世界では、眠るときは、必ず腕枕を」
「いくらでもしましょう。永遠にします」
「──腕が痺れます」
「それが静四郎の悦びであるとしたら?」
「ふふふ。いっしょに眠れば、ふたりで、ひとつ」
ふたりでひとつと胸中で繰り返す静四郎を見やって、月静は深く頷いた。
「静四郎様。月静は、早くふたりだけになりたい」
「はい。月静様が命じられれば、そこの屁っ放り腰の背骨にも力が入ります」
刀を手に惚けている薩摩の首斬り役人に月静が視線を投げた。
「土壇場に俯せのような無様な恰好は願いさげです。このまま、すっと斬りなさい」
月静の眼前で、静四郎の首が落ちた。薄く目を閉じて穏やかに頬笑んでいた。静四郎からは、青紫の光ではなく鋭い血の針があちこちを貫いていた。
たった一人、ほんとうの命の光を放って月静を刺し、魅了した男の首を見つめる。
額から射していた真紅の光が月静を誘うかのように、ゆるやかな弧を描く。その美しさに、月静は切なげな吐息を洩らす。
月静も自身が死すとき、青紫の光輝とは無縁であることを確信していた。なぜなら月静は、聞得大君が望むであろうことを読んで口にしていただけであったからだ。
月静は真の命の光を放っていた男の首を見つめる。静四郎の額から射していた真紅の光が、月静を包みこみむ。
静四郎の血で濡れた刀が、月静に向いた。
祝女月静、享年十五歳。
その首は首里城正殿の石畳を弾むように転がった。
〈了〉
(第七回に続く)
【第一回】 【第二回】 【第三回】 【第四回】
【第五回】 【第六回<上>】
花村萬月 はなむら・まんげつ
1955年東京都生まれ。89年『ゴッド・ブレイス物語』で第2回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。98年『皆月』で第19回吉川英治文学新人賞、「ゲルマニウムの夜」で第119回芥川賞、2017年『日蝕えつきる』で第30回柴田錬三郎賞を受賞。『風転』『虹列車・雛列車』『錏娥哢奼』『帝国』『ヒカリ』『花折』『対になる人』『ハイドロサルファイト・コンク』『姫』『槇ノ原戦記』など著書多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
