
ロマンポルノ無能助監督日記・第34回[『少女暴行事件・赤い靴』と『魔法の天使クリィミーマミ』と島田満さん]
撮影所に大悪評が巻き起こった『宇能鴻一郎の濡れて学ぶ』は、伊藤秀裕監督・渡辺良子主演『猟色』との同時上映で6月10日(83年)に公開され、客の入りも相当悪かった。
鈴木潤一監督は、この後の児玉高志監督・岡本かおり主演『ケンちゃんちのお姉さん』(12月2日公開)のプロデューサーとなり(当時、監督がプロデューサーを命じられるのは“降格”というイメージがあった)、何か出演者トラブルがあったようで、鈴木さんも児玉さんも、その後2年ほど仕事が無い状態になってしまった。会社から干されたのだ。
前回でも書いたように、僕はこの年の末に『宇能鴻一郎の濡れて打つ』で監督デビュー(公開は翌84年2月17日)することになるのだが、それまでの間は、上垣保朗監督・井上麻衣主演『少女暴行事件・赤い靴』(7月22日公開・崔洋一監督『性的犯罪』と同時上映)、2時間TVドラマ『白い涙』(中井貴恵主演・佐伯孚治監督)、お正月映画の五月みどり主演・小沼勝監督『奥様はお固いのがお好き』(12月23日公開・山城新伍監督『女猫』と同時上映)の現場で、3本チーフをやったが、ちょっと焦燥感にかられていて、思い出しても楽しく無い日々が多くて、記憶も記録も曖昧になっている。
今にして思うと、脚本も書いた『濡れて学ぶ』の失敗で、自分の才能に自信を失いかけているのを認めたく無い気持ちが無意識的にあっても本心を抑えて隠し、監督への道が遠のいたかも知れないという焦りから“他罰的”になっていて、気持ちが荒れていたようだ。
『少女暴行事件・赤い靴』は、実際にあった女子中学生殺人事件を題材にして、それを高校生に焼き直し、茨城県の古河を舞台に、地方都市(北関東)の若者の性的青春群像を描き、最後の最後に、主演のロマンポルノの百恵ちゃん井上麻衣が砂浜のボート脇で死体になっている、というもので、暴行事件自体は全く描かれない。

上垣さんは、『ピンクのカーテン』が前年大ヒットして、突然日活のエース監督のような存在感になり、83年3月25日には『ピンクのカーテン3』が公開されている。これは小森みちこ主演『あんねの日記』(監督はTVディレクターの北畑泰啓)との同時上映で、そこそこ入ったが、大ヒットとまではいかず、『ピンクのカーテン』シリーズも、この3で終わりになった。
そんなことで僕は、まさに上垣さんに嫉妬していた。嫉妬ですよ、嫉妬・・・
演出は下手じゃないけど、というか上手いけど、ヒットはノッてる美保純を得たからだろう、という羨望で見ていたが、上垣さんは「また傑作、作っちゃったよ」と悪びれずに言うので、そんなこと言うタイプだったっけ、助監督の時は無口で暗かったくせに〜、僕も美保純は自分のデビュー作で使いたいな〜という嫉妬だ。

実際、美保純は、現役ロマンポルノ女優としては初めて(だと思う)TVCM(焼きそばUFO)に出演するくらいの人気になっていた。
上垣さんと同年代の若手監督たち・・菅野隆、斉藤信幸さんらは、批評受けは良いが会社からは評価されず、川崎善広さんも便利屋のような扱い、伊藤秀裕さんも安全牌みたいに見えていたから、上垣さんは4番バッター的な風格を醸し出していた。
客観的に見ると、1971年から始まったロマンポルノも12年経ち、監督の新旧交代があって、若手が引っ張る時代到来、ということか。
この『赤い靴』も、大ヒットシリーズを産んだ上垣さんに、ご褒美のように与えられた“作家的作品”と言え、本人の出した企画だという記憶を確かめてはいないが、僕はそのように受け取っていて、脚本を読んで、本来はこんなものがやりたい人だったのかフ〜ンと思ったのであった。
そのフ〜ンというのは、僕が日本映画で結構キライな“等身大の青春”というやつで・・何故キライか理由を聞かれても「つまらんから」としか言えないが、宇能鴻一郎のようなバカバカしいポルノは許容出来ても、挫折とか傷つけ合いとかが描かれるリアルで暗い青春を映画で見せつけられると文句を言いたくなる、という傾向が、入社以来、育っていたのであった。
自分が高校一年で8ミリ映画を撮ってから大学生まで描いていたのは、そうした「等身大の青春」だったし、自分も出たりして、「リアル失恋もの」と「お笑い路線」を交互に撮っていた。「傷つけあい」や「挫折」なども同級生たちに演じさせて、暗い若者心理を映像にしようとしていたんだよな俺も・・・
見る側としても、大学生の時までは、日本映画のリアルな青春ものは好物であった(『星空のマリオネット』とか『赤ちょうちん』とか)のだが、ロマンポルノの現場に入ってからは、次第に、これを嫌うようになっていた。
そういういじましいものからは卒業だという気持ちと、「今の日本映画に必要なものは、強固なフィクションなのだ」という気持ちだった。
黒澤やスピルバーグの描く強いフィクションこそが映画だ、という想い・・
黒澤はリアリズムでは無いから面白いのだ、小津は過大評価されて中身はツマラン、今村昌平は面白いが日活の先輩だし学校も自分でやってるからスルー、鈴木清順なんてエセ芸術だ、いやもともと映画はエセ芸術だから面白いのだ、深作欣二はその最たるものだ、あのエネルギーとリズムが今の日本映画の最高峰だ。ハリウッドに勝てるのはフカサクだけ・・あ、いや、『宇宙からのメッセージ』は壮絶に失敗しとるんじゃがのぉ(広島弁)・・・
那須博之さんと飲んで話し倒して遊んで影響を受けているうちに、こんなふうに考えるようになっていた。環境が思想を形成していったのか・・・
藤田敏八や神代辰巳のようにリアルな物語を撮りながら俳優の魅力も引き出して、意表をつくストーリー展開で笑えたり感動したり出来るのならそれは良いが、パキさん(藤田敏八のニックネーム)(パキスタンの王子に似ていたかららしい)以外に、そういうことは出来てない。みんなパキさんや神代さんの上っ面を真似しているだけだ。
森田芳光は、そういう日本映画的な「重さ」「暗さ」から、軽く浮くことに成功した存在だった。
(この頃、「軽い」ということが、良い意味で使われ出していた時代だ)
上垣さんもパキさん一派だからな・・・「金子は経験不足」だと言ってパキさん組(『帰らざる日々』)に入れてくれなかったことを思い出したぞ、チーフだった上垣さんがぁ、そうだった、思い出した・・・
『赤い靴』は5/12にクランクインで、古河ロケに向かう前に、上野の陸橋から「去ってゆく列車」というラストカットをスケジュールに入れた。
主人公が、古河と東京を行ったり来たりする設定で、彼女が死んだ後に列車だけが故郷に向かってゆく、という意味でラストカットになっているのだと思った。
その日はナイター(夜間撮影)もあって初日から遅くなるから、上野駅に7時集合して、この実景をイッパツ撮ってから古賀に向かえば、調布の撮影所6:30出発するより効率が良くスタッフ受けも良いだろう、という判断からであった。
爽やかな朝で、テキパキと陸橋の上にカメラを構えて、時刻表で調べた列車を狙っていると上垣監督が現れ、
「愛情の無いスケジュールだ」
と言ったので、僕は一瞬で気持ちが凍ってムッとなった。
だが、無言であり、無表情であったろう。
意味は「ラストカットを初日の一番手に撮るなんて、監督に対して愛が無い」という意味、そんな意味は即分かりますよ。
その後も何とも言い返すことは無かったが、ずっと頭に残った言葉を反芻していた。
「あんたに愛情なんかないです。憎んでいないけど愛してもいない。仕事でやってるだけですから。愛さないといけないの?何故ですか?」
この頭の中の言葉は良く覚えてるんだよな・・・頭の中で何十回も何百回も繰り返したから。
言いたかったけど、本人には言わなかったから。
映画は撮影の効率を考えて順番通り撮らないなんて、当たり前のことではないか。そこになに?愛情なんて、入る余地無いところで仕事してるんじゃないすか、俺たちはさー
しかし上垣さんは、田中登組で僕が田中さんから怒鳴られてベソかきそうになってヤケクソにカチンコを叩いていた時に肩を叩いて「腐るなよ、助監督なんて屈辱だろ」と言ってくれた人だし、社長秘書との恋愛沙汰の時にカラオケの仕事をしていて地方ロケで一部始終を喋ってしまったという弱みも握られている・・・全部ひっくるめて「愛情」と言って言えないこともない・・・いや、「愛情」と呼べる感情までは無いですから〜奢ってもらったことも無いですから〜
僕が愛を感じてるのは那須博之だけですから。
デビュー作の『ワイセツ家族』で干されていた那須さんも、6月24日公開の山本奈津子・小田かおる主演の傑作『セーラー服百合族』で華々しく復活を遂げる。その後、直ぐにエース監督の存在感を示すようになる。那須さんの時代が、そこまで来ている。
ここまで書いて『赤い靴』を配信で見直してみたら、結構、きちんとした脚本構成(佐伯俊道・望月六郎)でセリフも特徴的で、悪くは無い。
今見ても、当時の若者の姿を真摯に描いており、ポルノシーン演出レベルは最高水準と言えるほどでエッチ度は相当高い、さすが上垣さんと思ったが、“面白さ”という意味では、最終盤で失速しているから、傑作とまでは言えないと思う。
少女たちが無軌道に深夜の歌舞伎町を遊び回る描写が長すぎるので退屈する。
これをもっと短くして、すぐに少女の死体になったら衝撃があったであろう。
また、上野の陸橋から撮った電車の風景は、ラストカットとしては使われておらず、別な箇所に挿入されていた。
撮影時、台本上はラストだったが、実際の映画では、編集で試行錯誤したのであろう、古河の風景で終わらせている。少女の父親(野上正義)が、ボート製造なので、淡々と作業する姿で哀愁を感じさせようとしているが、中途半端に終わっている印象は否めない。
だが、陸橋から撮った電車をラストカットに戻しても、印象は特に変わらなかっただろう。
この映画の良さは、古河で育った少女・マミが、両親の離婚によって母親と共に東京に移り住むが、地元のゲーム喫茶に集う友達に会うために毎土曜、電車に乗って古河にやって来る、友達がマミ不在の間の仲間日記を書いたりして子供っぽいところもありながら、バイク乗りの恋人とモーテルでセックスする、というような若者点描が、東京と古河の対比する風景に溶けこんで、こういう青春もあるよな、と、リアルに感じさせてくれるところであろう。
後に加来見由佳の名前で『残酷!少女タレント』で主演し、上垣さんと結婚することになる小泉ゆかもマミの友人で好演、古河のパン工場勤務で、マミの恋人の中根徹と鉄橋の下の夕方の河原でセックスするシーンがある。
そこへ、土手にランニングする女子高生運動部が現れ、見えるか見えないか、見せてやろうか、みたいな描写もある。
彼らが現地で遊ぶことと言ったら、シャコタン(改造車)とバイクを走らせることくらいしかなく、暴走族とまではいかないセコさだが、騒音を発しながら夜道を蛇行して面白がる、そこに平山みきの名曲「真夏の出来事」がかかるが、これは著作権の問題が起こるとまずいので、ヒマラヤ・ミキ(別名=やや)のそっくりカバーが使われている。
上垣さんは、ワンコーラス聴かせようとして、車の走りが長くなり、工夫を凝らせて、走りのバリエーションを増やしているが、「工夫」とは「スタッフ泣かせ」の結果に繋がる。
現地は地明かりが少なく、こっちから持って行ったライトも当然限られているので、殆ど真っ暗な画面でシャコタンとバイクが走り、若者たちが花火を座席から表に身を乗り出してぶん回している。それはとても楽しそうであるが、“こんなことが楽しいのかい貧しいよねバカ者たち”、と思わせるのは、上垣さんの狙い通りだったのであろうか。
だが、こうした撮影は物凄くタイヘンなのである。
映画の撮影で、「車の走り」は最大のタイヘンさで、台本上に1行書かれただけでも、スタッフは頭を抱えて対策を練る。
カメラが固定されていて、その目の前を車が走り去るだけならタイミングだけの問題で苦労も無いが、カメラも一緒になって移動するとなると、難易度が高まって、カメラ車でのカメラ固定など、作業にやたら時間がかかる。
手持ちでやろうとしても、カメラマンを助手が支える帯の装着などもしなければならないから、全て簡単には行かないのだ。
この時、セカンドに就いて『家族ゲーム』以来の付き合いとなっている明石知幸も言っている。
「車の走りはバケモンだからね〜」
と。この言葉も、様々な現場で、何度となく聞いた。(前にも書いたっけ?)
TVの探偵刑事モノを主に撮っている東映セントラルのスタッフなら慣れたものだが、ロマンポルノのスタッフにとっては手間がかかるし、上垣さん自身も、助監督での経験が余り無かったらしく、時間がかかり過ぎるのは想定外だったようだ。「初めてだからさー」と言っていた。
それで、現場に向かって走るロケバスの中で上垣さんが、制作部の三浦増博に「ちょっと、次の飯時間、短縮出来ないかな」と相談しているのを後ろで聞いた僕はカチン!ときてしまった。
そんなことを監督が言うのは越権行為だと思い、瞬間湯沸かし器のように感情が沸騰して激しく抗議したが、言葉は途切れ途切れにしか思い出せないが、「監督がそんなこと言っちゃダメでしょう」と言った気がする。
ロケバスのなかで、監督とチーフが言い合いして、スタッフも呆気に取られたであろう。
結局、飯時間はチーフ判断できっちり1時間取ったから「車の走り」は撮り残しとなった。上垣さんに嫌味したつもりでは無い。
別な日のダイアリーにも「ヒルメシおしでやるが、結局2時過ぎまでかかり失敗」と書かれてある。
5/12から始まった撮影は、5/24まで実働11日間だったが、そのうち6日がナイター撮影があって、そのナイターは2時くらいまでやられたから、スタッフ的にはかなりキツい撮影となったはずだが、体のキツさというのは記憶に残らないで、感情的なものが残るようである。
撮影最終日の5/24は、京王プラザホテルでワンシーン撮ったので、そこは一泊借り切っているわけだから、ナイターで歌舞伎町と花園神社を撮った後に、僕は京王プラザの撮影した部屋に戻って一人で寝た。
翌日は新宿松竹で根岸吉太郎監督の『俺っちのウエディングソング』と、新宿スカラ座で『ガンジー』を見て帰っている。
更にその翌日は渋谷東映で『楢山節考』、渋谷パンテオンで『E.T.』、日曜日には吉祥寺スカラ座で市川崑『細雪』を見ている。
『E.T.』は撮影所のなかで「見た?」「見た?」と大きく話題になったが、『赤い靴』仕上げ中の上垣さんが「なんで死んだのが生き返るんだよ」と文句を言っていたのを良く覚えている。
僕は、感動があったが、上垣さんが言ったところは、確かにそうだよな、と思ったから、感動も、それほどでも無かった。
世間ではスピルバーグの失敗作とされている『1941』が、僕にとってはそれまでの感動作であった。那須さんとも、よく『1941』の話をした。
『赤い靴』打ち上げの後、2週間くらい経ってから、制作の三浦が電話して来て、上垣組演出部と女優とで飲み会をやろうと言う。
調布の「とりまつ」で軽く飲み食いしてからカラオケ「メルヘン」へ。
上垣さん、三浦、明石、サードの工藤、井上麻衣と小泉ゆかというメンバーで楽しく飲んで歌った。
上垣さんの奢りであった・・・いろいろあったから僕を慰労しようとう上垣さんの計らいで、三浦と相談して皆を集めたのであろう。監督も気を使ってタイヘンだよな、と「愛情」が芽生えた。
偲ぶ会(2019/4/22 )でも、遺影に向かって「愛なきスケジュール組んですみません、いろいろありがとうございました」と呟いたのであった。
http://blog.livedoor.jp/kaneko_power009/archives/2019-04-22.html
話は、時間が戻って次元も微妙に変わるが・・・
『赤い靴』クランクイン前日の5/11に、三浦半島のロケハンから調布の撮影所に帰って来た夕方、通勤用のバイクで小金井の「スタジオぴえろ」に行って、原稿を渡して、三鷹の自宅に帰っている。
TVアニメ「魔法の天使クリィミーマミ」第8話の脚本である。
「うる星やつら」が大成功して信用を得たスタジオぴえろは、同社オリジナルの魔法少女モノの企画が日本テレビに通り、「うる星」では文芸担当でスタートした伊藤和典さん(10年後に『ガメラ』を書いてもらう)が、原案とシリーズ構成を任され、その伊藤さんから電話があっての発注であった。
ピエロでの打ち合わせで見たキャラクターのデザインは、「うる星」と同様に高田明美さんが描く、可愛らしいものであった。
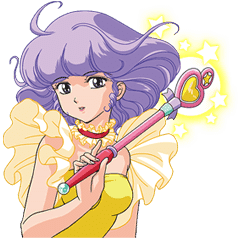
伊藤さんがまとめた企画書を読んで、とても面白いと思ったのは、10歳の少女・森沢優(両親は自宅前の屋台カーで人気のクレープ屋をやっている)が、異次元宇宙からの魔法を手に入れて14歳のアイドル歌手・クリィミーマミに変身する、そのマミの大ファンになる13歳の俊夫に、優は密かに幼い恋心を抱いているという“変則的三角関係心理ドラマ”であった。
優の声優は、前年に「スター誕生」で合格して訓練を受け、このアニメの主題歌「デリケートに好きして」で歌手デビューする太田貴子15歳。
俊夫の声は、アイドル声優として知られている水島裕。

伊藤さんは1〜3話を書き、僕は8話の「渚のミラクルデュエット」を書いた。
スタート時は全26話の予定だったが、この83年7月1日の放送開始から人気が出ると1年続いて52話となり、僕は、半年後にもう一本29話の「ロープウェイパニック」を書いている。
芸能界の裏話は、アニメ関係の人より知ってはいるが、その知識が必要とされていた訳では無い。魔法少女の世界に、SFやアイドルの話を混在させて、新たな視聴者を楽しませよう、いや、自分たちで楽しんでしまおうという路線で、そのごった煮的なところに惹かれて話を書いて楽しんだ。
昼は『赤い靴』のロケハン、夜や日曜に「クリィミーマミ」のシナリオを家で書いていたのだった。
書いていて楽しいので、もっと書きたかったが、『赤い靴』が終わって、直ぐにTV2時間ドラマ『白い涙』(月曜ワイド劇場)チーフを命じられ、書ける余裕が無くなって、次の依頼は断らざるを得なかった。
中井貴恵のソーシャルワーカーが世話をしている妊婦(伊藤公子)が事故にあい、脳死したまま出産、その乳房から白い涙のように乳が流れ出る、という悲惨な話だが、そこに至るまでに医師たちをめぐるドラマがあって、登場人物がやたら多い。
監督の佐伯孚治さんは東映出身で、労働組合の活動が長いらしく、TVでは「帰って来たウルトラマン」なども撮っており、この翌年、美保純主演で『高原に列車が走った』を組合制作で撮るが、とても紳士で、穏やかな人であった。
それに甘えたつもりではないが、現場では、僕は何度も失敗しており、思い出すのも恥ずかしい。(やっぱり甘えていたかな)
失敗というのは・・・
TVで顔を知られた役者というのが、いかにスケジュールが忙しいのかを思い知った、というのは、役者の空いている日を縫いながら撮影スケジュールを立てるという事に慣れていないというか初めてのことなので、基本的に頭が毎日混乱しているから、チーフとしての現場への指示が混乱するのである。
それ以前に「なんで自分はこんなことをしなきゃならないんだろう」という気持ちが解消されていないので、仕事にきちんと向き合えていないというか・・
1日で3人の役者の入り時間を伝えていなかったと分かった朝、メイクさんから言われてそれに気がついて、慌ててそれぞれの自宅へ電話を入れたら、向こうも慌てて家を飛び出してくれて、なんとか間に合った、でも、現場は1時間以上「待ち」になった、という事もあったが、女優さんから、
「私たちは、助監督さんの指示によって仕事と生活のスケジュールを立てているのですから、こんなことが二度とあってはなりませんよ、電話がなければ出かけるところでしたから」(携帯の無い時代)
と、至極当然のお叱りを受け、恐縮した。
この日が終わったら、監督の佐伯さんは穏やかな笑顔で、
「今日は金子さんにとっては最悪日でしたね」
とだけ言って、それ以上の追求は無かった。
待ちが1時間くらいで済んだのは、佐伯監督が、抜き撮りでこなしてくれていたからだった。感謝。
こんなチーフでも現場が何とかまわっていったのは、フリーのセカンドの萩庭貞明が優秀であったからだ。
日活にはいないタイプで、判断が早くて押しが強いので、現場は見事に仕切られる。
この8年後の91年に『遊びの時間は終わらない』で監督デビューし、東京ファンタスティック映画祭での上映に行き「おめでとう」と言って再会を祝し、にこやかに乾杯したが・・・
その8年前『白い涙』のエキストラで、日活作品でもエキストラとして数年の顔見知りであるHさんが、物陰で僕に言いつけた。
「あのぉ、萩庭さんが『あんなチーフいなくていいよ』なんて言ってましたよぉ」
さもありなん、と思いました。
そのことは萩庭には言ってない。
萩庭貞明はVシネ『ミナミの帝王』を57本全部監督した、凄い。
『白い涙』は6/25~7/6までで撮っているが、ダイアリーには空白の日が多く、記録する気分にもならなかったようだ。
ダビングの最終日の7/26、青山一丁目の「ダンケ」にて、「クリィミーマミ」の打ち入りパーティが開かれ、一転ハイな気分になって、駆けつけた。青山一丁目なんて、ロケ以外では初めて来たか。
「うる星やつら」のような大パーティでは無く、こじんまりとした感じではあったが、日活の調布居酒屋打上げなんかよりはずっと華やかだ。
パッと見て、アイドルか、という感じの目立って可愛い女の子がいるし。
ひらひらのついたブラウスにミニスカート。
スーッと近づいて自己紹介すると、
「脚本の島田満(みちる)です」
と言うのでビックリ、第4話を書いた人で生原稿も読んでいるが、男性だとばっかり思っていて、しまだまん、と読んでいたが、そう言えば、ちょっと丸文字ふうだったな、と思い出した。
24歳。
こっちは27歳。突然、「結婚」の文字が脳裏を渦巻き・・と、ダイアリーに書いている・・
「金子さんの優ちゃん、可愛いですね」
と言ってくれて、胸ズキューン!
二次会が新宿の「北の家族」だったが、当然行きました。
ぴったりくっついて行った。
信号を渡るときに「僭越ですが、僕の電話番号を教えます」と言うと、
「僭越ですが、私も電話番号を」と、教えてくれた。
こんなにスムーズに電話番号を教え合う、というのは初めてだ。
3日後に電話したが、男性が出た。
お父さんであった。
初デートは、だいぶ先のことになる。
監督になって翌年であった。
しかし、書いているうちに筆がにぶってゆく・・・
35年後の2017年12月15日、中国で島田さんの訃報に接しました。
フォローしていたTwitterに「島田満の娘でございます。僭越ながら母に代わりお伝え致します。 母、島田満は本日12月15日11時30分に昨年から患っていた病の為、永眠致しました。享年58歳でした。 38年に渡る長いキャリアの中で執筆してきた様々な作品を愛してくださった方々、誠に有難うございました。」
新たに文章を書くエネルギーが出ないので、その2日後12月17日にBlogに書いた追悼文を編集して終わりにします。
島田さんはアニメ演出志望で早大卒業後に新卒で東映動画にトップで合格したが、女性なので体力を心配されて脚本に回された、ということで「宮崎駿監督をいちばん尊敬してるんです」という言葉を初めて聞いた人で、アニメの知らないことをいろいろ教わったり、SFもお互い好きだったから、「夏への扉」の話で盛り上がった思い出がある。ミュージカルも好きな人で、ブロードウェイに「ファントムオブパラダイス」を観に行った話も聞いた。
接点はマミだけで、彼女もどんどん売れて忙しくなり、僕はその年の暮れに監督になって、翌年2作目の『OL百合族19歳』は、吉祥寺で一緒に見てくれて、批評してもらった。
出会って2年後『みんなあげちゃう』の時に、はじめ脚本で組んでいた高田純さんも既に亡くなっているが、一緒に旅館にこもって高田さんが風呂から上がって部屋に戻ると、僕は島田さんの書いた『魔法の妖精ペルシャ』のテレビ放送を見ていて、それが高田さんにはショックで「俺が風呂から上がると金子はミンキーモモをニヤニヤしながら見ていたのでこいつとは組めない」と言って降りてしまい、「シナリオ」誌の対談でも語っている。
後に高田さんからは謝られたが、神代辰巳監督と組んだ直後だったので世代間のギャップも大きかったろうし、そのアニメは好きな女性が書いた脚本だったという事も知りようも無いし、言えなかった。
その後『みんなあげちゃう』は伊藤和典さんに頼んだが、伊藤さんは「僕より向いている奴がいる」と25歳の井上敏樹くんを推薦してくれた。
島田さん、井上くんと何度か食事したり飲んだりして井上くんの結婚式にも行った。
『みんなあげちゃう』も三人で、やはり吉祥寺で見た。僕と島田さんが先に入っていて、井上くんが後から来た。映画の後での三人での食事は、とても楽しいものだった。二人は『ドクタースランプアラレちゃん』でデビューした同期生であった。
島田さんと僕の夢の方向は、重なっているところもあったが、違うところもあった。恋心と、成長しようとしていく一人の作家への敬意と・・・
そういう想いを乗り越えて、というと正確では無いかも知れないが、初めて僕の作品を書いてもらったのに実現出来なかった『ウルトラQザ・ムービー』はじんのひろあき・島田満・伊藤和典の3話オムニバスで、島田さんには怪獣の出ない夢と夢が合成する話「夢中デ眠ル」を書いて貰った。とてもミステリアスでファンタジックな物語で、これだけでも今からでも撮りたい気持ちが残っている。
97年『学校の怪談3』をオファーされた時は、お互いの家庭のことも話せて、絶対向いていると思って島田さんをサンダンスカンパニーに紹介して脚本を担当してもらった。古澤利夫さんに厳しく言われて書き直しさせられても、全くへこたれない感じだった。「ああいうタイプの人、慣れてるし、嫌いじゃないんです」と言っていた。
運動会に出られないで死んだタイチの話は島田さんのオリジナルで、「運命は自分で変える」というポジティブな言葉が島田さんらしかった。意外に「ゆかり~ん、キック」なんてセリフは実写畑の人だと書かないかも知れない。「キョンキョンが言ってたよ」とか「胸はダイアナ妃」とか・・・
その後、新井素子原作の『ひとめあなたに』をかなり変えて書いてもらい、地球滅亡の隕石衝突の一週間に別れた恋人に会いに歩くというスケールの大きいダークファンタジーが出来たが、これも実現出来なかった。脚本だけでも、読みたい人に読んでもらう方法は無いものだろうか。
更に後年東映で『怪談レストラン』も面白く書けた独創的なロングプロットの段階で流れてしまった、ということもあり、ずっと申し訳ない気持ちでいたところ、「締め切りに追われるアニメスタジオのすったもんだを小劇場で舞台化したら面白い」という話を持ち込まれてお会いしたのが暫く前のことになるが、まさかの最後になってしまった。
この時も、初めてお会いした頃の少女のような輝きで話され、細かいギャグまで語っていたが、お互い別な仕事で忙しくなり、実現には至っていない。島田さんのなかでは、物語はどのくらいまで出来ていたのであろうか・・・
島田さんのアニメにおける膨大なキャリアのなかでは小さな話かも知れないが、彼女のあくまでポジティブで前向きなエネルギーが、実写の世界では『学校の怪談3』だけに結実した、ということが悔しくてならず、ご健康の事を想像することも出来なかった不明をお詫びしたい・・しても仕方ないが、テニスの話もされていたし、小柄だが頑丈な人だとばかり思い込んでいた。
撮影中の中国で突然の訃報を聞き、体に変調をきたすほど驚いたが、年末年始まで帰れず、葬儀にも参加出来ないので、井上くんからも叱られると思うが、ご家族の方、関係者の方にお悔やみ申し上げ、心からご冥福をお祈りしたい。
・・・と言うことになるとは思いませんでしたよ、島田さん、会った日のことを何度も何度も思い返して気持ちは乱れ、この文も何度も書き直し、泣いてしまいます・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
