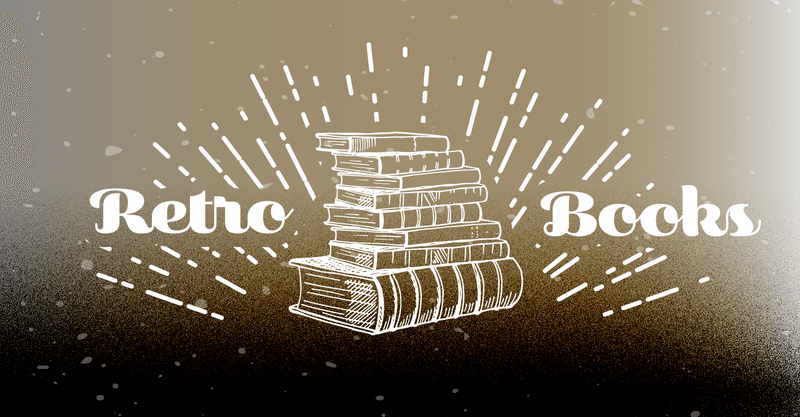
迷信は本当に取るに足らないものなのか?【個人的に面白かったアカデミックな話 1.格差と援助の経済学】
大学時代を思い返してみれば、聞くに耐えない講義が多かった。私の大学は特にそうだった。内部進学を多く抱える中で彼らを卒業させるのには、そのくらいでなければならなかったとも感じる。出回っている過去問を入手さえできれば、私の学部は特に留年することもなかった。(それでも留年する人間が私の周りに多かったのはまた別のお話)
そうした環境で行われる講義は当然教授のやる気もそがれ、質の低いものとなっていた。結局4年間通って「面白く価値がある」と感じた講義は20を数えるかどうかで、それ以外は正直レベルも低ければ、つまらないとも感じるものであった。
ホリエモンもすでに言及しているが日本の4年制の大学に通うことで得られる知識は、(特に文系において)書籍でも得られる可能性が高い。文系4年制大学に通う価値は確実に大卒のブランドによるものだと考えられる。(そしてその恩恵を私はかなり受けられてると感じている。)受験生はこの辺を考えて大学に入るかどうかも含めて検討して欲しい。(うちの大学が特に緩かった説は大いにあるが)
そんな中でも価値ある講義というものがちらほらあった。「個人的に面白かったアカデミックな話」ではそんな講義であった話も紹介していきたい。
「格差と援助の経済学」
詳しい講義内容は実家に置いてきた講義ノートを見なければいけないので掘り出してからになるので、今日は軽いジャブになるがこの「格差と援助の経済学」の講義は聞く価値があった。
出席点こそとるものの、中間、期末のテストで点数とれれば出席してなくても単位がもらえるものだった。余程首尾よくやらなければそんなことできない難易度であったことも評価のポイント。講義は講義でしか得られない知を得られるからこそ価値がある。(PDF配れよという話でもあるが、そこにはしっかりとしたテキストでは伝わらない講義があった)
実際にアフリカまで行っておこなう調査
援助を行っていくのだから当然といえば当然なのではあるが、教授らは実際にアフリカにまでいって援助にまつわる調査を行っていた。まずここが面白かった。(面白かったと表現するのが適切かどうかは難しいところではあるが、私の第一感は面白かったとなることが多い、ここはご容赦くださいませ。)
他の講義においては、当然社会的な実証実験とかも含めて現実社会を見ていくものもあったが「アフリカに行く」ことに比べればはるかにちっぽけにきこえてくる。あの大陸で援助がどのような形で行われているのかを実際に現地に行って見ようとすることに比べれば、経済効果がどうだの、金融政策がどうだの考えるのはどーでもよく感じた。
そんな中でも興味深い話があった。「迷信」の話である。
「迷信」とは何か?
現代において一番強く確実だと信じられているのは、キリスト教でもなければ仏教でもない。それは「科学」である。水道から水が出てくるのは、圧力を張った上水か通っているからと説明できるのも、圧力という概念が科学から生まれたからだ。
「科学」はこうした知識の体系のことを指しているらしい。(あまり科学に関して深く話過ぎるとそれだけで無限に哲学できそうな感じもするのでここまでにするとしよう。)
アカデミックな引用ではなくなってしまうが、「迷信」についてウィキペディアを見てみると…
人々に信じられていることのうちで、合理的な根拠を欠いているものは多くあるが、一般的には、そのなかでも社会生活を営むのに実害があり道徳に反するような知識・俗信を「迷信」と呼んでいる。
どうやら科学の対極にありそうなものが迷信らしい。(有識者の皆様には大変恐縮ですが、本当に精密な議論はやはり長くなるのでここでは割愛させていただきたい)
アフリカに行った「科学の最先端」とも言える教授は、面白いことを言い始めた。曰く
「迷信はあながちバカにできない」
科学を追い求めるものが、迷信の価値を認め始めたのである。なるほど、興味深いではないか。彼はこう続けるのであった。アフリカの現地に住む人々がこういったのだと。
「あの森には怪物が住んでいる、だから木を切ってはいけない」
実際に彼らの言う怪物が住んでいないのは、空から見れば明らかなのだが、木を少し切り拓いてみるとどうだろう。近くの川が氾濫しだしたのである。慌てて対応にあたったため事なきを得たが迷信に従っていればという感覚が否めない。
「あの森には怪物が住んでいる、だから木を切ってはいけない」の言葉の背景には、昔からそういった事情があったと考えられる。
もっと詳細に言えば、「あの森には怪物が住んでいる、だから木を切ってはいけない」という言葉は論理的なつながりこそ欠いているものの、現地の人々を守るのには大切な「迷信」であった。ここで迷信という言葉は迷走をはじめる。
迷信は本当に取るに足らないものなのか?
私たちが普段暮らしている中でも、迷信というものはありふれている。死をイメージされる4という数字は旅館において使われることは少ない。それを科学的な検証をもとに語り切れているかと聞かれればそうではない可能性が考えられる。
では迷信とどう付き合っていくべきだろうか?
私の答えは、「迷信」が生まれた背景があることを認識することだ。
迷信があるのにはそれなりに理由が存在する。当然それは人間的な勘違いによるものかもしれないが、そうでないことも考えられる。例え人間的勘違いであったとしても、なぜ現実の認識がずれるのか考えることに価値がある。そして「迷信」に人間的な勘違い以外の意味が考えられるとき、そこには科学による大きな見落としや、カオス理論に基づく人間的科学の限界が考えられる。
この「虚」さえも現実世界の一部として認識しようとする視点は、この講義を受けてなければ得られなかった可能性が高い。論理でものを語ろうとする人間は、往々にして論理「でしか」ものを語れなくなってしまうことがある。現実の世界をよくみて、人々が論理的に間違っていたとしてもその話を注意深く聞いて、例え一見ハチャメチャだと思える言説にもその背景に目をやる胆力が必要なのではないか。それこそが教養なのではないか。
そう感じさせる講義がこの授業の価値の一部だった。
よろしければnoteのフォローとスキお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
