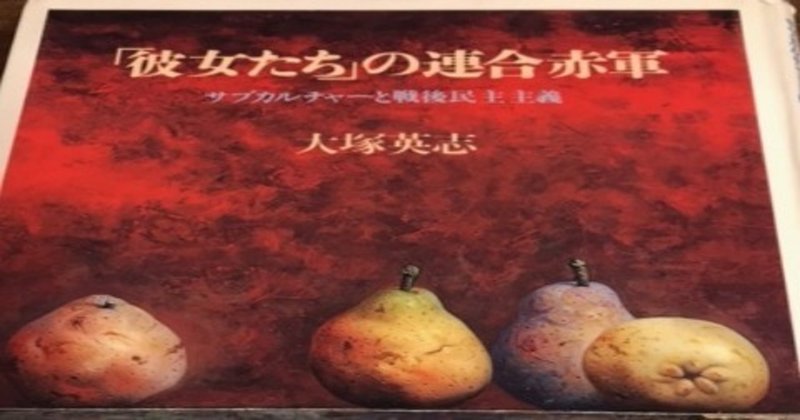
「「彼女たち」の連合赤軍」を読む。
数少ない友人のK君が山本直樹の「レッド」を読んでいるということで、彼に勧められた大塚英志の「「彼女たち」の連合赤軍」(文藝春秋)を図書館で借りて読んだ。
と言ってもこれは新刊ではなく、初版は1996年。およそ四半世紀前に書かれたものだ。
今から四半世紀前といえば、1995年。自分は30歳だった。当時は男性娯楽雑誌、いわゆる「エロ本」の編集者を辞めてフリーのライターになったばかりで、今から考えるとろくに仕事もなかった割には、特に悲観することもなく、楽しく生きていたと思う。ただ、社会としては大事件が相次いでいた。1月に阪神・淡路大震災。3月には地下鉄サリン事件。それを実行したのがオウム真理教だと判明し、5月に教祖の麻原彰晃が逮捕。関西と関東で地震と無差別テロに恐怖した年だった。「新世紀エヴァンゲリオン」の放送が始まったのもこの年で、翌年3月に終わる。自分は本放送ではなくその直後の再放送で初めて見たのだが、いま見直してみると(最終話以外は)割と普通のアニメに見える。だが当時は、設定もストーリー展開も描写も、その時代特有の閉塞感を持っていたように感じたのだった。
さて、この本のタイトルにある「連合赤軍」とは、もちろんあの「あさま山荘事件」を引き起こした連合赤軍のことだ。といっても、この事件が起きたのは1972年。現在48歳以下の人は生まれる前の出来事なので、「もちろん」と言われても困るだろう。だが、連合赤軍とは何かを説明するには、その前の1960年代末からの全共闘運動=学生運動も説明しないといけなくなり、ものすごく長くなるので、知りたい人はお手数ながらご自分で調べていただきたい。
当時、自分は7歳、小学2年生だった。これは、おそらく日本で初めてテレビで生中継された事件で、しかもそれが1週間以上にわたっていたので、事件の意味はもちろんわからなかったが、自分もテレビで見た記憶がある。と言っても、機動隊が時折パンパンと銃で撃ったり、でかい鉄球がガーンと家(犯人たちが立てこもっていた「浅間山荘」)にぶつかったりという程度の断片的な記憶ではあるが。ただ、その後、地元の高松北警察署に学校から見学に行った際、感想文を書かされたのだが、その中で「あさま山そうのときはたいへんでしたね」と書いている(のを数十年後に母親から見せられて思い出した)。まあ、そのくらい、子供でも強烈な印象が残る出来事だった。
このあさま山荘事件自体は、1972年の2月、連合赤軍のメンバーが人質を取って山荘に立て籠もり、機動隊の突入によって逮捕されたという、わりとわかりやすい事件なのだが、問題は「なぜ立て籠もったか」である。彼らはそれまでの違法行為の数々により警察に追われて逃げていたわけだが、実は事件前の1971年末から事件直前まで、連合赤軍メンバーがアジトを転々としていたときに、12人もの「同志」を「総括」という名目で殺害していたのである(「山岳ベース事件」と言われる)。
は? なんで同志を殺害? と、当時を知らない人は思うだろう。いや、自分も思う。要するに「内ゲバ」である。
現在50歳以上の日本人なら「内ゲバ」という言葉自体は知っていると思う。なんせ、「やめてけ〜れゲバゲバ〜」(左卜全の歌う「老人と子供のポルカ」の歌詞)とか「ゲバゲバ90分」(「アッと驚く為五郎」で知られるギャグ番組のタイトル)が流行していた時代である。この「ゲバ」とは暴力を意味する「ゲバルト」というドイツ語。「内ゲバ」とは「内部ゲバルト」の略、つまり仲間割れである。
当時の活動家なら、「いや、総括は内ゲバとは違うよ」と言い出すかもしれない。たしかに彼らの間では、「総括」とは「反省して次につなげる」という意味らしい。しかし反省を強要して殴ったり蹴ったり縛ったり、食事を与えず極寒の野外に放置したりするのは虐待以外の何物でもなく、外部から見れば内ゲバとしか見えないだろう。そんな異常行為の果てに、12人もの「同志」が殺されて土の中に埋められたのである。
この本の著者である大塚英志は、その「実行犯」のひとりである永田洋子に興味を持った。正確に言えば、永田が刑務所内で描いている「乙女ちっく」なイラストが載った雑誌の記事に興味を持った。つまり、森恒夫という連赤のリーダーとともに12人の殺害に積極的に関与した殺人鬼、のように思われている永田とイラストとのギャップに注目したのだ。それは、少女まんが好きの大塚英志にとってはきわめて自然なことだったろう。
殺害された12人の中には、4人の女性(うち一人は子供を身ごもっていた)もいたので、永田は嫉妬(容貌など)から殺害したのだろうと言われている。大塚は、それよりも、殺された女性メンバーが髪の毛を触る、化粧をする、パンタロンを買うなどの女性にとっては当然の行動に永田が文句をつけている事実などから、永田は自分の中の「かわいさ=女性性」を肯定できなかったからではないかと考える。
この論考の初出は、1994年6月、「文藝」に掲載された。その翌年、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起こる。そこで大塚は、オウム真理教の女性信者たちと永田を比較して、なぜ女性たちが「カルト」に走ったのか、についても考える。これらは、いわゆるフェミニズムの問題でもあるが、大塚はそれまでの「フェミニズム運動」が、必ずしも女性たちを救ってこなかったと批判している。
それからさらに四半世紀が経った現在はどうだろうか。今はネットがありSNSがある。有名無名を問わず、誰でもが自分の意見を世界中に発信できる。フェミニズムに関して言えば、今年の検察庁法「改正」を阻むきっかけとなった、フェミニズムに関心を持つ広告代理店OL「笛美」さん、職場でハイヒールを履かない自由を訴える#KuToo 運動を始めた石川優美さん、安倍晋三のお友達であるジャーナリストにレイプされた伊藤詩織さんなど、それまで一般的には知られていなかった女性たちが自分の意見を堂々と述べるような時代となった。夫婦別姓選択制度やアフターピル解禁など、女性の地位向上についての施策も進んでいるように見える。
大塚英志は、この本でフェミニズムや「女性性」だけをテーマにしているわけではない。ほかにも森恒夫・宮崎勤・オウム男性信徒の共通性や日本国憲法についての論考がある。ただ、この本で書かれた連合赤軍の時代、オウム真理教の時代(当時のリアルタイム)、そしてコロナ禍の現代は、偶然ながら四半世紀の間隔がある。それらを比較すると、ぼんやりと見えてくるものがある。それは、女性が次第に賢くなってきているのに対し、男性は一向に変われないままだということだ。
当たり前だが、フェミニズム=女性問題を考えるということは、男性のあり方を考えるということでもある。しかし、この国の多くの男性はそのことがわかっていない。逆に、「女性の地位が向上すれば男は不利益を被る」と思い込んでいる男性が多い。しかしそれは逆だと思う。「男だから〜○○するべき(しなければならない)」という規範(あるいは強迫観念)がなくなれば、精神的に楽になる男は多いはずだ。少なくとも自分はそうだ。女性の地位・権利が向上すれば、今まで男性が負うべきとされていた責任も軽減される。女性が解放されていけば、男性も解放されるのである。
日本の多くの男性が早くそのことに気づけば、この国はもっと住みよい、暮らしやすい国になると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
