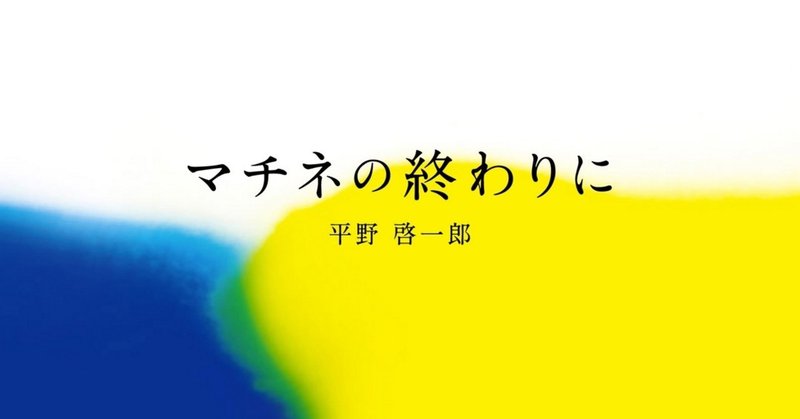
"マチネの終わりに"感想・考察 -大人の恋愛とは何か-
"試着室で思い出したら、本気の恋だと思う。"を読んでから、"大人の恋愛"というものに興味が湧いた。
齢27にして"大人の”という形容が持つ意味をイマイチ掴みかねている自分にとって、ぴったりなテーマを持つ小説を見つけた。
平野啓一郎の"マチネの終わりに"である。
天才クラシックギタリスト・蒔野聡史と、国際ジャーナリスト・小峰洋子。四十代という"人生の暗い森"を前に出会った二人の切なすぎる恋の行方を軸に、芸術と生活、父と娘、グローバリズム、生と死などのテーマが重層的に描かれる。いつまでも作品世界に使っていたいと思わずにはいられない!
-裏表紙の紹介文より-
「なんかよくわかんないけど複雑で大人の事情たっぷりな恋愛が描かれてる気がする!!!」と思い読み始めたのだが
前半は、"天才"という言葉に酔っ払って音楽やギターへの誠意が全く感じられない勘違い男と、育ちが良く容姿や能力に恵まれ選民意識ダダ漏れの勘違い女のナルシスティックな恋愛模様が描かれていた。
期待はあっさりと裏切られた。…三谷早苗が登場するまでは。
以下ネタバレあり---
"Pretender"は好きですか?
この小説全体を通したテーマの一つに"決定論vs自由意志論"がある。そしてどちらの視点からこの小説を眺めるかで印象も変わってくるように思う。
Amazonレビューを見ていても賛否両論ある作品のようだ。
ここで、ある曲を引用してからこの小説を語っていきたい。
昨年、紅白にも出場した"Official髭dandism"の"Pretender"だ。
"マチネの終わりに"を読み終えたときに、この小説に対する印象とこの曲に対する印象が完全にリンクした。
グッバイ 君の運命のヒトは僕じゃない
辛いけど否めない でも離れ難いのさ
その髪に触れただけで 痛いや いやでも 甘いな いやいや
グッバイ それじゃ僕にとって君は何?
答えは分からない 分かりたくもないのさ
たったひとつ確かなことがあるとするならば
「君は綺麗だ」 Official髭dandism - Pretenderより
サビだけ引用したが、この歌詞の全てが蒔野だ。Pretenderの歌詞を解釈することで、帰納的に"マチネの終わりに"に対する感想を表現できたらと思う。
"ローマの休日"と"週末のキャバクラ"
Pretenderは運命に翻弄されて結ばれない二人の恋を、甘く切なく、しかし"フリをする人"という曲名の通り、どこか冷静に歌い上げた曲である。
"ローマの休日"に登場する二人のような、王女と一般市民という、まるっきり立場が異なる叶わぬ恋を歌う曲であるなら、美しく聞こえる。
身分の違いというあまりに高い壁にも関わらず、湧き上がる恋愛感情。運命という巨大な壁に翻弄され、愛を確かめつつもお互いの生活に戻っていく二人は美しい。
しかし、例えば"キャバ嬢と中年男性"の恋愛を考えたときに"Pretender"をあてがうと、しょうもない曲に聞こえてしまう。
ガチ恋勘違いおっさんがキャバ嬢に恋してしまい、叶わぬ恋に嘆く。もはや恋とも呼べない幻想である。おっさんの客観能力の無さと叶わぬ恋に酔いしれるナルシシズムが痛々しい。
このように運命を悲劇的に美しく描く際、それ相応の状況設定が必要になる。
運命のいたずらに翻弄され、頑張っても頑張っても結ばれない二人は美しい。しかし、大した障壁が無いのに結ばれるための努力をするでも無く、あっさり諦めては嘆いてばかりの二人は痛々しい。
"マチネの終わりに"では、三谷早苗の登場前後で印象が逆転してしまったのだ。
心理学的に恋を解剖してみる
物語前半、蒔野と洋子が惹かれ合うのは当然だ。
蒔野は、洋子には無い類い稀な才能 -彼女が愛されていないと感じていた父親の持つ芸術的な才能- を持ち、自身の内面や芸術を探求する音楽家という、ジャーナリストとは正反対の職業に就いていた。
洋子は、蒔野には無い類い稀な血すじ -彼が尊敬する映画監督であったソリッチの血すじ- を持ち、世界の真実を探求し正しく伝えるジャーナリストという、音楽家とは正反対の職業に就いていた。
しかも出会う20年前から、お互いのことを演奏や映画を通して知っていたのだから、どっからどう見ても運命的な出会いだ。
語られ得ぬ天才の内面
前半は、あまりにも華やかに彩られた運命が、少し気持ち悪かった。
蒔野の、「本当に天才ギタリストか?」と思ってしまうような自己愛的な言動と、洋子の、思慮深さと優しさを隠れ蓑に潜む冷笑的な態度。
そんな二人がコンサートや婚約者そっちのけで恋愛に溺れていく様。それを愛と形容し、直喩的な表現を多用する著者の文章表現も鼻についた。
しかし、恋の発展と同時に、蒔野はギターの演奏でスランプに、洋子はテロに遭遇しPTSDになってしまう。
そんな二人が東京で三度目の再開をしようとする時、決定的な事件が起こる。三谷早苗の登場である。
三谷早苗の破壊と創造
ここまでの単調でズブズブな物語に彩りを与えたのが三谷早苗の行動だった。
蒔野がタクシーで携帯を失くしてしまったことをきっかけに、早苗は、蒔野を偽って洋子に別れのメールを送信する。それも、お互いのためを思って金輪際会うのをやめよう、というようなキツめの内容だ。
一見、大胆で卑劣で品性のかけらも無いような行動に見えるが、この行動が洋子の持つ冷たい優しさを暴き出す。
婚約破棄するほど愛し合っていたのにも関わらず、こんな不自然なメールを受け取ってなお、蒔野と連絡を取ろうともしない洋子の行動は、臆病な優しさか、冷徹な心変わりのように感じた。
ただ、蒔野のスランプと洋子のPTSDのこともあって、あまり強く批判することはできないのだが、少なくとも洋子には早苗のような、罪を犯して自分という人間を全て投げ出してしまうような愛し方はできなかった。
早苗の行動は、破壊的で身勝手極まりないものだったが、その反対側には蒔野に対する強い意志を感じることができる。
愛というものが独善的な感情の強さだと仮定した時、早苗の蒔野に対する想いの強さや意志の強さといったものが、洋子のそれを上回ったのだろうか。
新手のメタ小説?
事件以後、案の定洋子は結婚相手のリチャードに浮気され破局。養育権の半分を与えられ、息子の"健"を育てながら、新たな職に就く。
蒔野は早苗と結婚し、娘の"優希"を授かる。二、三年にわたる長いスランプを脱し、音楽活動を再開する。
物語の後半は、物語の前半と様相が大きく異なるように感じた。蒔野の自己愛的、洋子の冷笑的態度は鳴りを潜め、著者の文章表現も鼻につく感じがすっかりなくなってしまった。
スランプを乗り越えた蒔野と、失恋と離婚を乗り越えた洋子の変化が感じられる。文章の雰囲気すら変わってしまったのは著者の意図したことなのだろうか。それとも登場人物の心境と相互作用した結果なのだろうか…。
物語の前半を読みながら、感想を書くためにメモを取っていたんだけど、三谷早苗登場前に嫌気がさして、「途中で主人公の変化とともに筆致も変わるという新手のメタ小説かもしれない」とメモを残していた。
まさか本当にそうなると思わなかった。
名付けのカルマ
ところで、二人の子供の名前の付け方も、どこか運命的である。
母が長崎で被曝し、自身も被爆者二世である洋子の息子には、"健"と。
洋子を騙して蒔野との仲を引き裂き、罪の意識に苛まれた早苗の娘には"優希"と。
ある意味芸が細かいというか、こういった場面でも"業"といったものを感じさせる。
洋子のカタルシス
この小説で一番感動したのは、洋子の父"ソリッチ"が、反政府に捉えられる映画を創った事で目をつけられ、妻と娘のためを思い距離を置いていたという事実が、洋子に伝えられるシーンだ。
多分、洋子の優しくもどこか臆病で選民意識のある性格は、父親に愛されなかったという思い込みから来ていたのではないだろうか。
父親に愛されなかったという欠落感ゆえ、その穴を埋めるように蒔野に激しく恋してしまったのではないだろうか。
このシーンで洋子は救われ、新しい仕事、新しい恋愛が始まり、蒔野ともきれいな関係を保つことができた。よかった。
蒔野の成長、才能の居場所
蒔野も、共演した武知の死を乗り越え、自身の才能の使い道を悟り、自己愛的な態度から外に意識が向かうようになったのではないだろうか。これも一種の贖罪なのかもしれない。
蒔野が自身の才能を大衆向けに注いだ作品である《この素晴らしき世界〜 Beautiful American Songs》の中の一曲が、アメリカ軍によって心理的な障害を負ったジャリーラに感動を与え、クレジットに載っているというのも皮肉だが美しい話だ。
何より、蒔野がコンサートのアンコールで、洋子の父であるソリッチ監督の映画のテーマ曲である"幸福の硬貨"を演奏するシーンには感動して涙した。
"運命論"vs"自由意志論"
この物語がノンフィクションであれば、"ローマの休日"のような運命に翻弄される二人の儚くも美しい恋物語である。
しかし、この物語はフィクションだ。三谷早苗のメールの後、連絡を取り合わなかった蒔野と洋子を不自然に感じてしまうし、そもそも洋子程の女性があのメールの違和感にすぐに気付かなかったのも変な気がしてしまう。
このシーンで"Pretender"が流れたら文句を言いたくなる。
二人の運命的な出会いも、蒔野のスランプも、洋子が患ったPTSDも、突然の祖父江の脳卒中も、タクシーでの携帯の紛失も、全て仕組まれたものだった。
この辺りの演出を違和感なくこなし、黒子として終始存在を感じさせないのが著者の役割なんだと思う。
だがもう一歩踏み込んで"運命論的な立場"から、この小説自体が著者の意図を超えた神秘的な何かだとする。
作者の意図は消え去り、登場人物は勝手に動き出し、偶然という必然の、数々の事件がこの物語を動かしていたとする。
上手く言葉にできないが、フィクションだがそうならざるを得ないストーリーだった場合、決定論的な立場でこの物語を読んだ場合、やはり美しい。
まるでペルシャ絨毯のように
裏表紙の解説にある通り、この物語は本当に多くのテーマが重層的に重なり合っている。一筋縄ではいかない。
しかも、"気遣いと冷淡さ"、"身勝手と愛情"、"贖罪と献身"のような"ルビンの壺"のように対立する概念が同時に存在している。
「"大人の恋愛"ってなんだ?」という想いから手に取った本だったが、一言でいうと"受け容れること"だと、感じた。
前半のもやもやした読書体験は昇華され、四千字の読書感想文を書くに至ってしまった。見事に、未来は過去を変えてしまった。
最後に、蒔野のモデルになった福田進一さんのギターの演奏が素晴らしいので貼っておきます。
ぜひ聴いてみて本も読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
