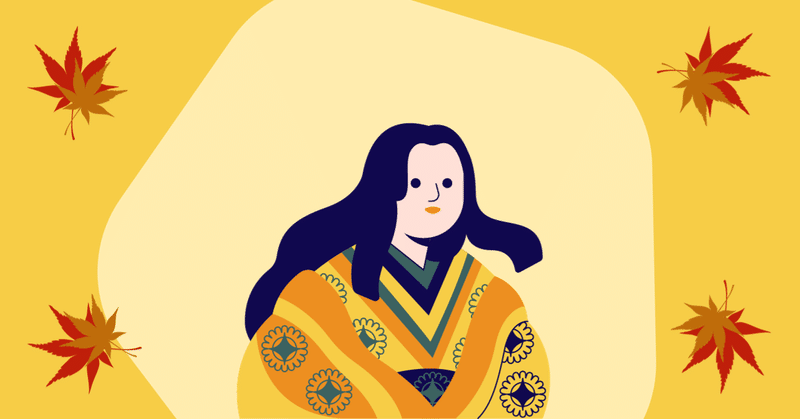
丸谷才一『輝く日の宮』
『輝く日の宮』(2003)を久しぶりに再読した。
いたく感動したというのでも、心を揺さぶられたというのでもないが、ひじょうに上質な物語を存分に味わったという心地よい充足感があった。
最初読んだときに面白いと思い、そのうちいつものように内容をあらかた忘れてしまい、いずれまた読みたいと思っていた。
大河ドラマの影響もあって、今年は『源氏物語』ブームになりそうな予感があり、そんなこともすこし再読のきっかけとなった。
読み終えてみて、あらためて、学識の深さと類まれなストーリーテラーとしての資質とをあわせもった丸谷才一の驚嘆すべき才能に脱帽するしかなかった。
*
主人公の杉安佐子は気鋭の国文学者だ。
『源氏物語』の成立の過程で失われたとする説がある「輝く日の宮」という巻の存否をめぐる論争に巻き込まれ、存在を強く支持する安佐子は、成り行きで、その失われた巻を復元することになる。
そのような大筋に、水事業会社に勤める長良と安佐子の恋愛がサイド・ストーリーとしてからむ。
物語自体としてもめっぽう面白いし、ひねりの利いた構成も巧みである。
さらに、ひとつひとつのエピソードのディテールが秀逸で、知的な刺激に満ちている。
見事というしかない。
例えば、安佐子と兄夫婦が父の誕生日を祝う家族団らんの場での会話のエピソード。
話の流れで、国史学者の父は古今和歌集の中の伊勢が詠んだ歌を話題に持ち出す。
難波なる長柄の橋もつくるなり今はわが身を何にたとへん
この歌の「つくる」は「作る」(=再建する)と「盡くる」(=朽ち果てる)の二つの解釈があるが、父がかつて師事した学者は後者が正しいと主張し、それを史実に基づき立証した、という話をする。
それに対して、安佐子は国文学者の立場からきっぱりと明快に反論し、父をあっと言わせる。
このあたりの描写は、実にエキサイティングで爽快ですらある。
あるいは元禄文学学会の研究発表において、安佐子が「芭蕉はなぜ東北へ行ったのか」というテーマで発表を行い、『奥の細道』は芭蕉がひそかに義経五百年忌を弔う旅であった、という注目すべき見解を論じる場面。
残念ながら浅学な一読者に過ぎない身としては、安佐子に託した作者(丸谷)の緻密な議論を十分理解し、その妥当性を判断するところまでは到底及ばなかったのだが、それでも近世文学という未知の領域に眼を開かせられる思いがして、知的興奮を大いに掻き立てられた。
*
安佐子のプライベートの描写においても、例えば、長良との会話は、味わい深く示唆に富む。
一か所印象に残る部分を引用したい。
「アラル湖は綿花畑の灌漑用水に使はれてゐたんだけど、昔の面積の半分になつてしまつた」と長良は嘆いた。「黄河は河口の手前で流れなくなくなつたし、リオ・グランデ川はメキシコ湾に届かないうちに涸れて。世界中、ひどいことになつてる。もうすぐ人間は亡ぶね。水がないんだもの」
「さう思ひながら水のため働いてるわけ?」
「昔からさうなんぢやないか、人間て。世界はもうぢき亡ぶと思ひながらやつてきた。健気なものです」
「あ、この世の終り……科学と宗教が違ふだけつてこと?」
「うん、さう思つて働いてゐる人、大勢ゐると思ふ。今度は多分本当なんだけどね。二十二世紀までぜつたいもたないと覚悟しながら、インドで雨水の利用方法教へたり、南アメリカで熱帯雨林に植林したり……」
「末法思想を信じて、もうすぐ世界は破滅すると思ひながら『源氏物語』書くみたいなものかしら」
この小説が書かれた二十年ほど前と比べ、事態は間違いなく一層切迫の度合いを増している。
果たして二十年後、人類はたしかな希望を見いだしているだろうか? それともあいかわらず「なるようにしかならない」と諦めているのだろうか?
*
安佐子の仕事と恋の二重構造で展開する物語は、やがて主人公に仕事をとるか恋をとるかの二者択一を迫ることになる。
安佐子が下した決断については、それでよかったのか、もっとちがう選択肢があり得たのではないか等、読者によってさまざまな意見があるように思う。
わたし自身の感想を言えば、ある種の人々にとっては、文学と向き合うということは人生そのものであり、例えば、そういった人間がある古典文学作品の謎を解き明かすという課題に取り組むということは、一生涯を賭けても決して悔いのない、それだけの価値がある、他に比肩しうるもののない経験なのではないだろうか。
*
小説は、最終章で、安佐子が復元した「輝く日の宮」の巻の一部(おそらく最後の部分)と思われる文章が何の説明もなくそのまま掲載され、そして唐突に終わる。
復元された文章は、より正確に言えば「輝く日の宮」の現代語訳の一部ということになるが、深い余韻を残す、心にくい出来ばえであったと思う。
ところで、『源氏物語』に「輝く日の宮」という巻が存在したことを安佐子が信じる重要な根拠のひとつが光源氏と藤壺の中宮との関係にかかわる事情であった。
光源氏は、父である桐壺帝の妃であり継母である藤壺を慕い焦がれてついに思いを遂げるのだが、その具体的な描写としては、二度目の逢引きの様子が「若紫」の巻にごくあっさりと描かれているのみである。
藤壺との最初の逢瀬がどこにも書かれていないのは不自然と考えた安佐子は、実は失われた「輝く日の宮」の巻にこそ、その場面がより実質的なディテールとともに描写されていたのではないかと推測するのだ。
「輝く日の宮」の巻では、藤壺だけでなく六条御息所と光源氏の交渉も描かれていたはず、と安佐子は考えるのだが、最終章の復元部分に登場するのは藤壺との場面である。
それはともかく、いずれにしても、安佐子は「輝く日の宮」の復元作業において、必然的に光源氏と高位の女性との情事の場面を書かなければならない。
親しい女友達との電話での会話で、ラブ・メイキングの場面はどんな風に書くのかと聞かれて、安佐子は答える。
「そんな『源氏』だもの。『ファニー・ヒル』と違ふ。露骨なこと、口にしない」
「でも、それぢや読者わからないでしよ」
「だから一行アキにしたの。一行アキになつてると、ははあ、この空白は意味ありげだな、と思ふでしよ。思はない人もゐるかもしれないけど」
「あ、一行アキ」
「歌の前後の一行アキは別よ。そうぢやない一行アキが暗号」
読み終わったその日に、日課の散歩の途中で、すっかり忘れていたこの会話をふいに思い出して、小さくあっと叫んだ。
「一行アキが暗号」
最終章の復元部分では、この暗号が思いもよらぬ使われ方をしていたのだ。
どんなふうに使われていたか?
それはぜひ読んでたしかめていただきたい。
※タイトル画像は、あさのしずくさんから拝借しました。ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
