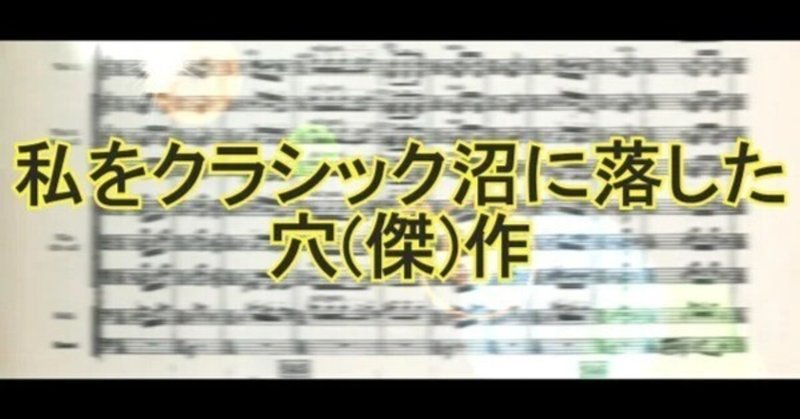
連載:私を「クラシック沼」に落した穴(傑)作~その5
前回は、《春の祭典》で人生最大の衝撃を受け、さらに素晴らしい音楽との出会いをかけて、バイトを始めたところで終わったこの連載。
今回は、その集大成とでもいうべき音楽との出会いが訪れますが、それも、一つの勘違いから始まりました。
交響曲第10番の呪縛にやられる
さて、冬休みも終わり、新学期が始まると、部活も定期演奏会に向けて本格的に動き出すため、バイトはそこで終了。
まず、給料を握りしめて向かうところは、CDショップ・・・の前に、家電量販店。その時点では、まだCDプレーヤーが無かったのだ。
当初、かなり高価だったCDプレーヤーも、1988年にもなると、安価で性能の良いモデルも出揃っていた。幸い、ラジオはセパレート型チューナーで聴いていたので、アンプもスピーカーもあったから、ポータブル型やCDラジカセではなく、セパレート型で良かったため、それなりの性能のプレーヤーを購入することが出来た。
そして、さらに幸いなことに、定価の10%引きで国内盤CDを買える安売り店(今でいえばドン・キホーテのような倉庫型店舗)が通学経路上にあった。
だが、そのショップに最初に行った時、具体的にどのCDを買うかは決めていなかった。
「とりあえず、《春の祭典》は買うとして、あと一枚くらい買いたいな」
そう思って見回っていると、ある一枚のCDが浮き上がって来た。
今でもハッキリ覚えているが、比喩でなく、何枚も陳列されている中で、本当に一枚だけ光り輝くように浮き上がって見えたのだ。
それが、これ。

カラヤン指揮ベルリン・フィルのショスタコーヴィチ交響曲第10番だった。
なぜか。
そう、「交響曲第10番」というのが、とても魅力的に見えたのだ。
そういうのも、当時、ベートーヴェン以降の作曲家で、10番目の交響曲を完成させている大作曲家を知らなかったからだ。それに、この頃、ベートーヴェンの交響曲第10番が話題になっていたことも影響していたかもしれない。
まあ、今にして思えば交響曲を10曲以上書いている作曲家は何人もいるし、数だけあればいいってもんでもない。
だが、演奏しているのは、三流指揮者でもどこにあるか分からない国のなんちゃってオーケストラではない。
カラヤンとベルリン・フィルが録音するくらいなのだから、作品自体もそれなりにしっかりした作品のはずである。ショスタコーヴィチなんて知らないけど・・・知らない・・・?
「ショスタコーヴィチ!?」
ここで、ハタと思い当たった。
「ショスタコーヴィチって、86年にヤンソンスがレニングラード・フィルの来日コンサートでチャイコフスキーの4番とやってたやつじゃん!?」と。
この時は、《春の祭典》と、同じストラヴィンスキーの交響曲集(《三楽章の交響曲》と《ハ長の交響曲》)を買って、ショスタコーヴィチについてはヤンソンス/レニングラード・フィルの演奏を確かめてから買うことにした。ストラヴィンスキーを買うにも、それなりに時間がかかったから。


ハ長の交響曲、三楽章の交響曲
マゼール指揮クリーヴランド管の《春の祭典》は、CD一枚にこれ一曲(33分)しか収録されていないという、恐ろしい仕様のもの。当時は、こういうのも当たり前にあったのだ。CDの収録限界ギリギリ、80分以上収録されるようになるのは、90年代後半になってからだ。もちろん、この録音の再発売盤は、チャイコフスキーの交響曲第4番やショスタコーヴィチの交響曲第5番とのカップリングで出ていた。
コリン・デイヴィス指揮バイエルン放送響の交響曲集は、現在まで単独では出ていないレア録音だが、当時はそんなこと知るよしもない。三大バレエ以外のストラヴィンスキーも聴いてみたいと思って探したが、これしかなかったから買ったもの。クラシック音楽専門のショップではなかったから、品揃えはよくなかったのに、なんでこんなの置いてあったんだろう(ポリグラム系を独占販売か、返品不可の買い取り販売する代わりに――販売価格をメーカーが設定する再販制度では、返品が可能という理屈を逆に考えた?――割り引き販売させてもらってたのか?)。
家に帰ると、ヤンソンス/レニングラード・フィルの録画は、先に入っているチャイコフスキーばかり見て、後の方のショスタコーヴィチの演奏は、ほとんど見ていなかったことに気づく。
当時の私は、もう、チャイコフスキーを聴いただけで満足していたからだ。続けて、交響曲をもう一曲聴こうなどという余力は到底無かった。
これでもう十分。HPは満タンだ、と。
しかし、「途中までしか見てなかったのか」と思いながらショスタコーヴィチを聴くと、最初の数小節を聴いただけで、今まで聴いていなかったことを心の底から後悔した。
「ハマる」ためのもうひとつの要素?!
「な、ん、だ、こ、れ、はっ!」←2回目
《春の祭典》とはまた別の意味で度肝を抜かれた。
全ての音符が、あるべき姿でそこにあり、無駄が一切ない。まるで、ベートーヴェンの交響曲第5番じゃないか。
当然、次の日は交響曲第10番のCDを買うためにショップに向かう。
他のCDを少し見ていると、交響曲第2番と第3番のCDもあったので、それも購入。

交響曲第10番、そして同第2番と第3番は、買って正解だった。
特に第10番は、これまでに聴いたことのないタイプの音楽だったが、無理やり当てはめればブラームス風の叙情に溢れた第1楽章、ワーグナー風トッカータの第2楽章、そしてシューマン風の第3楽章とシューベルト風の第4楽章と、カラヤンがショスタコーヴィチの交響曲の中で唯一取り上げたのが分かるような重厚さとユーモアに溢れた交響曲で、たちまち虜となった。
交響曲第2番と第3番は、『十月革命』、『メーデー』という副題からも分かる通り、一種の機会音楽で、一風変わっているけれど、チャイコフスキーの《1812年》の延長と考えれば、こういうのもアリなのかと思った。
そこで、ショスタコーヴィチは交響曲が15曲あるみたいだから、取り敢えず全部聴いてからだな、と感じ、当面の目標はショスタコーヴィチの交響曲を全て聴くことになった。
当時、ショスタコーヴィチの交響曲を全部聴くとすると、コンドラシンとハイティンクの交響曲全集があった。
しかし、コンドラシンのはCDにはなく、LPレコードも既に廃盤。ハイティンクの全集は、CDのセットが出たばかりだったが、¥36,000超え。とても手が出る代物ではない。

帯に「CD初」と書かれているのは、コンドラシンの全集を意識してのもの。
いろいろ調べてみると、どうやら東京・神保町に、ソ連音楽の専門店があると判明。もちろん輸入盤になるが、当時交響曲の全曲録音が進行中であった、ロジェストヴェンスキー指揮ソヴィエト国立文化省交響楽団のCDがいち早く、しかも格安(¥2,000くらい)で買えるらしい・・・。
こりゃ、当然、買いに行くしかないじゃないですか。
もしかすると、《禿山の一夜》原典版のCDもあるかも・・・。
ここまでくると、ほとんどトレジャー・ハンターの気分だ。
当時は、今のように、Wikipediaで調べれば、内容の正否はともかく、すぐになんらかの情報が得られて、さらに調べる目処がつく時代ではない。
例えば、《春の祭典》だって、デュトワ/N響の演奏と、マゼール/クリーヴランド管の演奏とで、細部に違いがあって、しかも、双方ともYAMAHAで買ったスコアとも微妙に違うのに、いくら調べても、その理由は分からないままだった・・・。
「『版の違い』というのが関係しているらしい」、となんとなく分かり始めるのは、数年後のことだ。
ショスタコーヴィチの作品だって、作品番号が147まであるのに、具体的な作品名は半分くらいしか分からなかった。
もしかすると、こういう「謎解き」みたいな要素も、なにかにハマるきっかけになるのではないだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
