
『ぼっち・ざ・ろっく!』細かすぎる全話演出解説を通して学ぶアニメ演出①
2022年10月から放送が始まった『ぼっち・ざ・ろっく!』。
今更『けいおん!』の二番煎じ?と思ったが、見始めてみると、意外にも、これが驚くほど作り込まれた尖った演出の数々で、黙ってはいられなかった。
2022年12月28日より、DVD&ブルーレイが発売開始されるので、twitterでの私のツイートの解説と、新たに解説を書き起こしながら、細かく解説しながら第1話からの演出をおさらいして行こうと思う。といっても、放っておくと全カットの解説(1話300cut程度)になってしまうので、重要な箇所だけね。
第1話「転がるぼっち」
『#ぼっち・ざ・ろっく』第1話。話が前後して非常に申し訳ないのだが、シリーズのファースト・ショットがこれ。原作未見なのでどの程度原作準拠か知らんが、4つの蛍光灯は、一人ひとりが輝いているバンドのメンバーを現し、突き上げられた左手人差し指は、4人で一つの結束を象徴しているかのようだ。 pic.twitter.com/SnswAHNEPO
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022
アニメーションに限らず、ドラマでも映画でも、1stカットは重要なもの。
本作のキャッチコピーは「4人でも、ひとり。」。
この言葉は、文字通り「4人で1人」という結束を表すものなのか、「4人いても独り(一人)」という孤独感、または独立心を表すものなのかは分からないが、ある程度その全ての意味合いを含有しているダブルミーニング、トリプルミーニングだと思う。それら、相反する気持ちが一緒くたに同居しているのが人間というものだろう。


そして、その突き上げられた指のショットが、次のひとりのバストショットに繋がり、さらに人物をフレームに見立てた縦の構図にすることで「覗き見る」感覚を視聴者に喚起させ、彼女が「1人」であることが強調される。トランジッションのないぶっきらぼうなストレート・カッティングにより、一つひとつのカットの独立性が強調されることでも、ひとりの「孤独さ」が印象付けられる。
『#ぼっち・ざ・ろっく』第1話。ビジュアル・イメージ・マッチングによる時間経過。幼女ぼっちが落とした毬が転がっていき、ディゾルブして遠足のお弁当の梅干しに。その際レジャーシート近くに揃えて置かれた靴が、中学時代の家の玄関の靴に同じくディゾルブして繋がれる。流れるような時間経過演出。 pic.twitter.com/xugRUf8KV9
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022
そして、前カットとはうって替わり、ディゾルブ(オーバーラップ)による時間経過により、ひとりの幼稚園から中学一年生までが一気に描かれていく。
その時間経過の同一性を担保するため、カット間は、「毬」「靴」のビジュアル・イメージ・マッチングで繋がれる。

ひとりの独白ナレーションが続く中、「それが私、後藤ひとり」と一段落ついたところで、中学一年生になったひとりが、垂直俯瞰によるクロース・アップで。
クロース・アップにしては、頭部のクロップ(切り取り)が大きめで、緊張感や押さえつけられた気持ちが表される。さらに、カメラ目線であることで、視聴者へ、見つめられることによるストレスを与えている。

次に、カメラはエクストリーム・カット・トラック・バックして、一気に引く。
前カットの緊張感からは開放されるが、「見下ろす」ことと、フル・ショットのフレーミングで構図に余白を多く取り込むことで、ひとりの孤独感が、ここで再度強調されていく。


そして、シークエンス終わりの句読点として、時計のカット・ウェイで時間経過が示されると、新たな展開として、もう一人の人物が現れ、テレビのチャンネルを変える。
ちなみに「時計」は、カット・アウェイとしてとても優秀で、ある実験結果によると、様々な小道具の中で、時計が最もカットの流れを損なわず、「フィルムが繋がっている」という感覚を視聴者に残すアイテムであるということが分かっている。
ここで、ひとりの独白ナレーションの後ろで、オーディオ・ブリッジとしてひたすら均一に流れ、カットの流れの統一性を担保していたテレビの音声も突如として変わり、「変化の兆し」を仄めかす。
カットやシーンの流れは、様々な手法で一貫した流れの統一性や分断を表すことが出来る。一般的に、BGMに代表されるそのシーン内で物理的に聞こえている音ではないノン・ダイジェスティック・サウンドが使われる場合が多いが、シチュエーションによっては、このシーンのように、シーン内で物理的に聞こえている音、ダイジェスティック・サウンドを使う方が効果的な場合もある。



父親がチャンネルを変えた音楽番組(ここで、父親が音楽好きだと仄めかされる)に出演していたバンド・メンバーのインタビューを見ていたひとりは、「友達いなかった」「バンドは陰キャでも輝ける」という発言を聞き、「自分と同じだ」と思って興味を示す。番組司会のお姉さんの「そうなんですねー」という愛想のいい呑気なリアクションと、真剣な目でテレビ画面を見つめるひとりとのギャップにより、ひとりのその気持ちが強調される。
モンタージュ技法の同一性と対立の弁証法の応用だ。
カメラは、ひとりをワイドショット→クロース・アップ→エクストリーム・クロースアッップと、カット・ズーム・アウトで段階的に近づいていき、ひとりのこのバンドへの興味を強調していく。

すると、ひとりは唐突にすっくと立ち上がり、父親に「お父さん、ギター貸して」と言う。
それまでギターや音楽に興味のなかったひとりが、音楽に突然興味を持ったことはこの後のシーンで父親の発言によって分かる。その切っ掛けがこのバンドであったことは、今までのモンタージュでも分かるが、ここでバンドが演奏している楽曲タイトルが「引き金」であることでも、それが担保されている。
通常、キャラクターの行動動機やモチベーションを、ここまで手厚くエクスキューズする必要はない。
しかし、ここが本作と『けいおん!』との大きな違いだが、ひとりが音楽をする、バンド活動をする動機やモチベーションは、こんごのエピソードの中で極めて重要なモチーフとなっている。
だから、視聴者が、ひとりがバンド活動を行う動機やモチベーションに疑問を持った時点で、作品としては致命的なのだ。
そこで、ここまで執拗にひとりが音楽を始めた時の動機とモチベーションを丁寧に描き出している、という訳だ。
ところが、ひとりにとってギターを弾くことは、いつしか現実逃避の手段となっていた。

公園で1人佇む後藤ひとり。
レイアウトでは、「明」と「暗」が強調され、ひとりは決してその境界線から外に出ることはない。

「私の居場所はネットだけ」「学校、行きたくないな」と落ち込むひとり。この落ち込んだ横顔は「サイド・オン」と呼ばれるもので、希望を失った大きな失望感を表すことが出来る。さらに、望遠レンズの効果で背後をぼやけさせ、ひとりの孤立感を強調している。
すると、そこに、「あ”っ!ギターーーーーーー!!」と素っ頓狂な叫び声がOFFで響く。

その叫び声にひとりが気づいて顔をあげると、カメラは一気に後退して、地面スレスレのロー・ポジション(ロー・アングルではない)となり、縦の構図でその叫び声を上げたと思われるキャラクターの足元だけを写し込む。
画面両側に見切れた足元がフレームの役割を果たし、ブランコの「檻」の中に後藤ひとりの姿が、その遥か後方に弱々しく映る。


そしてその人物は、「檻」を軽々とまたぎ、境界線を越えて「明」の世界からひとりの「暗」の世界へと入っていく。
自己紹介する虹夏を、ひとりのPOVではなく、ひとりナメのデプス・ステージングで描写し、二人の間にわだかまりや溝のあることを示唆。

特に、このブランコの緑色の支柱を分割線とし、ひとりと虹夏を左右に振り分けた構図。狭角側にひとり、鈍角側に虹夏を配置することで、二人の心情のネガティヴさ、ポジティヴさを暗示しており、まるで虹夏の「圧」にひとりが一方的に圧倒されているようだ。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』第1話。魚眼レンズの歪みと強調された奥行き感を利用した、ぼっちの画面奥から手前への大胆な寄り。演劇では奥が過去、前が現在を表すと言われる。画面の奥行きを強調することにより、ぼっちの決意と変化(成長?)が、長い道のりであったことを感じさせる。 pic.twitter.com/43UK6OcVKa
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022
第1話で、演出がもっとも尖っていた部分。
演出内容は、上記ツイートの通り。
魚眼パースといえば・・・


『パトレイバー2』の後藤隊長と相場は決まっているわけですが、比較的長尺シーンを保たすには、やはりこれくらいインパクトのある構図でないと「間」が保たない。
アニメでは、1カットに収まらない画角を、魚眼レンズで押さえるということはほとんど全くありません。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』第1話。実際(?)は――といっても、このショットも広角レンズで奥行き強調されているが――これくらいしか距離ないのよね。 pic.twitter.com/GD0EmNlCOx
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022
第2話「また明日」

第2話アバン開始早々、何の説明もなく水風呂に浸かるひとり。
すると、OP開けで、

「数日前」のテロップ。
これは「錯時法(さくじほう)」といい、「ストーリーとは、過去から現在へ、時系列順に語られるもの」という視聴者の先入観を逆手に取り、「物語世界で起こった出来事の順番と、物語内で語られる順番を入れ換え」て、入れ換えられた時間を印象的に描く手法。
大きくは先説法と後説方とに分けられ、前者は「フラッシュ・フォワード」と呼ぶのが一般的。
後説法は、時に「フラッシュ・バック」と呼ぶこともあるが、「伏線」や「叙述トリック」「フラグ配置」も含み、物語の最後の方で「ああ、これがそうだったのか」と気付く場合が殆ど。『ぼっち・ざ・ろっく!』第2話でも、後説法があるが、種明かしは後ほど。
これから起こる出来事を先に記述する「フラッシュ・フォワード」は、「錯時法」という名称の通り、語られる出来事の時間軸自体が前後する(例えば、卵が割れた事実を先に描写し、なぜ割れたのかをその後で示す)ので、ビジュアル的にも分かり易い。
それと、ストーリーが進みに従って、「フラッシュ・フォワード」で描かれたシーンに時間軸が追いつけば、そのカットを「再利用」することが出来るので、制作時間や予算の節約にもつながるおいしい効率の良いテクニック。

ライブ・ハウスに入ろうかどうか迷うひとり。
ここでもやはり、ひとりは明/暗の境界線の「内側」にいる。
パース(遠近感)が平板化され圧迫感のある背景の階段の横線が、入ろうか止めようか迷うひとりの「停滞感・平行線・どうどうめぐり」の象徴にもなっている。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』第2話。Aパート殆ど会話シーンの難しい場面演出。図例1のマスターショットと図例2のリヴィールアングルを軸に、肩ナメショット(図例3)を挟みつつ視線の動きに準じた各キャラのPOV(図例4)に繋げる、イマジナリーラインを意識した、会話シーンのお手本のようなカット割り。 pic.twitter.com/ZiDGWjebH0
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 22, 2022
会話(ダイアローグ)シーンは、アニメに限らず、実写でも難しいところ。ダイアローグ・シーン撮影に特化した教科書もいくつか出ているくらい。
ただし、実写は、撮影現場に物理的なカメラが存在し、カメラ・アングルを替える度にカメラの移動、露出やピント、照明の調整などを厳密に行わなければならないが、アニメーションは比較的自由な演出プランの下に、画面構成を練れるので、演出の腕の見せ所だ。
基本的には、マスターショット(人物同士の配置が分かるような全体ショット)とそのリバース・ショット(180°逆のアングル)を軸に、ピンショット、ツーショットを逐次切り替えていく。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』第2話(図例左)と第3話(図例右)のオブジェクトPOV。図例左はギター、図例右はサイコロトークで振ったサイコロからの見た目。POVは人物だけでなく、オブジェクト(物体)の見た目でも使えるのだが、2話連続で使われるとは、積極的に演出しようという意識の強さが伺える。 pic.twitter.com/0K8N625Prf
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 22, 2022
POVは「ポイント・オブ・ビューPoin of view」で、キャラクターが見ている視線そのものを描いたショット。
対して「オブジェクトPOV」はキャラクターではなく、オブジェクト、つまり人物以外の物体や物質の仮想的な視線からの見た目を描くもの。
映像作品を見ている際、キャラクターを見ているのは視聴者そのものであり、通常、「キャラクターから見られている」と意識することはないが、POVオブジェクトで、その物体や物質を見ているキャラクターを描写することで、キャラクターそのものの視線を視聴者に意識させることが出来る。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』第2話。「んん?なんかレイアウトおかしいな」と思ったら、ライヴハウス内でライヴの話が出る際は、どうもステージを写す仕様になっている模様。コンテの安定感半端ないな。 pic.twitter.com/FntTAl7mac
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022
捨てカット(カット・アウェイ)にも意味付けを持たせているショット。
視聴者の視線をリフレッシュするだけでなく、こういうちょっとした「お遊び」を入れると、ストーリーの流れに安定感が出る。
また、これはあまり知られていないが、通常、「(撮影)カメラはイマジナリー・ライン(仮想・想定視線)を越えてはいけない」と言われるが、カメラがイマジナリー・ラインを越える前後のショット(カット)にカット・アウェイを挟めば、イマジナリー・ラインを越えることも可能だ。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』第2話。「『Purizm(プリズム)』Vol.12 [巻頭特集]ぼっち・ざ・ろっく!」 スタッフインタビューで梅原Pオススメの演出回。演出については後々youtubeで動画作ろうと思うが、虹夏が屈んだ際、胸のリボンが垂れ下がる描写の細かさとかも、この作品の見所になりそう。 pic.twitter.com/AJEfiW0LE4
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 22, 2022
恐らく、このカットは、絵コンテでそこまで細かくは指定されておらず、原画段階で付け加えられたアイデアだろう。

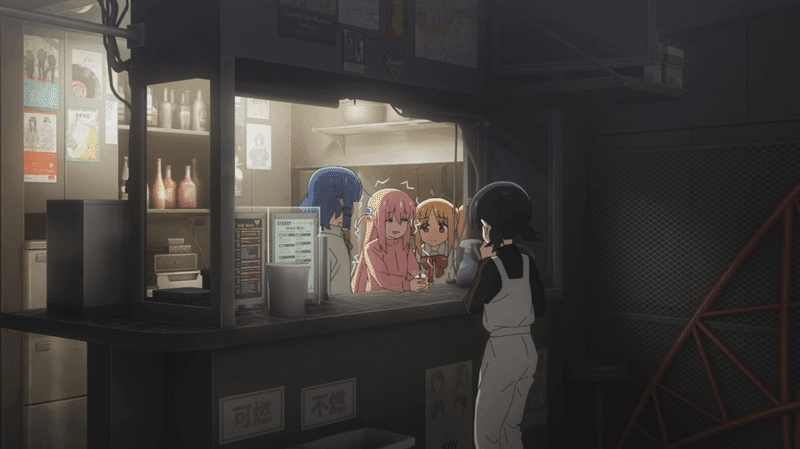

会話の流れを途切れさせないため、複数人の会話を1ショットで撮影する際、人物を一列に並べることを「アロング・ザ・ラインAlong the line」または「ライン・オブ・スリーLine of three(もちろん人数によって数字は変わる)」というが、後藤ひとりを右端から中央へ、立ち位置を変えることにより、彼女の「成長」と、結束バンドの「真の仲間に入った」ことを暗示している。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』。本作の場面演出として印象的なのは、やはり階段。階段は下上の階を繋ぐ橋渡しとしての役割があり、「進歩の途中」としての意味合いを持つが、現実と虚構の世界の境界でもある。ぼっちはライブハウスを出る度に、虚構→現実の世界への階段を登らなければならない。 pic.twitter.com/XNIde8hASD
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022

(上)「階段」の象徴的意味合いは様々あり、上記ツイートの他にも、「アイデンティティー(自己同一性)」や「権威」(王様は階段の最上階にいる)の意味合いも。
(下)バイトの初日終了後、階段を登って行く途中で虹夏に呼び「止め」られ、振り向くひとり。ここは、虚構の世界(明)と現実の世界(暗)の境界の狭間。未だ、ひとりのアイデンティティーは、その狭間で「停止」しているという暗示か。
『 #ぼっち・ざ・ろっく』。第2話で好きなのはこのカット。いつも元気な虹夏がテーブルに突っ伏してる。飲み干したドリンク(エネルギー切れという表現?)の透明な入れ物ナメて、歪んだ彼女の描写は、この疲れた感じが彼女の本質ではないと言っているかのようだ。そして、顔は左向き・・・。 pic.twitter.com/jD2fczTS5c
— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 23, 2022
文字数の関係で、ツイートではこのカットを掘り下げられなかったけど、ショットのポイントは「融けた」氷。


「氷」は、後藤ひとりの硬直した心情や、ひとりと結束バンドとの距離感の象徴だったが、ここで「3つ」の氷が融けているということは、ある程度ひとり、虹夏、リョウの三人が「打ち解けた」という暗示なのだろう。


そして、ひとりにSNSで連絡を取る虹夏だが、ひとりは水風呂に入ったのが祟って、今更の発熱(風邪は感染してから2、3日後に来るんだよ)でメッセージを読めない後藤ひとり。
虹夏の話がひとりに通じない、虹夏がそれに気づかないという「コードの断絶」はこれで三度目だ。
また、このシーンは、前半部で虹夏のSNSメッセージを受け取れたひとりのシーンと対応するアーチ構造(最初と最後が同じ)を構成し、「お話」としての統一感を担保。
その後、「後は・・・新しいヴォーカルを見つけるだけだ!」と発言する虹夏のOFF台詞をオーディオ・ブリッジ+映像ディゾルブで、繋がりを重視したカッティングをすると、



第1話で、ギターを背負って廊下を歩くひとりを見て「ギター?」と呟いたキャラクターが「はいはい! わたしわたしー!」と左手を上げる(ひとりはいつもジャージだから分かりにくいけど、同じ高校です)。
右手は与える手(発散)、左手は掴む手(吸収)と言われ、

このキャラクターが「ヴォーカル担当」を掴むという仄めかしか。
はい、これが「伏線回収」の後説法の答えです。
今回はここまで。
今月発売のDVD&ブルーレイも第2話までの収録ですから、まあ「おさらい」としては十分かと。
次回は、第3話から参ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
