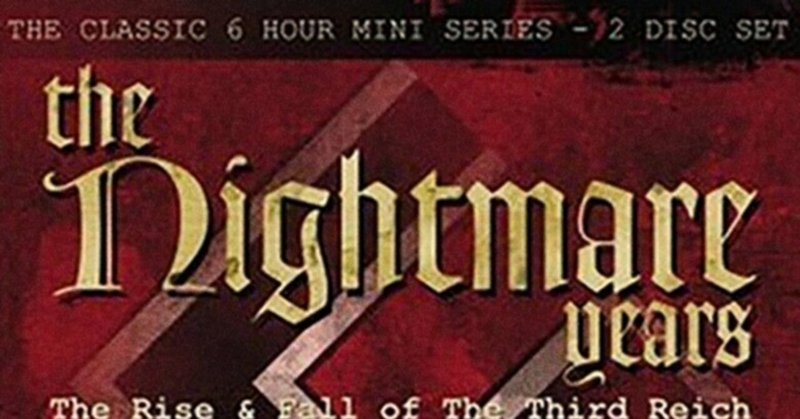
映画ではなく、ドラマだからこそ伝えられる何か
■海外ドラマ冬の時代に
湾岸戦争が終結し、日本のバブル経済とソヴィエト連邦が崩壊した激動の1991年から1年経った1992年の年末。
先の見えない社会情勢を憂い、その年の一年間の総括と来年はどういう年になるか予測合戦を繰り広げるテレビ番組に辟易していると、NHKで海外ドラマ(厳密にはテレフィーチャ)を放送することを知った。
当時は、海外ドラマの放送数が激減した1980年代後半の余波がまだあった。『600万ドルの男』『がんばれ!ベアーズ』『ナイトライダー』『白バイ野郎ジョン&パンチ』『ブルーサンダー』『特攻野郎Aチーム』『ヒルストリート・ブルース』など、海外ドラマを見て育ってきた私にとって、テレビを見るモチベーションがほとんど下がっていた時期だった。
『X-ファイル』『ビバリーヒルズ高校/青春白書』『ER 緊急救命室』『24』などで海外ドラマブームが起こるのは、まだ数年先であった。
そのような状況の中で、唯一、『ツインピークス』が話題となっていたが、私にはその良さが分からなかった。
『刑事コロンボ』の新シリーズが日本で放送され始めるのも1993年5月からで、その放送は渡りに船だった。
■これがドラマ!? クオリティの高さに衝撃
今は映画よりドラマが上?
近年では、プロデューサーも含め、様々な規制で作りにくくなった劇映画から、多くのスタッフがドラマ製作に流れて、質的な意味で劇映画とドラマの逆転現象が起こっている。
それまでテレビ・ドラマは、劇映画の下位ジャンルにあまえており、劇映画で成功した俳優がテレビ・ドラマに出演すると、「都落ちした」として揶揄されていた。
逆に考えると、1980年代までのテレビ・ドラマは、かつてのムーヴィー・スターを出演させ、その人気で視聴者を獲得する手法を取っていたとも言える。
しかし、特にハリウッドのヒットメーカー、ジェリー・ブラッカイマーがドラマの分野に進出した2000年あたりから潮目が変わり、その逆転現象が指摘されるようになる。出演する俳優も、「かつてのムーヴィー・スター」でも美男/美女でもなく、純粋に内容で勝負するものも増えた。
例えば『X-ファイル』のデヴィッド・ドゥカヴニーやジリアン・アンダーソン、『24』のキーファー・サザーランドは劇映画では芽が出ず、当時は「え、誰?」という存在だった(キーファーは『スタンド・バイ・ミー』に出演していたが、どちらかといえば父親で名優ドナルド・サザーランドの息子という認識)。
逆に、テレビから劇映画に進出して有名になった俳優には、ブルース・ウィリス、ピアース・ブロスナン、そして、ジョージ・クルーニーがいる。
考えてみれば、「一点賭け」の劇映画に対し、テレビ・ドラマはヒットすれば数年から十年間に至るシリーズとなり、各国での放送権・DVDなどのメディア商品の売り上げを長期に回収できて、ビジネス的にも劇映画より旨味のあるジャンルだ。
ヒットするかどうか分からない作品を10億ドル(140億円)かけて製作して、公開してみたら全然客が入らない!といった「完パケ」勝負の劇映画と比べ、人気がなければ打ち切りすればいいのでリスク的にもダメージは少ない。
俳優にとっても、人気作品の主演クラスでドラマ一話あたりの出演料は30万ドルとも40万ドルともいわれ(1話あたりです!)、劇映画と比べればケタが違うが、日本でいえば、劇映画の最高クラスで1,000万円、最高クラスのギャラといわれる水谷豊でも『相棒』1話あたりで150万円程度だから、1シーズン(24話)出演するとすれば、1話あたり30万ドルでも10億円程度になる。
これがドラマか?!
しかし、それは今の話。
1992年当時は、ドラマといえばスタジオ撮影まるわかりのセットや照明、それを隠すための限定されたカメラワーク、シナリオも物語の筋を追うだけでやっとという状況で、とても質的な意味で劇映画に対抗できるものではなかった。
しかし、私は、このドラマを見て衝撃を受けた。
その作品は、『陰謀 ナチスに挑んだ男』(原題:The Nightmare Years)。
ナチス研究の第一級史料である「第三帝国の興亡」の作者で、アメリカ人ジャーナリストのウィリアム・シャイラー(William L. Shirer)の著作『ベルリン日記』を映像化した作品。
第二次世界大戦開戦(1939年)当時、ナチス政権を取材するためにアメリカCBSラジオの記者で、ベルリンに赴任していたシャイラーが、自らの経験を元に第二次世界大戦直前から戦争序盤までのナチス政権の裏側を描いている。
製作は1989年で、第二次世界大戦開戦50年の節目に企画されたものだろうと思う。
製作はイギリスのコンソリーデーテッド・エンタープライで、アメリカのTNT、フランスTF1、オーストラリアSeven Network、イタリアRAIの5ヶ国共同製作である。
映像には、綿密な時代考証と豊富な記録映像が盛り込まれ、NHKで4回に分けて放映された。アメリカでは1989年9月17日に放送された。この日は、9月1日にポーランド侵攻を始めたドイツに二週間以上遅れて、ソ連がポーランドに侵攻を開始した日付だった。
同じ様な趣旨のテレビ・ドラマ作品といえば、海外ドラマ・ファンはスティーヴン・スピルバーグとトム・ハンクスが製作総指揮をした『ザ・パシフィック』(日本での放送は2010年)が思い出されるだろう(映画ファンなら、『シンドラーのリスト』か?)。
主演でウィリアム・シャイラーを演じたのは、日本語のWikipediaには記載がないが、サム・ウォーターストン。
劇映画では、『華麗なるギャツビー』や『カプリコン1』、そしてなんといっても『キリング・フィールド』に出演したことでも知られる名優だ。
テレビ・ドラマとしては16年の超長期シリーズとなった『Law&Order』にレギュラー出演していたので、海外ドラマ・ファンにはこちらのほうが馴染みあるだろうか。
また、サムは架空のテレビ局の報道番組制作陣の活躍を描く『ニュースルーム』で、報道局長役にも出演しており、このドラマの製作陣がそれを意識してサムに報道局長役として出演をオファーしたのではないだろうが、「シャイラーとシャンバーグ(『キリング・フィールド』でサムが演じた、主役のアメリカ人記者)が報道記者から報道局長になったのか・・・』とスター・システム的な偶然の恐ろしさを感じた。どうでもいい話だけど・・・。
このドラマは、ウィリアム・シャイラーがドイツにいた1934年から1940年までを描いたもの。
第1話は、シャイラーがベルリンに向かう列車の中で、ナチ将校がユダヤ人らしき人々を拘束する場面をたまたま見かけ、ナチ政権に懐疑心を持ったとから始まる。
ドラマは、シャイラーがベルリンにいた1940年までの物語なので、まだドイツ軍はソ連侵攻も行っておらず、大日本帝国も大東亜戦争前で、ドイツはアメリカには宣戦布告を行っていない(日本と同盟を組んでいる建前上、宣戦布告を行った)から、ド派手な戦闘シーンや連合国兵士や将軍の活躍はない。
つまり、このドラマは第二次世界大戦そのものを描いたというよりも、二度目の世界大戦が本格化するまでに至るまでの、不穏な情勢の過程そのものを描いた、稀有な作品だ。その意味で、『シンドラーのリスト』のような「戦争ドラマ」ではない。
あくまでも、外国人特派員の目からみた、ナチス・ドイツの裏側を描いたものだ。
しかし、次第に勢いを増していくユダヤ人への迫害(当初、ポーランド系ユダヤ人は迫害の対象にはなっていなかった)と、戦線が拡大していくに従って、シャイラーへの対応が硬直化していく、ヒ○ラーやゲッベルスなどのナチス高官。
シャイラーの同僚や友人には、ユダヤ人がいたため、彼は、ゲッベルスなどナチの高官たちに対し、ユダヤ人への迫害を非難し、ナチ政権のユダヤ種族への攻撃を世界に告発するために記事を書く。
結果、そのことがナチ政権の逆鱗に触れ、シャイラー自身はおろか、家族にまで危機が迫る。
ドラマの描写は、戦前から現地でナチス政権を直接的に取材していたジャーナリストの記録が原作であるだけに、次第にナチスのユダヤ人迫害が強化されていく中で、それに加担していく市民、報道機関に対して厳しくなっていく検閲、ナチスの暴挙を放置し続けている民主主義陣営国家の無能さなど、さすがに緻密で説得力あるものとなっている。
また、ヒ○ラーやゲッベルス、ヒムラーなどナチス高官とのやり取りだけでなく、国家社会主義ドイツ労働者党(NSDAP, ナチ党)の第6回全国党大会を記録したドキュメンタリー映画『意志の勝利』を撮影中のレニ・リーフェンシュタールが出てくる(シャイラー「彼女は?」、案内人「映画監督のリーフェンシュタールだよ。プロパガンダ映画を撮っているのさ。総統閣下のお気に入りでね」)とか、細部の表現も、当時の雰囲気を醸し出すことに寄与している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
