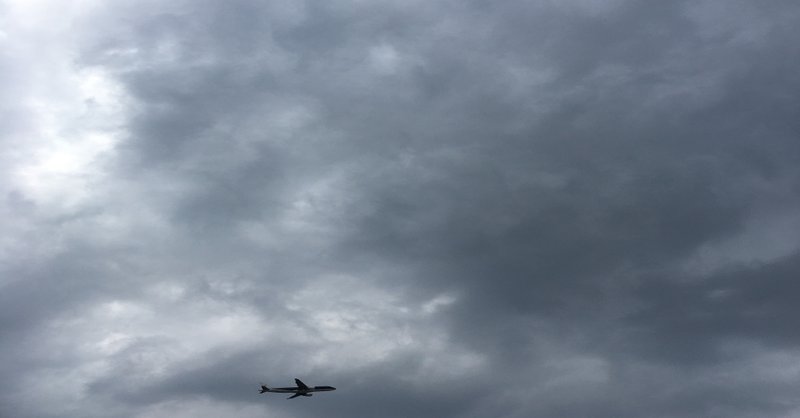
祖父のこと
「なんだ、揃いも揃ってのぞきこみやがって。」祖父の容体がおもわしくないと告げられた祖母があわてて招集した親族にベッドを囲まれて、祖父が目をあけてはっきりとした口調でそう言って、そこにいた全員が呆気にとられた。祖父からみたら異様な光景にうつったのかもしれないが呼ばれた方はそれぞれの思いをもってのぞきこんでいたのだ。だから危篤だという祖父がいつもの調子で放ったその言葉を聞いて、驚きでもなく、安心とも違うなんともいえない感じで、呆気にとられたのだ。今、思えばそれは祖父らしい一言だったけれど。
そのあと、集まった皆が、それぞれに声かけていたのだが、祖父のすぐ下の妹が「にいさん。」というと「なんだ、おめえかぁ。おめぇはもう帰っていいぞ。」と言った。7月の中頃で湿度の高い暑い日で、大汗をかいて慌ててきてくれたおばさんに。だ。わたしはおばさんの心中をおもって、おじいなんということをいうのだ。と内心やきもきとした。「おじいちゃんそんなこといわないで、せっかく急いで来てくれたんだから。」というまわりの声はとても虚しく、老いというのはなんだか正直で残酷なものなのだなと思った。
その日はそのままはっきりとしていてとてもひどいことを言ったりしていたが日に日に弱っていってほどなく祖父は亡くなった。1991年の梅雨があけるころだった。
お酒が何より好きで毎晩の晩酌を時間になるといそいそと準備していた。焼酎を好んでよく小鼻を赤くしていた。いまって酒焼けしている人っているのだろうか。酔うと机をたたいて拍子をとって時に立ち上がって歌ったり、いつもご機嫌で、「おじいさんが呑めなくなったらおわりだよ。」といっていた祖父。本当に呑めなくなって逝ってしまった。
当時は今のように高齢者に対する様々な行政サービスも少なく、介護は家族がやることで、それがふつうのことだった。明治の生まれでしっかり者の祖父だったので家族は頼りにしていたけれど、知らない間に老いは加速していってしまったのだろう。
夜中に電気をつけてひとり布団の上に座っていたり、朝ご飯を食べた後に、さっきしていた朝の身支度をまたしている祖父に母が声をかけると「朝飯をお願いします。」と言ったり明らかな呆けの症状が出る前に気がつけるほど情報もなかった。祖母のいびきで眠れないと、寝室を別にしていたことも気がつけなかった要因だったのかもしれない。梅雨の頃でお天気も不安定な中、食欲が急に落ちて、好きだった鰻も食べられず、いよいよ病院へ連れていった方がよいのではないかと家族が話しているのを社会人になって間もないわたしは曖昧な感じでみていた。
(つづく。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
