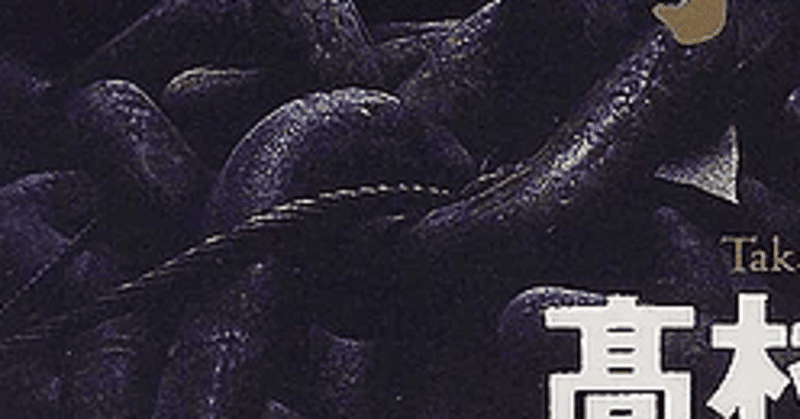
やっぱり冬にはエスピオナージが似合うのです。(髙村薫の『リヴィエラを撃て』)
RIVIERA
先日、スパイ小説の大御所 ”ジョン・ル・カレ” をnoteしたのですが、国内作家さんのエスピオナージ(スパイ活動)ものを紹介しようと考えてみると、意外と思い浮かぶ作品は少なかったりしたんですよね。
公安警察とかはよく出てくるんですが、エスピオナージって感じになると、『外事警察』の麻生幾さんの諸作品や、大戦中の”D機関”の暗躍を描いた柳広司さんのシリーズぐらいだったりします。
そんな中で、エスピオナージとして際立っているのは、やっぱり、髙村薫さんの『リヴィエラを撃て』だと思っています。
国際政治の楽屋裏を発狂させた男〈リヴィエラ〉。夥しい諜報戦士たちの血を吸込んだこのコードネームは、一人の天才ピアニストに死を賭した東京公演を決意させる。顔のない東洋人スパイをめぐって、東京・ロンドン・ベルファストに繰り広げる、流血の頭脳ゲーム。
髙村薫さんというと、警視庁の合田雄一郎を主人公とした一連のシリーズ、『マークスの山』や『レディ・ジョーカー』が有名です。
合田雄一郎シリーズも重厚な筆致で読み応え抜群なのですが、合田シリーズ以前に描かれた『リヴィエラを撃て』も、間違いなく傑作だと思うんですよね。自分の中では、髙村薫さんの著作で一番好きな作品だったりします。
何が、そんなに面白いのかというと、スパイたちの諜報戦はもちろんですが、主人公が明確でない物語構成が面白いんですよね。
あらすじにあるように、正体不明の東洋人スパイ<リヴィエラ>を巡る物語なんですが、CIAエージェントや、北アイルランドのテロリスト、イギリスの諜報機関、日本の公安警察と、それぞれ背景の違う人物たちが、まるで<リヴィエラ>の謎をバトンのようにして、死のリレーをしながら物語が進むのです。
<リヴィエラ>の謎を追求する者は、道半ばで死んでいくのですが、でも、バトンはつながれていくんですよね~。
読者にとっては、それぞれの走者の思いも受け継ぎながら、<リヴィエラ>の謎が明らかになっていくわけなのです。
物語の3分の2はイギリスが舞台で、出てくる人物も外国の人ばっかりなので、まったく、日本の小説を読んでいる感じがしません。
空気感や、そこで暮らす人々の様子なんかも、翻訳かと錯覚してしまうぐらいの出来で、これを日本人作家が書いたとは思えないぐらいです。
残り3分の1ぐらいになって、ようやく日本の主人公が行動し始めるのですが、ささやかに日本人としてのアイデンティティについても考えさせられてしまいました。
翻訳が苦手な人には読みにくい部分もあるのかもしれませんが、エスピオナージは冬に似合うので、ぜひ、この冬に挑戦してもらいたい作品なのです。
(関係note)
*
