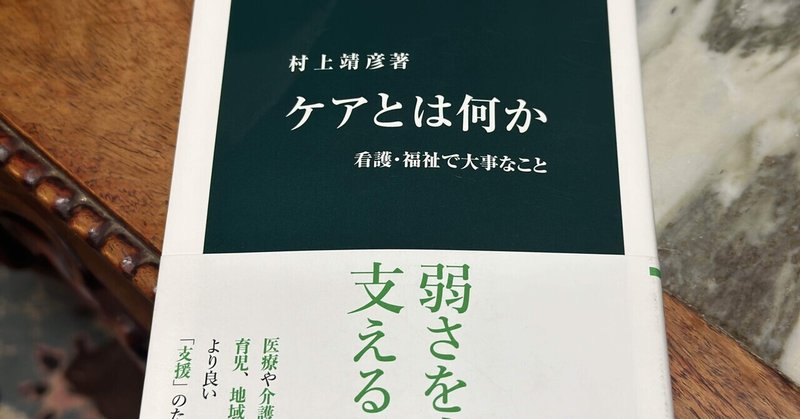
SOSのケイパビリティ——村上靖彦さんの『ケアとは何か』を読む
そこで私は、こうした潜在的なSOSのサインと、そのサインを受け止める力双方の組み合わせによって成立するケアを〈SOSのケイパビリティ〉と名づけたい。(中略)
スウェットにサンダルを履き、茶髪で青白い顔をした少女が産婦人科の外来で「おかっぱ呼べ!」とスタッフを怒鳴りつける。詰め所で仕事をしていた助産師のひろえさんは、「何怒られるかな」と思いながら出ていく。症状は病院に理不尽な因縁をつけているように思えたが、ひろえさんは少女のふるまいから、「困ったから来た」というSOSのサインを感じ取る。そして、人を信頼することができない環境を強いられてきた少女が、初めて人格的な関係を求めてきたのだと感じ取る。少女が怒鳴り散らしている理由はわからないが、おそらく産婦人科とは無関係の生活上の不安によるものだったのだろう。自分がSOSを出しているということも気づいていない。しかし、ひろえさんの受容的な応答によって、彼女の怒号は〈SOSのケイパビリティ〉に変わる。ここでは、自らケアを呼び寄せた少女の力、少女の見えづらいサインを感じ取るケアラーの力、その双方の働きかけが重要となる。
現象学研究者の村上靖彦さんの著書『ケアとは何か』より引用。村上さんはメルロ=ポンティやレヴィナスなど現象学(哲学)の研究者だが、自閉症の研究、看護師の実践の研究、大阪西成区の生活困窮家庭の研究など幅広いテーマを現象学という視点で鋭く分析している。すでに医療・看護現場の研究には20年来携わっており、その立場から「ケアとは何か」というテーマを村上さんらしい言葉で語っているのが特徴である。目次は、第1章「コミュニケーションを取る」、第2章「〈小さな願い〉と落ち着ける場所」、第3章「存在を肯定する」、第4章「死や逆境に向き合う」、第5章「ケアのゆくえ」となっている。
村上さんは「コミュニケーションを取ろうとすること自体が本質的にケアの営為であり、患者の存在を支える力になりうる」(同書, p.149)と言う。その出発点となるのが「声をかけること」である。弱さを抱えた人や、病や死など逆境のなかにある人は孤立している。孤立とは、外からの声が届いていないという現象でもある。声をかけることは、そうした状況にある人との〈出会いの場〉を開くことであり、孤立に代わる新たな意味を生み出すことだと言う。
「声かけ」が起こるとき、そこにはどんな現象が起こっているのだろうか。声かけは、何らかのサインをキャッチすることによってはじめて可能となる。しかし、SOSの声を発することができない人もいる。優れたケアラーは、そうした声を発することができない人の〈声なき声〉を拾い上げるという。例えば、村上さんの本では「暗い廊下のベンチにひとり佇む女性の姿」を見て、そこからSOSのサインを受け取る看護師の話が出てくる。この看護師の声かけは、〈からだ〉が表現した孤立と悲嘆を、彼女がSOSとして受け取ったことで成立した。このような潜在的なSOSのサインと、そのサインを受け止める力双方の組み合わせによって成立するケアを〈SOSのケイパビリティ〉と村上さんは名づけている。
冒頭の引用に出てくる「おかっぱ呼べ!」と産婦人科外来で呼ぶ少女の例も同じである。助産師のひろえさんは、少女の叫びをSOSのサインとして受け止める。先ほどの沈黙して佇む後ろ姿によるSOSのサインとは対照的であるが、患者が怒鳴ったり怒りを示しているというのも医療現場ではよく見かける光景である。そのとき、その怒号の裏には「私を助けて」というSOSのサインがあり、その微かなサインを読み取るという力がケアラーには備わっている。そうした双方の働きかけによる現象が〈SOSのケイパビリティ〉であり、ケアという行為の本質を表現するものの一つである。
村上さんは「ケアは人間の本質そのものである」(同書, まえがき)という。人間は「独りでは生存することができない仲間を助ける生物」と定義することもできる。つまり「弱さ」を他の人が支えること、これが人間の条件であり、可能性でもあると言えるのではないか、と。援助職によるケアは、第三者として「弱さを抱える人と関わる実践」なのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
