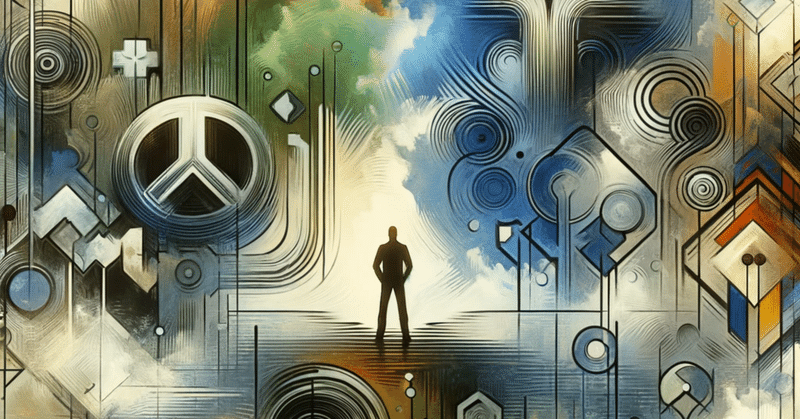
マネジメントの言語戦略:「空気の支配」に抗うために
マネージャーの仕事は、例外処理としての意思決定である
組織におけるマネージャーの役割とは、下位階層の標準フロー内で対応方法を決められない事項の処理方針を決定することである。ここでいう標準フロー内で対応できない事項とは、定型化された業務の機械的なフローでは対応できない複雑性や不確実性の高いイシューであり、組織としてどのように処理するべきかに対する明確な共通認識がない不確実性の高い問題一般を指す。
このような不確実性の高いイシューに対して、適切な階層までエスカレーションを行ったのちに適当な処理を決定/実行することを、組織論の文脈では例外処理と呼ぶ。そして、組織におけるマネージャーの役割は、この例外処理の方針を決定するdecision-makingに集約されるというのが、私の考えである。組織論における例外処理を考察した記事を以下に添付するので、関心のある方は参照されたい。
曖昧な言葉づかいが生む空気の支配と集団的無知
マネージャーは、意思決定を行う際に、解釈の余地や曖昧さを含む言語を使うことを避けねばならない。なぜなら、曖昧な言語の利用が常態化すると、組織全体がマネージャーや集団の非言語的なメッセージ、すなわち”お気持ち”を忖度し、場の「空気」で物事を進める文化が醸成されるためである。
「空気」が判断基準として固定化された状態とは即ち、人が自分の頭で物事を相対的/批判的に思考しなくなり、無限に場の「空気」を忖度することにばかり頭を働かせる「集合的無知」の蔓延を意味する。こうなると、人々の最優先事項は、言語の外にある含意を読み取る忖度であり、眼前の問題に最善に対処するための理性的/批判的議論の一切は劣後していく。
この「集合的無知」が働くと、組織は傍目から見れば極めて非合理的な行動を取りはじめる。しかし、各々を問いただしても、その意思決定を主体的に行なっている人がどこにも存在しないというとんでもない状況が生まれる。あくまで人々が互いの心情を忖度しあった結果として集団の意思決定が行われるためであり、その決定が無人称のものとなるからである。赤信号、みんなで渡れば怖くないとはまさにこのことだ。
このような「集合的無知」が集団に引き起こす災禍については、山本七平が”臨在感的把握”という概念を通じて批判した日本人の「空気」への信仰と理性的思考の軽視、そして丸山眞男が”無責任の体系”として見出した日本軍の徹底的な主体的思考の欠如を通じて、日本人の歴史的記憶にしっかりと刻まれている。組織を担う責任ある立場にある人は、このような「集合的無知」が再現する状況をあらゆる手立てで防がねばならない。
意思決定の言語における曖昧さは、空気の支配による「集合的無知」を引き起こす。曖昧な言語の使用は、コミュニケーションに言外のお気持ちの忖度を要求し、必ず「空気の支配」に結びつくためだ。だから、意思決定を担う立場としてのマネージャーは、この意思決定における言語の曖昧さを可能な限り排除する責任があるというのが私の主張である。
こうした言語の曖昧さを生む原因は、日本語の言語学的な特質や、無意識に発言の責任を負う事を忌避する社会心理学的背景、対人コミュニケーションの未熟さなど、様々な観点で要因分析をすることができる。こうした諸々の知見に簡潔に触れつつ、自分の言語から曖昧さを排除するための実践的な方法論を提示したい。
①主語を省略しない
一つ目は読んで字の如く「主語」を省略しないことなのだが、まず言語学的な見地に立って前提となる知識を整理しておく。主語は文において「誰が」という動作の主体を指示する役割を持つ。主語が言語の中でどのように現れるかは、その言語が動作の主体をどのように判別しているかを紐解くのに重要な情報である。
日本語をはじめとする東アジア言語は、統語論的な特質として主語を極めて頻繁に省略することが知られている。これに対して、英語は主語をいつでもどこでも厳格に要求するという統語論的な特質を持つ。英語の授業で形式主語のitや能動態/受動態の書き換えを学んだ時の、言いようのない違和感を覚えている方も多いだろう。日本語話者からしたら、文に主語もへったくれもあったものではない。
反対に、日本語を学ぶ英語話者にとって障壁となるのは、日本語の主語/述語の対応の曖昧さである。「飲んだ?」「食べた?」「お腹すいた?」といった疑問文に対して、「私が?あなたが?/Are you asking me?」と聞き返す英語話者が多いのは、主語述語の対応関係を文の内部に求める英語と、言語外のコンテクストに求める日本語の言語的な特性の違いが大きな原因となっている。
では、他の言語はどうかと言えば、インド=ヨーロッパ系言語の多くは、主語を英語ほど厳格に要求しないものの、動詞が主語の人称に応じて語形を変える人称変化が発生し、動詞を主語の統制下におくことが一般的である。例えばロシア語は、一人称単数/複数、二人称単数/複数、三人称単数/複数のように動詞が主語の影響で語形変化するから、動詞の語系を見れば主語を特定することはそこまで困難ではない。

しかし、日本語には動詞の人称変化は存在しない。動詞は主語から極めて自由である。そのため、動詞の主語を読み取るためには多くの場合、言語表現の外側にあるコンテクストを参照する必要になる。英語などの主語優勢言語に対して、日本語含めた東アジア言語が主題優勢言語と呼ばれるのはこのためである。
主題優勢言語を操る私たち日本語話者は、コンテクストに意味を託して、単体では主語が判別できない文章を量産する傾向がある。こうした文のキャッチボールは曖昧さに繋がり、解釈をお気持ちの忖度に依存する「空気」の支配を生みだす。このような曖昧な言葉のキャッチボールとお気持ちの忖度が常態化した状態を、私は「空気コミュニケーションの蔓延」と呼ぶ。
「空気コミュニケーションの蔓延」を防ぐため、私が一番簡単かつ重要だと思っているのが、全ての文章に主語をおくことである。誰がそれを言っているのかを明示するのだ。例えば、以下が主語を置くことで曖昧さを排除できる会話の例だ。
悪い例:
その資料のこの部分は誤解を招く表現かもしれません。
良い例:
私は、その資料のこの部分は意味が通らない表現かもしれないと感じました。
悪い例の文章のような「指摘」や「レビュー」は巷にあふれていると思うが、もし私がこのような指摘を受けたならば「え、誰の誤解ですか?」と半ギレで聞き返してしまうだろう。誰の懸念であるかが明確にならないと、次の具体的な行動につながらないからだ。「誰が」を明示しない時点で、悪しき「空気コミュニケーション」に片足を突っ込んでしまっている。
反対に良い例は、「私は」とあえて主語を明示することで、この件は「私が」感じていることを示している事を明示したものだ。受け手は「このひとは気に入らないらしいので、なにかしら気に入る表現に変えれば良いのだな」と合点し、納得するか否かは別にして、次の具体的な行動に繋げることができる。「私が」このコミュニケーションから生じる不和(部下からイラつかれる)を引き受けるだけで「空気コミュニケーション」を防ぐことができるのだ。
全ての文章に主語をおく事を心がけることのメリットはもう一つある。例えば、ネガティブフィードバックをする時、私たちは安易に以下のような文章を作ってしまいがちである。
悪い例:
あなたの服装、気にする人もいるので気をつけてくださいね
良い例:
私は、あなたの服装は職場のTPOに合っていないという他メンバーからのクレームを受けています。業務規定に照らして、Aという点は変える必要があると思っています。
日本語の伝家の宝刀である「気にする人がいる」「世の中にはいろんな人がいる」「私は気にしていないけどうるさい人がいる」といった言葉の数々。私は発話の責任を宙吊りにして「空気コミュニケーション」を呪いのように他人に埋め込むだけのこうした言葉遣いを、文字通り蛇蝎の如く嫌っている。
このやりとりから受け手が学べることはなんだろうか。「空気」を読まなきゃ、忖度しなくちゃという不安を内面化し更なる「空気コミュニケーション」を再生産するだけだろう。そんな不安を植え付けようとするのは、「空気」の力を借りて、自分の都合よく他人を抑圧しようとする浅ましいやり方だから、絶対にやめなければならない。こういう言葉は気を抜くとふとした時に使ってしまうので、意識を高めたい方には以下の書籍を薦める。
本当にその人の服装に問題があると考えるのであれば、「私は」という主語を置き、その言葉の責任を引き受けるべきだ。そうすれば受け手は、「わたし」という人間とのコミュニケーションを行い、落とし所を探るという行動に繋げることができる。
また、主語を置くことを意識すれば、自然と続く言葉に対するオーナーシップが生まれるから、無責任なことや誤解を招くことは言うまいとする心理的規制も働く。反対に「空気コミュニケーション」はあくまで集団忖度の結果として生じる無人称な言葉でしかなく、発話者の意思や責任は宙吊りにされてしまう。だから辞めないといけない。
なお、主語を置くというテクニックは、いわゆるI messageを多用するという臨床心理学的な知見を、私が自分の使いやすいようにパラフレーズしたものである。I messageの重要性についての私の考えは以下のnoteに記載したので、関心ある方は参照されたい。
②一文は短く、語尾を断定調で統一する
言語学者の加藤重広は「その言い方が人を怒らせるーことばの危機管理術」という著作の中で、日本人は言い切りの形を作ることが極めて不得意であると述べている。というのも、日本語は、…で、…ですから、…と、のように接続助詞を自由自在に使いこなす事で論理関係の曖昧な文章を次々に言い連ねる事ができる。このことが、リスク回避的にひたすら文章を連ねて言い切りの形を作らないで、流れや「空気」でコミュニケーションを乗り切ることを可能にしているのだ。
加藤が示す通り、一文をダラダラと長く話すのは、言い切りをすることで発言の責任を問われたくないというリスク回避的な心理の現れであると同時に、従属節の形で文章を連ねることで、旗色が悪ければ後からそれをひっくり返してしまいたいという心理が働いていると考えるべきである。
「後からそれをひっくり返す」とは、どういうことか。日本語では長々と「〜と、〜と、〜ですと、言うようなことをおっしゃる方もいますが、〜で、〜であり、〜と思い、また〜」のように、延々と連なった接続助詞の後に動詞が来る場合が多い。長々と「〜と」で連ねられた中身は英語で言うところのthat節に相当し、その意味の確定は動詞が登場するまで保留されている。
例えば、この一連の文章は文末で「と思っている次第です」という己の主張で締めるか、「と思っている向きも強いです」という時流への言及で締めるか、はたまた「というのはとんでもない誤解です」と反論するつもりでいるのか、聞き手は最後の述語部分に辿りつくまで意味を確定することができない。論理関係をあやふやにしながら、従属節を何重にも重ねることで意味の確定を意図的に遅延させることができる日本語の言語的特質は、私たちのコミュニケーションを間延びさせることで、意味の把握を困難にする。このことも、言語の曖昧さを生み出す原因の一つになっている。
この問題に対する私の対処法が、一文は短く、語尾は断定調で統一することだ。まず、「…で、…ですから、…と」などと、従属節を多用することを避け、こまめに文を区切ること。文を区切れば、論理関係を明示するため接続詞を適切に利用することが否応なしに求められる。そのことだけで、発言の内容に論理的整合性を保ち、曖昧さをある程度排除しようとする意識が働くことになる。以下を参照されたい。
ChatGPTに書いてもらった悪い事例/良い事例
悪い事例: 「このプロジェクトが抱えている問題について、多くのスタッフが様々な意見を持っている中で、一部の問題は解決策が提案されているものの、それらの解決策が実際にどれだけ効果的であるかはまだ分かっておらず、そのため、プロジェクト全体の進行においては、まだ多くの課題が残っていると言えるでしょう。」
良い事例: 「このプロジェクトは、Aの問題に対してBの解決策を試していますが、Cの問題は依然として解決していません。」
悪い事例: 「私たちの製品が市場でどのように受け入れられているかを考慮すると、その市場の動向が日々変化していることを踏まえ、その変化に応じて製品のアップデートを考える必要があるかもしれないと、いくつかの部門から提案されていることを考えると、製品の改善策を検討すべきかもしれません。」
良い事例: 「市場調査によると、顧客はX機能を求めています。したがって、製品にX機能を追加することを提案します。」
悪い事例は文章に落としてみると滑稽にすら感じるが、実際口に出して読んでみると案外口馴染みがよいのではないだろうか。スラスラと話している感じがする人は大体こんな感じで会話しているのだが、聞き手はその論理を追いかけるだけで手一杯である。コンサルティング業界で「結論ファースト」が奨励されるのも、それもこのような言語的特性が大いに関係しているのだ。
③具体にこだわる
人は自らの抽象化の能力を過大評価する傾向があることが認知バイアスの研究からわかっている。十分なサンプルがないまま帰納的推論を進める「早まった一般化」(男性のAさんもBさんもCさんもXなので、男性はみんなXだ)、あやまった因果推論を行う「誤帰属」(他人の失敗の原因は性格や育ちなどの内的要因に求め、自分の失敗の原因は環境などの外的要因に求める)、自分が頻繁に目にするものや印象に残っている情報を元に意思決定を行う「利用可能性ヒューリスティック」(身の回りにいる人がそう言っているから、Xは悪い人だ)など、認知バイアスの横暴は枚挙に遑がない。
私たちは個別具体的な事項を逃れて「一般的な」事実を語る能力に乏しい。にもかかわらず、認知バイアスによって歪められた因果推論や一般化を語りたがる。それもまた、言語の曖昧さを生み、「空気コミュニケーション」の蔓延を作り出す一因である。だからこそ、コミュニケーションは「具体」にこだわるべきだ。
とはいえ、「具体」のコミュニケーションとはどんなものなのだろうか。わかりやすいのは「具体」でないコミュニケーションの形を探ることだろう。以下に、控えるべきワードをいくつか挙げておこう。
①常に、いつも、みんな
-> いつ、誰が?を具体的に伝える
②〜しがち、〜する傾向がある
-> 何を、どのくらい?を具体的に伝える
③〜に違いない、〜に決まっている
-> なぜそう思ったのか?を具体的に伝える
「具体」にこだわることは、今ここに存在している相手を尊重するということだ。自分の抽象化や一般化の力を過信せず、見聞き体験したことを適切に伝え、相手に対して決めつけをしない。それを心がけるだけでも、自分の言語から曖昧さを排除することができる。
往々にして、「空気コミュニケーション」が蔓延している状態とは、人が認知バイアスによって歪められた行動や言動を取っているものだ。認知バイアスは私たちを、今ここで起こっている「具体」から目を背けさせ、「こうに決まっている」と信じ込んでいるものしか見なくさせてしまう。それは日々の生活を送る上での認知負荷を下げる分には有効に作用している心の働きだが、集団としてより良い意思決定をすることの妨げにもなる。だからこそ、意識して「具体」を見ようと心がけることは極めて重要だ。
特にマネージャーのように日々意思決定が求められる仕事をしている人は、こうした認知バイアスの特性を適切に把握することに努めねばならない。その上で、本当に今起こっている「具体」を見極め、そこから紡ぐべき言葉を見出すのだ。
結び
今回は、組織におけるマネージャーの重要な責務を例外処理としての意思決定と置いた上で、意思決定における言語の曖昧さが引き起こす問題にどう立ち向かうべきかを考えてみた。個々のアクションはそこまで難解ではないが、私たちがどんな論理世界を生きているかの解像度を上げるために言語学や心理学の観点を引き合いに出した。
とにかく色々な意思決定に追われているマネージャーは、責任を負うことに疲弊して「空気コミュニケーション」を誘発する言葉を使いがちであり、認知バイアスの効力に逆らえず誤った一般化を行いがちである。だからこそ、今一度「具体」の世界に踏みとどまることを意識したい。抽象化の力は、徹底的な「具体」から出発せねば発揮することはできないと信じている。そういう思いで、このnoteを書いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
