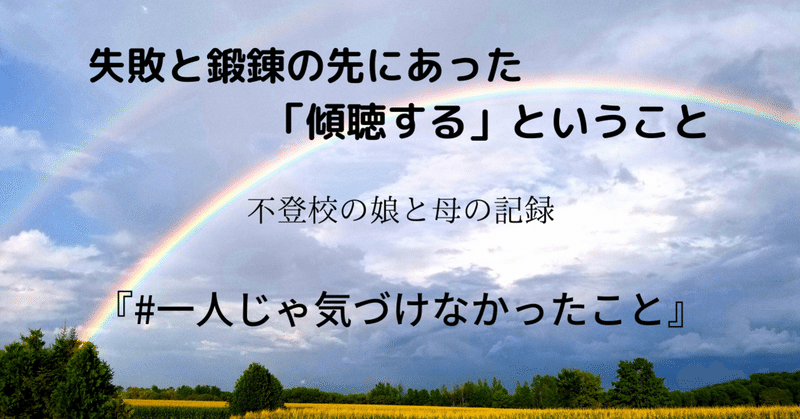
失敗と鍛錬の先にあった「傾聴する」ということ
おしゃべりが大好きな娘、良いことも嫌なことも、なんでも話してくれていた娘、私は娘との会話が大好きだった。
病気を発症し、不登校になっていく過程で、そんな娘の心がだんだん壊れていくのを感じた。
何に対しても苛立ち、自己否定を繰り返し、一緒にいるのに孤独を抱えているようにも見えた。
私は、母親として自分ができることは何か、必死になって探した。
学校に行けないことで、自分を責めるように過ごしている娘を励ましたい、元気をあげたい、自信をあげたい、勇気をあげたい、とあげたいものがたくさんあった。
「学校に行きたいけど、行けないんだ」と言われれば、
・・・あなたは頑張り屋さんだから大丈夫。
・・・あなたはやればできる子だから大丈夫。
・・・ママの時はこうだったからあなたなら大丈夫。
自己否定的なことを言われれば、
・・・そんなことはない。
・・・なんでそんな言い方するの?
・・・もっとこう捉えたほうがいいよ。
この時の私は、できること前提の言葉でプレッシャーを与え、自己否定を繰り返す娘の言葉をさらに否定していることにまるで気づいていなかった。
どう話せば伝わるのかと、与えることばかりを考えていた。
これは今でも最大の失敗だったと思うけど、今だからこそ最大の学びを得るための失敗だったんだとも思う。
当時は強迫性障害というよく理解できない病気についても、その影響で不登校になってしまったことについても、どこかで気持ちの問題だと思い込んでいる自分がいた。
私自身、メンタルが強いわけでもないのに、だからこそなのか、励ましでしか娘を救えないと思っていた。
伝えても伝えても伝わらない、それどころか、娘自身も「ママに言ってもわかってくれない」と、自分の気持ちを言葉で伝える代わりに、苛立ちを剥き出しにしていた。
これまで培ってきたはずの娘との信頼関係が、どんどん失われていくのを感じて苦しくなった。
この頃、「不登校」というキーワードにヒットする記事をたくさん見ていた。
たくさんの専門家やカウンセラー、子供の不登校問題を克服した親御さんたちが声を揃えて言っていたのが、とにかく子どもの話を「傾聴する」ということ。
傾聴とは『相手の言うことを否定せず、認め、耳も心も傾けて、相手の話を「聴く」』こと。
ところが、この「傾聴する」が当時の私にはとにかく難しかった。
否定するつもりはなくても、口を挟みたくなってしまうのだ。
「傾聴する」ことで、得られるものがあると分かっていても、励まし癖が抜けない私には難しかった。
そういえば娘は昔から、「何も言わずにただ聞いて」とか「言っても怒らない?」と言う前置きをしてから話すことが時々あったことを思い出す。
特に、それはどうなの?という、よくはない内容の話に関して。
それは、娘の中でもよくないということが分かっているけど、私に打ち明けることで許してもらおう、認めてもらおう、そんな気持ちの表れだったように思う。
私は、起きたことにだけ目を向け、その裏にある娘の気持ちを汲み取ろうとはしていなかったことに気づく。
娘の気持ちが知りたい、話がしたい、と思えば思うほど、「傾聴する」ことを諦めてはいけないと思い直す。
そんな時、友人の紹介で「子ども色彩知育」という習い事と出会う。
始めたばかりの頃の娘は、創作意欲に溢れ、集中して取り組んでいたが、回を重ねるごとに、作成途中で別のことをしたり、お話に夢中になってしまったり、飽きてしまったり、横で見ていてハラハラすることが多かった。
でも、先生は、どんな娘であっても急かすことなく、無理矢理作業に戻すこともなく、ただただ優しく声をかけ、笑ってくれていた。
親としては、「ちゃんとできていないのにいいのかな?」という思いでいた。
いっぽうの娘は、より活き活きと自分のペースで取り組み、どんな自分もOKと認めらる喜びを体いっぱいに表現していた。
まさにこの、「子供のありのままを認める」ということが、色彩知育の「色と言葉がけによって、知性と個性を伸ばし、生きる力を育む」というコンセプトそのものだということを知った。
得るものしかないのではと、私自身も先生のもとで言葉がけのヒントをたくさん学ばせてもらった。
子供の感情(か)・視覚(し)・行動(こ)のありのままを認める言葉がけ、「かしこ式言葉がけ法」を得たのは大きかった。
だが、この言葉がけも、簡単そうで最初は難しかった。
例えば、「太陽が黒かった」と言われれば、「黒くはないでしょ」や「なんで黒く見えるの?」という私の思いをぐっとこらえ、「黒かったんだね」という言葉で返すなど、「娘には太陽が黒く見えているんだ」とありのままの娘を認め、自分の主観は置いておく鍛錬が必要だった。
最初のうちは「娘が発した言葉をなぞる」ことを意識して始めてみることで、だんだんと見えてきた。
まず、娘の言葉の中にある感情や表現を丸ごと言葉にして認めることが、まさに「傾聴する」ことなんだと気がついた。
そうか、「傾聴する」ことが難しかったのは、娘を信頼できていない、認めていない私がいるからだ。
当時は若干10歳の娘、私の中では「まだまだ」と娘を認めきれていない思いが、「傾聴する」ことを妨げていたことにも気がついた。
共感できなくてもなぞる、とにかくありのままを認めようと何度も自分に言い聞かせ、鍛錬に鍛錬を重ねた。
娘の言葉を繰り返し、娘の感情を言葉にすることを心がけていくうちに、娘の表情が変わっていくのを感じた。
私が話を聴いてくれている、自分を認めてくれているという感触があったのか、娘がだんだんと、思っていることを伝えてくれるようになってきた。
最初は「学校に行ってないからダメかもしれないけど・・・」と、後ろめたい自分の思いを、恐る恐る添えるところから始まった。
時には耳を塞ぎたくなるような心の叫びも、心を込めて聴いた。そして繰り返した。
どんなに鍛錬を重ねても、私の中の伝えたい思いが全て消えるわけではない。
悲痛な思いほど聴いていて苦しかったけど、「伝えるのは今じゃない、求められた時まで待とう。」と言い聞かせた。
どんな言葉も、聴いて、認めて、を繰り返していくことで、どんどん会話の量が増え、分かってくれないからと閉ざされた娘の心が徐々に開いていくことがわかるだけで、とてつもなく嬉しかった。
嬉しいと、もっと聴きたくなる。もっと娘を知りたくなる。
「ない」を拾っていた自分から、「ある」を見つける鍛錬を同時期に重ねていたことで、娘を知れば知るほど、娘は大丈夫と、信じられるようになった。
娘の好きなことの話には特に興味をもって聴いた。
聴くだけではなく、みんなが学校に行っている間に、行ってみたいやってみたいという意欲も、後回しにせずに可能な限りつき合うようにした。
意欲を逃さないことで、娘の成長の記録をたくさん目の当たりにした。
いつしか、前のようにおしゃべりが止まらなくなってきた娘を見て、娘の中で、私への信頼貯金が増えていっている感触を感じると同時に、私の中の娘への信頼貯金も増していたことに気づいた。
そして、気がつくと私の伝えたい思いなんてどうでもよくなり、「傾聴する」ことも、私の中で難しいことではなくなっていた。
今では、娘の気持ちをなんとか引き出そうとしなくても、きっかけがあれば娘から話してくれるし、行動を起こしてくれる。
私は最初の失敗があったからこそ、今この日常がたまらなく尊い。
娘との会話で感じる娘の成長も、意欲的になっている時の娘を全力でサポートできることも嬉しい。
そしてその一つ一つに対し、評価したり、良い悪いとジャッジするのではなく、「ママは楽しいよ、嬉しいよ」という気持ちを、言葉に乗せて伝えるようにしている。
娘にとって不登校であるという後ろめたさの中に、私の嬉しい気持ちが伝わると、娘の表情が明るくなることにも気づけたから。
不登校になってしまった子供の中には、親に対して「こんな自分が子供でごめん」と思ってしまう優しい子が多いという。娘もその1人。
だから、私が母親としてできることは、娘のありのままを認め、「あなたが不登校でもママは幸せだよ。」という安心を感じてもらうことだと「傾聴する」ことを通して気づき学んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
