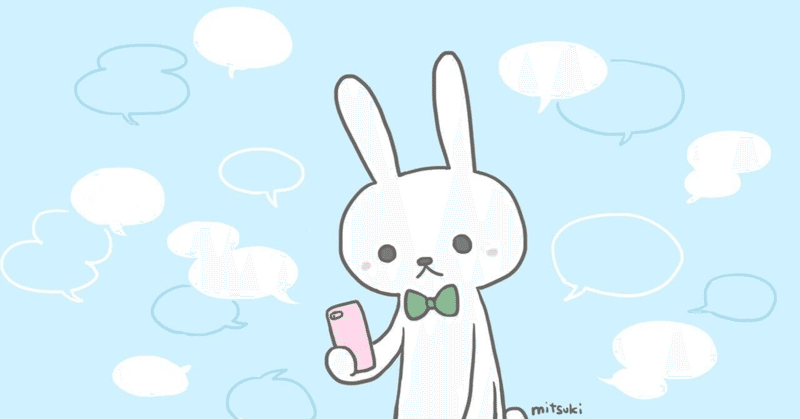
コメントがもっとうまくできたら
恥ずかしながら私はコミュ障です。長年の療養生活によって普段から話す人が少なくなっていたせいか、気付いたらネット上でもうまく話せなくなってしまっていました。そのせいかコメントすることも苦手意識があります。
投稿する前にもおかしいところはないかと何度も確認しますし、投稿した後でもこう思われたらどうしようと思って心配になり、書き直すことすらあります。コメントする勇気が最初から持てないこともしばしばです。
またコメントの返信についても気にしてしまったりと、かなりの挙動不審なタイプになってしまっています。そのため、無事に返信頂けるとものすごくほっとします。
そんなコメントをする側でも悩んでいた私ですが、コメントを頂く側でも同じように挙動不審になっている面がありました。こちらはこちらで「せっかくコメント頂けたのに失礼はなかったか?」という悩みが付きまといます。
その一方で、やっぱり「コメントを頂けたら」という願いも浮かんできてしまいます。そのうちもっと自分がうまくコメントを返せたのなら、全然違うのかもしれないと思うようになりました。
コメントから学ぶ
そんな中で、習慣応援家shogoさんのこちらの記事に出会いました。
私はこちらの記事の「魅力的な記事を書く人は、総じて『人を惹きつける人柄』を持っています」「そして、note内でもっとも『人柄』の現れる場所とは、まさに”コメント”にあるのです」という言葉に、ものすごく衝撃を受けました。
ああ、だから自分はだめだったんだと思ってしまったのです。人柄が理由じゃどうしようもないな……とがっかりしました。
確かにnoteでコメントをたくさんもらっている方たちは「また話したい!」と思うような魅力を持っていますし、自分自身そういった方とお話することによって元気をもらうことがたくさんありました。
けれども、記事には続きがありました。「『魅力ある人柄を身に付けたい』と考えるなら、ぜひとも自分以外の場所に訪れて、たくさんのコメントに触れることをおススメします」――つまり、他の方のコメントを学ぶことで自分も近付けるようにとのことが書いてあったのです。
それぞれの工夫を
私はまず、自分がコメントを実際にしに行く方のコメントを見に行ってみることにしました。いろんな方がコメントをしていますが、やっぱり「また話したい!」と思われるようなことを返しています。
そのうちわかってきたのは、おそらく基本的にはほとんどの方が「来るもの拒まず去る者追わず」という考え方があるのだろうなということでした。もちろんそうではない方もいると思いますが、私にはなんとなくそう見えました。
コメント欄にはいろんな方が来ます。これを返すのは難しいのでは……というものもあったりするのですが、うまく返していたりしてすごいと思わされました。私だったらどうしようと戸惑ってしまうでしょう。
そして何らかの自分らしい工夫をされているようにも見えました。それは面白い返しをすることや、プラスアルファの情報を教えることや、相手の記事に対しての感想を言うなどのことです。
私はここで自分が大きな誤解をしていることに気付きました。それはリアルのように聞き上手でいるのが一番いいと、すっかり思い込んでいたことです。もちろん、相手の話を積極的に聞いている方もいるのですが、返し方がそれを踏まえてさらに一段階上のことを言っていたりすることに気付きました。
つまり、相手の話をちゃんと受け入れたうえで自分らしいコメントができている方が多かったのです。
テクニックの一例
例えばこんな感じです。
「今日は寒いですね」
「そうですね。寒いですね。早く暖かくなって欲しいですね」
「そろそろ4月ですし、もうすぐでしょうか」
「今日は寒いですね」
「ああ、朝方も冷えていましたしね」
「暖かい日差しが恋しいものです」
「4月はもうすぐですよ」
うまい例文が書けなかったような気もしますが、私的にはこんな印象があります。まず「そうですね」と同意して話を進めようとするよりも、情報量が多くなっている気がします。
この返しにも本人のユーモアやまさに「人柄」が現れているように感じました。そして、話し言葉と書き言葉は違うということも見えてきます。
コメントしたくなるような記事を書くのも大切だと思いますが、それだけで終わらせなくするのがこのコメントの返しというテクニックです。
相手に興味を持つ
何よりすごいと思わされたのは、先程も書きましたが「記事の感想を言う」「過去の記事を覚えている」「近況を踏まえて話をする」など、相手に興味を持っているということが伝わることを書いている方でした。まるでリアルのような丁寧な付き合いです。
いろんな記事を読んだりしていると「こんな記事があった」という大雑把な記憶しか残らなかったり、「この方の書く記事は好きだなあ」くらいのことで印象に残った記事があってもいくつもは思い出すことができなかったりします。
もしかしたらこれは記憶力の悪い私だけかもしれませんが、まるで本の感想を覚えているのと同じように記事の名前と内容をいくつも覚えていることはけっこう難しいです。けれども、自分がしてもらえるととても嬉しいです。
ここはリアルと同じですが、「私はあなたに興味を持っています」ということを態度に出して、自分たちの共通点を探したり適度に質問したりすることはやっぱり大切なんだと思った発見でした。
このことを応用していくと、最終的に相手が「この人に自分の話をしたい」「また話を聞いてほしい」と感じるような「話を聞く」スタイルにもなっていくことができるのだと思います。
今回の考察はここまでです。なんだかコメントを学んでいるうちに、コミュニケーションの本質というものを見つけることができたような気持ちになりました。
そして私は、今日もコメントの工夫に勤しんでいます。まだまだ納得のできる返しには辿りつけていませんが、少しでも「コメントしてよかった」と思って頂けるようなことを書けるようになれたらと思っています。
習慣応援家shogoさん、素敵な記事をありがとうございました。
ここまで読んで下さってありがとうございました。
サポートして頂けるととても励みになります🙌頂いたサポートは元気をチャージしていくことに使っています🔥
