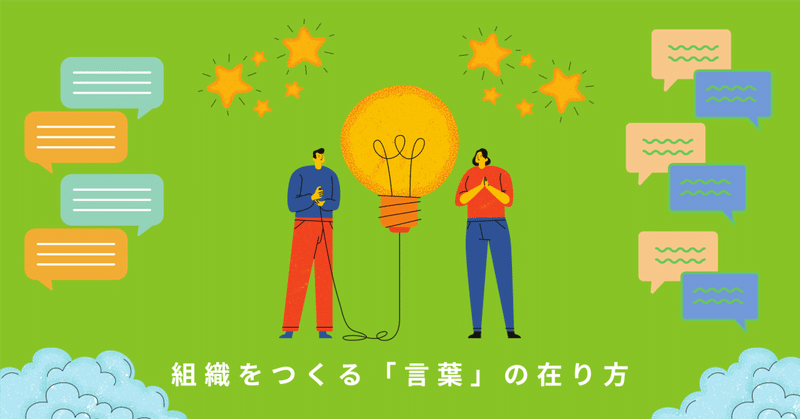
組織をつくる「言葉」の在り方
最近はよく、株式会社ベイジCEO・枌谷さんのXポストから、考えるきっかけを頂いている。
2人以上の人が集まり、同じ目的のために行動すると、それは組織になる。
— sogitani / baigie inc. (@sogitani_baigie) October 17, 2023
その組織において人と人を繋げて組織たらしめてるのは、ルールや制度や仕組みと思いがちだが、もっとも基盤となってる構成要素は、会話ではないかと思う。…
2人以上の人が集まり、同じ目的のために行動すると、それは組織になる。
その組織において人と人を繋げて組織たらしめてるのは、ルールや制度や仕組みと思いがちだが、もっとも基盤となってる構成要素は、会話ではないかと思う。
明るい組織には明るい会話が流れており、暗い組織には暗い会話が流れている。組織のモードやムードを変えるには、会話の質や内容を変えるのが基本である。組織のカルチャーを作るのも、組織に流れる会話が鍵になる。
その会話の構成要素は、言葉である。なので会話の質を変えるには、使う言葉を変えるのが有効である。
つまり、だからこそ、組織の問題を解決したり、さらなる成長を促す第一手として、組織の中で使う言葉を定義する、言葉を整える、言葉の意図を説明する、言葉を共通言語化する、ということが、重要になる。
世の、組織を上手に動かす経営者やリーダー、マネージャーは、言葉の違いに対して繊細な感覚を持ち、言葉を上手に取捨選択することができる人が多いように思う。
たとえ広告キャッチのような洗練された言葉でなくても、社内でみんなが口にしたくなるような言葉の発明が上手かったり、その意図を言語化して、腑に落ちる説明が上手かったりする。
おそらくそれも、組織や人を動かす上で言葉は何より重要であり、言葉の力を知っているから、言葉の違いによる影響の違いを知っているからこそ、身に付けた能力なのだろう。
最終更新:2023/10/18 AM7:27
ついていきたくなる人、一緒に頑張りたいと思う人の言葉には力がある。
— しおり|community manager (@spin_my_story_s) October 18, 2023
一貫性のあるメッセージ(同じワードじゃなくても「軸」や「背骨」)によりモチベやチームワークは高く/強くも低く/弱くもなる。
そして同じことを言うにしても、言い方や伝え方でコミュニケーションはgoodにもbadにもなり得る🙂 https://t.co/0h2RegIGl7
ついていきたくなる人、一緒に頑張りたいと思う人の言葉には力がある。
ミッション・ビジョン・バリューの浸透/体現というのも同じ話なのかなと思っている。社員がMVVを自分事にしていない状態で、顧客にそれが響くのだろうか。
コミュニティマネージャーの学校でも「スローガン(キャッチコピー)よりStatement/Manifestを書けるようになるといい=共有価値を想起させる拠り所となる言葉」ということを習ったなと思い出す。
(詳しくはこちら)
集まるといつも愚痴や誰かの悪口大会になってしまうような組織(コミュニティ)は生産性もないし、何かを前向きに進めていくことはできない。共通の敵がいることで生きやすくなっている部分はあるかもしれないけれど。笑
会話がムードをつくっていくのは仕事に限った話でもなく、納得感がある。
一貫性のあるメッセージによりモチベーションやチームワークは高く/強くも低く/弱くもなる。同じワードではなくても「軸」や「背骨」が一貫しているか、筋が通っているかは重要だと痛感している。
アウトプットが変わったとしても、一貫性のある人にはついていきたくなるし、応援したいと思うのだけど、目先のことに囚われて言うことがコロコロ変わってしまう人に従うのは結構難しいなと思っている。
とはいえ、何でも「言葉」をつくればいい訳でもない。つくり込みすぎた言葉に囚われて何を言っているか分からなくなる瞬間は、受け手・送り手の両方に生じ得る。
(ちょっと文脈は違うけど、以前読んだnoteがよかったのでシェア)
そして同じことを言うにしても、言い方や伝え方でコミュニケーションはgoodにもbadにもなり得る。
不遜な態度で損している後輩たちを嗜めている時期があり(当時は「ナチュラル失礼」という言葉を提唱していた笑)、根が悪い子たちじゃないのに誤解されてしまって勿体ないなと思っていた。他人事じゃなく、自分にもそんな状況はあると思う。
また、同じことを注意されるにしても言い方次第で、心から反省できることもあれば、傷ついたり反抗心しか生まれなかったりすることもある。
テキストコミュニケーションでも、(ベースは共感できたとしても)どこかネガティブで読後感のよくない言葉遣いだと感じる人とはすこし距離を置いてしまう。かと思えば、リアルと遜色ない対応で気持ちよく仕事をさせてくれる人も大勢いる。
自分も日々反省を重ねているけど、せっかくなら、いい組織/コミュニティをつくる一員でありたい。そして、そのための言葉の在り方を突き詰めていける人で在りたい。
頂いたサポートは自己研鑽のため有意義に使わせていただきます。Xでも繋がってください!
