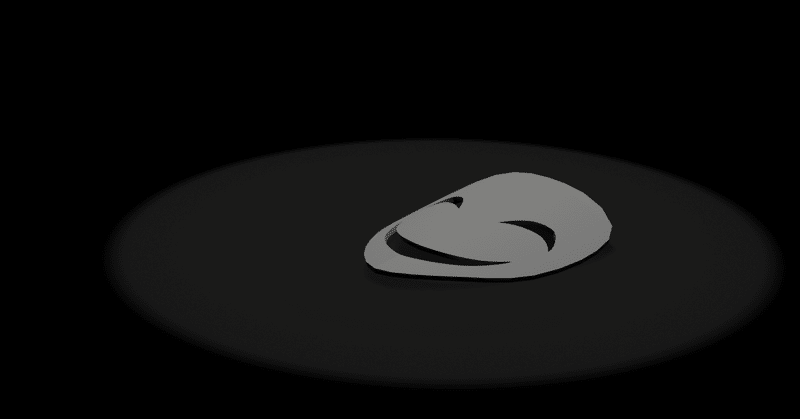
匿名マスク
スポットライトがあたった。真っ暗闇の中に、小さな光の円が縁取られた。ハッとして、ぼくは自分の置かれた状況を手探りに確認し始める。ここは、どこだ。手を伸ばす。何かに触れたいと思う願いもむなしく、手のひらはただ虚空を掴む。指先は何にも触れない。重い空気だけがその指の隙間から通り抜けていく。冷や汗が頰を伝う。ツーっという冷たい筋が、いやにはっきりと感じられる。そこにあるのは無音だ。無限遠まで広がる、しんとした静寂。何かが間違っていた。
その時、ふいにスポットライトの中へ何かが落ちてくる。カラン、カラン…カラン。闇の中にこだまする不吉な軽い音。何か仄白く光っている物体だ。地面にぶつかって跳ね回ったままとどまらない。それは平らな板状のものだった。物理法則の一挙手一投足に、ぼくの目は釘付けになる。ゴクリ、と唾を飲み込んだ音が、まるで遠い世界の出来事のように聴こえる。何かが起こるのを全身で待っていた。ぼくの身体は指先まで硬直して、ピクリとも動かせなくなっていた。
仮面だ。そう気づいた途端、強迫観念となった「仮面」の二文字が頭をぐるぐる駆け巡る。白い仮面。その白さは妖艶な怪しさを湛えている。目と口は細長く引き伸ばした三日月のように鋭い。口角は上がり、目尻は下がっていて、ニヤッとしたその表情は、どこも見つめてはいない。しかしその視線は、どういうわけか周囲の気温をグッと下げたような気がする。頰がスーッとした。ここは、どこだ。声に出さないまま、ぼくは自分の外部に再び問いかける。
突然、全身に衝撃が走る。反射的に、目を強く瞑り、手で耳を抑え小さく縮こまった。コンクリートの塊で全身を殴りつけられたような衝撃が、身体の芯で響いている。と、同時に、ぼくはそれが物理的な衝撃ではなかったことに気づく。音だ。古くなったピアノがあげる断末魔の叫びのような、様々な音階が入り混じった強くて大きい音の波が、ぼくを襲ったのだ。そう気づいて、顔をあげると、スポットライトの灯りは消えていた。音も消えている。周囲を見渡す。そこには闇があるだけだ。
*
…微かに音が聴こえる。小さな音だ。耳の奥をくすぐる小さな音。カタカタという音が聴こえる。暗闇のずっと向こうの方で実体を持った何かが動いているのだ。この音はどこから聴こえるのだろう。そう思って、再び目を閉じ、耳に精神を集中する。少しずつ音の輪郭がくっきりとつかめてくる。慣れてきたのだ、と思ったが、それはどうやら違うようだった。次第に音が大きくなっているのだ。それはどこかある場所から聴こえてくるのではない。あらゆる方向から聴こえてくるのだ。慌てて目を開ける。空間のあちこちに浮いた無数の白い塊が、それぞれの場所で蠢いている。
仮面だ。ぼくはまたしても気づく。ぼくは今仮面に囲まれているのだ。全て同じ顔をした仮面たちは、何かを嘲笑うように小刻みに震えていた。その震えは空間を揺らし、カタカタというリズムを重層的に奏でていた。一つ一つの仮面は、それぞれ思いのままの方向を向いている。じっと目を凝らしていると、いくつかは割り当てられた場所から離れ、この暗闇の中を動き回っているようだった。
ふわふわと浮いた仮面が、すぐ目の前を漂い流れていく。ぼくは自分がなぜかホッとしていることに気づく。無数のカタカタ音は一定のリズムを刻んでいる。仮面たちは、ぼくのことを少しも気にかけていない。そこには感情というものがなかった。ただ「穴」のような、表面的な欠落感だけがその場に充満していた。匿名性の中に埋もれることに、ぼくは安心感を感じていたのだ。
しかしその時間は長くは続かない。全ての仮面がピタッと動きを止める。無重力が全てを支配し始める。目の前の仮面だけが、何かを思い出したように、ゆっくりと回転し始めた。そうして彼はぼくの方をまっすぐに見つめる。身体中の毛が逆立つような、不気味なゾクゾク感が身体を走った。全ての仮面が回転を始める。標的は、ぼくだ。表面的な欠落感は、今や攻撃的な視線となって、ぼくを見つめる。匿名性がぼくを刺そうとしていた。
急に喉の奥から笑いが込み上げてくる。ぼくは口元でそれを必死に抑えるが、どうにもならない。笑いが来る。笑いが来る。笑いが来る。
気づくと、ぼくは仮面を被っている。もう頰に汗は伝わっていない。無数の仮面たちは、またそれぞれの方向を向いて、それぞれのカタカタ音を鳴らし始める。それぞれの仮面は厭世的な嘲笑を浮かべていて、それがぼくには心地良い。もうどこにも行きたくはない。ずっとここにいたい。もう誰もぼくのことを見てはいないのだ。世界とぼくとの境界は、暗闇の中で曖昧に溶け始める。心地良い。このまま笑いと共に最後の一滴まで世界と一体になりたい。
*
頭の中で何かがピンと弾けた。いや、何かが突き刺したのだ。誰かがこちらを見ている。仮面は未だそれぞれ勝手な方向を向いている。「誰だ」とぼくは問う。それは答えない。でもぼくにはわかっているのだ。澄んだ青い瞳が、ぼくに哀れみを向けていることを。全てを見抜いていることを。
ぼくの中の純粋な部分は、汚れきることを求めている。どうしようもないガラクタの中に埋没することを求めている。しかしその瞳は、それを認めない。認めないまま、どうもしない。ぼくの被った仮面から涙が落ちる。仮面は剥がそうと、自分の顔に手を伸ばす。仮面は外れない。悲しみに任せて力一杯引っ張る。仮面は外れない。仮面に爪を立てる。爪から血が出るまで引っ掻き続ける。しかし傷一つ、爪痕一つ残すことはできない。もう後戻りはできない。その現実だけが徐々に染み込んでくる。
そう。ぼくは無数の仮面に囲まれていた。
そして、ひとりだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
