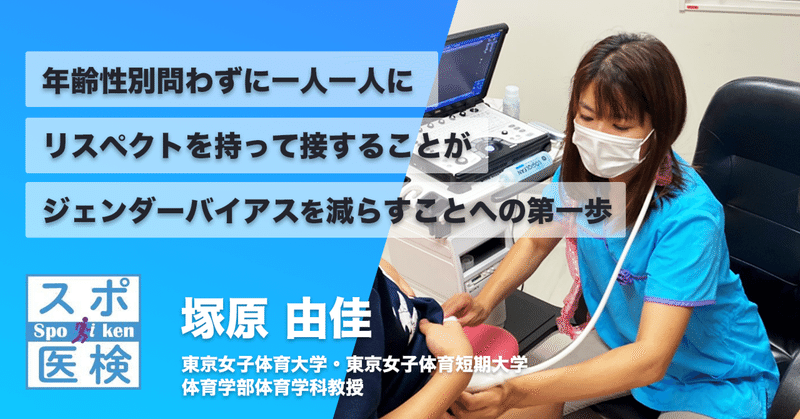
年齢性別問わずに一人一人にリスペクトを持って接することがジェンダーバイアスを減らすことへの第一歩
塚原由佳 東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 体育学部体育学科教授

塚原由佳先生は整形外科医として選手をサポートしながら、女性アスリートの戦略的強化の研究やジェンダー問題に積極的に取り組んでいる。ジェンダー問題に取り組むきっかけは「競技指導者からの“女子選手は〇〇だから”という発言が多かったこと。そしてどうしても自分が医師として、他の男性医師との扱いが異なるように感じること」と話してくださった。「女性の先生でしょうから、アメフトなんかわからないでしょう」や「自分だけ“塚原先生”ではなく、“塚原さん”だった」ことなど、なにげなく投げかけられる言葉から見えてくる根底にあるものは何か。今回は、自分でも知らず知らずにバイアスがかかっていないか、考えさせられ、気づかされることの多いインタビューとなった。
――陸上競技のみならず、多くのスポーツのサポートをされている塚原由佳先生ですが、はじめに先生ご自身とスポーツの関わりを教えていただけますか。
塚原由佳(以下塚原):私は選手として陸上競技をやっていました。専門種目は400ハードルで、高校時代からも県で3位には入っていました。さらに名古屋市立大学に進学してからも、グッと成績が伸びまして、日本選手権や全日本インカレなどで出場できるまでになりました。
記録も高校のときに比べると大幅に伸びたのですが、大学時代はどうすれば速くなれるのかを自分で考えて、自分で取り組んできたのです。それと同時に、高校時代は私より速かった選手が故障をしてしまって、記録を落としてしまっているケースもありました。
自分のように記録を伸ばす選手もいれば、故障によって記録が低迷してしまう人もいる。そういう選手たちを見ているなかで、自然と医学のなかでも整形外科に興味を持ち、そして「スポーツに関わる道に進もうかな」と思うようになっていました。
――ご自身の経験から、スポーツ医科学の道に進もうと思われたのですね。
塚原:はい。それで、研修医をやっているときに、スポーツ医科学界の第一人者である福林徹先生と出会って学ばせていただくなかで、どんどんスポーツ界に関わらせていただくようになりました。
最初は女子サッカーから関わったのですが、その後、日本陸上競技連盟の医事委員会に入らせていただいて、それから陸上競技選手たち、おもに女子選手を中心にサポートしています。
陸上競技の場合、女性アスリートは高校時代に活躍しても大学進学後に伸び悩む、という選手が散見されます。逆に男子は伸びる選手が多い。なぜ女子選手は伸びないのか、というところに興味が出てきました。コーチング環境なども関係があるのかな、と考え始めたところで、スポーツ科学の世界に足を踏み入れました。

陸上競技女子選手たちを中心にサポートを行っている
――これまで研究を続けられたなかで、先生が疑問に感じられていた点について、何か見つけたものはありますか。

(市内マラソンのサポート)
塚原:よく言われるのは、「体形が変わるから」ということですよね。確かに体脂肪率が上がる選手はいますし、体形に変化がある選手もいます。ただ、アメリカ留学したときに行った研究で、アメリカのアスリートにも体組成に調べてみました。実は同レベルの選手で比較した場合、日本人選手よりもアメリカ人選手のほうが体脂肪率も高いし、食事制限などもしていない選手も多いという結果でした。でも、きちんと試合で力を発揮する選手はたくさんいます。
――実は体形の問題ではなかったのですね。
塚原:体型が全く関係がないとは思いません。ただこだわり過ぎても仕方ないのかなと。その代わりというわけではないですが、私が見てきたアメリカの女性アスリートたちは、みんな自分の意見をコーチたちにはっきり言うところが素敵だなと感じました。
――なるほど。体形だけでない男女の違い、というものもあるのですね。そういったなかで、近年ジェンダーに対する問題提起が多くなされるようになってきました。塚原先生もジェンダーに関する論文を発表されています。ぜひ、スポーツ界におけるジェンダーの問題点等についてお話いただけますか?
塚原:そうですね、スポーツ界にも男子選手と女子選手の扱いの差は多々見られますが、医師の世界でも男女の差というものは歴然としたものがあります。たとえば、二人の医師が目の前にいるとします。ひとりは私、もう一人は男性の先生。そうすると、私は『塚原さん』なのですが、男性の先生のほうは『○○先生』なんです。これは結構“あるある”なんです。もちろん私も先生と呼ばれたいわけでもないですし、「塚原さん」でも全然良いんです。問題なのは、男性と並んだときに、なぜ呼び方が変わってしまうのか、です。そしてそれを指摘すると、“親しみやすいってことだよ”と論点がすり代わり、“面倒くさい人”というレッテルが貼られかねないことです。
あとよくあるのは、海外遠征などに帯同したとき「お母さんみたいで男子選手も甘えられて良いよね」と言われること。それが嫌だとかやめてほしいという問題なのではなく、男性医師が帯同したときに「お父さんみたいで選手も甘えられて良いよね」などという話は出ませんよね。そういうところで、男性である、女性であるというバイアスを持つのではなく、大切なことはプロフェッショナルなドクターであること。そこに性別は関係ないですよね、というところなのです。

――とても良くわかります。たとえばですが、“ママさんアスリート”とは言われますけど、“パパさんアスリート”ってあまり言われないですよね。
塚原:そうなのです。もちろん出産は一大イベントなどのそれを乗り越えた女子選手には敬意を払うべきだと思います。しかし男性アスリートだって、練習してきついなか、子育てを一緒に頑張っている選手もいるはずなのです。そういう男性アスリートの努力は取り沙汰されることなく、女性アスリートの、“ママさん”というところだけが取り上げられること、また女子選手が結婚したら“妊娠はしていません”というフレーズが報道の文章で入ることが多いのは、やはり変だなと感じるところですよね。
――選手たちのメディアでの取り上げられ方も、もっと考えなければなりませんね。
塚原:どの競技でもありますけど、“美人すぎるアスリート”とか言ってマスコミが取り上げますよね。海外ではそういうルックスを中心とした取り上げられ方というのは減ってきているにも関わらず、日本はやはりそういう記事が多い、というのはまだまだ考えなければならないところなのかな、と感じます。そういう記事がもっと減っていくと良いな、と思います。
――そういう言葉がなくなっていくと、感じ方や考え方も変わっていくのかもしれませんね。
塚原:そうですよね。たとえば「女医」という言い方もそうですよね。「男医」という言葉はありませんものね。
ただ、今は少しずつ変わり始めているのかな、とも感じています。若いアスリートや若い人たちは、少しずつ男女の差というものがなくなっているように感じています。その理由のひとつが、先入観だと思います。
たとえばこういう話があります。
ある男の子とそのお父さんが事故に遭いました。お父さんはその場で死亡が確認されましたが、男の子は手術を要するため病院に運び込まれました。海外の多くでは親族は手術をしない、という決まりがあるのですが、男の子を担当した外科医の先生が「その男の子は自分の息子だから手術ができない」と言いました。
この話に何か違和感はありますか?お父さんは死んだはずなのに、なぜ外科医としてまた登場したのか、疑問に思った人はいませんか?
この外科医の先生が男の子のお母さんだった、または同性婚という可能性を考えていたかどうかという話なのですが、答えられない人もたくさんいるのです。なぜかと言うと“外科医は男性”という先入観があるからです。その先入観が強いと、先ほどのお話が良くわからなくなってしまいます。
今、私は東京女子体育大学で指導していますが、そこでは半分くらいの学生が「外科医がお母さんだった」という答えに辿り着きました。残りの半分の学生はその子が誘拐されていた、という発想でした。それはなぜかと言うと、学生たちの近くにいる外科医が私だから、彼女らには“外科医は男性”という先入観がないのです。
これはひとつの例ですけど、やはり先入観というのは大きくて、今の日本はまだまだ男性像、女性像というものの先入観が強いのかもしれません。
——―なるほど、とても良くわかります。それが少しずつ変わってきている、というのであれば、変わってきた子どもたちの周りにいる大人も変わっていかなければならないのかもしれませんね。
塚原:そうですね、コーチたちは「そういうのは女々しい」とか「男勝りだ」とか、そういう言葉は使うべきではないですね。
――そういう指導者の人たちが先入観をなくしていく、ということが大切なことですね。
塚原:やはり選手にとって、コーチを含め、特に年齢が上であった場合はそのような人の存在はとても大きいと感じています。そういう意味でも、指導者含め、我々、選手をサポートする立場の者が勉強し続け、考え方をアップデートしていく環境というのは大事なのだと思います。
日本でももっと選手が指導者を含めたサポートスタッフに対して自分の思いや考え方、意見をしっかり言えるような環境になっていくことも、ジェンダーバイアスを減らすひとつの方法なのではないかと思っています。
――あらためて、スポーツ界に関わる人たち全員でジェンダーの問題に対して向き合っていく必要があると感じます。最後になりましたが、このジェンダーの問題に対して取り組む人たちに向けて、先生からメッセージをいただけますか?
塚原:そうですね、女性アスリートというところに関して言えば、今の日本の女性アスリートは、もっと自信をもって欲しいと思っています。素晴らしいアスリートはたくさんいます。しかしながら昔ながらの“出る杭は打たれる”環境もいまだに根強いこともあってでしょうか、自分の意見を自信をもって言える選手が少ない気がします。これはアスリートに限らず、医師の場合も顕著で、優秀な女性医師であっても、チャレンジングな課題を与えられた時に私にそれができるかと、自分の能力を疑問視してしまうことが多いと感じています。ただその背景には、男性と女性医師が同じように扱われていないことも背景にあると思います。
先日『British journal of sports medicine』という雑誌に、私がアメリカの医師とともに手がけた「Gender bias in sports medicine」というテーマの論文が掲載されました。51カ国のスポーツドクターに対してアンケートを配布した結果、女性医師は男性医師と比較して、男女のアスリート・コーチ・学年が上の医師・アスレチックトレーナーから敬意に欠ける態度をとられていたり、女性というだけで医学的判断を疑問視されていたことがわかりました。このようなことが積み重なると自信を失うきっかけになります。そしてどんどん意見が言えなくなります。私もそうでした。ただ、年齢や経験を重ねて少しずつ言えるにようになったことで、若い方など、なかなか言いにくい方の意見を代わりに発信していけたらなと思っております。
特にパワーバランス的に選手よりも上になりやすい指導者が、何かバイアスを持って選手に接するのではなく、きちんと選手それぞれのことを理解して指導していくことが大切なのではないでしょうか。
――本日はとても勉強になりました。長い時間ありがとうございました!
<編集後記>
ジェンダー問題は、五輪を契機にさまざまなところで考えられるようになってきました。塚原先生のお話をおうかがいし感じたことは、このジェンダー問題を考えることは、スポーツ界をもっと良くする大きなきっかけになる、ということです。問題に対して取り組む、という言い方をすると、何かマイナスをゼロにするような印象がありますが、そうではなく、ジェンダー問題の解決が、スポーツ界をさらに発展させることにつながると考えて、前向きに取り組んで行きたいと思いました。
◇プロフィール◇

塚原由佳(つかはら・ゆか)
東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 体育学部体育学科教授。 名古屋市立大学医学部医学科卒。大学時代には400mハードルで全日本インカレ、日本選手権などで活躍。卒業後はスポーツ科学の世界に携わり、整形外科医として陸上競技を中心にさまざまな女性アスリートをサポートしてきた。2021年の東京五輪では選手村で整形外科部門に勤務。今も陸上競技をはじめとするアスリートのサポートを続けると同時に、 ”Gender bias in sports medicine”というタイトルの論文をBritish Journal of Sports Medicineに発表するなど、ジェンダー問題にも積極的に取り組む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
