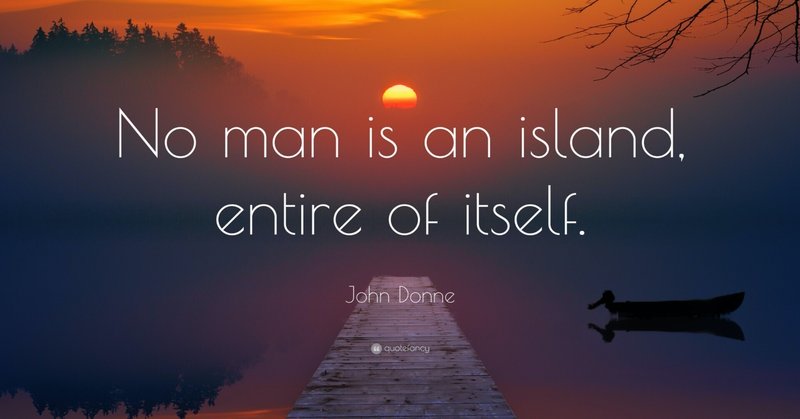
【創作大賞応募作】 ロックダウン・ラヴ (Lockdown Love) 《その一》
<1>ラヴ・ロスト Love Lost
「君は一緒にいるだけで楽しいっていう、でも、僕には何か違うんだ」
最初は戸惑い、信じられずにおどけて、驚いたふりをして見せる。「ちょっと冗談だよね」スマイルを可愛らしく、それからおどけてヘラヘラとしてみせる。
この言葉を発した、視線を斜め下に落としている彼の横顔に笑みは浮かばない。その目は沙月を見ていない。
去ってゆく彼の後ろ姿はまるで映画の一シーン。沙月の目にはスローモーションの映像のようだった。
カフェテリアに一人取り残された沙月は、最後の言葉を反芻する。昼下がり、数刻前には埋め尽くされていた客席は寂しげで、歓談を楽しんでいた賑やかな女性客の一群や、カップルらしい二人連れの男女の残していったマグカップなどが今もなお、テーブルには置かれたままになっている。
恋の翼を羽ばたかせて、天に輝く太陽までも、光が届く最も遠い世界の果てまでも、二人で飛んで行けるのだと信じていた。今朝も香坂康介に逢いたくて逢いたくて待ちきれなくて、待ち合わせの時間の25分も前にいつも座る窓際の、二人で向かい合えるこの場所で待ち続けていた。
なんだかいつもよりも深刻な顔の香坂は、話したいことがあふれ出て仕方がない沙月の話を無理やりさえぎって、別れ話を切り出したのはほんの数分前のこと。沙月の向かいの席の香坂の残像は消えて、彼がもうそこにはいないという事実だけが、目に見えない壁のように聳え立っている。
別れを告げる香坂の言葉の一つ一つに、沙月の心はロックアップされてゆき、穢れを知らぬ純潔の翼は、生気を失って崩れ落ち、土くれとなった残骸は白い塵となって風に吹かれて雲散霧消する。飛ぶことに慣れ過ぎたがために、浮力を失った心は、二つの足を歩ませようにも、歩き方を忘れてしまっている。香坂の姿は、もはやどこにもない。
立ち上がろうとするが、鉛となった心はあまりにも重く、一歩たりとも前に足を踏み出すことさえままならない。
会計は済ませられているようで、カフェテリアの入り口の女性店員は、血の気を失った蒼白な沙織を、明るく送り出す。
「ありがとうございました」。
足枷をはめられた徒刑囚の重い足取りで、モノレールの駅に辿り着く。
定期券をスキャンして、列車を待つ。それから先は、何も覚えていない。
最後の記憶は「僕には何か違うんだ」という言葉を残して去った、彼の残像ばかり。いや、そのような記憶が、かつて実際に存在していたのかすらも、不確かだ。
鍵を回して家のドアを開く。「ただいま」も言わずにシャワーを浴びる。
降り注ぐ冷たい液体も一向に気にならない。
沙月ははじめ、抵抗した。
どうして自分が捨てられないといけないのかという憤りを抑えきれずに、混乱した頭の中で、何がいけなかったのかを考えた。自分のどこに落ち度があったのかと思いを巡らせる。優しかった頃の彼の姿と言葉がよみがえる。自分に対してかけてくれた優しい言葉は、彼の最後の残した冷たいシャワーのような言葉によって相殺されてしまう。
ようやく涙が溢れてきて、むき出しの乳房を伝うシャワーには、苦い悲しみが入り混じる。鉛となった胸の内は、収縮して、重く、きつく締め付ける。シャワーの音だけが浴室には響いている。嗚咽はシャワーの音が抹消する。こうして沙月は、ある冬の日の昼下がりに、本当の恋だと信じていた、初めての恋を失った。
<2>そうだよね Isn't he?
外国からの報道も、心を閉ざした沙月の耳には入らない。
中国の武漢から発生した謎の伝染病のために、都市封鎖する街が世界中で増殖して行く中、沙月は彼女自身をロックダウンした。
沙月の住む北大阪の地方都市にも、非常事態宣言の発令が伝えられ、沙月の通う大学もまた、授業はオンライン空間へと移行した。
パソコンを持たない沙月は古いタブレット端末で、外界と彼女とを繋ぐ連絡網を辛うじて維持したが、一番大切だったパーソナルネットワークは相手側からの一方的な遮断によって失われている。友人や妹らから時々届くメッセージも、灰色に霞んで、もはや判別できなかった。しようともしたいとも思えなかった。
香坂とのパーソナルネットワークが本当に遮断されてしまったのかを確かめたくても、残酷な現実を認めたくなくはない。過去のメッセージやメイルをいつまでも読み返してみる沙月は、最後のメッセージのあとには、永遠に沈黙する文字が幾つも並んでいるようにしか見えなかった。
沙月のスマホの通知画面には、クラスメートたちからのメッセージが幾つも届いている。妹の弥生からのチャットメールも既読スルーする。音信不通になった沙月のことを心配して大学の誰かが電話してきても、着信拒否を決め込んだ。
香坂が別の女子学生と会っているなどと伝えるメイルがクラスメートの日葵から送られてきたならば、死んでしまいたくなる。何も聞きたくないし、見たくもない。沙月はスマホの電源を切り、外界との接触を一切遮断した。
完全ロックダウンした沙月。本当に独りになる。誰一人訪ねてこない沙月の狭い部屋は光りなき暗い心の牢獄になる。
一人で泣いた。あまりに悲しいと涙が出てこない。心が動かない。全てが閉じて、締め付けられた心は肉体的な欲求を拒否してしまう。固形物は喉を通らない。水だけを飲んだ。涙も出ないけれども、泣いていた。
青い空の向こう、白い雲の余りの眩しさに、沙月の口からは何度も深い溜息が零れ出た。おもわず漏れた、目に見えない幽かな吐息は、宙に舞い上がり、あの空の彼方へと吸い上げられて白い雲の一部になるのだと、遠い目をした少女は寂しげにひとり呟く。
声がまだ出る事さえ不思議なほどに、もう長い間誰とも言葉を交わしていない。同居している母はもう何日も見えない。ここにはもう誰もいない。何も食べたくない。何も飲みたくもない。息さえもしていたくない。
何もすることのない沙月は、時々古い本を手に取るも、言葉は頭に入らない。大好きだった東村アキコの漫画も元気にはしてくれない。慰めを求めて共感誘うかもしれない歌ばかりを聞いてみる。aikoの『えりあし』とかHYの『NAO』や『366日』とか。「あなたに逢いたい」とかそんな言葉を聞いただけで涙が溢れてくる。
失恋の歌なんて山ほどある。母が好きだった古い歌、岡本真夜の『Alone』を見つけて聞いてみる。沙月の彼氏は誰か別の女性に奪われたのではなく、彼はわたしの人格を否定して、わたしの前から姿を消したのだ。「たぶんそうだ」。そう思えば思うほど、我が身の情けなさに心の鎧の重みは増した。
YouTubeでラップを探す。かつては心地良かった英語のリズムも、足枷をひきずる沙月の心には追いつけない。恋の翼に羽ばたいていた頃の自分には、この前のめりのビートさえももどかしかったのに、ラップのビートもやがて沙月の心には一切届かなくなる。
知らず知らず、心の動画を再生する。たくさんの思い出が、沙月の心には未整理のまま蓄えられている。
再生される動画。大学の近代的レクチャーシアター。つまり大きな視聴覚室だ。英文学のある初夏の日の講義。鮮明な映像。
「 ...若い頃に書いた官能的な恋愛詩とは全く違った作風の、
深い瞑想や思索にあふれる言葉を、
宗教者となったジョン・ダンは晩年に書き遺した...
瞑想録がもっともよく知られている。
その中の17番目のものは、特によく知られている...
まあこの人はほとんどあのウィリアム・シェイクスピアと同じ時代の人や。
生い立ちとかぜんぜん違うんやけど。」
途中から土地の言葉に変えて、森准教授はダンの英詩の書かれた時代を説明する。詩が朗誦される。准教授の英語はネイティブに近い響きを持つ、延びる音にRのない、リエゾンのほとんどない、古風だが、分かりやすいイギリス英語だ。
No man is an Island, entire of it self
every man is a piece of the continent, a part of the main
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less,
as well as if a promontory were,
as well as if a manor of thy friends
or of thine own were
Any man's death diminishes me, because I am involved in Mankind
And therefore never send to know
for whom the bell tolls;
it tolls for thee.
レクチャーシアターには30人ほどの学生。学生たちの間には程よく空間が作られていて、沙月と香坂は教室の上と下の対角線上の反対側に座っている。円形劇場のように後方の席は上段にある。
沙月は授業をいつも見下ろしている。香坂は准教授から最も近い席となる、最前列の右側に一人でいつも座る。
詩の朗読が終わると、准教授は訳してみろと教室中の学生を見回す。誰もが自信なさげに准教授とは目を合わせようとはしないが、沙月の隣に座っていた日葵がやってみると言い出す。
「どんな人も孤島ではなく、
だれもが大陸の一部であり、全体の一部であり、
その一部が海の波で削り取られても、ヨーロッパは小さくなり、
岬や友人の土地やあなたの土地もなくなってしまう。
誰かの死も自分をすり減らしてしまう、
えー、
自分も人類と関係があるから。
自分も人だから。
だから、知ろうとするな、
誰がために鐘は鳴るかを、
あなたのためになるのだから」
学生らは女子学生の訳に感心したのか、拍手をして彼女の勇気ある挑戦を褒め称えた。准教授は
「ここに来る前にネットで調べてきてへんか、
『誰がために鐘は鳴る』って
映画のタイトルそのまんまやないか」
と冗談めかしていう。
わざとらしく笑いをとろうとしていることは明白だが、そんな森準教授に対して、教室は大きな笑いに包まれる。
「逐語訳で全然面白みのない訳やけど、意味は分かる。まあ模範日本語訳は自分らで勝手にネットで調べといてくれ。あんまりに有名やから、いろんな翻訳者の訳がみつかるわ…
詩の翻訳っていうのはやな、
訳してしまったら死んでしまうんや。詩の魂やな。アメリカの詩人のローバト・フロストは
Poetry is what get lost in translation
やっていうてはるわ。意味わかるか。『Lost in Translation』って、名作ゴッドファーザーのコッポラ監督の娘さんの作った映画、知っとるかあ?…
詩というものは翻訳されると詩情を失くしてしまうから、翻訳する人は、なくなってしまったたいせつなものを意訳して補うてやらんといかんのや。英語やないけど、カール・ブッセってドイツの詩人の、「山のあなたの空遠く」って上田敏の訳は凄い、原文のある言葉を削って
元のドイツ詩以上の日本語の詩を書いたりしてる… 」
森准教授の授業は関西弁で難しい英詩を読む解くことに定評がある。先生は教室の一番奥まで届く深い声で、自分自身の訳で詩を読み上げる。
「誰も一人ぼっちの島なんかやない
みんなつながってる
誰もが世界の一部で、誰もが掛け替えのないもの
波に削られて、どんどんちいさくなってゆく
海に突き出てる岬も、
友達とか居るところもあんたのいるところも
どんな人であっても
いなくなってしもうたら悲しいねん
みんな同じ、人なんやから
でも無理に知ろうとせんでええ
弔いの鐘がだれのために響いているのだとか
みんなだれもが同じなんやから、
あなたのためにも鳴るんやから」
森準教授のユーモラスな訳をクスクスと笑い出す学生も少なくない。翻訳されて足りない詩情は関西弁で補われたか。先生の言葉を聞かずに、スマホをいじったりしている学生の姿も、沙月の位置からはよく見える。
微笑みを浮かべることもなく、関西弁の朗誦詩人を射抜くような鋭いまなざしで見つめている男子学生の横顔が沙月の目に入る。
印象的なまなざしはどこか異国風で、最後には笑いに包まれた蒸し暑い教室のなかで、彼の周りにだけは違う空気が漂っていた。独りだけ他の学生たちの哄笑に和せぬ、無表情で生真面目な男子の、清涼たる空気。沙月は教室の向こうの遠い清涼な空気に触れた思いを抱いた。No one is an island, isn't he?
そう英語で呟いてみる。
<3>プレイバック Playback
教室の一番上の左の隅の席からわたしが見つめているのは、斜め下向かいのいつも同じ席に座る男子生徒。
別の動画。教室の後ろの方から正面のスクリーンを見ないで、彼ばかりを見つめている。そしてまた、じぃッと見つめている。彼は意識しているのかもしれない、わたしの視線を。彼に気づかれたのか、こちらの方をちらりと見る。わたしは視線を落とす。
心の動画はいくつもいくつも再生されてゆく。
日葵と森先生が言い争っている。森先生は彼女がある授業を出席しなかったと言い張る。森先生は授業の出席日数に異常なほどに拘ることで知られている。どんなに優れたレポートやエッセイを提出しようとも、きちんと出席しない学生には決して及第点を与えない。
彼女は確かに出席したと涙声で弁明するが、授業に出席すると出席した者は教室の前に置かれた出席簿に名前を書いてゆくという非常に古いシステムをいまだに採用しているこのクラス。時々名前を書き忘れる生徒も出てくるはずだが、森先生はそうした理屈を一切認めようとしない。
泣き崩れそうな憐れな女子学生のもとに、意外な助け舟が送られる。
「彼女、たしかにちゃんと出席してましたよ、その日。オスカー・ワイルドのレクイエスタを読んだ日でしたよね。先生は小川さんに詩を読ませようとしたじゃないですか
Tread lightly, she is near、
Under the snow,
Speak gently, she can hear、
The daisies grow
っていうやつですよ」
森先生はそうだったかなと首をひねるが、「まあ香坂がそういうんやったらそうなんやろうなあ」と日葵の出席をしぶしぶ認める。
助けられた女子生徒は、香坂の騎士的な行いに感動して丁重に礼を述べるが、ニヒルなクラスメートはどうってことないよと言う風に、蕭々と教室をひとりあとにする。上の方からからすべてを見ていた沙月は「イケメンやわあ」と心の中でつぶやいた。
「ヒマリ、よかったなあ、すごいな香坂君、あの森先生にええって言わせるなんてなあ、でもかっこつけてんなあ。あんたのこと意識してるとか。でもなんて詩暗誦したん、わたしは全然わからんかったわ」
「えー、カッコつけとったわりには、カタカタ英語やったけど」
奇声を上げて喜び合うクラスメートたちをよそに、沙月はその輪には加わらずにクラスメートたちを眺めている。
胸の奥があたたかになる。香坂をずっと見ていた自分の正しさを証明されたようで嬉しくて、まだ口さえもきいたことのない横顔だけしか見ていない香坂に夢中になる。もう一方の横顔に隠された香坂を見た日として、この日を香坂に恋に落ちた日なのだと決めた。動画ファイルにはSir_Knight_Kosukeと名前を付ける。
<4>王様の耳はロバの耳 Can't keep a secret
胸の疼きは収まらない。
春になり、新学期となるが、リモートとなった大学の授業。オンライン授業は、どこからでも、どのような端末からでも出席できるようになっている。誰も沙月が外に出て人と逢わないことをとがめない。誰もが引きこもりとなって、表面上は沙月もまた、世界中に生み出された無数の引きこもりの一人でしかない。
自発的にロックダウンしたつもりでも、世界中が彼女と同じくロックダウンしてゆくとは、なんという運命のいたずらなのか。神様は重い心を抱えた沙月をまったく特別扱いしてくれない。想いの深さの余りに、美しい愛を失った、悲劇的なヒロインのようでありたくもあったのに。だれも沙月のロックダウンを特別視しないし、だれも沙月の閉ざされた心の意味を知ることはない。
オンラインでの受講は顔見せでなくてはならないものと、顔見せでなくてもいいものがある。英文学科の英詩のクラスの森準教授は顔見せを全ての学生に強要はしなかった。相変わらず出席簿はしっかりとる律儀な先生なのだが、顔見せしていないと、黒い画面の向こうで何をしているのかは誰にもわからない。あなたが犬であろうが、素っ裸だろうが、誰にもわかることはない。
ほとんど下着でまともに着衣せず、乱れた髪の沙月は、ベッドの上に寝転がり、タブレットを開いて講義を聞き流す。ノーブラのタンクトップのしどけない姿で「いつから香坂くんにあんな風に思われていたのだろうか」とまた同じことを思い起こす。初めて手を繋いでくれた日のことを。初めて二人だけで映画を見た時のことを。そして最後の言葉…
森先生の言葉が耳元をそよ風であるかのように流れてゆく。羽音が聞こえてくる。わたしは枯れ果ててゆく花で、花粉を集めて回るマルハナバチにさえも相手にもされはしない。Eternal Oblivion(永遠の忘却)という言葉が耳に届く。若くして自死したアメリカの女流詩人の言葉。
I am nude as a chicken neck, does nobody love me?
<なんにも持たない、よそ者のわたし、誰が愛してくれるというの?>
森先生のイギリス仕込み英語は流暢だが、アメリカの詩を読むにはアクセントが可笑しいとクラスメートの誰かが発言する。目をつむる。画面には小さな四角い長方形の枠がたくさん並んでいて、幾つかには見知った顔があるが、香坂の真っ黒な長方形のカメラはミュートのまま。わたしに遠慮してくれているの?と沙月は独りよがりな妄想をする。
沙月の長方形も黒い画面のまま。カメラには映したくはない。自分自身の姿を。食べることを拒んで、終には食べれなくなった沙月は痩せ衰えて骨と皮だけに変わり果てている。
母親ならば、そんな娘の姿を見ていられなくなるものなのだが、大人の階段を上り始めて、踏み外してまだ立ち上がることのできない娘は、母の差し出す手にさえもすがろうとはしない。
緊急事態宣言下の社会の中、食料品関係の母の仕事は在宅勤務にならないことが沙月には幸いだった。狭い家の中であの母と四六時中同じ空気を吸ってはいたくない。母のいない小さな家は沙月の城だ。
何が駄目だったのかを今でも考えている。楽しかった時のことを再生する。二人が無邪気に戯れる事の出来たあの頃に帰りたい。再生される心の動画の中の香坂はいつだって過去のもの。何度も再生された過去動画はいつしかセピア色を帯びてゆく。懐かしい色に変容して行く沙月の心の映像は次第に魅力を失ってゆく。そんな過去動画はフォルダーから削除したつもりでも、自己増幅するファイルは沙月の心のハードドライヴを埋め尽くして、もはや新しい映像を保存保管するスペースの余裕さえない。
あふれかえる記憶を消去するただ一つの方法は、だれかにファイルをシェアすることだ。共有されることで、もはや唯一無二の価値は失われて、いつしか消えてはしまわないだろうか。
久しぶりにスマホを手に取る。充電ケーブルにつなぎっぱなしだったスマホには、妹に電話するに十分の電力は蓄えられている。数か月ぶりに一つ年下の父親の家に暮らす妹に電話する。スマホの画面には妹の名前と二人が子供の頃に買っていた小さな犬の写真が浮かび上がる。
「トゥルルー、トゥルルー、トゥルルー」
四度目が鳴ろうとしたところで、懐かしい弥生の声が耳元に響く。
<小説つづき>
ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。
