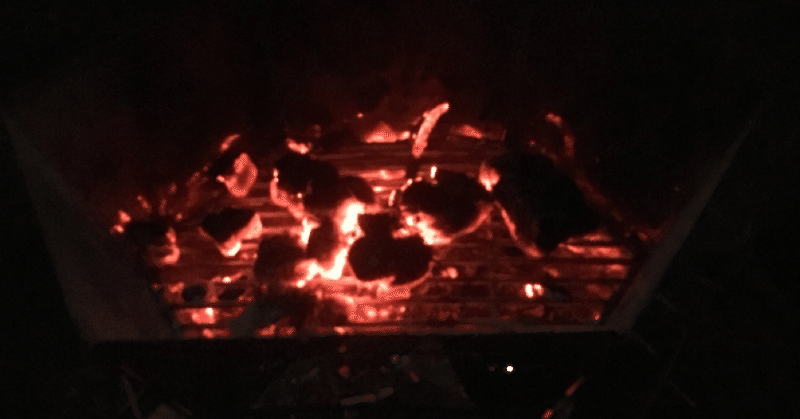
「書く」ということ
僕にとって作文の時間は、とても気が重いものだった。
集中力が続かないとか、原稿用紙のひとマスに収まるよう字を書くのが難しいとか、理由を考えるときりがない。
「読む」ということは、昔から好きだ。
小学生の頃は、「読む」ということの正に虜だった。絵本でも、スーパー戦隊の写真が載っている雑誌でも、漫画でも、少し難しい百科事典でも、活字しか載っていない児童文学でも、ホールケーキにかぶりつくようにして、読み漁ったものだ。
何でも買ってもらえるというほど裕福な家庭でもなかったけれど、書籍だけは、どんなジャンルでも、お願いするとだいたい買ってもらえた。とても恵まれていたのだな、と今になって思う。
物心つく前からそんな環境で育っていたからか、同年代と比べて語彙も多かったような気がするし、文章を読むことに対する苦手意識もなかった。
ただ、自分の考えを「書く」という課題が出され始めたころ、読むことすらひどく億劫に感じられるようになった。
僕は、与えられた課題の中で、特段なにか書きたいことがあるような人間ではなかった。
あえて「書く」という手段を取ってまで、僕に、伝えたいと思うことがなかった、というべきだろうか。
自分の考えがないというタイプではけしてない。むしろ、僕という人間は、悪い意味で自分の意思が強く、妙な美学を持ち、それにがんじがらめになっているとさえ思う。
しかし、僕は、「書く」という表現技法を用いる以上、なにか壮大な大義名分が必要なのではないか、と真面目に考えていた。下らないことは書けないというプレッシャー。自分の意思、美学なんて、どれだけちっぽけなものだろう。まして、日々の回想など、とても書けやしない。
何を書くべきかは、評価する人の目線を気にしながら、大義名分を掲げやすいということを最も重視して選んだ。そこに自分の意見などない。どこかで見たことのあるような、テンプレートな解答文が出来上がる。
解答文の草稿が出来上がると、次はひとつひとつの文章それ自体が気になってくる。
導入の文章はどうするか、どこで句読点を打とうか、ひとつの言葉ばかり使っていないか、と言ったことを、センター試験の答案を何度も確認するかのごとく、慎重に慎重を期して見渡した。
そのようなわけで、僕にとって「書く」ことは、大変な重労働だった。
その結果かは分からないが、小学校から高校まで、国語はむしろ得意教科だった。大学でも、テストが壊滅的な中、レポートでは一定以上の評価をもらうことが多かった。
それでも、書いたものを見返すとき、僕はひどく憂鬱になる。
「書いたものが全く面白くない」「なぜこの表現をしたのだろう」「自分が書いたのに何を言っているのかわからない」「…何で思ってもいないことを書いたんだろう」
昨日、この文章を書いたのは、果たして自分だったのだろうかと訝しむことさえある。
それでも、僕には、たまらなく何かを書きたくなるときがある。
なにかを伝えたいとか、人の役に立ちたいとか、そんな高尚な大義名分を捨て去って。
ひどく下らない個人的なことを、巧拙など考えもせず(最低限人に読んでもらうための推敲はするけれど)、ただ、何かを書き殴る。
書くことは大変だと分かっているのに、精神的に多大な負荷を与えると分かっているのに、後に自分を否定する材料にすらなりえるのに。
それでも、無性に、人に何かしらの教訓を与えるでもない、「書きたい」というだけの独り善がりな欲求を解消するだけのものを書きたくなる。
僕にとって「書く」ということが何なのか、その輪郭さえつかめていない。
つかめていないけれど、どうやら、現在の僕には「書く」ということが必要らしいということは分かる。
僕は、「書く」ということを、とても神聖で清らかなもののように思っていたし、今でも思っている。
けれども、僕も大人になった。
もっと人間的で、生々しく、下らないことも、綺麗じゃないことも、矛盾したことも、「書く」ということは許してくれるのではないか、というような気もしている。
最大限に書くことを楽しむために、どんな文章を書いても許容される、あるいは自分が許容できる、ごちゃまぜの闇鍋のような場所があるといいな、と思っていた。
noteがどのような媒体なのか、未知数ではあるけれど、当分好きなことを書く場になったらいいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
