
物質世界の現実と心の世界の現実をつなぐ「トポス量子論」
「無人の山中で木が倒れたら音はするか?」
スピリチュアルな世界観は好きだが、「唯心論」にはどこか違和感を覚える。
「唯心論」とは、「客観的実在は存在せず、あなたが住んでいる宇宙は一人一人の心の中に映った現実にしか過ぎず、人の数だけ異なった宇宙が存在するんですよ」、という考え方。仏教における唯識派の思想は、たいていの場合そういった説明の仕方がされる。
だが、率直に言ってこれは嘘だと思う。嘘とは言わずとも、真理の一面しかついていない。
客観的実在を否定する「唯心論」(独我論)は、カントが代表する大陸系哲学者が好むタイプの思想でもある。悪く言えば、頭でっかち。何でも自分の頭(心?)の中で起きていることだと見なしたがる。客観的実在への到達可能性をバッサリ切って捨てた後で、あらゆる「真実」というものは、個人個人の相対的真理の間における合意によって形作られるものだとする。(ちなみにカントはヒュームのおかげで「独我論のまどろみから覚めた」とか言ってるけど、実際には全然独我論から目覚めてないじゃないですか、という批判も多い。)
我慢ならないのは、量子力学をもこの種の「唯心論」の根拠として利用されているという現代の状況だ。「観測者がいなければ物理量は存在しない」、つまり「無人の山中で木が倒れたら音はするか? いや、観測者がいなければ音は存在しない」といったやつだ。量子力学の用語ではこういった状況を「非実在性」と呼ぶ。
「観測するまでは確率的にしか存在しないけど、観測した瞬間に出現する」、こう言った説明はもっともらしく聞こえるけどどうも腑に落ちない。あまりにも人間中心主義、これだとコペルニクスが主張した天動説への逆戻りじゃあないですか?
つまり我々は現在、天文学における天動説は抜け出したけれど、もっと存在論的な意味では依然として天動説のままであるというのが実情なのだと思う。
ここに鋭い批判を加えるのが、哲学と物理学の世界における「新実在論(Neo Realism)」。哲学においては言葉はすぐに陳腐化して使い古されたものになるから、この「新実在論」という名前もVer2.0くらいのものらしいことは申し添えておくとして、この考え方は今哲学でかなり盛り上がっているらしい。カンタン・メイヤスーの「思弁的唯物論」やグレアム・ハーマンの「オブジェクト指向存在論」などがその代表格。(マルクス・ガブリエルをこの流派に加える人もいるが、彼の「世界は存在しない」論はメイヤスーが嫌悪する「相関主義」の域を出ていないように見えるのは私だけだろうか。)
メイヤスーらの主張は一言でまとめるとこういうこと。「客観的実在は実在するし、私たちはそれに到達することも可能だ。だが、その客観的実在のあり方は、私たちの想定するようなものではない」。その観点から、痛烈にカントを批判する。
分かったようでよくわからない。
ここで登場するのが、物理学における「新実在論」。量子論の基礎づけの一つのアイデアとして注目を集めている。
https://www.researchgate.net/publication/1904800_Topos_Theory_and_'Neo-Realist'_Quantum_Theory
相対性理論における革新というものは、空間を「多様体」として捉えた視点だった。正確に言えば、微分位相多様体として空間概念をアップデートした。そのことによってさまざまな説明が可能になったが、しかしその理論的範疇は、ペンローズによって「裸の特異点」の出現が避けられないことが証明されてからは限界が画された。つまり、この宇宙は「多様体」として記述し尽くそうとしてもどうしてもできない綻びがあることが証明されてしまった。
「多様体」という概念は「位相空間」という、人間が通常「空間」として想定するものを数学的に抽象化した「集合論」の考え方に根ざす。つまりそこでは、「点」とその集まりである「集合」が実在として想定されている。
ところが相対性理論が挫折した以上、私たちが想定する通常の「空間」の奥にある背後構造を探求し、そこに理論的解決を求めるしかない。それをグロタンディークという数学者が1956年に発見した。その名も「トポス」。
宇宙際タイヒミュラー理論で有名になった望月新一教授の師匠でもあるフランスの数学者・グロタンディークは、エッセーとも数学書ともあるいは社会学の文献とも取れるような得体の知れない書物「収穫と蒔いた種と:数学者の孤独な冒険」の中で、こう述べる。
つまり、位相空間において本当に考慮すべきなのは、その「点」や点からなる部分集合や点の間の近さなどの関係では全くなく、この空間の上の層と、これらが作るカテゴリーであるということです。
なんだかよくわからないが、グロタンディークは「点とその集まり」の空間をあらしめているのは、「その空間の上の層とカテゴリー」であると喝破した。これこそ、多様体という時空ナメクジのDNAである、と言ったところか。しかしだからと言ってすぐに、グロタンディークの考え方を物理に応用することができるかといえば、そう簡単にはいかない。
そこで登場したのが「トポス量子論」。量子力学を圏論的に捉え直すという動きが増えている中で、「位相空間上の層のなす圏(Wikipediaより)」としてのトポスを、量子論の基礎づけとして用いるというアイデアが、イギリスの量子重力研究者クリストファー・イシャムによって提出された。このアプローチを「筋なし」と切り捨てる人もいる中で、「イギリスで最も偉大な量子重力の専門家」イシャムは1997年以降、トポス量子論の構築にその頭脳をささげているという。
量子力学という言葉が叫ばれるようになって久しいが、その理論的基礎づけは、相対性理論の物理数学的基礎づけからすると非常に怪しい。その基礎づけを与える際に、どのような理論的枠組みを用いるか、今までにもさまざまなアプローチが試みられてはきたが、哲学的に最も深淵なのはこのイシャムの「トポス」による基礎づけであることに疑いはないだろう。
「トポス」は空間の背後にある構造だが、直観主義論理と相性がいい。直観主義論理とは、言い換えれば人間の心の論理。「Aも真であり、Aでないも真である」(排中律の不成立)という状況が起こりうる世界。龍樹の言った「中論」、木岡伸夫の「レンマ」。人間の心の世界では、こういった論理が自然に成立する。
一方で、量子力学における性質を描写した「量子論理」は、排中律は成り立つものの分配則「A∧(B∨C)=(A∧B)∨(A∧C)」は成り立たない。つまり、「白米と、梅干しまたはシャケ=白米と梅干しまたは白米とシャケ」という状況が成り立たないというのだ。変な世界。

三つの論理の比較
心の世界の論理である「直観主義論理」と、粒子の世界の論理である「量子論理」をつなぐものとして、トポス量子論が提示するのが、「現存在化」という概念。

ここにおいて登場するのが、「測定の文脈」という概念で、比喩的に言えば、人間の認識の体系のようなものらしい。イヌイットは雪にも何十種類の区別を見出すが、日本人は雪といえば雪。日本人でいう兄と弟は、英語で言えばどちらもBrother。同じ主体があっても、区別の仕方が違うと、見えてくるものも違う。そんな感じのソシュール的「差異の体系」が、「現存在化」において重要な役割を担う。つまり量子論理における実在は、「測定の文脈」というフィルターを経た上で直観主義論理を備えた主体(心)に現前する。
生齧りの知識ゆえに話題がまとまらないが、要はこうした「新実在論」の世界では、客観的実在は確かに存在する。しかしそれは、私たちが通常想定するような実在のモードではない存在のモードで存在するのだ。そのモードには、私たち自身が、あたかも空間をトポスにまで解体するような形で、存在を解体しない限りは到達できない。アレイスター・クロウリーの言う「熱狂」が必要だ。自分の存在のモードをトポス的に変容させて初めて、人間は真の実在にアクセスできる。
ここで、「無人の山中で木が倒れたら音はするか?」という質問への、新実在論的立場からの答えを想像するとしたらこうなる。
無人の山中で木が倒れたら、トポスで音がする。しかし、その音は私たちの住む位相空間においては「無」である。
何だかよくわからないような気もするが、ここで同じ質問に対する私なりの解答案を提出して、本稿の締めくくりとしたい。(以下の感覚的説明は、一見今までの議論とは関係がないように聞こえるかもしれないし、私もうまく言語化できないが、自分の中の主観的な感覚として一致している。)
無人の山中で木が倒れた、という事実は、「私のみている宇宙」が下記のようなひだ構造を持つものだとしたら、その隅っこの奥の奥のまたその奥で展開している事実だ。それは認識できないが、確かに実在する。宇宙はあまりにも大きく、広く、そして深い。私たち人間の表面的な意識でその音を聞くことは絶対に不可能だが、そのひだの奥の奥の奥に分け入るとき、確かに木が倒れたその音は、宇宙全体に響き渡っている。
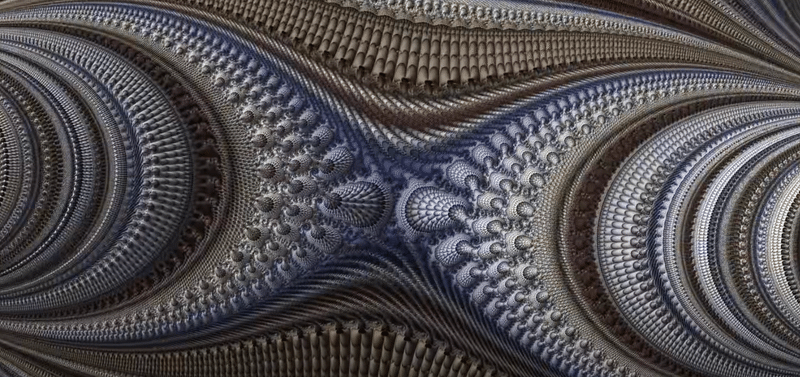
無人の山中で木が倒れたら{音}はする。しかしその{音}は私が見ている世界という模様のひだの奥の奥の奥で通奏低音のように響く、事象以前の事象である。
皆さんの回答もぜひ、教えてほしい。
参考動画
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
