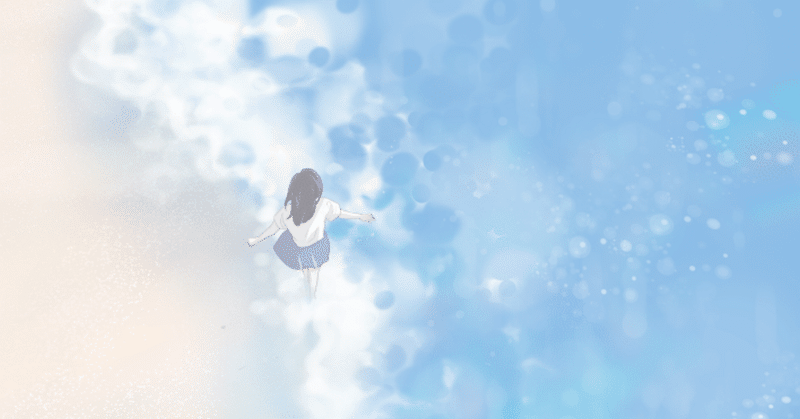
恋愛短編小説 「夏恋彼女」
授業が終わった後のひと時は、僕にとってほっと一息つける時間だ。高校二年生の僕は、季節を問わずいつも長袖を着ている。日焼けが嫌いだからだ。そんな僕が、靴に履き替えて帰ろうとしたとき、女の子の声が聞こえた。
「帰るの?」声の主はアヤカ。彼女はクラスでも目立つ存在で、いつも元気で明るい。その日も制服を腰に巻き、Yシャツの袖をまくり上げて、まるで夏が来たかのように爽やかだった。
「うん、もう帰るよ。でも、その格好で大丈夫? 日焼けするよ」と僕は彼女に忠告した。
アヤカは笑って、「私、日焼けしたいの。日焼けした肌が好きなんだ」と言った。
「僕は日焼けが嫌いだ」と僕は正直に答えた。何故かその話題で少し盛り上がり、僕たちは下駄箱のそばでしばらく話し込んだ。
「日焼けって健康的でいいよ。太陽の下で元気に過ごしてる感じがして」とアヤカが言う。
「そうかもしれないけど、日焼けすると肌が痛くなるし、ケアするのが大変だからなあ」と僕は苦笑いをした。
「へえ、そんなに気を使ってるんだ。ちょっとキモいけど、素敵だと思う」とアヤカは優しく言った。その言葉に少し驚いた。僕の顔にはキモいニヤけ顔が浮かんでいたはずだ。
時間が経つにつれて、僕たちはお互いの好きなことや興味のあることについても話すようになった。アヤカは海が大好きで、夏になるとよくサーフィンをするらしい。それに対して僕は、読書や静かな場所で過ごすことが好きだ。
「じゃあ、僕たち、全然違う休日の過ごし方してるね」と僕が言うと、アヤカは「うん、でもそれがいいのかも。お互い新しい世界を教えあえるから」と楽しそうに答えた。
ある日、アヤカが「海に行かない?」と誘ってきた。正直、日焼けが心配で躊躇したが、彼女の明るい笑顔を断ることができずにうなずいた。
その日、僕は日焼け止めをたっぷり塗り、長袖のラッシュガードを着て、アヤカと一緒に海へと向かった。
海に着くと、アヤカはさっそくサーフボードを海に持ち込み、僕は砂浜で彼女を見守った。彼女のサーフィンする姿はとても自由で、太陽に向かって輝いているように見えた。その姿を見ているうちに、僕も少し太陽の下で過ごすことの楽しさが分かってきたような気がした。
「どう? 楽しい?」アヤカが海から上がってきて僕に聞いた。
「うん、意外とね」と僕は答えた。彼女と過ごす時間が、僕の心を少しずつ変えていくのを感じた。それからの僕たちは、お互いの好きなことを尊重しながら、一緒に多くの時間を過ごすようになった。
夏の終わりには、僕はアヤカに、「君と一緒なら、日焼けのことなんて気にならないよ」と言った。
アヤカはその言葉に大きく笑い、僕たちは互いに手を取り合った。それが、僕たちの新しい関係の始まりだった。太陽のように明るい彼女との日々は、僕にとって新しい発見と喜びに満ちていた。
時間を割いてくれてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
