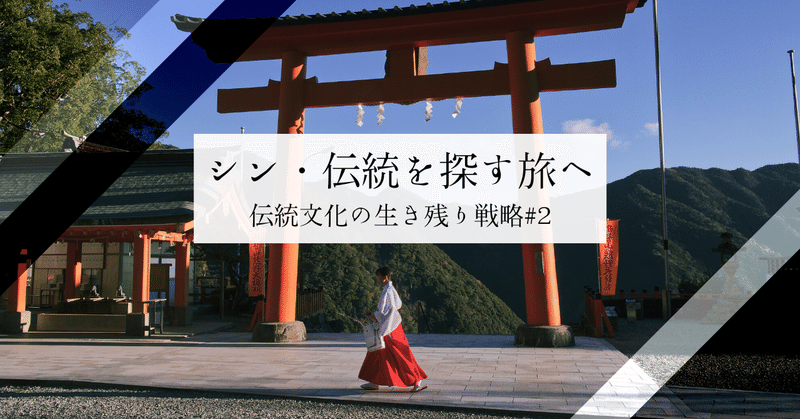
伝統って何?を問いたい【伝統文化の生き残り戦略#2】
こんにちは、Studio Topitaです!
私たちは理想郷を本気で「想像」「創造」するサークルと称し、毎月テーマを決めて語り合い、議事録をアップロードしています。
ぱっと聞いただけでは「?」かもしれませんので、どうぞ是非、自己紹介をご一読いただきたいです。
(常連さんは、いつもありがとうございます!)
Studio Topia 3月
第1回「伝統って何?を問いたい」
こんにちは。Studio Topiaです。
私たちは今月、「伝統」について考えることにしています。
理由は様々ですが、コロナ禍や多様性、グローバル化の波によって社会が変わっている今、改めて考え直したいと思ったのがきっかけです。
…「伝統」。
それは、簡単にイメージできますし、何か挙げろと言われれば多少説明はできるでしょうが、その正体は、と問われたら、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
今回は、「伝統とは何か」という問いに対し、私たち自身との関わりを起点に考えていきました。私たちの生活の中にどう根付いているか、疑問だったからです。今後考えるべき問いも多く見えてきましたので、是非一緒に考えながら読んでみてください。
議事録
そもそも、「伝統」の定義とは。
あるものを他に伝える,または与えることで,一般に思想,芸術,社会的慣習,技術などの人類の文化の様式や態度のうちで,歴史を通じて後代に伝えられ,受継がれていくものをいう。またある個人または集団,時代などの特性が受継がれていく場合をいうこともある。しかし形式のみが伝えられる場合は伝承と呼び,伝統とは区別して考えられることが多い。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「伝統」の解説
(https://onl.la/yG6cyAQ)
伝統は、ざっくり言えば「長いこと受け継がれている文化」と、いうことになるでしょうか。この定義においては、形だけ受け継がれている場合は「伝承」というようですが、今回は全て「伝統」として考えてみました。
あなたは伝統を踏襲しているか?
はじめに話題に上ったのは「自分達は伝統を踏襲しているか?」ということでした。皆さんはどうでしょうか。
会の中では、「形だけ」「日常のなかに採れ入れやすいものは」という回答がされました。例えば、お正月のような年中行事を行ったり、お散歩道に神社があればお参りしたりする、ということでした。
とはいえ、それで伝統を踏襲したことになるのか?というのもあります。年中行事を楽しむという意味ではクリスマスも同じような位置付けになりますが、クリスマスはなかなか伝統とは言い難いですよね。伝統に伝統として触れる機会はあれど、それを踏襲したり継承したりするのはまた別の話のようです。
形にこだわる?中身にこだわる?
ポイントはこの二つです。つまり、形が大切か、その伝統が本来持つ精神性や中身こそが大切か。
現在、多様性やグローバリゼーションに即して様々なものが変わっていっています。
会では、「どのような思いがその文化の中心にあるのかが大切」と、形よりも中身を重視するコメントが出ました。
伝統の担い手は誰か
さて、伝統工芸品や芸能になるとまた話は変わりますが、誰でも関わるような、日常の中にある伝統は、本来「お年寄り」が担い手であるべきなのではないかという意見が出ました。と、いうのも、生まれて20年やそこらではその意味や大切さに気づきにくく、徐々にその意義や核心に触れ、後世に残したいと思うようになるからではないか、ということです。
一方で、最近では若い世代にも「伝統ブーム」も感じる部分があるというか、伝統を大事にすることがかっこいい、という雰囲気があるのも確かです。それこそ「形だけ」で伝統自体に向き合っていない可能性もありますが、伝統文化の担い手ももしかしたら変わりつつあるのかもしれません。
伝統を残す意味
では、伝統を残す意味とは。
「伝統はアイデンティティと結びついているので必要」という意見が一つ。集団の伝統を受け継ぐことで集団の成員と見なされ、また自分でもそう感じたり、と言うのはあるでしょう。「自分が日本人であると言う感覚は、感覚でしかわからない」という意見も出されましたが、そういったものと伝統も結びついているでしょう。そうなってくると、「日本人とは何か」から考えなくてはならないことになって難しいですが、例えば明治時代に、地域ごとに存在した伝統を「日本の伝統」として再定義して、地域の伝統と国の伝統がごっちゃになってわかりにくくなったという可能性もあります(ここら辺詳しくないので、詳しい方がいたら是非教えてください)。
また、「それによって守られてきたものがあるから、それを守るために受け継ぐ」という意見もだされました。
サンタさんも日本の伝統になるか
最後に、これからの伝統についてもちょっと考えてみました。「サンタさんも日本の伝統になるか」。これはなかなか面白い問いです。
まず一つ目に、長い間受け継がれれば伝統になるのか、という問いをはらみます。もともとクリスマスはキリスト教のもので、日本発祥ではありませんので日本の伝統とはならないはずですが、今やクリスマスは一大イベント、それでは今後、クリスマスやサンタクロースも伝統になるでしょうか。1000年後の日本伝統文化を考えてみるのもとても面白そうです。
そして二つ目に、テクノロジーと伝統を考えるきっかけになります。サンタさんの例で言えば、テレビやインターネットの情報を元に、小さい頃から「サンタなんていない」と言うようになったら成立しませんし、あるいは「あの池には河童が住む」などの言い伝えも赤外線で調べれば1発で白黒が着きます。少し話は変わりますが、ショートメッセージが簡単に送れる現代になったから年賀状(が伝統かはおいておいて)が廃れたとも言えます。一方、形にこだわらないという点では、このコロナ禍に「リモートお参り」が可能になれば、それは伝統の継承につながるかもしれません。次回以降考えるいいきっかけになります。
次回に向けて:伝統は(どのように)継承されなくてはいけないか
今回は「伝統」の本質や担い手、変化などを中心に、自分達の例も踏まえて考えてみました。次回は、それを発展させて、伝統は継承されなくてはいけないものなのか、その際の倫理は、商業化はいいものなのか、などの「意義」の観点や、残るとしたらどうなっているのか、といった想像もしていけたらと思います。
面白かった話
今回の本筋と離れますが、面白かった意見・話を載せています。
伝統の取捨選択
家族のなかで伝統を継承していく際、親の伝統が違う場合は伝統の取捨選択が起きる。(わかりやすい例で言えば、関西のお父さんと関東のお母さんではお雑煮の餅の形が違うから、どちらかを選ぶことになる)
もったいない精神の本質は「ものを大切にする」
もったいない、という言葉が流行したことが10年くらい前にあったが、そのもの自体を大切にする、という考え方に立てば、形を変えてしまう「リサイクル」は「もったいない精神」の本質をついていないのでは。
編集後記
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
今回からは「伝統」がテーマです。
もともと、考えて面白いテーマではありますが、記事内にもあったように、現代社会の変化や、「国」を考え直すきっかけとして、取り上げられればいいかなと思います。
日本に生きていて、なんとなく、ぼんやりと、しか伝統について考えてきていなかったなあと改めて思いました。小中高で「日本文化」を教えられて、伝統を理解した気になっていた部分もあります。
今回は前提を揃えるような形になりましたが、まずは「伝統」ってなんぞや、を明らかにしてみて、その上で100年後、1000年後の日本文化を想像してみてもいいなあと思ったりもしています。
次週以降もお楽しみに。(奈都)
・・・・・・・・・・・・
Studio Topia 3月テーマ「伝統文化の生き残り戦略」
第1回「伝統って何?を問いたい」
Zoom(カメラオフ)
今後も更新していきます!
楽しんでくださった方はぜひフォローしてお待ちください😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
