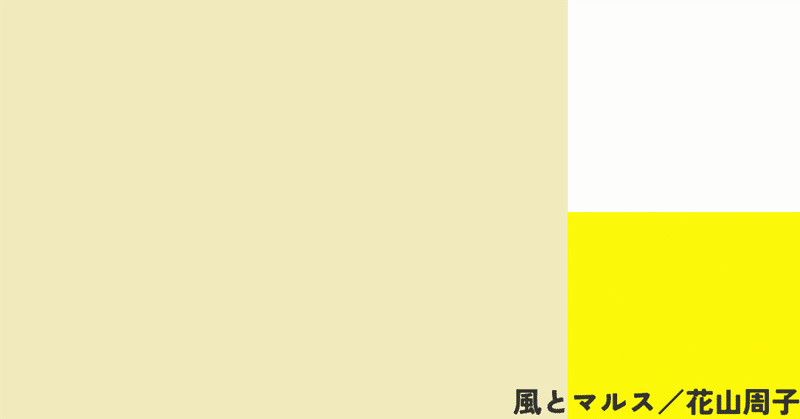
角曲がるたび、風に出会う頬
『風とマルス』を開いたときに、堀静香さんの文章をふと思い出したのだった。
————「五月はうーん、風が爽やかだよね。朝自転車で学校まで来る道のりが気持ちよくて、それが最近はうれしい、かなぁ」と苦し紛れに返すと、「えっ、先生自転車乗れるんだ」「想像できない」「てか〇〇先生もチャリやろ」と口々に言われ、その話題はさして盛り上がらずに流れていった。ほらこんなに緑がかがやいてるのに! と窓を指さしても、反応がない。若い彼らに、五月の爽やかさはどうってことないのだろうか。
(百万年書房)
そういえば、もっと若い頃、10代のときは風なんて気にも留めなかった。今よりずっと周りが見えていなくて、部活の疲れや友達と歩く帰り道、無意味な長電話が生活に自然に組み込まれていた。なにか、触れている時間そのものに価値があったと思う。
何も考えなくても、時間の輝きを感受できていたのかもしれない。しかし、大人になった今振り返るとき、見えていなかったものごとを思う。例えば、それは吹く風のことで、私がスポーツや電話で遊んでいたときに、ひとり頬を風にそよがせていた人がきっといたのだろう。
角曲がるたび、風に出会う頬すこし火照りゆくなり梅の香のして
(青磁社)
『風とマルス』のなかに、こんな短歌が置かれている。
坂の上に祖母の家があって、毎朝そこに寄ってから登校していた。道の途中に、祖母が丁寧に育てていた梅の木が三本。梅が実をつける季節には、大きな硝子瓶のなかにぱんぱんに漬け込まれ、緑の実が梅干しや梅ジャムに変わっていった。梅は身近な木だった。
そう思えるのは思い出そうとしているからで、当時は梅なんて視界に入ったこともなく、いまとなってはその道に吹く風の涼しさは想像するしかないのだ。なんてもったいないことをしていたのだろうと思う。
頬にうれしく当たってくる風の様子。<角曲がるたび、風に出会う頬すこし火照りゆくなり梅の香のして>。わたしは、『風とマルス』のなかでこの短歌が一番好きだ。花山さんは子どもの頃から、こうやって頬で受ける風の感触を知っていたのだろうか。
二〇〇七年に詠まれた歌だという。とても関係のないことだが、二〇〇七年の私はといえば剣道をしていた。一生懸命だった。いま過去に行けるなら、分厚くて汗のしみついた面を外して、ちいさな私を外に連れ出してあげたい。外には風が吹いていたのだった。
読んでくださってありがとうございます! 短歌読んでみてください
