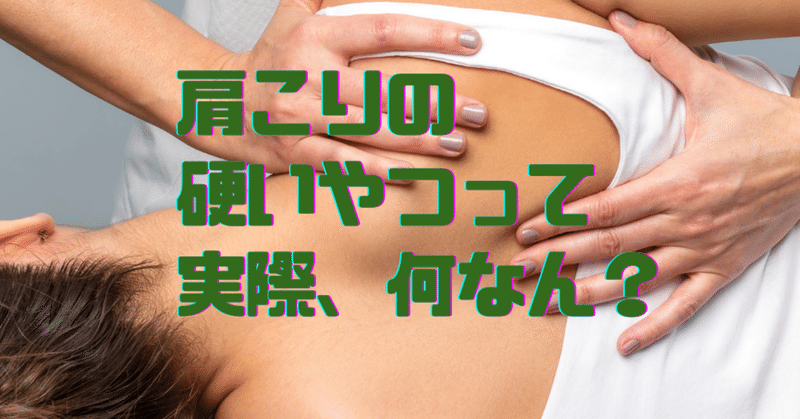
肩コリの硬いやつって、実際何なん?
こんにちは、丸山です。
整体など徒手療法をやっているとちょっとカッコつけて言いたくなる。
コリというより筋緊張って言った方が何だか出来る奴に見える気がするから。
医学のこととかあんまり分かっていないけど、それっぽい言葉を使って説明すると、それっぽく見えて説得力が増すような気がしてね。
触れてみて硬いところがあると「僧帽筋の緊張が~」
なんてよく使いがちです。
ただやっぱり言葉って、正しく使うことで意味を理解できるようになりますし、症状を把握するためには意識して言葉を正確に用いないと細かな対応ができなくなりますね。
ということで今回は
コリ(筋硬結)と筋緊張の違いと、そこを踏まえた臨床時の対応を考えてみたいと思います。
ちなみにこんな記事も書いていますので、良かったら読んでみてください。
筋緊張って?
筋緊張は誰でも常に起きています。絶えず不随意におこる一定の筋緊張は活動に応じて平衡状態にあります。しかし、ヒトの活動を制限する位の筋緊張が起きている時は正常とは言えません。
動作や姿勢によって、その筋緊張の度合いは変化しますのでどこまでが正常でどこからが異常かという線引きが難しいですが、筋緊張の異常は関節運動に支障を来したり、活動量に制限がかかったり、精神的な不安や痛みなども発現しやすくなります。
筋収縮は一回の神経伝達に対し、一回の収縮を単収縮(攣縮)という。それに対し、繰り返しおこなう収縮を強縮と言います。単収縮よりも長く大きな収縮が得られます。
筋緊張は持続的に筋収縮が続くことを言い、主に他動運動時の抵抗感を指します。
この抵抗感は
①筋組織の粘弾性によるもの
②その筋組織を支配している末梢神経によるもの
③中枢神経系による姿勢制御などによるもの
が総合された結果として生み出されています。
筋緊張の異常は運動器疾患のみならず、中枢性疾患、呼吸器疾患などでも見受けられ、リハビリテーション分野では見過ごすことができないものです。
整体などの民間的な徒手療法では、慢性痛や急性腰痛などの症状に伴う筋緊張が主体で、リハビリテーションという視点で筋緊張に触れることがありません。
民間的徒手療法はリラクゼーション的な技術であることがほとんどです。そのため、正常範囲の筋緊張(高筋緊張ないし低筋緊張)へのアプローチになります。
民間的徒手療法はコリをほぐす、筋硬結を緩める事にフォーカスしがちですが、リハビリテーションは機能回復(ADLの改善、QOLの向上)を目的としています。
このような患者ニーズの違いからも認識のズレが起こり、医療と商売が混在することで医療用語がビジネス的な目的で使われてしまうのでしょう。
異常な筋緊張
異常な筋緊張について理解を深めたいと思います。異常な筋緊張は亢進と低下です。
異常な筋緊張と一言で言ってもそれを否定的に考えてはいけません。
筋緊張は障害に対して適応的にはたらく場合もあります。
例えば、痙縮は異常な筋緊張の亢進です。
しかし、一方で痙縮によって下肢の支持性が維持され、立位や歩行が可能となります。神経生理学的には機能低下ですが、活動としては代償的に置き換えとなり、問題とするには疑問を挟みます。
筋緊張の異常は生理機能として見るだけでなく、その人の生活や活動を考慮しながらそれがどんな妨げになっているのかを含めた視点を持つべきだと考えます。
筋緊張亢進
筋緊張の亢進は痙縮と固縮(筋強剛)について理解が必要です。
痙縮は中枢神経系の障害によっておこります。
通常、中枢神経系の上位運動ニューロンは下位運動ニューロンをコントロールすることで筋緊張を保ったり、強めたり、弱めたりします。
しかし、中枢神経系に障害がおこると上位運動ニューロンは下位運動ニューロンを抑制できずに伸張反射を亢進させてしまいます。
「ジャックナイフ現象(折りたたみナイフ現象)」が代表的な徴候です。
他動運動により関節を動かすと、その途中で急に抵抗感が軽減します。
固縮は筋強剛とも言われ、痙縮とは異なった異常な筋緊張の亢進です。
固縮は錐体外路の障害です。
運動制御には錐体路系と錐体外路系があります。
痙縮は大脳皮質の影響によるので錐体路系の障害ですが、固縮は大脳基底核の影響なので錐体外路系の障害です。
錐体外路は随意運動の調節で、スムーズに動きを行う上での微調整や姿勢の保持などに関与します。
錐体外路の障害がおこると大脳基底核からの抑制が亢進し、動きにブレーキがかかってしまいます。
固縮がおこると鉛管や歯車現象という、関節可動域いっぱいまで抵抗がある(鉛管)や、抵抗が断続的にある(歯車現象)がおこり、この筋の硬さによって運動に制限ができてしまいます。
機械的要素による筋緊張異常
機械的要素による筋緊張異常は、骨格筋の不活動に伴う機能的変化により認められる筋委縮、筋短縮、線維化が原因であることが多い。
筋委縮は筋肉がやせてしまうことです。筋原性、神経原性、廃用性と大きく分類すると3種類があります。
筋委縮では筋線維の小径化と筋線維数の減少が生じます。
筋原性はミオパチーといい、代表的な疾患は筋ジストロフィー、神経原性はニューロパチーといい、代表的な疾患は筋委縮性側索硬化症(ALS)、脊髄性筋委縮症(SMA)、球脊髄性筋委縮症があります。
廃用性筋委縮は過度な安静や活動量の低下によって生じた筋委縮です。一定の診断基準がなく、今までできていたことができなくなったり、動きにくさを感じるようになった場合は廃用性萎縮を疑うことがあります。
身体機能や筋力低下、インスリンの抵抗性発現、基礎代謝量の低下、体脂肪の増加など様々な健康上の問題が惹起されます。
廃用性筋委縮は長期的に観察が必要で、主にベッドレストや関節固定による不活動が調査対象になることがほとんどです。
廃用性筋委縮では除神経や非荷重によって起こる、タンパク質合成の減少、タンパク質分解の亢進が認められます。
骨格筋の横断面積は筋線維数と相関性がある。
そのため、筋線維数の減少を伴う筋委縮は活動張力が低下することによる筋緊張低下を示します。
筋力を維持する場合はより多くの運動単位数を参加させる必要があるため、エキセントリック・コントラクションによるエクササイズになります。
筋短縮は筋長が短縮位となる位置で関節が固定された場合にみられる現象です。短縮のメカニズムは骨格筋は不活動中に加わる張力に応じて筋節を減らして筋長を短縮させることで、骨格筋に加わる張力を一定に保とうとするからです。
筋短縮における筋緊張は亢進ぎみになります。
線維化は筋委縮と共にコラーゲンが筋に増殖し、個々の筋線維が縮小して各線維間の間隙が拡大すると、それを埋めるために筋周膜、筋内膜が肥厚し、筋横断面積に占める筋膜の割合が増加する。
筋委縮、筋短縮、線維化のメカニズムと特徴を知っておくと、単に「緊張」と考えずにそれぞれに有効的なアプローチを選択しやすくなります。
ここまでで、異常な筋緊張に対して改めて医学的な基礎知識を振り返ってみました。
じゃあ、肩こりや腰痛などの筋骨格筋痛に見られる筋のコリのようなものは異常とは言い難いと思います。
ここで挙げた筋緊張は、脳や中枢神経系に障害をきたしたり、末梢神経の障害やケガや疾病によって不動を余儀なくされた場合に起こるものです。
脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアなどによって起こった筋力低下や慢性腰痛患者に見られる運動不足による筋短縮などは、これらが痛みの原因と考えがちなところもありますが、筋緊張の知識を踏まえて考えると、痛みによって筋緊張の原因となる不動がおこり、それによってADLの低下、QOLの低下につながったことが痛みの感受性を高めると考えた方がいいかもしれません。
では、ここまで異常とも言い難い肩こりなどの筋緊張は正常範囲の高筋緊張の部類ですが、どういったものでしょうか?
肩こりのコリは筋硬結
運動器疾患の患者や慢性痛患者が訴える「コリ」「しこり」のようなに表現されるものの代表が筋硬結というものです。
有痛性の硬い部位のことを指しますが、触診による筋硬結の評価基準は再現性に欠けます。
理学療法士、作業療法士、柔道整復師の触診による筋硬結のイメージは筋の厚さの中央より、浅い位置にあり、正常な筋より硬さが1.78倍あるアーモンド形状のもので「コリコリ」とした触感
徒手的理学療法従事者がイメージする筋硬結の形と性状
磯貝 香, 岡本 正吾, 山田 陽滋
だということから主観的ではあるが、多くの徒手療法家が同じようなイメージを持っているところが面白い。
筋硬結の特徴は
・局所的である(筋全体には現れない)
・押圧や圧迫で強い痛みを感じる
1843年にFroriepがリウマチ患者に見受けられる「有痛性の筋の硬い部分」について報告したのがはじまりで、筋変化の原因は結合組織の沈着であるとしました。しかしその後も
線維性結合組織炎によるもの
筋スパズムによるもの
酸素欠乏によるもの
炎症によるもの
と少なくとも6つの原因がわかりました。
筋硬結の病理組織学的な所見としては
浮腫
プロテオグリカン増殖
エネルギー供給と酸素流量の低下
pHの低下または酸性化
核の増加
肥満細胞(ヒスタミンの放出)の増加
筋線維サイズのばらつき
ミトコンドリアの変化
グリコーゲンの増加
Ragged Red およびmoth-eaten線維の出現
収縮フィラメントの溶解とZバンドの破壊
血小板(セロトニンの放出)の増加
などが認められています。
発生の機序としては、筋の損傷や疲労が過剰になった時をきっかけに、カルシウムイオン濃度が上昇し、筋原線維の滑走性が膠着することによっておこる局所循環障害が酸素欠乏とエネルギー欠乏を招き、さらに膠着が持続することで筋硬結が形成されます。
筋硬結は筋原線維の強固な結合がカルシウム濃度が下がらなくなることで起こった状態と言えます。
慢性化した肩こりや腰痛の硬いコリは正にこの状態です。
ちなみに間違いやすいのが筋スパズムです。
筋スパズム
筋硬結と似ているが少し違うのが筋スパズムです。
筋スパズムは骨格筋が不随意に急速な収縮を起こす状態です。
痛みの感受性に対する、防御作用による筋の反射的かつ持続的な筋緊張の亢進と理学療法領域では言われます。
筋硬結が筋線維の結合(まさに硬くなる)だとすると、筋スパズムは筋の高テンションのような状態です。
筋硬結や筋スパズムへの対応
このように筋硬結や筋スパズムは筋肉が固まったわけではなく、損傷や疲労などで筋形質内のカルシウム濃度の上昇が起こり、持続すると筋硬結となり、痛みや刺激に反射的に反応すると筋スパズムとなります。
どちらも筋の異常収縮であり、カルシウム濃度が高いということはATPが不足しています。エネルギー不足が筋への促通を促す神経の興奮を過剰にします。
・血流の促進(温熱刺激や反復運動)
・神経の鎮静化(リラクゼーション)
・水分補給(ATPの枯渇によって脱水状態になる)
漸く、肩こりへの対応が分かってきましたね。
マッサージには血流促進やリラクゼーション効果が期待されるため、マッサージなどの徒手療法が筋硬結の治療に用いられてきました。
しかし、このように生理的な機序を追っていくと、マッサージより温熱療法のような物療の方が効果的に思えますし、ターゲットを絞った運動療法が不可欠だという事に改めて気づかされます。
強い指圧のような刺激は逆に筋の興奮を強めてしまう恐れも懸念できます。
さて、では肩こりを姿勢で改善するという考えについてはどうでしょうか?
姿勢の変化はたしかに筋緊張の変化があります。姿勢を変えれば肩こりは改善されるのでしょうか?
姿勢と筋緊張
肩こりや腰痛などの慢性的な筋骨格筋痛を扱っていると、その筋のコリ(筋硬結)が長時間の姿勢の果てに起こったものだと思うことがしばしばあります。
長時間の同姿勢は特定の筋に過剰な収縮を促し、筋緊張を亢進することで肩こりや腰痛を引き起こすのではないか?という推察が入るからです。
しかし、これまでのことから筋緊張が痛みを誘発するというよりも、痛みが筋緊張や不良姿勢を招くという考えの方が推奨できます。
姿勢は
・痛みの回避
・作業や活動への適応
これらを適度な筋緊張によって制御しています。
構造的(解剖学的)には、骨盤と脊柱の安定と言われますが、実際の臨床の場で考えますと、これを解剖学的に評価し、慢性痛と結び付けるのは難があります。
急性期のような痛みが強い時期ですと、姿勢は疼痛回避姿勢が主となり、解剖学的なランドマークは判断基準になりません。
慢性期では、痛みの原因となる場所が不明瞭なことや、痛みの誘発姿勢があってもそれがどんな機序で痛みを表現しているのかが明確になりません。
どちらかというと重力と活動に対し、過剰な筋緊張を生じさせるのは動きのベクトルと心理的抵抗そして外部環境が大きいようにも思えます。
デスクワークによる僧帽筋の活動について
デスクワーク時における僧帽筋の活動はいくつかの研究によって同じような報告が見られます。
安静時の筋緊張は「不動」と言うには、意味が違いすぎます。デスクワーク時には少なくとも神経的には活動があるため、全く動かないまたは、動けないのとは違う。
しかし、ほぼ肩から上に上肢を挙上することはないため、背部の筋の運動不足にはなり得ます。
デスクワーク時の僧帽筋の活動についての研究では、数分に一度の上肢の挙上を伴う運動または、昼休みに上肢を挙上するようなエクササイズで能動的な休息を心がけることで午後以降の僧帽筋の活動を減らすことができるという報告があります。
Ind Health. 2017 Apr 7;55(2):162-172. doi: 10.2486/indhealth.2016-0189. Epub 2017 Jan 13.
J Electromyogr Kinesiol.2009 Dec;19(6):e4307.doi:10.1016/j.jelekin.2008.11.011. Epub 2009 Jan 8.
デスクワーク時には僧帽筋の活動は活性化しており、能動的な休息によって背部の筋の活動を行うことで神経系に変化を与え、血流を促進し、ATPによってカルシウム濃度を減らし、筋の弛緩を促します。
肩こり=筋硬結という発想から、肩こりは神経系を含む生理的な反応であると理解した方が良さそうです。
デスクワーク時の肩こりには
・能動的休息を定期的に行う
・上肢を肩より上に挙上するエクササイズ
・胸椎の伸展エクササイズ
・水分の摂取
・入浴などの温熱
これらを使ってセルフケアをしていくことは手段として一案だと思います。
筋緊張に影響を与える6つの要因
筋緊張に影響を与える主な因子は
・環境
・意識・注意
・筋力
・関節可動域
・痛み
・感覚
これらが考えられます。
姿勢が筋緊張に働くというよりは、筋緊張がこれらによって影響を受け、助長します。
このことから筋緊張が刺激の入力に対する反射であることも分かります。
よってセラピストが思うように筋緊張を弛緩させることは一時的であり、持続的な弛緩を保つには患者自身の自発的または能動的なコントロールが必要です。
筋緊張のコントロール
ヒトは進化の過程の中で直立二足歩行を獲得し、大地を長距離移動できるようになり、体幹部の可動性を拡大させ、上肢を地面から話すことで巧緻動作を可能にし、口腔顔面機能を発達させてきました。
ヒトの中枢神経系は学習によって、様々な感覚情報を受信、統合して、筋肉への指令を出し、姿勢や動作を無意識レベルで維持できるようになります。
これらは「筋力」ではなく、中枢神経系による情報処理能力であるため、姿勢のコントロールは中枢神経系による活動状態について考える必要があります。
筋緊張について考えるというのは、筋の硬さや痛みの強さを評価することは明らかに違います。
むしろ、筋の硬さや痛みによって起こる様々な固有感覚の変化が、位置情報や動きや力のベクトルに変化を与え、筋緊張でコントロールしているという視点が必要になってきます。
肩こりへのアプローチは筋肉を揉みほぐすのではなく、皮膚の伸張性や筋収縮による筋紡錘への刺激によって末梢神経に変化を与えることで受容器としての働きを変化させることで、筋緊張の状態にも変化を与えることができると考えます。
様々な徒手療法はあれど、皮膚、または運動やストレッチによる筋紡錘に対するアプローチである以上、どんなものであっても特別なことはなく、どれもこの理屈による操作です。
また、注意や意識が筋緊張に関与することもある。痛みや不快感に対して過剰な注意は緊張を生じる要因になり、視覚的な意識、聴覚や嗅覚による他の感覚への意識や注意の拡大によって痛みの閾値は高くなるとも言われています。
これは予測や反応という脳の統合的な機能とも関係があります。肩こり患者の治療では、患者にどんな環境でどんな課題を与えるかに取り組ませることで筋緊張に変化を与えることがあります。
手を伸ばして目標物を捉えることや、痛みをうまくコントロールしながら動くといった課題を与えながら訓練することで動きや姿勢のスキームに変化が起こることで慢性的な筋緊張に違った刺激になります。
筋緊張はその人の生きてきた姿でもある
姿勢の筋緊張について考える時、支持面(地面)についても理解しておきたいことがあります。ヒトの接地面は足底であり、そこからの入力は姿勢変化に大きな影響を与えます。
以前、私が書いたこの記事には姿勢がいかにその地域の土壌にも反映されているか?ということを書いたものです。
もし良ければ、合わせてお読みください。(一部有料記事です)
そして、その人の姿勢はその人自身の表現、感情、情緒、既往症など生きてきたものの集大成でもあります。
その一つ一つを丁寧に拾っていくことで、肩こりという症状を理解していけるのではないでしょうか?
単なる、同姿勢によっておこる筋の硬結…ではありません。
慢性的な腰痛や肩こりに見られるコリというものは、実は奥が深く中枢神経系の活動だというこがわかりました。
慢性痛や肩こりの治療が非常に難しく、患者もその場しのぎを求めやすいのは、このように神経系が根っこにあるからです。
肩こりの治療には
・痛みの知識
・リラクゼーションの技術
・カウンセリングスキル
・姿勢分析
・運動療法
・温熱や血流促進
このような他分野にわたる知識と技量が必要です。
そして、知識や技量のない人が「たかが肩こり」
そういう気持ちで施術にあたることはあってはならないと改めて思いました。
参考文献:筋緊張に挑む 文光堂 斉藤秀之 加藤浩
カンデル神経科学 メディカルサイエンスインターナショナル
バトラー・神経系モビライゼーション 触診と治療手技 協同医書出版社
姿勢の脳・神経科学ーその基礎から臨床までー 市村出版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
