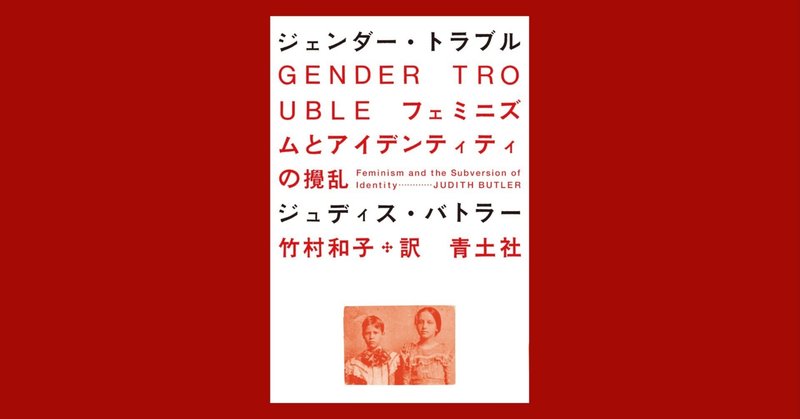
精読「ジェンダー・トラブル」#037 第1章-5 p57
※ #025 から読むことをおすすめします。途中から読んでもたぶんわけが分かりません。
※ 全体の目次はこちらです。
フーコーはエルキュリーヌの体験を、「猫がおらず、猫のニヤニヤ笑いだけが漂う快楽の世界」と想像している。ここでの笑いや幸福や快楽や欲望は、それらが結びついているはずの不動の実体をもつものではない。これらの属性は自由に浮遊するがゆえに、実体化し階層化する名詞(もの全般)と形容詞(本質的かつ偶発的な属性)の文法では把握することができないジェンダー体験の可能性を、示唆するものである。
両性具有者エルキュリーヌは、医師や法律家の介入を受けるまでは、「アイデンティティのない幸福な中間状態」にいた、とフーコーは記しています。詳しくは次の hiyamasovieko さんの記事を参照ください。
〈われ思う〉は実際は〈思うのはわれ〉であり、まず思考が発生し、あとから、あくまで文法上の制約により、〈われ〉という主語が生じる、という議論がありました(#032 参照)。そのことをミシェル・アールは「思考が、『われ』のところに到来する」と表現しました。
フーコーの想像するエルキュリーヌには、「笑いや幸福や快楽や欲望」が発生しても、その行き先である実体としての〈われ〉がありません。なぜならエルキュリーヌには、実体の形而上学が要求するようなジェンダー・アイデンティティが成立不可能だからです(#036 参照)。
このように、男女二元体の枠組みから「自由に浮遊する」ような、「文法では把握することができないジェンダー体験」がありうるのではないか、とフーコーは示唆しているのです。
ある「男」が男性的な属性をもっており、その男性的な属性がたまたま、うまい具合にその男の性質であると考えるなら、べつの「男」が女の属性(それがどんなものにせよ)をもっていて、しかもそのジェンダーは揺るがないということも言える。
ジャイアンがホームランを打ったとします。ホームランを打つことは「男性的な属性」です。それは「うまい具合に」ジャイアンの性質です(ホームランを打つのは、いかにもジャイアンらしい)。
のび太がホームランを打ったとしたらどうでしょう(もちろん秘密道具の力で)。ホームランを打つことは「男性的な属性」ですが、それは「うまい具合」にはいきません(のび太らしくない)。
のび太があやとりの新技を披露したとします。あやとりは「女の属性」です。が、だからといって、のび太は女なのでは、と疑う人はいません。男が「女の属性」をもっていても、男は男であり、「そのジェンダーは揺るがない」です。
けれども「男」や「女」を不動な実体として何よりも優先することをやめてしまえば、不調和を奏でているジェンダーのさまざまな性質を、基本的には無傷であるとみなしているジェンダー存在の下位において、それから派生したものとか、偶然のものとみなすことは、もはや不可能である。
「基本的には無傷であるとみなしているジェンダー存在」とは、アレサ・フランクリンのところで出てきた「あなたのせいで当たり前の女のように感じる」の「女」のことです(#034 参照)。すなわち、制度的異性愛において恋愛相手が自分に投影する、自分が目指すべき「ジェンダー存在」のことで、それはイデアのようなものであり、首尾一貫した統一体であるので「基本的には無傷」です。
今はどうか知りませんが、昭和のドラえもんでは〈男のくせにあやとりなんかして〉とのび太を囃し立てるのが定番でした。なぜ男なのにあやとり好きなのか、という疑問に対して、〈あやとりはのび太が一番(一番というのは男の属性です)になれることだからだよ〉とか〈なぜだか分かんないけど(偶然にも)、あやとりが好きなんだよ〉と、派生や偶然を理由に答えるのは尤もらしく聞こえます。
が、ここで「男」をとっぱらってしまうと、〈男のくせに〉という疑問が消えてしまう上に、〈男だから一番に〉〈男なのになぜか〉という説明も成り立たなくなり、「不調和」自体が消失します。
不動の実体という考え方そのものが、首尾一貫したジェンダーの序列のなかにさまざまな属性を強制的に秩序づけることで生みだされる架空の構築物だとするならば、実体としてのジェンダーーー名詞としての男と女の存在の可能性ーーに疑義がつきつけられるのは、連続的または因果的な理解可能性のモデルに合致しない不調和な属性の戯れによってである。
〈男〉らしさという基準で〈ホームラン〉や〈あやとり〉に「首尾一貫したジェンダーの序列」が付与される、と思いがちですが、バトラーは逆に考えます。
「首尾一貫したジェンダーの序列」がまず先にあって、そこに「さまざまな属性を強制的に秩序づける」ことで、〈男〉という「不動の実体」が構築される、と言うのです。
バトラー によれば、ジャイアン > スネ夫 > のび太、という序列がまずあり、〈ジャイアン=ホームラン=男〉、〈のび太=あやとり=女〉と秩序づけることで、〈男〉が実体として構築されます。
もし出来杉くんがあやとりが上手だったらどうなるでしょう。この場合はのび太とは違って、〈出来杉のやろう、そんなことまでできるのか〉と、出来杉くんの完全無欠さ(これは男性的な属性です)に花を添える形になります。つまり〈出来杉くん=あやとり=男〉となります。だから序列のほうが先なのです。
このようにして構築される「名詞としての男と女」は、「連続的または因果的な理解可能性のモデル」で説明できない例外が現れた時、「疑義」がつきつけられます。
「連続的または因果的な理解可能性のモデル」とは、〈男のくせにあやとりなんかして〉を説明するさいに用いる、〈男だから〉〈男なのに訳あって〉といった、〈男〉を起点とした理由づけのことです。これで説明できない例外のひとつが、両性具有者エルキュリーヌのケースです。別の例外としてバトラーは別の箇所で、ドラァグ・クイーンをとり上げています。
(#038 に続きます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
