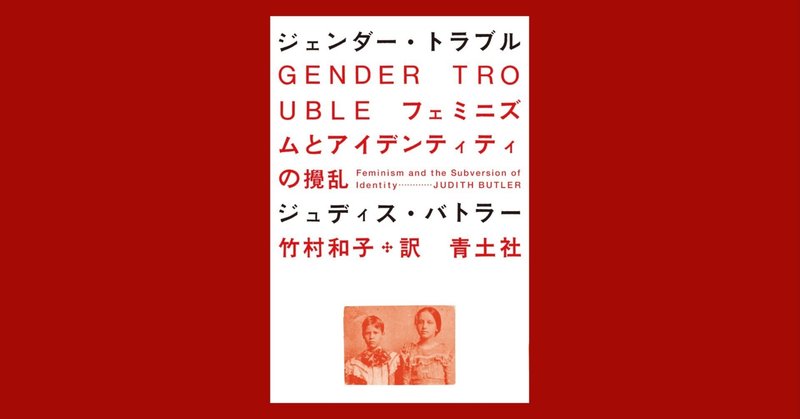
精読「ジェンダー・トラブル」#046 第1章-6 p67
※ #039 から読むことをおすすめします。途中から読んでもたぶんわけが分かりません。
※ 全体の目次はこちらです。
唯物論者がフーコー派から批判を受けたという話の続きです。
同じ批判を、男根的セクシュアリティとは根本的に異なる女特有の性的快楽があるという考え方にも、向けることができる。イリガライはときに、女特有のセクシュアリティを女特有の解剖学的現実から導き出そうとするが、彼女のこの考え方は、このところずっと反本質主義の標的となってきた。
カント以来、〈物自体〉が決して認識できないことは哲学の常識です。
生物学的に見て男女が異なるのは明白ですが、人はその違い自体を直視することは不可能で、必ず〈物自体〉を覆う〈意味のヴェール〉ごしにしか違いを知ることはできません。そして大事なのは、その意味でなくてはならない必然性がないことです。原理的には、セックスという〈物自体〉がとりうる意味のヴァリエーションは無限にあります。
この〈意味のヴェール〉はどうやって作られ、どのような効果をもたらすのか、そしてどう変えるべきなのか、ということを「反本質主義」の人々は問うてきました。
だから、〈物自体〉から唯一の意味を導き出す行為は、間違っているだけでなく、抑圧(意味の押し付け)の原因となり、とうぜんに批判されるべきことなのです。
原注にはこうあります。
おそらくイリガライの主張のうち、もっとも議論を呼ぶものは、「二つの唇が触れ合う」外陰唇の構造が女の非統合的で自体愛的な快楽を構築しており、そののち、ペニスの挿入という快楽の剥奪行為によって、その二つのものは「引き離される」と主張したことである。
言い逃れはできなさそうですが、イリガライはラカン派の人なので、「外陰唇」「ペニス」はそれ自体ではなく象徴なのだ、と強弁できるかもしれません。
しかし、フロイトが即物的に〈ペニス〉と呼んだものを、ラカンは象徴的に〈ファルス〉と言い換え、そうすることで〈象徴界〉の理論を作り出したことを思い出すと、イリガライが再び即物的な「外陰唇」「ペニス」という語を用いていることは、どう贔屓目に見ても先祖返り、普通に見れば素朴な本質主義へ大幅に後退していると言えます。
事実セクシュアリティが文化的に構築されているのか、それとも男根と関わってのみ文化的に構築されているのかは、イリガライのテクストでしばしば不明瞭である。言葉をかえれば、女特有の快楽は文化の前史として、あるいはユートピア的な未来として、文化の「そと」に存在しているのか。もしそうなら、セクシュアリティを社会構築されたものと考えてセクシュアリティに関する闘争をおこなっている現在、このような考え方はどのような有効性をもちえるのか。
セクシュアリティが「男根と関わってのみ文化的に構築されて」いて、「女特有の快楽」が「文化の『そと』」にしか存在しないのであれば、文化の内側にとどまってセクシュアリティを変えようとすること自体が無意味になります。
そうでない、つまり男根と関わらない「セクシュアリティが文化的に構築されている」とすれば、すべてが男根ロゴス中心主義の支配下にあるという前提で論を進めるイリガライの、前提そのものが嘘だということになります。
フェミニズムの理論や実践のなかのセクシュアリティ論者は、セクシュアリティはつねに言説や権力に関連して構築されるものだと説得的に論じてきた。その場合の権力は、ある部分、異性愛的で男根的な文化慣習として理解されているものである。したがって異性愛的で男根文化的な次元で構築された(決定はされない)セクシュアリティが、もしもレズビアニズムや両性愛や異性愛の文脈のなかに出現したとしても、それは何らかの還元的な意味での男への同一化を意味する記号ではないはずだ。
たとえば思春期の少女がボーイッシュな格好をしていたとして、昆虫のように短絡的な人なら〈彼女は女性性の受け入れを拒否しているのだ〉〈彼女は男になりたいのだ〉と言うかもしれません。が、まともな人なら、彼女はボーイッシュなファッションが好きなだけなのだ、と思います。
彼女はまわりの友達から、ボーイッシュなファッションが似合うね、と言われたり、自分でもそう思っていたりします。その背景には確実に、男女二元体を基盤とした象徴の体系があり、彼女の属性に対するジェンダーへの強制的秩序づけがあります。そして彼女にボーイッシュなファッションをさせようとする権力が働いています。
彼女がそのような覇権的な権力に自ら従うとき、彼女は抑圧されているのでしょうか? もちろん違います。そのような権力は単に「異性愛的で男根的な文化慣習」であり、風に吹かれた風車が仕事をするように、彼女は権力の磁場に逆らわずに行動して、そして少しばかりの利益(「似合うね」)を得ているだけなのです。どこへ行っても覇権的な磁場は必ずあるので、すべての磁場に逆らいながら生きていくのはどだい不可能なのです。
バトラーがここで言いたいのは、ブッチフェム(レズビアンにおける男役と女役)は単なるファッションであって、二元的な男女観への肯定を表明しているのではない、ということです。
(#047 に続きます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
