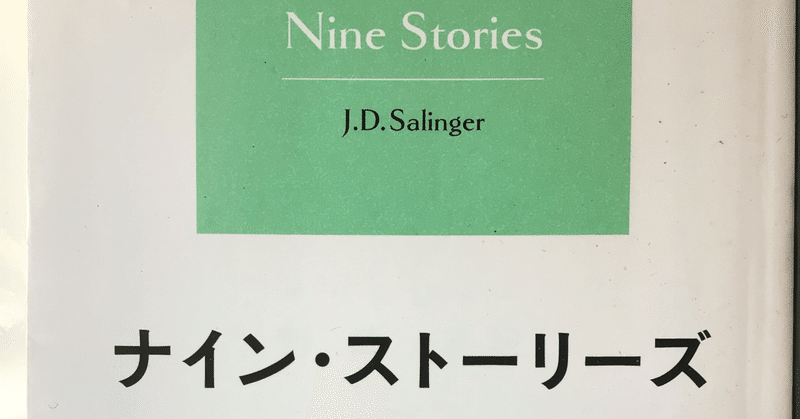
J・D・サリンジャー「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」
近年サリンジャーの影響力を知らない人も多いのかもしれない。とは言っても、私も文学青年でもなんでもなかったので、浪人するまでそういう作家がいるということも知らなかった。いや、知らなかったというと不正確で、浜田省吾の楽曲に「僕と彼女と週末に」の間奏の部分での語りで「…先週読んだサリンジャーの短編小説のこと…」みたいに出てくることだけは記憶していた。
というわけで文学やろうという時に勇んで買ったのが旧版デザインの新潮文庫版『ナイン・ストーリーズ』だった。有名で仕方がない「バナナフィッシュにうってつけの日」を読んで、免疫もないので、おお、と思い、こういうのが小説なのだと錯覚した。今は、もうボケかかっているので、それが錯覚だったのかどうかも定かではない。いずれにしても、他の短編の記憶がない。あ、「笑い男」だけは、「オペラ座の怪人」ぽくて覚えている。
今回はだから、そのうちの印象のなさそうなものを選んでみようと思った。で、この「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」を選んだ。面白かったっけ?結論から言うと、サリンジャーの作品は切羽詰まったようなシリアスな空気が張り詰めていて、読むのが結構辛くなることも多いのだけれども、「ド・ドーミエ=スミスの青の時代」はその中でもユーモアあふれる作品だった。オッサンにもおすすめである。自分の若い頃の背伸びを恥ずかしく懐かしく感じられるはずである。
あらすじ
「わたし」の父と母が離婚した後、母はロバート・アガトギャニアン・ジュニアという不可思議な男と再婚した。すぐに、継父についてパリに行かねばならなくなった。そして、母が亡くなり、「わたし」は継父と一緒にニューヨークに戻って美術学校に通うことが決まる。しかし、学校の雰囲気は合わず、ニューヨークにも馴染めず、いわばムカつくことばかりある生活に嫌気がさしてくる。そんなある日に一つの新聞広告が目に入る。
ケベックのモントリオールで、どうやら日系人主催による美術通信講座が立ち上がるので、講師を募集している。「わたし」はさっそく、オノレ・ドーミエは大叔父にあたるジャン・ド・ドーミエ=スミスと名乗り、偽の経歴をでっちあげる。両親はパブロ・ピカソが友人であり、その忠告に従って展覧会に出品したことは一度もないこと。しかし、上流階級にはそれなりの顧客がいること。その上で、何枚かの作品を仕上げ、同封して、郵送した。しかるに、後日合格通知が届いた。
継父とその再婚相手に、講師になる旨を告げて、家を出る。そして、モントリオールに到着し、〈古典巨匠の友〉という名前の美術学校の主催者であるI・ヨショト氏と合流する。ヨショト氏は、若干、「わたし」のいでたちをいぶかしむも、それなりの待遇で迎えてくれる。
朝食をともにしたヨショト氏とその妻、そして「わたし」だったが、まず与えられた仕事は翻訳の仕事だった。おかしい、通信添削の美術講師の仕事を与えられるはずではないのか?嘘がバレているかもしれない、と不安になりながら、昼食をとりに外へ逃げ出し、バレていないかどうか確認して、再び仕事に戻る。
なんとかお世辞と嘘で塗り固めながら、ヨショト氏の疑惑を解消しようとしていたところに、とうとう講師の仕事が与えられる。とどいた三人の絵に、手を入れてくれないか、と依頼された。一人めは、バンビ・クレーマーという23歳の主婦。好きな画家はレンブラントとウォルト・ディズニー。「彼らの過ちを赦せ」という題名で、平凡な内容だが、非常に奇怪で「斬新」としかいいようのない技法を用いて、送ってきていた。二人めは、R・ハワード・リッジフィールド氏であり、オンタリオ州在住の56歳の「社交界専門の写真家」という人物。風刺画が好きだという
三人目が来た。聖ヨセフ修道会の修道女で、シスター・アーマと「わたし」は読んだ。彼女は通信欄の年齢の欄が空欄になっていた。このアーマの作品をみて「わたし」は衝撃が走る。今までの生徒たちに対しては、若干の皮肉を交えつつ眺め、手直しした上で、返信していたものだが、シスター・アーマの作品には感激してしまい、つい長文の手紙をしたためることになる。
しかし、その内容があまりに熱烈だったためなのか、修道院長から通信美術学校へと通う(投稿して添削する)ことが許可できない旨が届いた。失望する「わたし」。その間、二人の通信添削投稿者のへたくそな絵画に手を入れたりして、索漠たる時間を過ごす。
もういちど、シスター・アーマに、それでもなお画家を目指すように推奨する手紙を書こう。「わたし」はふたたび長文の手紙を書きあげ、同時に他の四人の受講生には退学勧奨の手紙を書いて投函してしまう。ただ、シスター・アーマへの手紙は結局出せずに終わってしまう。ただ、出すかどうか迷って、タキシードを着こんでホテルに夕食を行こうとするも、途中で気が変わって、スナックで食事を済ませて、学校へと戻ろうとする。その途中で、なんとも奇妙な出来事に際会する。
脱腸帯がついていたマネキンが飾られていたショーウィンドウをタキシードを着た「わたし」が眺めていると、女性がいて脱腸帯を付け替えている。そんな「わたし」に気づいた女性は慌ててしまい転びそうになって、それに手を差し伸べようとするもガラスに指を「わたし」はしたたか打ち付けてしまう。心配そうに覗き込んだ「わたし」は、眩しいライトを浴びせられて、それに目が眩んでいるうちに女性は消え去ってしまう。
勢いで、退学勧奨をしてしまった四人の受講生に、手違いだったという謝罪の手紙を「わたし」は書く。しかし、結局、この通信添削校は、認可が得られず、廃校となり、講師の立場も水泡に帰す。「わたし」は、継父の元に帰り、ふたたび美術学校に通うことになる。今でも、バンビ・クレーマーさんとは手紙のやり取りがあるらしい。
感想
すごいね。落ち着いて読むと、やっぱり面白いね。若い時に、読まなきゃという焦燥感と義務感に駆られて読むと、このド・ドーミエ=スミスの語りがまだるっこしくてしょうがなかったんだと思う。正直、ストーリーはユーモア小説のそれで、尊大な若者が背伸びをして色々やってみたけれども、空回りしながら、元の場所に戻ってくるという構造で、なんだろう町田康の「くっすん大黒」を思い出したりした。
語り口が、皮肉っぽくて、何かに当てつけた表現の一つ一つが分かっているかというと全然わかってないのだが、それでも、家出した「天気の子」の少年が本土に向かう船の中で読んでいた程度には、社会に対して距離をとりつつ、精一杯抵抗している感の強い文体で、大変に興味深い。オッサンになった今となってしまっては、いささか大仰で、シアトリカルにすぎるような気がするけれども。
『ライ麦畑でつかまえて』は、おじさんすでに読みづらくなってしまっているところがあるものの、自嘲を含んだド・ドーミエ=スミスの語りは、今読んでも結構ハマる。美術に関する知識を下敷きにしたうんちくや皮肉が満載なので、そっちの話に詳しくないと、何がどうなのか分かりづらいということはある。そういう点では、知識的なもの、経験的なものが少なかった頃に読めなかったのは当然かもしれない。
それにしても、ド・ドーミエ=スミスのように、背伸びして自分をとにかく大きく見せようとしていた時代があった。背伸びできることが若者の特権だと思う。背伸びはおそるおそるだし、それで間違えたり、指摘されてやり込められたりして、少しずつ成長していく。背伸びすることを恐れてはいけない。生意気だと思われて、色々言われても、負けなければきっといいことがある。ド・ドーミエ=スミスが今後どんな人生を歩むのかわからないけれども、そんな出来事をも自分の人生という作品の章立てにして、その作品の完成に向けて、試し続けていくと年老いた時に楽しい思い出ばかりが思い出されることと思う。
『ナイン・ストーリーズ』は、多くの大人がそうであったように、若かりし時期に読む機会を得た作品ではあるが、中年を超えたあたりで読んでも、ある種の懐かしさがあるようだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
